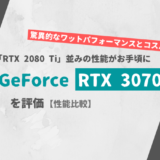この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
Microsoft Surfaceシリーズの最新モデルの仕様や特徴のまとめ記事です。対象はノートPCやタブレットです。
2画面折りたたみスマホのSurface Duoや、大型ディスプレイの一体型デスクトップPCのSurface Studioなども存在しますが、それらは別枠の製品として記載しておりませんのでご了承ください。
また、対象は最新モデルとしていますが、旧モデルの概要もページ下部に残しておりますので、興味がある方は参考までにご覧ください。
最新モデルの簡易比較表
Surfaceシリーズの最新モデル(個人向け)の簡易比較表です(2025年12月23日時点)。機種名のリンクを押すと、ページ内の紹介部分へスクロールします。
個人向けモデルでは、全モデル「Microsoft Office Home and Business」が標準付属しています(法人・教育機関モデルでは無くなるので注意)。
また、2025年12月23日現在では「Surface Pro 10」「Surface Laptop 6」「Surface Go 4」はなどが法人向けとして販売されていますが、個人向けとしては販売されていないので、とりあえずは除外しています。
掲載の価格は公式ストアにおける通常価格となっていますが、Surfaceは学割もある他、セールやキャンペーンも多いため、実際にはもう少し安く買える可能性も高いので、その点も一応考慮に入れてご覧いただくと良いかと思います。
 Surface Pro 第11世代 |  |  Surface Laptop 第7世代 |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2in1タイプ | セパレート | セパレート | クラムシェル | クラムシェル | クラムシェル | 画面が手前に スライド |
| 価格* | ¥204,380~ | ¥149,380~ | 13.8インチ: ¥204,380~ 15インチ: ¥268,180~ | ¥164,780~ | ¥109,560~ | ¥334,180~ |
| CPU | Snapdragon X Elite (12コア) Snapdraton X Plus (10コア) | Snapdraton X Plus (8コア) | Snapdragon X Elite (12コア) Snapdraton X Plus (10コア) | Snapdraton X Plus (8コア) | Core i5-1235U (10コア) | Core i7-13700H (14コア) |
| NPU | 〇 (45TOPS) | 〇 (45TOPS) | 〇 (45TOPS) | 〇 (45TOPS) | × | × |
| メモリ | 16GB/32GB LPDDR5X | 16GB LPDDR5X | 16GB/32GB LPDDR5X | 16GB LPDDR5X | 8GB / 16GB LPDDR5 | 16GB/32GB/64GB LPDDR5X |
| ストレージ | SSD 1TB 512GB 256GB | UFS 512GB 256GB | SSD 1TB 512GB 256GB | UFS 512GB 256GB | SSD 256GB 128GB | SSD 1TB 512GB |
| GPU | Adreno X1-85 (3.8 TFLPS) | Adreno X1-45 (1.7 TFLPS) | Adreno X1-85 (3.8 TFLPS) | Adreno X1-45 (1.7 TFLPS) | Iris Xe G7 80EU | Iris Xe G7 80EU RTX 4050 RTX 4060 RTX 2000 Ada |
| 画面 ※全モデル タッチ対応 | 13インチ 120Hz 2880×1920 LCD or OLED Gorilla Glass 5 | 12インチ 90Hz 2196×1464 | 13.8インチ 120Hz 2304×1536 Gorilla Glass 5 15インチ 120Hz 2496×1664 Gorilla Glass 5 | 13インチ 60Hz 1920×1280 | 12.4インチ 60Hz 1536×1024 Gorilla Glass 3 | 14.4インチ 120Hz 2400×1600 Gorilla Glass 5 |
| 無線 | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
| バッテリー 容量 | LCD:47~48Wh OLED:51~53Wh 最大 14 時間 ローカル ビデオ再生 | 最大 16 時間 ローカル ビデオ再生 | 13.8インチ:52~54Wh 最大 20 時間 ローカル ビデオ再生 15インチ:64~66Wh 最大 22 時間 ローカル ビデオ再生 | 最大 23 時間 ローカル ビデオ再生 | 40~41Wh | 56~58Wh |
| 重量 | 895g | 686g | 13.8インチ:1.34kg 15インチ:1.66kg | 1.22kg | 1.13kg | 内蔵GPU:1.89kg RTX:1.98kg |
| Office | Microsoft 365 Personal (24ヶ月版)/ Microsoft Office Home & Business | Microsoft 365 Personal (24ヶ月版)/ Microsoft Office Home & Business | Microsoft 365 Personal (24ヶ月版)/ Microsoft Office Home & Business | Microsoft 365 Personal (24ヶ月版)/ Microsoft Office Home & Business | Microsoft Office Home & Business | Microsoft Office Home & Business |
上述の仕様まとめを見れば分かることではありますが、Surfaceシリーズでは、他PCでは当たり前ではない共通の仕様がいくつかありますので触れておこうと思います。Surfaceシリーズは全体的に高価で、CPUやメモリ等の基本仕様から見たコスパは悪く見えるのが基本なのですが、下記に挙げる仕様が用途と合っている場合には意外とコスパが良いこともあります。
全モデルタッチパネル搭載
Surfaceシリーズは、全モデルがタッチパネルを搭載しています。操作にマウスやタッチパッドが必須ではありません。他PCではタッチパネル採用率の低いクラムシェル型(普通のノートパソコン)でもタッチパネルが搭載されています。
Microsoft Officeが標準で付属
Surfaceシリーズでは、個人向けモデルではMicrosoft Office Home&buisiness が標準で付属しています。Surfaceの大きな魅力です。
Microsoft Officeは自社のソフトなので実質的なコストは0で導入している形です。ただし、その分価格はやや加算されている印象です。
また、一般の方は基本的に購入できませんが、Surfaceには法人・教育機関向けモデルがあり、そちらではOfficeが付属されません。包括ライセンス契約などをしている法人や教育機関では、該当機関に所属する人は無料でOfficeを利用できる場合があるためです。その分価格が少し安くなっています。また、法人・教育機関向けモデルではOSもHome版からPro版へと変更されています。余談ですが、個人事業主なら法人モデルを購入できるという話もあるので、気になる方は調べて見ると良いかもしれません。
ディスプレイが 3:2で縦の領域が広く、品質も良い
Surfaceシリーズはディスプレイの品質が全体的に良い点もポイントです。
まず、ディスプレイのアスペクト比(縦横比)が「3:2」となっています。2025年現在、一般的なノートPCやタブレットの縦横比(アスペクト比)は「16:9」や「16:10」の横ワイド画面ですが、Surfaceはやや縦方向の割合が長いため、縦に長いページで利用する際に便利です。
使用の仕方にもよると思いますが、文書やWebページ等は縦長の方が一度に見える領域が広いことが多いため、それを意識したものと思われます。ビジネス用途でも役立つことが多い仕様だと思います。
また、色域も全モデルで優れており、色鮮やかな描写が可能となっています。
その他の点はモデルにより異なりますが、ノートPCでは一般的ではない強化ガラスが採用されていたりもします。どのモデルを選んでも質の悪いディスプレイということはないのは安心です。
公式のMicrosoft Storeでは学割があり、通常価格よりも少し安く購入することができます。対象は学生、保護者、教職員となっています。対象の方は是非チェックしてみてください。
ただし、他の割引とは併用が不可能な場合が基本で、通常割引やキャンペーン等と比べて大きくお得になるとも限らないので、学生割適用外の方の方が常に不利という訳でもないです。学割対象の人はいつでもセール価格で買える感じだと思います。
参考 学生割引のご契約条件Microsoft Store各モデルの特徴解説【最新モデル】
Surface Pro 第11世代(13インチ)

※タイプカバーは別売り
Snapdragon X 搭載 の 13インチ 2 in 1 タブレット
「Surface Pro 第11世代(13インチ)」は「Snapdragon X Plus / Elite」搭載の高性能なWindowsタブレットPC です。
本体には無段階調整のキックスタンドが付いており自立させる事ができます。また、別売りのタイプカバーを装着することでキーボードを利用する事ができ、2in1PCとしても運用できる汎用性の高さが魅力です。Surfaceシリーズの中でも特に人気が高いモデルです。
プロセッサーには「Snapdragon X Plus(10コア) / Elite(12コア)」が搭載されています。Windowsで一般的なx86系ではなく、スマホなどで主流のArmアーキテクチャによるプロセッサーです。
Armに対応していないアプリケーションはエミュレーション動作となり、パフォーマンスが少し低下したり動作が安定しないケースがある点には注意が必要です。
しかし、CPU性能は非常に優れている他、省電力性能が高いのは大きな魅力です。WindowsタブレットはiPadやAndroidと比べるとバッテリー駆動時間が短いのが弱点でしたが、Arm採用で克服しています。
また、高性能なNPUを搭載しており、AI性能が高いのもポイントです。NPU単体で45TOPSの処理性能を持っています。Copilot+ PCの要件(40TOPS)を満たしているため、次世代のAI PCとして期待できる性能です。
しかし、GPU(グラフィック性能)は価格を考えれば微妙です。仕様的にはそれなりに優れた性能を持つはずなのですが、Snapdragon XのWindowsでの最適化がまだ万全ではないようで、やや微妙な性能であることが多い印象です。特に、DirectXを用いたベンチマークでは本来の半分7割程度の性能しか発揮できていません。今後のドライバーによる最適化に期待したいところです。
また、外観は先代機とほぼ同じですが、上位モデルではOLED(有機ELディスプレイ)を選択できるようになった他、最小メモリ容量が先代では8GBだったのが16GBに増量されています。
気になる点はやはり価格です。高すぎます。公式価格は最安値でも207,680円(タイプカバー別売り)と非常に高価です。
大手の量販店では多少安くなっていることが多い他、ポイント還元も大体10%ほどあるものの、それらを考慮しても15万円以上が基本です。Officeが必要ない人にとってはコスパは悪い感は否めないです。
バッテリー駆動時間が大きく向上したことで利便性は向上したと思うものの、やはり予算に限りがある場合には厳しい金額だと思います。
| スペック表 | |||
| 参考価格 | 204,380円 ~ (税込) | ||
|---|---|---|---|
| OS | Windows 11 Home(Arm版) | ||
| CPU | Snapdragon X Elite(12コア) Snapdragon X Plus(10コア) ※NPU搭載(45TOPS) | ||
| RAM | 16GB /32GB (LPDDR5x) | ||
| SSD | 256GB / 512GB / 1TB | ||
| GPU | Adreno X1-85 (3.8 TFLOPS) | ||
| 画面 | 13インチ タッチ対応 最大 120Hz SDR 輝度 600nits(標準) HDRvi:ピーク輝度 900nits Plus:LCD(液晶) Elite:OLED(有機EL) | ||
| 表面 | グレア(光沢あり) Gorilla Glass 5 | ||
| 解像度 | 2880×1920(3:2) | ||
| Microsoft Office | 365 Personal(24か月版)/ Office Home & Business 2024 | ||
| バッテリー持続時間 | ローカルビデオ再生:最大14時間 アクティブWeb使用:最大10時間 | ||
| 無線機能 | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 | ||
| その他機能 | カメラ | ||
| サイズ | 約 287 x 209 x 9.3 mm | ||
| 重量 | 約 895g | ||
| インターフェース | USB Type-Cx 2(USB4.0/Thunderbolt4対応) | ||
| 生体認証 | 顔認証 | ||
| 備考 | キックスタンド付き タイプカバーは別売り | ||
プロセッサーには「Snapdragon X Plus(10コア)」もしくは「Snapdragon X Elite(12コア)」が採用されています。どちらでもタブレットとしては優れた性能です。重い処理にも対応することができます。
しかし、アーキテクチャが従来のWindowsのx86系とは異なるArmとなる点に注意が必要です。Armに対応していないアプリケーションはエミュレーション動作となり、パフォーマンスが少し低下したり動作が安定しないケースがあります。
特に、Windows向けに設計されたゲームでは安定動作しないという報告があります。
PlusとEliteの性能については、Eliteの方がPコア(高性能コア)が2つ多いためやや高性能となります。しかし、価格差は約5万円と非常に大きいので悩みどころです(同じメモリ・ストレージ容量のとき)。
Plusでも軽作業には十分すぎる性能ですし、個人的にはPlus(10コア)でも良いのかなと思っています。特別重い処理を想定している訳ではないなら、Plusでも十分かなと思います。
また、PlusとEliteの両方とも、AI処理に活用されるNPU(最大45TOPS)が搭載されています。Copilot+のローカル動作要件の40TOPSをクリアする処理性能を備えているので、次世代のAI機能への対応もできます。
ディスプレイはタッチ対応の13インチディスプレイです(アスペクト比3:2)。解像度は2880×1920と高く、ピクセル密度は267PPIと高くなっており、繊細な画像表示が可能です。
リフレッシュレート(最大fps)も最大120Hzとなっており、映像を滑らかに表示することが可能です。色域も広めで、Gorilla Glass 5の記載もあるので耐傷性も高いです。どの面を見ても品質の高いディスプレイです。
イラスト制作等などのクリエイティブな用途でも十分使える性能だと思います。ただし、表面は光沢ありなので好みが分かれると思います。
また、「Snapdragon X Plus」搭載モデルではLCD(液晶)ですが、「Snapdragon X Elite」搭載モデルではOLED(有機EL)になります。
ただし、有機ELでもそこまで大きな優位性はないです。OLEDの映像品質の大きな強みは高いコントラスト比ですが、液晶が1000:1、OLEDが1200:1となっており、その差は大きくありません。価格差も大きいので、その点は理解した上で選択する必要があります。
また、厳密にはディスプレイ自体の機能ではないと思いますが、Surface Slim Pen 2を利用することで触覚フィードバック機能を利用することができます。他のタブレットではほとんどついていない機能で、イラストなどで利用する人には嬉しいかもしれません。
GPUは「Snapdragon X Elite / Plus」の統合GPU「Adreno X1-85(3.8 TFLOPS)」です。GPU性能はEliteもPlusのどちらのモデルでも同じです。
実際のグラフィック処理性能については、正直微妙です。GPUの仕様やメーカーの発表や発売前の案件実機レビューを見る限りは「Core Ultra 7 155H」に近いグラフィック性能を持っているはずですが、DirectXのベンチマーク(3DMark)では最適化がまだ不十分なようで、本来の50%~70%程度の性能しか発揮できていない状況がある点には注意が必要です。特にゲーム性能を重視したい場合には注意が必要です。価格を考えると性能が低い点だけでなく、まともに動作できないという報告も結構あります。
今後改善される可能性はあるとは思いますが、2025年時点ではゲーム性能は期待しない方が良いです。
「Surface Pro 第11世代(13インチ)」約895gです(本体のみ)。タイプカバーの重量は300g前後なので、合計すると1.2kg前後です。
同サイズのノートパソコンと比較すればやや軽い部類ですが、13インチのタブレットとしては重い方です。iPad Pro 12.9インチ(Apple M4)では600gを切っていたりします。手で持って使うのはやや辛い重量だと思います。
続いてバッテリー面を見ていきます。バッテリー容量は50Wh前後で、メーカー公表の駆動時間はローカルビデオ再生時に最大14時間、アクティブなWeb使用の場合は最大10時間となっています。
Windows機としては優秀な部類であり、先代までよりも格段に良くなっているので、充電する頻度はかなり減ると思います。
しかし、AndroidタブレットやiPadと比べると特別良い訳ではないです。
ストレージ容量は256GB / 512GB / 1TBの3つがラインナップされています。価格を考えるとかなり渋いです。
しかも、各容量の価格差は約3.3万円(発売時点)となっており、非常に高価です。
一応、本体搭載のSSDは割と簡単に個人で交換できる仕様になっているようなので(ただし、恐らく保証の範囲外になる)、出来るだけ安くSSD容量を増やしたいという方は交換を検討しても良いかもしれません。ただし、M.2のType2230というメジャーでない規格となりますので、その点には注意です。
「Surface Pro 第11世代(13インチ)」はArmアーキテクチャと「Snapdragon X」採用のおかげで省電力性が向上した、優れたAI性能とCPU性能を持つタブレットです。ディスプレイ性能も非常に高いです。
しかし、価格が高すぎるので厳しい印象です。公式の最安値は20.7万円ですし、最小ストレージは256GBです。量販店などでポイント込みでの実質最安値で見ても15万円を切ることがほとんどないレベルの高額さです。
また、Armアーキテクチャにも懸念があります。x86系が基本だったWindowsでは各アプリケーションでのArmでの動作がまだ完璧ではないです。特にグラフィック性能は最適化不足が顕著です。
付属のOfficeに価値を感じない限りはコスパは良くないと思います。
Surface Pro 第11世代(12インチ)

タイプカバーは別売り
Snapdragon X 搭載 の 12インチ 2 in 1 タブレット
「Surface Pro 第11世代(12インチ)」は「Snapdragon X Plus(8コア)」搭載のWindowsタブレットPC です。13インチと比べて価格が少し安くなっているのが魅力です。
発売当初はOfficeサブスク(24か月間)固定だった上に高価だったので微妙でしたが、後に永続版も選択可能になり、価格もセールや値下げ実施が多くて思ったより安く、2025年末時点では割とおすすめの選択肢です。
軽く仕様について触れていきます。
まず Surface Proはシリーズ共通で無段階調整のキックスタンドが付いており、自立させる事ができます。別途でスタンドカバー等は必要ありません。また、別売りのタイプカバーを装着することでキーボードを利用する事ができ、2in1PCとしても運用できる汎用性の高さが魅力です。
プロセッサーには「Snapdragon X Plus(8コア)」が搭載されています。Windowsで一般的なx86系ではなく、スマホなどで主流のArmアーキテクチャによるプロセッサーです。
Armに対応していないアプリケーションはエミュレーション動作となり、パフォーマンスが少し低下したり動作が安定しないケースがある点には注意が必要です。
CPU性能はタブレットとしては高く、軽作業には十分な性能です。また、Windows機にしてはバッテリー駆動時間が長いのも魅力です。WindowsタブレットはiPadやAndroidと比べるとバッテリー駆動時間が短いのが弱点でしたが、Arm採用で克服しています。
また、高性能なNPUを搭載しており、AI性能が高いのもポイントです。NPU単体で45TOPSの処理性能を持っています。Copilot+ PCの要件(40TOPS)を満たしているため、次世代のAI PCとして期待できる性能です。
しかし、GPUのグラフィック性能が低めなのが懸念点です。13インチモデルでは 3.8 TFLOPS ですが、12インチモデルでは1.7 TFLOPS となっており、半分未満の性能です。タブレット全体では高めの性能ですが、10万円を大きく超えるPCのグラフィック性能としては低いです。
しかも、主にArmアーキテクチャによる制限と最適化不足のせいで、仕様値よりも低いパフォーマンスとなっていることが多いのもかなり厳しいです。特に、DirectXを用いたベンチマークでは本来の半分から7割程度の性能しか発揮できていません。
とはいえ、高画質動画などを観るくらいには十分な性能があり、CPUの方は普通に高性能です。13インチモデルよりは大きく安価ということもあり、用途次第では気にならないと思います。
総評としては、グラフィック性能が価格の割には低すぎるのが気になりますが、用途次第では気になりません。
最適化不足の懸念は否定できないものの、時間が経つにつれてかなりの速度で対応が進んでいます。今後のドライバーによる最適化にも期待できるので、価格も考えれば以前ほどは選びにくいモデルではなくなったと思います。
ただし、最適化不足の問題がなくなっても、価格の割には性能は低いという点は留意する必要があります。
一番の問題はやはり価格です。13インチモデルよりは安いですが、価格自体は非常に高価です。
公式価格は最安値で149,380円(タイプカバー別売り)です。手を出し易いモデルとしての投入に見えるのですが、その割には高すぎます。
ただし、発売当初にOffice永続版が無かったことや、Arm版Windows(Snapdragon)への不安から人気が無さ過ぎたため、各ショップでは大きな値下げが行われているところが多いですし、公式でも大幅値引きセールが頻繁に実施されています。
各ショップの値下げやポイント、公式セールを考慮すると、実質的には大体12万円前後で手に入れることが可能となっています。
Officeが必要な人なら普通にコスパは良いと思いますし、そうでなくても重いグラフィック処理や専門的なソフトを使わないなら、バッテリー持ちの良さと2 in 1 タブレットの良さのおかげで実用コスパは高いと思います。
「優れたバッテリー性能を持つWindows機」という魅力は非常にあるので、用途次第では普通にアリな選択肢になりました。
| スペック表 | |||
| 参考価格 | 149,380円 ~ (税込) | ||
|---|---|---|---|
| OS | Windows 11 Home(Arm版) | ||
| CPU | Snapdragon X Plus(8コア) ※NPU搭載(45TOPS) | ||
| RAM | 16GB (LPDDR5x) | ||
| ストレージ | UFS 256GB / 512GB | ||
| GPU | Adreno X1-45 (1.7 TFLOPS) | ||
| 画面 | 12インチ タッチ対応 最大 90Hz SDR 最大輝度 400nits(標準) | ||
| 表面 | グレア(光沢あり) 強化ガラス | ||
| 解像度 | 2880×1920(3:2) | ||
| Microsoft Office | 365 Personal(24か月版)/ Office Home & Business 2024 | ||
| バッテリー持続時間 | ローカルビデオ再生:最大16時間 アクティブWeb使用:最大12時間 | ||
| 無線機能 | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 | ||
| その他機能 | カメラ | ||
| サイズ | 約 274 x 190 x 7.8 mm | ||
| 重量 | 約 686 g | ||
| インターフェース | USB Type-Cx 2 (USB3.2/Thunderbolt 4対応) | ||
| 生体認証 | 顔認証 | ||
| 備考 | キックスタンド付き タイプカバーは別売り | ||
プロセッサーには「Snapdragon X Plus(8コア)」が採用されています。タブレットとしては高い性能で、軽作業には十分な性能です。
しかし、アーキテクチャが従来のWindowsのx86系とは異なるArmとなる点に注意が必要です。Armに対応していないアプリケーションはエミュレーション動作となり、パフォーマンスが少し低下したり動作が安定しないケースがあります。
特に、Windows向けに設計されたゲームでは安定動作しないという報告があります。
また、AI処理に活用されるNPU(最大45TOPS)が搭載されています。Copilot+のローカル動作要件の40TOPSをクリアする処理性能を備えているので、次世代のAI機能への対応もできます。
ディスプレイはタッチ対応の12インチディスプレイです(アスペクト比3:2)。解像度は2196×1464と高く、ピクセル密度は220PPIと高めで、比較的繊細な画像表示が可能です。
リフレッシュレート(最大fps)は最大90Hzとなっています。色域も広めです。全体的に見ると優れたディスプレイです。表面は光沢ありなので好みが分かれると思います。
また、厳密にはディスプレイ自体の機能ではないと思いますが、Surface Slim Pen 2を利用することで触覚フィードバック機能を利用することができます。他のタブレットではほとんどついていない機能で、イラストなどで利用する人には嬉しいかもしれません。
比較的良い仕様ではありますが、Gollira Glass 5 の記載が13インチモデルから無くなってしまったのは残念です。やや傷が付きやすくなっている可能性があります。
GPUは「Snapdragon X Plus(8コア)」の統合GPU「Adreno X1-45(1.7 TFLOPS)」です。
13インチモデルでは 3.8 TFLOPS ですが、12インチモデルでは1.7 TFLOPS となっており、半分未満の性能です。
とはいえ、「Core i7-1255U」などに搭載の「Iris Xe Graphics 96EU」に近い性能と言われており、タブレットとしては高めの性能ではあります。動画視聴などには問題なく、動画編集も軽いものには対応できます。
ただし、2025年の最安13.5~15万円のPCとして考えるなら低い性能です。同額帯のノートPCでは、2倍近い性能を持つものも一般的となっています。
ノートPCと捉えるか、タブレットとして捉えるかによってグラフィック性能の評価は大きく分かれそうです。
また、Windowsゲームで主流のAPIである「DirectX」のベンチマーク(3DMark)では最適化がまだ不十分なようで、本来の50%~70%程度の性能しか発揮できていない状況がある点には注意が必要です。
シンプルに基本性能も高くないですし、不具合の懸念もあるということで、ゲーム目的ではおすすめできません。まともに動作できないという報告も結構あります。
最適化などについては今後改善される可能性はあるとは思いますが、「Adreno X1-45」ではフル活用できても強力とは言えないので、グラフィック性能に大きな期待はしない方が良いです。
「Surface Pro 第11世代(12インチ)」約686gです(本体のみ)。専用キーボードの重量は約340gなので、合計すると1kg強です。
13インチから1インチしか小さくなっていない割には大幅な軽量化となっています。13インチモデルと比べるとかなりコンパクトで軽い印象を受けると思います。持ち運びも苦ではないと思います。
続いてバッテリー面を見ていきます。メーカー公表の駆動時間はローカルビデオ再生時に最大16時間、アクティブなWeb使用の場合は最大12時間となっています。Windows機としては優秀な部類です。
AndroidタブレットやiPadと比べると特別良い訳ではないですが、Windowsでとにかくバッテリー性能が良いタブレットが欲しいなら魅力的だと思います。
ストレージ面は微妙です。容量は 256GB / 512GB がラインナップされています。10万円を大きく超える価格を考えると大分渋いです。
また、SSDではなくUFSが採用されています。最大速度では最新のSSDには少し劣るものの、速度面では十分なパフォーマンスがありますし、電力面も悪くないので、あまり気にしなくても大丈夫です。
ただし、SDカードスロットもなく、内蔵ストレージは個人の交換も不可能という点には留意が必要です。
必要量を購入時に搭載しておくか、クラウドストレージを上手く活用する必要があります。
「Surface Pro 第11世代(12インチ)」は小型のWindowsタブレットとしては非常に優れたバッテリー駆動時間が魅力のタブレットです。
発売当初の評価はかなり微妙でしたが、その後にOfficeが永続版になったり、人気の無さによる各ショップの値下げや公式セールが常態化したことで、実質12万円前後で買えるようになっており(2025年末時点)、この価格なら普通に有力な選択肢だと思います。
世間的には最適化不足やGPU性能の低さが取り沙汰されることが多く、その懸念は事実ではあります。
ただ、最適化不足は想像よりも早く改善が進んでいてかなり使い易くなったと思いますし、GPU性能の低さは用途次第では気になりません。
CPU性能の方は普通に高性能で、元々軽作業には十分すぎるので「バッテリー持ちの良いWindowsタブレット」という魅力がかなり強く感じられる機種になっていると思います。
発売当初の評価はかなり微妙なものでしたが、用途次第では実はかなり良くなっていると思います。
Surface Laptop 第7世代(13.8 / 15インチ)

Snapdragon X 搭載で高性能な高品質ノート
「Surface Laptop 第7世代(13.8 / 15 インチ)」は「Snapdragon X Plus / Elite」搭載の高品質ノートPCです。2-in-1ではないクラムシェルタイプのノートPCですが、タッチには対応しています。
プロセッサーの「Snapdragon X」シリーズは、Armアーキテクチャによる省電力性能の高さが魅力の一つです。この「Surface Laptop 第7世代(13.8 / 15 インチ)」は公称でローカルビデオ再生で最大20時間以上のバッテリー性能を誇ります。
CPU自体の性能も高性能ですが、Armに対応していないアプリケーションはエミュレーション動作となり、パフォーマンスが少し低下したり動作が安定しないケースがある点には注意が必要です。
更に、高性能なNPUを搭載しており、AI処理性能も高いのもポイントです。Copilot+のローカル動作要件の40TOPSを超える45TOPSの性能を備えており、次世代のAI PCとして期待できる性能です。
しかし、GPU(グラフィック性能)は価格を考えれば微妙です。仕様的にはそれなりに優れた性能を持つはずなのですが、Snapdragon XのWindowsでの最適化がまだ万全ではないようで、やや微妙な性能であることが多い印象です。特に、DirectXを用いたベンチマークでは本来の半分7割程度の性能しか発揮できていません。今後のドライバーによる最適化に期待したいところです。
気になる点はやはり価格です。高すぎます。公式価格は最安値でも207,680円と非常に高価です。
大手の量販店では多少安くなっていることが多い他、ポイント還元も大体10%ほどあるものの、それらを考慮しても17万円以上が基本です。Officeが必要ない人にとってはコスパが悪い感は否めないです。
バッテリー駆動時間が大きく向上したことで利便性は向上したと思うものの、やはり予算に限りがある場合には厳しい金額だと思います。
| スペック表 | |||
| 参考価格 | 13.8インチ:207,680円 ~ (税込) 15インチ:268,180円 ~ (税込) | ||
|---|---|---|---|
| OS | Windows 11 Home(Arm版) | ||
| CPU | Snapdragon X Elite(12コア) Snapdragon X Plus(10コア) ※NPU搭載(45TOPS) ※15インチはEliteのみ | ||
| RAM | 16GB /32GB (LPDDR5x) | ||
| SSD | 256GB / 512GB / 1TB | ||
| GPU | Adreno X1-85 (3.8 TFLOPS) | ||
| 画面 | 13.8インチ/15インチ 液晶 最大120Hz タッチ対応 | ||
| 表面 | グレア(光沢あり) Gorilla Glass 5 | ||
| 解像度 | 13.8インチ:2304×1536(3:2) 15インチ:2496×1664(3:2) | ||
| Microsoft Office | 365 Personal(24か月版)/ Office Home & Business 2024 | ||
| バッテリー持続時間 | 13.8インチ: ローカルビデオ再生:最大20時間 アクティブWeb使用:最大13時間 15インチ: ローカルビデオ再生:最大22時間 アクティブWeb使用:最大15時間 | ||
| 無線機能 | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 | ||
| その他機能 | カメラ | ||
| サイズ | 13.8インチ: 約 301 x 220 x 17.5 mm 15インチ: 約 329 x 239 x 18.29 mm | ||
| 重量 | 13.8インチ: 約1.34kg 15インチ: 約1.66kg | ||
| 主な インターフェース | 13.8インチ: USB-C ×2(USB4.0/Thunderbolt4対応)USB-A 3.1 ×1 15インチ: USB-C ×2(USB4.0/Thunderbolt4対応)USB-A 3.1 ×1 microSDXCカードリーダー | ||
| 生体認証 | 顔認証 | ||
| 備考 | |||
プロセッサーには「Snapdragon X Plus(10コア)」もしくは「Snapdragon X Elite(12コア)」が採用されています。優れた性能を持ち、重い処理にも対応することができます。
しかし、2025年時点の15万円超えの高額ノートとしては平均的な性能です。アーキテクチャが従来のWindowsのx86系とは異なるArmとなり、Armに対応していないアプリケーションはエミュレーション動作となり、パフォーマンスが少し低下したり動作が安定しないケースがあるという点を考慮すると実質コスパはやや悪めの印象です。
特に、Windows向けに設計されたゲームでは安定動作しないという報告があるので、ゲーム目的の人にはおすすめできません。
PlusとEliteの性能については、Eliteの方がPコア(高性能コア)が2つ多いためやや高性能となります。しかし、価格差は約5万円と非常に大きいので悩みどころです(同じメモリ・ストレージ容量のとき)。
Plusでも軽作業には十分すぎる性能ですし、個人的にはPlus(10コア)でも良いのかなと思っています。特別重い処理を想定している訳ではないなら、Plusでも十分かなと思います。
また、PlusとEliteの両方とも、AI処理に活用されるNPU(最大45TOPS)が搭載されています。Copilot+のローカル動作要件の40TOPSをクリアする処理性能を備えているので、次世代のAI機能への対応もできます。
「Surface Laptop 第7世代(13.8 / 15 インチ)」のディスプレイはタッチに対応しています。解像度はそれぞれ2304×1536、2496×1664となっており高めです。ピクセル密度はどちらも201PPIです。
ノートPC全体で見ると精細なディスプレイですが、高額ノートとしてはやや低めではあります。しかし、その他の点は非常に良いです。
リフレッシュレート(最大fps)は最大120Hzとなっており、映像を滑らかに表示することが可能です。色域も広めで、コントラスト比も1300 or 1400:1となっているため、液晶としては映像品質は非常に高いです。
更に、Gorilla Glass 5の記載もあるので傷も付きにくいです。ノートPCで強化ガラス採用はやや珍しいです。
解像度こそ特別高くありませんが、全体的には非常に高品質な液晶ディスプレイです。
ただし、表面は光沢ありなので、その点は好みが分かれると思います。
GPUは「Snapdragon X Elite / Plus」の統合GPU「Adreno X1-85(3.8 TFLOPS)」です。GPU性能はEliteもPlusのどちらのモデルでも同じです。
実際のグラフィック処理性能については、正直微妙です。GPUの仕様やメーカーの発表や発売前の案件実機レビューを見る限りは「Core Ultra 7 155H」に近いグラフィック性能を持っているはずですが、DirectXのベンチマーク(3DMark)では最適化がまだ不十分なようで、本来の50%~70%程度の性能しか発揮できていない状況がある点には注意が必要です。特にゲーム性能を重視したい場合には注意が必要です。価格を考えると性能が低い点だけでなく、まともに動作できないという報告も結構あります。
今後改善される可能性はあるとは思いますが、2025年時点ではゲーム性能は期待しない方が良いです。
サイズと重量は、13.8インチモデルが約1.34kg、15インチモデルが約1.66kgとなっています。サイズから見た重量は平均的です。
ただし、バッテリー容量はサイズの割にはやや多めですし、省電力性に優れるArmアーキテクチャ採用なので、バッテリー持続時間はWindows機としては長いです。
公称バッテリー駆動時間は、13.8 / 15 インチそれぞれ、ローカルビデオ再生時は最大20、22時間で、WebブラウザーによるアクティブWeb使用時間は最大13、15時間となっています。
このバッテリー駆動時間の長さは「Surface Laptop 第7世代」の大きな強みです。
ストレージ容量は256GB / 512GB / 1TBの3つがラインナップされています。最安15~20万円で最小256GBはかなり渋いです。
しかも、各容量の価格差もSurface Proと同じ約3.3万円となっており、非常に高価です。
15インチモデルにはmicroSDカードスロットがあるのでそちらで対応することができますが、13.8インチモデルは始めから必要量を選択しておく必要がある点に注意が必要です。
また、個人でのSSD交換も不可能ではありませんが、Surface Proと違い難易度が高いです。PCの蓋をがっつり開ける必要があり、工程もやや難しいです。保証もされていないので自己責任となります。
「Surface Laptop 第7世代(13.8 / 15インチ)」は優れたバッテリー駆動時間と非常に優れたディスプレイを持つのが魅力のノートパソコンです。高性能なNPUを持つAI PCでもあります。
しかし、やはり価格が高すぎるので厳しい印象です。公式の最安値は20.7万円ですし、量販店などでポイント込みでの実質最安値で見ても15万円を切ることがほとんどないレベルの高額さです。
しかも、最小構成は256GBです。2025年の15万円超えのPCとは思えない設定です。15インチモデルに関してはmicroSDカードスロットを備えるので補助が可能なものの、13.8インチモデルはクラウドストレージなどを活用するしかないです。
また、Armアーキテクチャにも懸念があります。x86系が基本だったWindowsでは各アプリケーションでのArmでの動作がまだ完璧ではないです。特にグラフィック性能は最適化不足が顕著です。
付属のOfficeに価値を感じない限りはコスパは良くないと思います。
Surface Laptop 第7世代(13インチ)

Snapdragon X 搭載でバッテリー持ちが良い13インチノート
「Surface Laptop 第7世代(13インチ)」は「Snapdragon X Plus (8コア)」搭載のノートPCです。2-in-1ではないクラムシェルタイプのノートPCですが、タッチには対応しています。13.8 / 15 インチモデルと比べて価格が少し安くなっているのが魅力です。
ただし、始めに言ってしまうと、15万円以上という価格に見合った性能ではないです。
以下から、軽く仕様について触れていきます。
まず、プロセッサーには「Snapdragon X Plus(8コア)」が搭載されています。Windowsで一般的なx86系ではなく、スマホなどで主流のArmアーキテクチャによるプロセッサーです。
Armに対応していないアプリケーションはエミュレーション動作となり、パフォーマンスが少し低下したり動作が安定しないケースがある点には注意が必要です。
CPU性能はそれなりに高く、軽作業には十分な性能です。また、省電力性能が高いのは大きな魅力です。WindowsタブレットはiPadやAndroidと比べるとバッテリー駆動時間が短いのが弱点でしたが、Arm採用で克服しています。
ただし、15万円以上という価格を考えると微妙な性能です。処理性能自体は6~8万円の高コスパ機と変わらないレベルです。性能コスパはかなり悪いです。
更に、GPUのグラフィック性能が低いのも大きな懸念点です。13.8 / 15 インチモデルでは 3.8 TFLOPS ですが、13インチモデルでは1.7 TFLOPS となっており、半分未満の性能です。15万円クラスのPCのグラフィック性能としては非常に低いです。超軽量モバイルという訳でもないのにこの性能は擁護できません。
特に顕著なのが、DirectXを用いたベンチマークでは本来の半分7割程度の性能しか発揮できていない点です。今後のドライバーによる最適化に期待したいところですが、改善したところで価格に見合った性能ではありません。
しかし、高性能なNPUを搭載しており、AI処理性能も高いのはポイントです。Copilot+のローカル動作要件の40TOPSを超える45TOPSの性能を備えており、次世代のAI PCとして期待できる性能です。
NPUの性能だけ見れば、特別高価でもないので、そこを重視したいなら選択肢としては一応入るとは思います。
また、プロセッサ以外の面では、ディスプレイのリフレッシュレートが最大60Hzになってしまっているのが非常に残念です。明るさも400nitsと低いです。高額機でこの仕様はちょっと酷いなと思います。
そして何度も触れていますが、一番ネックなのが価格です。性能の割に高すぎます。公式価格は最安値でも164,780円です。
公式以外では多少安くなっていることが多い他、大手の量販店ではポイント還元も大体10%ほどあるものの、それらを考慮しても15万円弱くらいです。
Surface Proのようなタブレットであれば、Windowsというだけで希少性の魅力がありますし、モバイル性の高さによる実用性の高さもあったのでまだ多少考慮の余地がありました。同価格でも微妙な性能なのに、なぜかSurface Proの最安値モデルよりもちょっと高くて、意味わからないです。
しかも、Surface Laptopのような普通のノートパソコンの場合、性能コスパに優れたライバル機が非常に多いのも厳しいです。
15万円出せるなら、最新の「Core Ultra」や「Ryzen AI」搭載で重めのゲームや動画編集にも対応できるノートが普通に検討できてしまいます。
| スペック表 | |||
| 参考価格 | 164,780円 ~ (税込) | ||
|---|---|---|---|
| OS | Windows 11 Home(Arm版) | ||
| CPU | Snapdragon X Plus(8コア) ※NPU搭載(45TOPS) | ||
| RAM | 16GB (LPDDR5x) | ||
| ストレージ | UFS 256GB / 512GB | ||
| GPU | Adreno X1-45 (1.7 TFLOPS) | ||
| 画面 | 13インチ タッチ対応 最大60Hz 明るさ:最大 400nits(標準) | ||
| 表面 | グレア(光沢あり) 強化ガラス | ||
| 解像度 | 1920×1280(3:2) | ||
| Microsoft Office | 365 Personal(24か月版)/ Office Home & Business 2024 | ||
| バッテリー持続時間 | ローカルビデオ再生:最大23時間 アクティブWeb使用:最大16時間 | ||
| 無線機能 | Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 | ||
| その他機能 | カメラ | ||
| サイズ | 約 328.65 x 214.14 x 15.6 mm | ||
| 重量 | 約1.22kg | ||
| 主な インターフェース | USB-C ×2(USB3.2/Thunderbolt4対応) USB-A 3.1 ×1 | ||
| 生体認証 | 顔認証 | ||
| 備考 | |||
プロセッサーには「Snapdragon X Plus(8コア)」が採用されています。比較的高性能で、軽作業には十分な性能です。しかし、15万円~という価格を考えると微妙な性能です。
また、アーキテクチャが従来のWindowsのx86系とは異なるArmとなる点に注意が必要です。Armに対応していないアプリケーションはエミュレーション動作となり、パフォーマンスが少し低下したり動作が安定しないケースがあります。
特に、Windows向けに設計されたゲームでは安定動作しないという報告があります。
一応の良い点としては、AI処理に活用されるNPU(最大45TOPS)が搭載されています。Copilot+のローカル動作要件の40TOPSをクリアする処理性能を備えているので、次世代のAI機能への対応もできます。
Windows向けのプロセッサのNPU性能はスマホやタブレットと比べると少し遅れており、40TOPS以上の機種は軒並み超高額機なので、ここは悪くないです。
「Surface Laptop 第7世代(13インチ)」のディスプレイはタッチに対応しています。解像度は1920×1280となっており、低額機よりはわずかに良いくらいです。ピクセル密度は178PPIで高くはありません。
リフレッシュレート(最大fps)は最大60Hzとなっており、滑らかではありません。色域も広めですが、コントラスト比は1000:1となっています。
表面は光沢ありなので、その点は好みが分かれると思います。
15万円~の機種のディスプレイとしては、大分微妙です。せめてリフレッシュレートくらいは90Hz以上にして欲しかったです。
GPUは「Snapdragon X Plus(8コア)」の統合GPU「Adreno X1-45(1.7 TFLOPS)」です。
13.8 / 15 インチモデルでは 3.8 TFLOPS ですが、13インチモデルでは1.7 TFLOPS となっており、半分未満の性能です。
「Adreno X1-45」の性能は「Core i7-1255U」などに搭載の「Iris Xe Graphics 96EU」に近い性能と言われています。動画視聴などには問題なく、動画編集も軽いものには対応できます。
ただし、2025年発売の15万円~の機種のものとしてはかなり微妙です。現在の同額帯のノートPCでは、2倍近い性能を持つものも一般的となっています。
また、Windowsゲームで主流のAPIである「DirectX」のベンチマーク(3DMark)では最適化がまだ不十分なようで、本来の50%~70%程度の性能しか発揮できていない状況がある点には注意が必要です。
シンプルに基本性能が低いですし、不具合の懸念もあるということで、ゲーム目的ではおすすめできません。まともに動作できないという報告も結構あります。
最適化などについては今後改善される可能性はあるとは思いますが、「Adreno X1-45」ではフル活用できても強力とは言えないので、グラフィック性能に大きな期待はしない方が良いです。
重量は約1.22kgとなっています。サイズから見た重量は平均的です。
しかし、省電力性に優れるArmアーキテクチャ採用なので、バッテリー持続時間はWindowsのモバイルノートPCとしてはかなり長いです。
公称バッテリー駆動時間は、ローカルビデオ再生時は最大23時間で、WebブラウザーによるアクティブWeb使用時間は最大16時間となっています。
このバッテリー駆動時間の長さは「Surface Laptop 第7世代(13インチ)」の大きな強みです。かなり批判的な意見ばかり言ってしまっていますが、バッテリー性能だけは素直に褒められます。
ストレージ面は微妙です。容量は 256GB / 512GB がラインナップされています。最安15万円クラスという価格を考えるとものすごく渋いです。
また、SSDではなくUFSが採用されており、速度でやや劣ります。消費電力を考えれば優秀なので、一概に悪いとは言えませんが、一般的にはスペックダウンと捉える方が多い気がします。
SDカードスロットもなく、内蔵ストレージは個人の交換も不可能です。色々と微妙感が強めのストレージ仕様です。
「Surface Laptop 第7世代(13インチ)」は優れたバッテリー駆動時間と高性能なNPUを持つAI PCです。
しかし、性能の割には価格が高すぎるので厳しい印象です。ストレージ容量も少ないです。
公式の最安値は約16.5万円ですし、量販店などでポイント込みでの実質最安値で見ても15万円程度です。
CPUとGPU性能は数世代前の機種並みなのに、この価格はさすがに微妙です。しかも、ディスプレイが60Hzとなったのも気になります。
また、Armアーキテクチャにも懸念があります。x86系が基本だったWindowsでは各アプリケーションでのArmでの動作がまだ完璧ではないです。特にグラフィック性能は最適化不足が顕著です。
個人的には、せめて12~13万円くらいまで下がらないと選択肢に入らないかなと思っています。
Surface Laptop Go 3

12.4インチのコンパクトモバイルノート
Surface Laptop Goは12.4インチのコンパクトなクラムシェル型ノートPCです。画面がくるっとは回転しないクラムシェル型ですが、タッチパネル搭載で使い勝手は良いです。コンパクトで軽いので持ち運びも苦になりません。
先代(Surface Laptop Go 2)では4コアの「Core i5-1135G7」採用だったために処理性能は高くありませんでしたが、CPUには10コアの「Core i5-1235U」採用となり、処理性能が格段に向上しました。ただし、その代わりに価格も格段に上昇し、最安モデルが先代の9万円台から14万円台となってしまったのは残念です。
先代ではメモリとSSDの最低構成が4GB/128GBだったのが、8GB/256GBになったり、指紋認証が最低構成でも搭載されるようになったのも良い点ですが、それを考慮してもさすがに値上がり幅が大きい気がします。
先代はオフィス付きの高品質なモバイルノートを安価に導入したい場合にはおすすめできるモデルでしたが、値上がりによってリーズナブルとも言えたなくなったため、ターゲット層が難しくなった印象のある機種です。
[/cell][/yoko2]| スペック表 | |||
| 参考価格 | 109,560円 ~ 160,600円 (税込) | ||
|---|---|---|---|
| OS | Windows 11 Home | ||
| CPU | Core i5-1235U | ||
| RAM | 8GB/16GB (LPDDR5) | ||
| SSD | 128GB / 256GB | ||
| GPU | 内蔵 (Iris Xe G7 80EU) | ||
| 画面 | 12.4インチ タッチ対応 | ||
| 表面 | グレア(光沢あり) | ||
| 解像度 | 1536×1024 | ||
| Office | Microsoft Office Home and Business 2021 | ||
| バッテリー持続時間 | メーカー公表値:最大15時間 | ||
| 無線機能 | IEEE 802.11 b / g / n / ac / ax (Wi-Fi 6対応) Bluetooth 5.1 | ||
| その他機能 | カメラ | ||
| サイズ | 約 278x206x15.7 mm | ||
| 重量 | 約1.13kg | ||
| インターフェース | USB Type-Cx1,USB Type-Ax1 | ||
| 生体認証 | 指紋認証(電源ボタン) | ||
| 備考 | |||
CPUは「Core i5-1235U」の一種類のみです。10コア(2P+8E)で、先代の4コアの「Core i5-1135G7」よりは格段に性能が向上しています。
比較的重めの処理も出来る性能で、軽い処理なら非常に快適です。ただし、高性能コア(Pコア)は2コアのみの、省電力性を重視したCPUなので、重めの処理を前提とするのに適したCPUではないので過信は禁物です。
ディスプレイは、タッチ対応の12.4インチのIPS液晶です(アスペクト比3:2)。解像度は1536×1024とやや低く、ピクセル密度も148PPIと低めなので、精細なディスプレイという訳ではありません。
ただし、sRGB対応で色域は広めで、Gorilla Glass 3の記載があるため、強度も比較的高いです。安価なノートPCなどと比べると質は高いディスプレイです。
表面は光沢仕様なので好みが分かれると思います。
GPUはCPUに内蔵の「Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)」です。性能は高くはありませんが、動画視聴等には十分な性能です。
また、ゲームも軽いものなら快適にプレイできる他、データ量の少ない簡単な動画編集もある程度行うことができます。とはいえ、高性能とは言えないので、重めのゲームや動画編集を前提とするなら、GeForce等の単体のビデオカードを搭載した機種の検討をおすすめします。
重量は1,13gと軽量です。厚みも15.7mmと薄くコンパクトなので、持ち運びも苦にならないと思います。
バッテリーの駆動時間は、メーカー公表値では最大15時間と長めです。しかし、同じCPUを採用したSurface Pro 9では実際にはWi-Fiテストで7.5時間~8時間程度しか持続せずに優れている訳でなかったので、Surface Laptop Go 3もそこまで良くはない可能性があります。
ただし、USB PDにも対応しており、USB Type-Cで充電する事が可能ですし、ノートパソコンとしては薄型軽量なのでモバイル性能は低くありません。タッチ対応の点も含め、モバイル性能は高い機種だと思います。
ストレージは128GBか256GBのSSDです。メイン機とするには少ないと思う上、SDカードスロットも標準搭載していないのがやや残念です。
Surface Laptop Go 2は12.4インチの薄型コンパクトでモバイル性能の高さが魅力の機種です。
10コアの「Core i5-1235U」搭載により先代よりも処理性能も格段に向上しており、やや重めの処理にも対応できるようになりました。
価格は約11万円~(2024年3月時点)と安くはないものの、Office標準付属と機体品質の高さを考えれば他のSurfaceよりもコストパフォーマンスは優れていると思います。
ただ、タッチ対応とはいえクラムシェルというスタンダートなノートPCとしては高価な割には、さすがにメモリとストレージ容量が弱すぎます。サイズ的にも、がっつり使うメインというよりはサブ機や持ち運び用の端末だとは思いますが、13インチ台まで許容できるなら、Surface以外でもっと安価で魅力的な機種がたくさんあるので、そこが難しいところ。
Surface Laptop Studio 2

グラボ搭載可能な14.4インチ2in1ノートPC
Surface Laptop Studio 2は14.4インチサイズの2in1ノートPCです。特殊なヒンジを採用しており、画面を手前にスライドさせることができます。その仕様によって、素早くタブレットモードへ移行することができます。
CPUには「Core i7-13700H(14コア)」を搭載し、2 in 1タイプとしては非常に高性能な他、「RTX 4050 / RTX 4060 / RTX 2000 Ada」ビデオカード搭載モデルもあり、該当モデルでは重い動画編集やゲームなども可能となっています。内蔵GPUモデルだとコスパ的に見合わなさすぎる価格なので、ビデオカード搭載機をおすすめしたい機種です。
あらゆる事に一台で対応したい人に最適な、ハイエンド2 in 1 ノートPCとなっています。
ただし、価格は発売時で336,380円~とめちゃくちゃ高価なのがネックです。タイプとしては類似機がない唯一無二の2 in 1 PCなので魅力はありますし、バッテリー駆動時間は長く、画面の強度なども高いので、長期利用も期待できる魅力はありますが、処理性能だけならもっと安価なゲーミングノートやクリエイターノートがたくさんあるので、予算との相談になると思います。
| スペック表 | |||
| 価格 | 336,380円 ~ 582,780円 (税込) ※2023年9月25日時点 | ||
|---|---|---|---|
| OS | Windows 11 Home | ||
| CPU | Core i7-13700H | ||
| RAM | 16GB / 32GB / 64GB (LPDDR5X) | ||
| SSD | 512GB / 1TB | ||
| GPU | RTX 2000 Ada Generation Laptop GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4050 Iris Xe G7 96EU(CPU内蔵) | ||
| 画面 | 14.4インチ 120Hz タッチ対応 | ||
| 表面 | グレア(光沢あり) | ||
| 解像度 | 2400×1600 | ||
| Office | Microsoft Office Home and Business 2021 | ||
| バッテリー持続時間 | 内蔵GPU:最大19時間 RTX:最大18時間 | ||
| 無線機能 | IEEE 802.11 b / g / n / ac / ax (Wi-Fi 6E対応) Bluetooth 5.3 | ||
| その他機能 | カメラ | ||
| サイズ | 約 323x230x22 mm | ||
| 重量 | 内蔵GPU:1.89kg RTX:1.98kg | ||
| インターフェース | USB Type-C(Thunderbolt4)×2 USB Type-A×1 MicroSDXCカードリーダー | ||
| 生体認証 | 顔認証 | ||
| 備考 | |||
CPUには14コア(6P+8E)の「Core i7-13700H」が搭載されています。ゲーミングPCやクリエイター向けPCによくされるモデルで、モバイル端末向けのCPUとしては非常に高性能です。重い処理もこなすことが出来る性能があります。
その代わり、高負荷時の消費電力は多いため、バッテリー駆動時には少し注意する必要があります。
ディスプレイはタッチ対応の14.4インチです(アスペクト比3:2)。解像度は2400×1600と高めで、リフレッシュレートも最大120Hzで比較的滑らかな映像描写が可能です。
sRGB対応の色域も広めのディスプレイで、Gorilla Glass 5の記載もあり、強度も高いです。全体的に非常に高品質なディスプレイです。
イラスト制作等の用途でも十分使える性能だと思いますし、リフレッシュレートも高いので、ビデオカード搭載モデルではゲームでも使えると思います。
価格を考えれば特段優れている訳ではありませんが、どの方面を見ても弱点となる点がない優れた品質のディスプレイです。
表面は光沢仕様なので好みが分かれると思います。
GPUは、最安値モデルでは「Core i7-13700H」内蔵の「Iris Xe Graphics(96EU)」で、ビデオカード搭載モデルは「GeForce RTX 4050」「GeForce RTX 4060」「RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU」の3種類が用意されています。
内蔵GPUモデルでは、軽いゲームやFHD以下くらいの簡単な動画編集程度は行えると思いますが、重いゲームや動画編集はやや厳しいです。最安33万円台のPCで低性能な内蔵GPU搭載というのは明らかにコスパが悪いので、ビデオカード搭載モデルをおすすめします。
ビデオカード搭載モデルの場合は、最低性能の「RTX 4050」でも優れた性能を持っており、重めの動画編集やゲームもそこそこ快適に行えるレベルです。より上位の「RTX 4060」や「RTX A2000 Ada」では更に高い性能となります。
2 in 1タイプのPCでこれだけ高いグラフィック性能を備えた機種は他にほぼないので魅力的です。
重量は内蔵GPU利用モデルは約1.89kg、ビデオカード搭載モデルは約1.98kgとなっています。14.4インチにしては重めの重量で、側面下部には排熱のための通気口が設けられている関係上、厚みも22mmと結構あるので、モバイル性能は低めだと思います。
公称のバッテリー駆動時間は最大18~19時間と長いですが、microsoftの公称時間はスタンバイ時間を含むためあまり参考になりません。
とはいえ、18~19時間というのは他の機種と比べても長いですし、実際のWi-Fiテストでも輝度 150 cd/m²で大体8時間以上持続するので、仕様を考えればやや優れたバッテリー駆動時間だと思いますし、非常に効率に優れたGPUを搭載するため、動画再生などではより優れた性能を発揮するかもしれません。
一番少ないモデルでも512GBなので、特に重いデータを保存する前提なければ困ることはないと思います。また、MicroSDカードリーダーを搭載しており、SDカードを補助ストレージとして利用できます。
ただし、最安30万円以上のPCで512GBというのは微妙ではあると思います。
Surface Laptop Studio 2は、画面を手前にスライドさせて素早くタブレットモードに移行できる特殊なヒンジを採用し、非常に高い処理性能を備えた14.4インチと大きめの2 in 1 PCです。
ビデオカード搭載モデルもあり、重い動画編集やゲームなどにも対応することができます。
重量は重めで厚みはあるため、モバイル性能は高いとは言えませんが、重いグラフィック処理も含めた様々な用途にできる万能な機種として魅力があります。
ただし、ネックはやはり価格で、価格は発売時で336,380円の33万円以上とめちゃくちゃ高価です。
しかも、最小構成ではビデオカードが搭載されておらず性能コスパが悪いのでおすすめできず、ビデオカード搭載モデルだと最安約40万円と更に高価になります。
これだけの性能を備えた2 in 1 PCは貴重ですし、長時間バッテリー駆動の万能機種として長期利用を期待することができるので、多少高くても魅力はあるものの、さすがに高価すぎる印象です。
処理性能とコスパではもっと優れたゲーミングノートやクリエイターノートがたくさんあるので、予算が潤沢なので、高くても良いから万能で優れた機種が欲しいという人向けのハイエンドノートPCです。
旧モデル
Surface Pro 9 (Intel)【旧モデル】
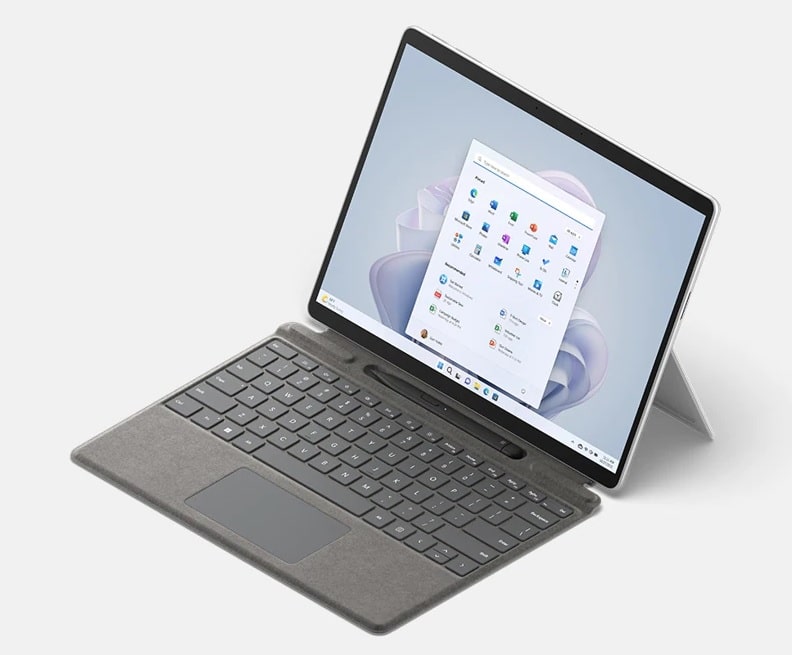
第12世代Core搭載の13インチの2in1タブレット
Surface Pro 9(Intel)は13インチサイズのタブレットPCです。本体には無段階調整のキックスタンドが付いており自立させる事ができます。また、別売りのタイプカバーを装着することでキーボードを利用する事ができ、2in1PCとしても運用できる汎用性の高さが魅力です。Surfaceシリーズの中でも特に人気が高いモデルです。
Pro 9ではCPUが前世代の第11世代Coreから第12世代Coreへとアップグレードされました。前世代では4コア8スレッド(Core i5以降)だったのが、10コア12スレッドとなり、コア数が大幅に増えたためマルチスレッド性能が大幅に向上しました。
CPU以外も微妙な違いはあるものの、機体は同じものなので、CPUが更新されWi-Fi 6Eに対応した以外はPro 8からほぼ据え置きといった仕様になっています。
CPUについてですが、従来の高性能コア(Pコア)は2コアだけになり、省スペース化と低消費電力動作に特化している代わりに性能や電力効率ではやや劣るEコアを8個搭載する仕様となっている点に注意です。この仕様によって、CPU全体としての電力効率は前世代から向上とは言い切れないレベルになっており、実際バッテリー持続時間もほぼ変わりません。そのため、重い処理を行わない場合には在庫処分価格となったPro 8の方がコスパが良い可能性がある点は留意しておくと良いかもしれません。
また、Surface Slim Pen 2を使用することで、触覚フィードバック機能を利用することができる珍しい機能を備えています。クリエイターの中には嬉しい人が居るかもしれません。
| スペック表 | |||
| 参考価格 | 157,250円 ~ 365,800円 (税込) ※2024年3月26日時点 | ||
|---|---|---|---|
| OS | Windows 11 Home | ||
| CPU | Core i7-1255U Core i5-1235U | ||
| RAM | 8GB / 16GB /32GB (LPDDR5) | ||
| SSD | 1TB / 512GB / 256GB / 128GB | ||
| GPU | Iris Xe G7 96EU Iris Xe G7 80EU | ||
| 画面 | 13インチ 最大120Hz タッチ対応 | ||
| 表面 | グレア(光沢あり) | ||
| 解像度 | 2880×1920 | ||
| Office | Microsoft Office Home and Business 2021 | ||
| バッテリー持続時間 | 公表値:最大15.5時間 | ||
| 無線機能 | IEEE 802.11 b / g / n / ac / ax (Wi-Fi 6E対応) Bluetooth 5.1 | ||
| その他機能 | カメラ | ||
| サイズ | 約 287x208x9.3 mm | ||
| 重量 | 約879g | ||
| インターフェース | USB Type-C(USB4.0/Thunderbolt4対応) x 2 | ||
| 生体認証 | 顔認証 | ||
| 備考 | キックスタンド付き タイプカバーは別売り | ||
CPUには「Core i5-1235U」もしくは「Core i7-1255U」が採用されており、タブレットとしては非常に高い処理性能を持ちます。
また、どちらも10コア(2P+8E)のCPUとなっており、Core i5とCore i7のどちらでもCPU性能は大して変わりません(後述のGPU性能は少しCore i7の方が高性能)。
比較的重めの処理にも対応できる性能となっており、軽い処理なら非常に快適に行うことができます。ただし、高性能コア(Pコア)は2コアのみの省電力性を重視したCPUとなっているため、重めの処理を前提とするには向かないCPUではある点に注意です。
ディスプレイは、タッチ対応の13インチの液晶です(アスペクト比3:2)。解像度は2880×1920と高く、ピクセル密度は267PPIと高くなっているため、繊細な画像表示が可能です。リフレッシュレート(最大fps)は最大120Hzとなっており、映像を滑らかに表示することが可能な他、色域も広めで、Gorilla Glass 5の記載もあるので強度も高いです。どの面を見ても品質の高いディスプレイです。イラスト制作等などのクリエイティブな用途でも十分使える性能だと思います。ただし、表面は光沢ありなので好みが分かれると思います。
また、厳密にはディスプレイ自体の機能ではないと思いますが、Surface Slim Pen 2を利用することで触覚フィードバック機能を利用することができます。他のタブレットでは聞いたことのない機能で、イラストなどで利用する人には嬉しいかもしれません。
GPUはCPU内蔵です。Core i5では「Iris Xe Graphics G7 80EU」、Core i7では「Iris Xe Graphics G7 96EU」となっており、EUというのが実行ユニット数を表しますが、Core i7の方が少し多いため、処理性能が少し高いです。
軽いゲームやFHD以下のデータ量の少ない簡単な動画編集なら快適に行えると思いますが、重いゲームやデータ量の多い動画・画像編集をするにはやはり性能不足感が否めません。
上記のような用途で使いたいなら、別の外部GPUを搭載したPCを検討することをおすすめします。
Surface Pro 9は、13インチで重量は879gです(本体のみ)。重量とサイズ的には持ち運びも苦ではないと思いますが、サイズの割にはやや重い方です。手で持って使うのはやや辛い重量だと思います。iPad Pro 12.9インチ(第6世代)だと約682gだったりします。
ただし、タイプカバーは約280gと軽量で、本体との合計重量は約1,159gです。タイプカバー搭載で13インチのノートPCとしては捉えるなら、やや軽量な部類になります。
バッテリー駆動時間は、一般的な使用方法を意識した測定でメーカー公表値最大15.5時間です。
ですが、これはスタンバイ時間を含むので、実際には特別優れている訳ではなく、輝度150 cd/m²のWi-Fiテストで大体7時間半~8時間程度と言われています。平均かやや短めといった具合です。
ただし、ノートパソコンよりは薄型軽量で、USB Type-Cから充電することが可能なため、ACアダプターの持ち歩きが必須ではないのでモバイル性能は低くないです。
総合的に見て、手で持って使うには重いためタブレットとしてはやや劣る汎用性ですが、PCに近い形の使い方を想定した場合のモバイル性能は優れている方だと思います。
ストレージはSSD(PCIe接続)となっており非常に高速です。ただし、最低の128GBだとやや物足りない感はあります。
また残念なことに、Pro 9ではmicro SDカードスロットが搭載していないので、補助容量を用意するのも難しいです。USB Type-Aポートもないので、一般的なUSBメモリも使いづらく、物理ストレージでの容量確保は全般的に難しいです。クラウドなどを上手く活用することが推奨されている感じだと思います。クリエイターの方や、容量を多く使いたい方は留意しておきましょう。
ただし、一応本体搭載のSSDは割と簡単に個人で交換できる仕様になったそうです(ただし、恐らく保証の範囲外になる)。M.2のType2230というメジャーでない規格となりますが、出来るだけ安くSSD容量を増やしたいという方は交換を検討しても良いかもしれません。
Surface Pro 9は、タブレットにしては優れた処理性能と非常に優れたディスプレイで、タイプカバーを利用すればPCのようなスタイルでも使える、13インチと大型の2 in 1タブレットです。
タイプカバーは別売りですが、無段階調整のキックスタンドは本体に付属しています。ディスプレイ性能の高さも相まって、特にイラストなどのクリエイティブ用途では非常に使いやすいと思います。そうでなくても、高いグラフィック性能を要する処理でなければ、様々な使い方に適用できる、非常に汎用性が高いのが魅力の機種です。
ただし、ネックはやはり価格です。最安でも15万円台からという価格に加え、タイプカバーを導入するには更に費用が必要になります。Office標準付属の点を考えれば、Officeが必要な人にとってはコスパは少し改善はするものの、やはり処理性能コスパは全体で見ると悪いのは確かなので、購入は予算と相談する必要があると思います。
Surface Pro 9 (5G/Arm)【旧モデル】
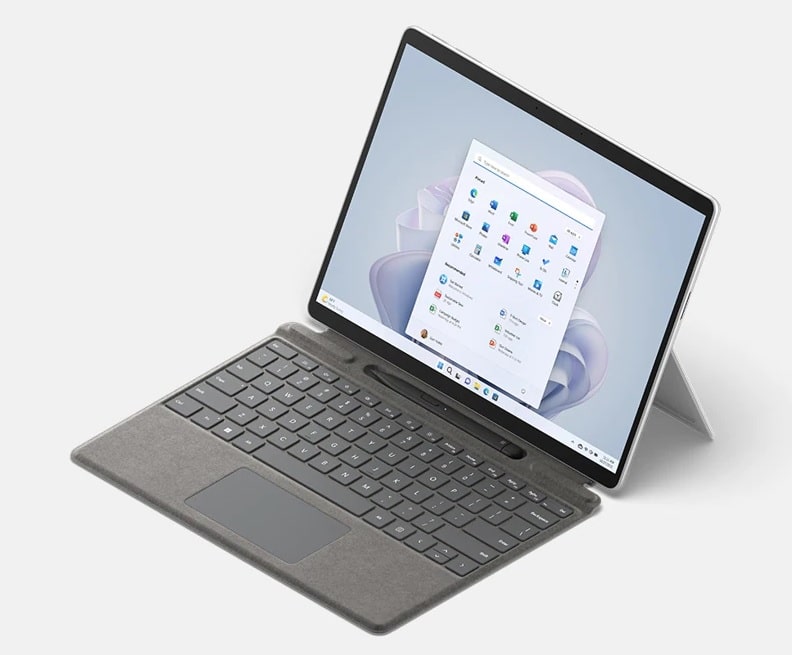
5G対応の13インチの2in1タブレット
Surface Pro 9(5G)は13インチサイズのタブレットPCです。NanoSIMおよびeSIMによるモバイル回線の5Gに対応しており、Wi-Fiなどに頼らずネット利用することができます。この5Gモデルは、従来のSurface Pro XがPro 9へと統合された形になっています。
本体には無段階調整のキックスタンドが付いており自立させる事ができます。また、別売りのタイプカバーを装着することでキーボードを利用する事ができ、2in1PCとしても運用できる汎用性の高さが魅力のモデルです。
プロセッサには「Microsoft SQ3」が採用されています。これは「Snapdragon 8cx Gen 3」と同様のものと言われており、一般的なWindows機ものとは異なるスマホ等に採用されるタイプのArmアーキテクチャのSoCとなっている点に注意が必要です。この設計の関係で一部のアプリケーションがネイティブでは利用できません(x64系のみ対応のアプリ)。x64系アプリは現在のWindowsでは主流なので、使えるアプリは結構制限されてしまうので事前に自分が使うアプリの対応状況を調べておく必要があります。また、その処理性能は先代機搭載の「Microsoft SQ1 / SQ2」よりも大きく向上しているものの、Intelモデルの「Core i5-1235U / Core i7-1255U」と比べると圧倒的に低い点も注意です。
ただし、Armアーキテクチャの最新SoC搭載なので、省電力性と電力効率は非常に優れており、バッテリー持続時間が公称で最大19時間と非常に長いのはメリットです。
また、Intelモデルと同様にSurface Slim Pen 2を使用することで、触覚フィードバック機能を利用することができる珍しい機能を備えています。クリエイターの中には嬉しい人が居るかもしれません。
Intelモデルのような、様々な環境や用途への対応はなく汎用性は劣りますが、大型のAndroidタブレットやiPadとして捉えるなら優れたものになっていると思います。
ただし、発売時で最安21万円台という価格はさすがに高価で、Pro 9のCore i5モデルにも処理性能は格段に劣る上に、ArmアーキテクチャというWindowsではやや致命的な汎用性の弱点もあります。そのため、コスパではPro 9の方が間違いなく圧倒的に上なので、どうしてもモバイル回線を使用したい場合か、Arm対応アプリしか基本使わない人でバッテリー性能を最も重視する人以外にはおすすめしにくい製品だと思います。
| スペック表 | |||
| 参考価格 | 216,480円 ~(税込) ※2023年9月26日時点 | ||
|---|---|---|---|
| OS | Windows 11 Home ARM | ||
| CPU | Microsoft SQ3 | ||
| RAM | 8GB / 16GB (LPDDR4x) | ||
| SSD | 512GB / 256GB / 128GB | ||
| GPU | Adreno 8CX Gen 3 | ||
| 画面 | 13インチ 最大120Hz タッチ対応 | ||
| 表面 | グレア(光沢あり) | ||
| 解像度 | 2880×1920 | ||
| Office | Microsoft Office Home and Business 2021 | ||
| バッテリー持続時間 | 公表値:最大19時間 | ||
| 無線機能 | IEEE 802.11 b / g / n / ac / ax (Wi-Fi 6E対応) Bluetooth 5.1 5G | ||
| その他機能 | カメラ | ||
| サイズ | 約 287x208x9.3 mm | ||
| 重量 | 約878g(Sub6) | ||
| インターフェース | USB Type-C(USB4.0/Thunderbolt4対応) x 2 | ||
| 生体認証 | 顔認証 | ||
| 備考 | キックスタンド付き | ||
プロセッサは「Microsoft SQ3」の1種類のみとなっています。これは「Snapdragon 8CX Gen 3」と同様のものと言われています。Armアーキテクチャ対応のSoCとしては2022年10月時点では最上位のハイエンドSoCとなっており、タブレット端末としては高性能です。
性能は「Microsoft SQ2」から大幅に向上しており、スマホで行うような軽い処理なら非常に快適にこなすことができます。
ただし、WindowsノートPCに搭載されるようなCPUと比較すると高性能とは言えない点には注意です。Intelモデルの「Core i5-1235U / Core i7-1255U」と比べると、ベンチマークでは1.5倍~2倍ほどIntelモデルの方が優秀な結果となっており、明らかに劣ります。価格も安い訳ではないので、処理性能コスパ重視ならIntelモデルの方がおすすめです。
ただし、こちらの方が消費電力の少なさや効率面では上回っているため、重い処理を行わない前提で、バッテリー駆動時間の方を重視したいならこちらのArm版の方が優れている可能性もあります。
Intel CPU版とほぼ同じです。一応、「Dolby Vision IQ対応」「自動カラーマネジメント対応」の記述が消え、動的リフレッシュレート対応ではなくなっている点では違いがありますが、基本的にはあまり重視はされない項目だと思います。
タッチ対応の13インチの液晶ディスプレイです(アスペクト比3:2)。解像度は2880×1920と高く、ピクセル密度は267PPIと高くなっているため、繊細な画像表示が可能です。リフレッシュレート(最大fps)は最大120Hzとなっており、映像を滑らかに表示することが可能な他、色域も広めで、Gorilla Glass 5の記載もあるので強度も高いです。どの面を見ても品質の高いディスプレイです。イラスト制作等などのクリエイティブな用途でも十分使える性能だと思います。ただし、表面は光沢ありなので好みが分かれると思います。
また、厳密にはディスプレイ自体の機能ではないと思いますが、Surface Slim Pen 2を利用することで触覚フィードバック機能を利用することができます。他のタブレットでは聞いたことのない機能で、イラストなどで利用する人には嬉しいかもしれません。
GPUはCPU内蔵です。「Adreno 8CX Gen 3」と記載されていますが、「Snapdragon 8cx Gen 3」搭載の「Adreno 690」と同様のものと言われています。
先代の「Surface Pro X」の頃よりはGPU性能も大幅に向上しており、タブレットで行う一般的なグラフィック処理や軽いゲームは快適に行える性能があります。イラスト関連の処理も快適だと思います。
ただし、やはりIntelモデルと比べるとGPUも大幅に劣る性能となっている上、Armアーキテクチャという点で高度なグラフィックソフトを存分に使えないケースも考えられますので、動画編集など重いグラフィック処理には基本的には向かないと思います。処理性能コスパを考えるならやはりIntelモデルの方が上です。
とはいえ、GPU性能もArmアーキテクチャのものとしてはハイエンドなので、スマホで行うような処理なら非常に快適で、消費電力や効率ではこちらが上回っていると思われるので、重い処理を基本行わずにバッテリー性能を重視するなら逆に優れている可能性もあります。
Surface Pro 9(SQ3版)は、13インチで重量は878gです(本体のみ)。重量とサイズ的には持ち運びも苦ではないと思いますが、サイズの割にはやや重い方です。手で持って使うのはやや辛い重量だと思います。iPad Pro 12.9インチ(第6世代)だと約682gだったりします。
ただし、タイプカバーは約280gと軽量で、本体との合計重量は約1,158gです。タイプカバー搭載で13インチのノートPCとしては捉えるなら、やや軽量な部類になります。
駆動時間は一般的な使用方法を意識した測定でメーカー公表値最大19時間です。バッテリーは容量が47.7Whとサイズの割に少ないながら、優れたバッテリー駆動時間です。Armアーキテクチャの恩恵はやはり確かにあるようです。
また、USB Type-Cから充電することが可能なため、ACアダプターの持ち歩きが必須ではありません。
手で持って使うには重い点は注意ですが、このサイズのWindowsタブレットとしては非常に優れたバッテリー性能を持つため、PCに近い形の使い方を想定した場合のモバイル性能は優れていると思います。
ストレージはSSD(PCIe接続)となっており非常に高速です。ただし、最低の128GBだとやや物足りない感はあります。
また残念なことに、Pro 9ではmicro SDカードスロットが搭載していないので、補助容量を用意するのも難しいです。USB Type-Aポートもないので、一般的なUSBメモリも使いづらく、物理ストレージでの容量確保は全般的に難しいです。クラウドなどを上手く活用することが推奨されている感じだと思います。クリエイターの方や、容量を多く使いたい方は留意しておきましょう。
ただし、一応本体搭載のSSDは割と簡単に個人で交換できる仕様になったそうです(ただし、恐らく保証の範囲外になる)。M.2のType2230というメジャーでない規格となりますが、出来るだけ安くSSD容量を増やしたいという方は交換を検討しても良いかもしれません。
Surface Pro 9 Arm版は、5Gのモバイル回線に対応しつつ、非常に優れたディスプレイ性能とバッテリー駆動時間の良さが魅力の機種です。持ち運びを頻繁に行う人に適した機種と言えると思います。
ただし、処理性能と性能コスパがIntel CPU版よりも大幅に劣っている点はやはりネックです。また、WindowsでのArmアーキテクチャのSoCの稼働も、現状ではやや不安が残る点ではあるため、総合的に見てIntel CPU版の方が正直無難な選択だとは思います。
Arm版を選ぶのは、性能の大きな差よりもモバイル回線対応やバッテリー駆動時間を優先する場合に限られると思います。
Surface Go 3【旧モデル】
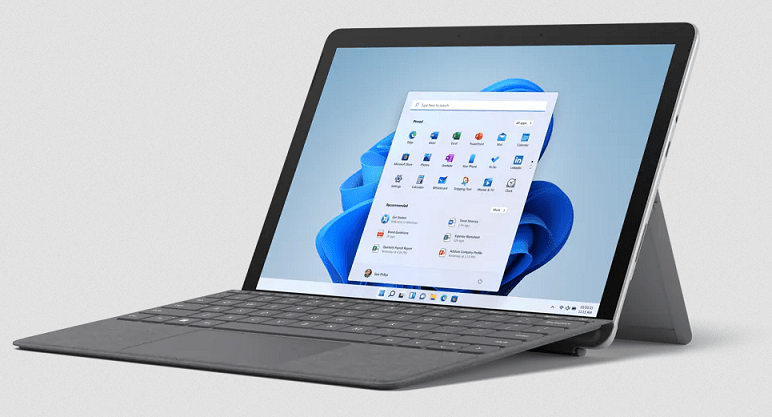
小型軽量でお手頃な10.5インチタブレット
Surface Go 3は10.5インチサイズのタブレットPCです。本体には無段階調整のキックスタンドが付いており自立させる事ができます。また、別売りのタイプカバーを装着することでキーボードを利用する事ができ、2in1PCとしても運用できます。
価格は公式だと6万円台中盤からとなっていて、他のSurface製品よりも安いのも魅力です。
ただし、古い低グレードCPUを採用しているため、処理性能は低く重い処理には向きません。また、バッテリー容量も少なく、他モデルよりも駆動時間は短めな点も注意が必要です。
| スペック表 | |||
| 参考価格 | 65,780円 ~ 107,580円(税込) ※2023年9月26日時点 | ||
|---|---|---|---|
| OS | Windows 11 Home(Sモード) | ||
| CPU | Core i3-10100Y Pentium Gold 6500Y | ||
| RAM | 4GB / 8GB | ||
| SSD | eMMC:64GB SSD:128GB / 256GB | ||
| GPU | 内蔵 (UHD 615) | ||
| 画面 | 10.5インチ タッチ対応 | ||
| 表面 | グレア(光沢あり) | ||
| 解像度 | 1920×1280 | ||
| Office | Microsoft Office Home and Business 2021 | ||
| バッテリー持続時間 | メーカー公表値:最大11時間 | ||
| 無線機能 | IEEE 802.11 b / g / n / ac / ax (Wi-Fi 6対応) LTE Bluetooth 5.0 | ||
| その他機能 | カメラ | ||
| サイズ | 約 245x175x8.3 mm | ||
| 重量 | Wi-Fi:約544g LTE:約553g | ||
| インターフェース | USB Type-C×1,SDカードスロット nano SIM×1(LTE対応モデルのみ) | ||
| 生体認証 | 顔認証 | ||
| 備考 | キックスタンド付き タイプカバーは別売り | ||
CPUは「Pentium Gold 6500Y」もしくは「Core i3-10100Y」が搭載されています。どちらも2コア4スレッドの超省電力CPUなので、処理性能は低いです。Web閲覧やオフィス作業をするには困らないレベルの性能だと思いますが、重めのソフトを使用したり複数のソフトを同時に使用したりしようとすると動作がモタつく事があるかもしれません。重い処理をさせるには厳しい性能です。
Core i3モデルの方がPentiumモデルよりはわずかに処理性能が高いですが、差は小さく、Core i3でも性能自体は高くはありません。元々重い処理をさせるための端末ではないですし、予算を抑えたいならPentiumで良いと思います。ただし、LTEモデルだとCore i3モデルしか選ぶことができません。
ディスプレイは、10.5インチの液晶です(アスペクト比3:2)。解像度は1920×1280とフルHDより少し縦長です。色域も広めで、安価な機種と比べると品質の高いディスプレイです。低価格モデルながらディスプレイ性能は悪くありません。
表面は光沢があるので好みが分かれると思います。
GPUはCPU内蔵の「Intel UHD Graphics 615」です。グラフィック性能は低いです。基本最低限のことが出来るレベルの性能で、動画視聴や簡単な画像編集くらいなら可能だと思いますが、その他の高いグラフィック性能を要求するような処理は厳しいです。
重量はWi-Fiモデルだと544g、LTEモデルだと553gです。サイズが小さいので軽いです(このサイズのタブレットPCとしては平均的)。専用のタイプカバーは243g程度なので、タイプカバー込みでも800g未満と軽いです。
バッテリーは容量が28Whと少ないため、短めの駆動時間です。USB PDには対応しており、USB Type-Cで充電する事が可能なので、ACアダプターの持ち歩きが必須ではありません。
また、LTE対応モデルがあり、モバイル回線を使用可能です。ただし、LTE対応はCore i3モデルしかないこともあり、価格は大幅に高くなります。
小型で持ち運びは楽なのでモバイル性能は悪くはないですが、サイズの割にはやや重く、バッテリー駆動時間も短めなので、同サイズの競合機と比べるとやや劣るかなと思います。
64GBモデルではSSDより低速なeMMCが採用されているので注意が必要です。
そもそも、OSインストール分も考慮すると64GBではやや厳しめなので、128GB以上のモデルをおすすめします。128GB以上のモデルはPCIe SSDが採用されているので高速です。
Surface Go 3は、最安6万円台という安価さでOfficeを標準付属し、無段階調整のキックスタンドも本体に付属しているのが魅力の10.5インチタブレットです。
バッテリー駆動時間が短めなのと、処理性能が低い点はネックですが、特にOfficeが必要な方にとってはコスパは良い機種だと思います。
Surface Laptop 5 13.5インチ【旧モデル】

薄くて優れた機体性能の13.5インチノート
Surface Laptop 5 13.5インチモデルは、13.5インチの一般的なタイプのノートPC(クラムシェル型)です。14.5mmという薄さによるスリムさと、長いバッテリー持続時間が魅力のモデルです。
また、キーボード面についてはメタルボディだけでなくファブリック素材が使用されているモデルを選ぶことができ、一般的なノートPCとは肌触りや見た目が異なるものが用意されているのも特徴です。
5でCPUが第12世代Coreプロセッサになり、マルチスレッド性能が大幅に向上しました。先代までは価格の割に処理性能が低くコスパは悪い印象が強かったですが、それがやや改善されています。とはいえ、それでも価格の割には高い処理性能とは言えないのでそこは注意です。
インターフェース面ではSDカードスロットが無い点は注意が必要ですが、Pro 8/9と異なりUSB Type-Aを備える他、最安値モデルでもストレージ容量が256GBあるため、Proよりも少し使いやすいです。
| スペック表 | |||
| 参考価格 | 132,720円 ~ 237,690円 (税込) ※2023年9月26日時点 | ||
|---|---|---|---|
| OS | Windows 11 Home | ||
| CPU | Core i7-1255U Core i5-1235U | ||
| RAM | 8GB / 16GB / 32GB (LPDDR5X) | ||
| SSD | 256GB / 512GB / 1TB | ||
| GPU | Iris Xe G7 96EU Iris Xe G7 80EU | ||
| 画面 | 13.5インチ タッチ対応 | ||
| 表面 | グレア(光沢あり) | ||
| 解像度 | 2256×1504 | ||
| Office | Microsoft Office Home and Business 2021 | ||
| バッテリー持続時間 | 最大18時間 | ||
| 無線機能 | IEEE 802.11 b / g / n / ac / ax (Wi-Fi 6対応) Bluetooth 5.1 | ||
| その他機能 | カメラ | ||
| サイズ | 約 308x223x14.5 mm | ||
| 重量 | ファブリック:約1,272g メタル:約1,297g | ||
| インターフェース | USB 4.0/Thunderbolt 4 対応 USB-C x 1 USB Type-A x1 | ||
| 生体認証 | 顔認証 | ||
| 備考 | キーボード面にファブリック素材を選べる | ||
CPUは「Core i5-1235U」と「Core i7-1255U」の2種類です。どちらも10コア(2P+8E)のCPUとなっており、処理性能は低くありません。比較的重い処理にも対応できる性能がありますし、軽作業なら非常に快適です。ただし、高性能コア(Pコア)は2コアのみの省電力性を重視したCPUとなっているため、重めの処理を前提とするには向かないCPUではある点には注意です。
また、最安13万円台のクラムシェル型のノートPCとしては特別高性能ではなく、コスパという点では高くありません。最安モデルだとメモリは8GBでストレージも256GBと少ないです。
Proのような選択肢の少ない2 in 1タブレットなら多少高くても目を瞑れますが、クラムシェル型のノートPCは選択肢が非常に豊富で、より安価で高コスパ機種もたくさんあります。Officeが必要な場合にはコスパはやや改善されるため悪くはありませんが、その恩恵を受けれない場合にはコスパは良くないという点は留意しておいて損は無いと思います。
ディスプレイは、タッチ対応の13.5インチの液晶です(アスペクト比3:2)。解像度は2256×1504と高めです。色域も広めで、品質の高いディスプレイです。ただし、リフレッシュレートは60Hzとなっており滑らかな映像描写にはならないです。ディスプレイ単体で見れば優れていると思いますが、価格を考えれば良い訳ではありません。
表面は光沢ありなので、好みが分かれると思います。
また、パームレスト部がファブリック素材のものはGorilla Glass 3なのに対し、メタル仕上げのものはGorilla Glass 5となっている点でも微妙に違いあります。ただ、クラムシェルタイプのPCで画面の強度はそこまで重要ではないと思うので、個人的にはあまり気にする必要はないかなと思います。
GPUはCPU内蔵です。Core i5では「Iris Xe Graphics G7 80EU」、Core i7では「Iris Xe Graphics G7 96EU」となっており、実行ユニット数がCore i7の方が少し多いため、処理性能が少し高いです。
軽いゲームやFHD以下のデータ量の少ない簡単な動画編集なら快適に行えると思いますが、重いゲームやデータ量の多い動画・画像編集をするにはやはり性能不足感が否めません。
上記のような用途で使いたいなら、別の外部GPUを搭載したPCを検討することをおすすめします。
メタル仕様のものは1,297g、ファブリック仕様のものは1,272gです。画面サイズからすると平均的で、持ち運びも十分できるモバイルノートPCだと思います。ただし、14.5mmという薄さの割には思ったより軽くないです。
バッテリー駆動時間は、メーカー公表値では最大18時間と長いですが、microsoftの公称時間はスタンバイ時間を含むためあまり参考になりません。
とはいえ、18時間というのは他の機種と比べても長いので、優れたバッテリー性能を発揮するのではないかと思います。推測ですが、輝度 150 cd/m²のテストで大体9時間前後程度の持続になるのではないかと思います。
また、USB PDに対応しており、USB Type-Cで充電する事も可能なので、ACアダプターの持ち歩きが必須ではないです。
長めのバッテリー駆動時間に加え、薄型でサイズ通りの軽量さを持ち合わせており、モバイル性能は高いと思います。Surface Proよりも使いやすいキーボード・タッチパッドに加え、ディスプレイもタッチ機能に対応していますし、モバイルノートPCとしてのモバイル性能は上位になるのではないかと思います。
ストレージ容量は256GB~1TBです。256GBの場合は不安がありますが、最低限の容量は備えています。
最安13万円台のクラムシェル型でこの容量は少ないと思います。クラムシェル型はメイン機としての運用を考える人が多いと思うので、場合によっては致命的かもしれません。
ただ、SDカードスロットはありませんが、USB Type-Aポートがあるので、一般的なUSBメモリは普通に使うことができるため、補助容量として活用して運用することは可能です。
Surface Laptop 5(13.5インチ)は、モバイル性能の高さが魅力の使い勝手の良いサイズのノートPCです。
10コアの第12世代Core搭載により処理性能も比較的高いですし、クラムシェル型ながらタッチに対応しているのも良いです。
メモリとストレージの最小構成は8GB/256GBとなっており、最安13万円台という価格を考えれば明らかに微妙ではありますが、Officeが標準付属するので、Officeが必要な人はコスパがやや改善するため悪くはないと思います。
ただし、Surface Proなどと違い、このようなクラムシェル型のPCは他の選択肢が非常に豊富なので、Officeが必要無い方ならより高コスパで高性能な他の選択肢がたくさんある点は留意しておいて損はないかと思います。
Surface Laptop 5 15インチ【旧モデル】

薄くて軽量な15インチモバイルノート
Surface Laptop 5 15インチモデルは、14.7mmという薄さと15インチながら約1,560gという軽量さが魅力の、一般的なタイプのモバイルノートPCです(クラムシェル型)。
その仕様は大きめのノートPCを日常的に持ち歩きたい方に適しています。処理性能も高く、その他のディスプレイ等の機体性能も優れているので、据え置きのメイン機としても優れているのも嬉しいです。
ただし、15インチという小さくはないサイズにも関わらず、SDカードスロットとテンキーが付属していない点は注意が必要です。
| スペック表 | |||
| 参考価格 | 171,780円 ~ 321,083円 (税込) ※2023年9月26日時点 | ||
|---|---|---|---|
| OS | Windows 11 Home | ||
| CPU | Core i7-1255U | ||
| RAM | 8GB / 16GB / 32GB (LPDDR5X) | ||
| SSD | 256GB / 512GB / 1TB | ||
| GPU | Xe Graphics G7 96EU | ||
| 画面 | 15インチ タッチ対応 | ||
| 表面 | グレア(光沢あり) | ||
| 解像度 | 2496×1664 | ||
| Office | Microsoft Office Home and Business 2021 | ||
| バッテリー持続時間 | 最大 17時間 | ||
| 無線機能 | IEEE 802.11 b / g / n / ac / ax(Wi-Fi 6) Bluetooth 5.0 | ||
| その他機能 | カメラ | ||
| サイズ | 約 340x244x14.7 mm | ||
| 重量 | 約1,560g | ||
| インターフェース | USB 4.0/Thunderbolt 4 対応 USB-C x 1 USB-A 3.1 x 1 | ||
| 生体認証 | 顔認証 | ||
| 備考 | |||
CPUは「Core i7-1255U」の1種類です。10コア(2P+8E)CPUとなっており、比較的重い処理にも対応できる性能があり、軽い処理なら非常に快適です。
ただし、最安17万円台のPCのCPUとしては低めの処理性能です。高性能コア(Pコア)は2コアのみの省電力性を重視したCPUとなっているため、重めの処理を前提とするには向かないCPUではある点には注意です。
CPU自体の処理性能は「Core i5-1235U」とも大差ないですし、処理性能よりもモバイル性能を意識した機種だと思うので、Core i5採用でより安い機種があると嬉しかった感が正直あります。
ディスプレイは、タッチ対応の15インチ液晶です(アスペクト比3:2)。解像度は2496×1664と高く、繊細な画像表示が可能です。色域も広めで、Gorilla Glass 5の記載もあり、品質の高いディスプレイです。
ただし、リフレッシュレートは60Hzとなっているため、滑らかな描写にはならないのが残念です。最安17万円台という価格を考えれば120Hz以上には対応していて欲しかった感はあります。
また、表面は光沢ありなので、好みが分かれると思います。
GPUはCPU内蔵です。「Core i7-1255U」では「Iris Xe Graphics G7 96EU」となっており、軽いゲームやFHD以下のデータ量の少ない簡単な動画編集なら快適に行えると思います。ただし、重いゲームやデータ量の多い動画・画像編集をするにはやはり性能不足感が否めません。
上記のような用途で使いたいなら、別の外部GPUを搭載したPCを検討することをおすすめします。
15インチで重量は約1,560gで、厚さは14.7mmと薄型です。タッチ対応の15インチクラスの機種としては薄型軽量なので、大きめの画面サイズで持ち運びたい人に適しており、これが本機の最大の魅力だと思います。
公称のバッテリーの駆動時間は最大17時間です。しかし、microsoftの公称時間はスタンバイ時間を含むためあまり参考になりません。
実際には、輝度 150 cd/m²のWi-Fiテストで大体8.5~9時間程度の持続となっています。公称値ほどの良さはありませんが、平均よりもやや上といった具合で、優れたバッテリー性能です。
また、USB PDに対応しており、USB Type-Cで充電する事が可能なので、ACアダプターの持ち歩きが必須ではありません。
15インチクラスのPCとしては優れたモバイル性能のPCといえると思います。
容量は256GB/512GB/1TBの3種類が用意されています。
最安の17万円台だと256GBしかなく、価格を考えれば非常にコスパは悪いです。512GBにすると約2.5万円価格が上昇します。
ただ、256GBでもあまり大きなデータを保存しないなら大丈夫だとは思いますし、USB Type-Aポートがあるので、一般的なUSBメモリーも使えるため補助容量として使用することはできます。
ただ、やはり価格的にはもう少し容量を多くして欲しかった感はありますし、サイズ的にSDカードスロットも搭載しているとより嬉しかった感はあり、総合的にはやはり微妙な項目になると思います。
Surface Laptop 5(15インチ)は、15インチという画面サイズの割に軽い約1.56kgと厚み14.7mmの軽量薄型さが魅力の機種です。
その軽量薄型さながらバッテリー駆動時間も比較的長く、タッチ対応のディスプレイもあるので、15インチクラスとしては高いモバイル性能となっており、貴重な存在です。
ただし、価格は最安171,810円(2023年9月時点)と非常に高価で、特にメモリとストレージから見た価格が非常に高くてコスパは悪めなのがネックです。Officeが必要ならコスパが少し改善するため、その場合に大きめのモバイルPCが欲しい場合には選択肢に入る可能性はあるものの、クラムシェル型のPCは他の選択肢も豊富なので、あえて選ぶ必要性があるかは他機種を見てから考える方が良いと思います。