この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
Intelの主流CPUシリーズのCoreシリーズと、AMDの主流CPUシリーズのRyzenシリーズの違いについてざっくり解説しています。(Coreの末尾Xシリーズや、Ryzen Threadripperシリーズは除外しています)
デスクトップPC向けの主要世代(2025年12月26日時点)のものを対象としています。
掲載の情報は記事更新時点(2025年12月26日)のものであり、ご覧になっている際には異なる可能性があるため注意してください。また、価格は主に価格.comやAmazonを参考とした市場価格となっています。
主にデスクトップPC向けの新しい世代のCPUが対象
本記事は、PCの主流CPUであるIntelのCoreシリーズとAMDのRyzenシリーズ各種の主にデスクトップPC向けの市場で主要な新しめの世代のものを対象としています。
現在(2025年11月時点)で主要モデルとして扱うのは、Coreは「Core Ultra 200S(Arrow Lake) / Core 第14世代(Raptol Lake)」で、Ryzenは「Ryzen 7000~9000シリーズ(Zen 4 / Zen 5) / 5000シリーズの一部(~Zen 3)」です。
まずは、細かい数値を見ていく前に主要な「Core」と「Ryzen」の各性能についてざっくりとした比較を載せています。「なんとなく各シリーズの特徴を掴めれば」といった感じのものになります。
しっかりとした比較ではないため、そのことを頭の中に置いた上でご覧ください。
| Core Ultra 200 | Ryzen 9000 | Core 第13,14世代 | Ryzen 7000 | Ryzen 5000 | Ryzen 8000 ※内蔵GPUが魅力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コア Pコア:高性能コア Eコア:高効率コア | 10~24 コア Eコア:4~16コア | 6~16 コア | 4~24 コア Eコア:0~16コア | 6~16 コア | 6~16 コア | 4~8 コア |
| スレッド | 10~24スレッド | 12~32 スレッド | 8~32 スレッド Eコア:0~16スレッド | 12~32 スレッド | 12~32 スレッド | 8~16 スレッド |
| マルチスレッド性能 Cinebench R23 | Ultra 9 285K:★5.0 Ultra 9 285:★4.5 Ultra 7 265K:★4.75 Ultra 7 265:★4.25 Ultra 5 235~:★4.0 Ultra 5 225:★3.5 | Ryzen 9 9950系:★5.0 Ryzen 9 9900系:★4.5 Ryzen 7 9700~:★4.0 Ryzen 5 9600系:★3.5 | i9-14900K:★5.0 i7-14700K:★4.75 i7-14700:~★4.25 i5-14600K:★4.0 i5 -14500:★3.75 i5 -14400:★3.5 i3:★2.25 | Ryzen 9 7950系:★4.75~ Ryzen 9 7900系:★4.25~ Ryzen 7 7700~:★3.75 Ryzen 5 7600系:★3.25 | Ryzen 9 5900XT:★4.0 Ryzen 7 5700系:★3.25 Ryzen 5 5600系:★2.75 | Ryzen 7 8700系:★3.75 Ryzen 5 8600G:★3.25 Ryzen 5 8400F:★3.25 Ryzen 5 8500G:★2.75 |
| シングルスレッド性能 Cinebench R23 | Ultra 9(K):~2,380 Ultra 7(K):~2,200 Ultra 5(K):~2,140 Ultra 5(10コア):~1,900? | Ryzen 9:~2,253 Ryzen 7:~2,232 Ryzen 5:~2,217 | i9:~2,317 i7:~2,174 i5 K:~2,060 i5 K無:~1,940 i3:~1,720 | Ryzen 9:~2,070 Ryzen 7:~2,010 Ryzen 5:~1,980 | Ryzen 9:~1,640 Ryzen 7:~1,600 Ryzen 5:~1,570 | Ryzen 7:1,800 Ryzen 5:1,780 |
| ゲーミング性能 ※ハイエンドGPU使用時 | Ultra 7 / 9:★4.5 Ultra 5:★4.25 | 9000X3D:★5.0+ X3D以外:★4.5 | i7 / i9:★4.75 i5(K):★4.5 i5(K無し):★4.0 i3:★3.75~ | 7000X3D:★5.0 X3D以外:★4.5 | 5000全般: ~★4.0 | ★3.75+ |
| 参考価格 ※2025年12月時点 | Ultra 9:89,980円~ Ultra 7:46,980円~ Ultra 5(14コア):32,880円~ Ultra 5(10コア):26,900円~ | Ryzen 9(16コア):~115,500円 Ryzen 9(12コア):67,800円~ Ryzen 7:47,800円~ Ryzen 5:37,200円~ | Core i9:76,980円~ Core i7:49,800円~ Core i5:25,980円~ Core i3:13,980円~ | Ryzen 9:~129,800円 Ryzen 7:44,800円~ Ryzen 5:27,280円~ | Ryzen 9:~49,800円 Ryzen 7:24,480円~ Ryzen 5:15,980円~ | Ryzen 7:~47,800円 Ryzen 5:~31,800円 Ryzen 3:OEM |
| 対応メモリ ※公式最大速度 | DDR5-6400 | DDR5-5600 | DDR5-5600※ DDR5-4800 DDR4-3200 ※Core i5 K付き以降 | DDR5-5200 | DDR4-3200 | DDR5-5200 |
| 消費電力 Blender Test 平均消費電力 | K(9):~235W | 9:~220W 7(X3D):~155W 7:(X3D以外)~80W | K:~287W K無し:~65W | X:~237W X3D:~147W X無し:~88W | 全体的に少なめ ~約133W | 非常に少ない ※省電力モデルしかない ~88W |
| 内蔵GPU 3DMark Time Spy | ×~〇 ~2,330程度 ※末尾FはGPU非搭載 4コア(245~):2,330程度 3コア(235):1,860程度 2コア(225):1,100程度 | △ 2CU:720程度 | ×~△ ~800程度 ※末尾FはGPU非搭載 | ×~△ 2CU:720程度 ※末尾FはGPU非搭載 | ×~〇 Vega 8:1570程度 ※末尾GのみGPU搭載 現在は8000Gの方が良い | ×~◎ 780M:3,350程度 760M:2,700程度 740M:1,900程度 ※末尾FはGPU非搭載 |
| NPU | 〇 ~13TOPS | × | × | × | × | × / 〇 ~16TOPS ※860G以降で搭載 |
| 付属クーラー ※BOX版 | × / 〇 K付きは無し | × / 〇 X付きは無し | × / 〇 TDP:65W以下のみ付属 ※一部例外あり (性能は良くはない) | × / 〇 TDP:65W以下のみ付属 ※一部例外あり (性能は良くはない) | × / 〇 X付き以外は付属 (性能は良くはない) | 〇 基本付属 ※一部例外あり (性能は良くはない) |
各シリーズの特徴(良い点・気になる点)をざっくりとまとめています。ここで言及する「ゲーム性能」とは、基本的にハイエンドなグラフィックボードを使用した場合のものな点を留意してください。
Core Ultra 200
優れたマルチスレッド性能コスパ 比較的優れた内蔵GPU NPU搭載 やや高価

| 価格 | (2.5) |
| マルチコア性能コスパ (265K) | (3.5) (5.0) |
| ゲーム性能 | (3.5) |
| 消費電力・電力効率 (ゲーム時) | (4.0) (3.0) |
| 内蔵GPU (2~4コア) ※F版は無し | (3.5) (3.0) (2.0) |
| NPU | 〇(~13TOPS) |
Core Ultra 200シリーズは、数多くの刷新を伴うCoreの新世代です。
コアアーキテクチャの刷新だけでなく、プロセスの大幅微細化、タイル設計の採用、NPU搭載、内蔵GPU性能の向上などたくさんの改善が含まれます。多くの刷新を印象付けるためにブランド名まで変更されています。
そして、Intelは設計刷新による電力面の改善を特に大きくアピールしていました。
実際、電力面は先代と比べると大きく改善しています。
Core Ultra 200 の 前世代(14000番台)と比較した際の主なメリットは、このマルチスレッド効率の良さ、それからNPUの搭載、性能高めのGPU などとなっています。
Core Ultra 200では、多くの変更を含むものの、CPUのコア数と構成は前世代(第14世代Core)と同じで、マルチスレッド性能も同水準です。少し上回ってはいるものの、差は大体1割未満なので同等レベルです。
しかし、実は内部的には大きく変わっています。まず、Eコア(小型コア)の性能が格段に向上しました。そして、Pコアのハイパースレッディング(1コア2スレッド)が無くなり1コア1スレッドとなりました。これにより、コアあたりの消費電力が減り、効率が改善しています。最終的な性能こそほぼ変わらなかったですが、前世代で問題視されていた電力面が改善しているのは嬉しい点です。
しかし、上述のように前世代で大きく問題視された点が改善されても、Core Ultra 200の評価は正直低いです。その大きな理由は、グラボ利用時のゲーム性能が前世代から若干低下しているためです。ゲーム性能は競合のRyzenに対しても基本少し劣りますし、X3Dモデルが相手となると大きく劣っています。
ゲーム性能は非常に注目度が高い項目なので、これは結構致命的に感じる人が多いと思います。
ゲーム時の電力面や温度は前世代から改善していたり、良い点もあります。ただ、肝心の性能がダウンとなってしまっていると、中々評価し辛いところです。一応、Intelは2025年でのBIOS更新などでの改善を示唆しているものの、2月時点ではまだほとんど変わっていない状況なので、微妙な立ち位置です。
一応、既存CPUとの明確な優位性としては、NPUが搭載されている点があります。
ただし、これはゲーミングPCではあまり重視されない項目です。最近の高性能グラボは高いAI性能も持ち合わせているためです。
内蔵GPUの性能が先代から最大3倍程度に性能が向上し、軽いゲームなら快適にプレイできるくらいになった点も大きく改善した点ですが、こちらもゲーミングPCでは重視されない項目です。
新世代ということもあって、旧世代CPUよりはやや高価ですし、マザーボードも同様なので、総合的に見てゲーミングPC基準では微妙さばかりが気になるCPUとなっています。
Ryzen 9000(X3D)
トップのゲーム性能 優れた効率(ゲーム時) ものすごく高価
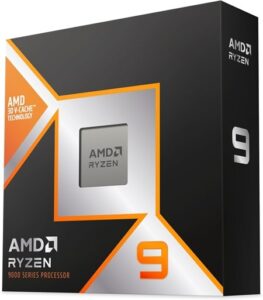
| 価格 | (1.5) |
| マルチコア性能コスパ | (1.5) |
| ゲーム性能 | (5.0) |
| 消費電力・電力効率 (ゲーム時) | (3.0) (4.5) |
| 内蔵GPU | (1.5) |
| NPU | 無し |
Ryzen 9000 X3Dはモデルは、ゲーム性能に特化したCPUで、2025年現在でトップのゲーム性能を持つCPUです。
64MBの追加L3キャッシュ「3D V-Cache」を搭載した「Zen 5」のRyzenとなっており、ゲーム時の性能が高められているのが大きな魅力です。X3D以外のRyzenや、競合のCoreを上回るゲーム性能を持ちます。
Ryzen 9000X3Dの第2世代の「3D V-Cache」は、CCDの下に配置されるようになったことにより、コアの冷却効率が高められました。これによりクロック増加やオーバークロックも可能になりました。
2025年4月時点では他モデルでは対抗できないレベルのトップのゲーミングCPUとなっています。
しかし、価格は非常に高価になっているのが大きなデメリットです。ベースモデル(非X3D)と比較すると、おおよそ2~3万円も高価になっています。それでいてCPUのコア数自体は変わらないので、マルチスレッド性能コスパは悪いです。
また、9000X3Dでは消費電力も先代(7000X3D)から増加した点は要注意です。9000X3Dでは、恐らくコアの冷却がしやすくなったこと最大温度が先代の89℃から同じ95℃になっていますが、この変更により負荷を高く保ち易くなったことで、性能が上がった反面で消費電力が増加したのではないかと推測されます。
電力制限などの調整をすることで負荷を下げることは可能なので、CPU自体が悪化した訳ではありませんが、先代の標準設定でも省電力で効率も非常に優れていた点は大きな魅力だったと思うので、電力面を重視する場合は調整が必要となったのは大衆的にはマイナスだと思っています。
Ryzen 9000(X3D以外)
優れた電力効率(マルチスレッド) やや高価
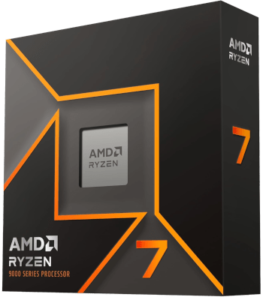
| 価格 | (2.5) |
| マルチコア性能コスパ | (3.0) |
| ゲーム性能 | (3.5+) |
| 消費電力・電力効率 (ゲーム時) | (4.0) |
| 内蔵GPU | (1.5) |
| NPU | 無し |
Ryzen 9000は「Zen 5」アーキテクチャ採用の最新シリーズです。X3Dモデルについては前述しているため、ここではXおよび無印モデルを対象としています。
Ryzen 9000(非X3D)は、優れたマルチスレッド効率と悪くないゲーム性能を持ち、2027年までの長期サポートが明言されているソケットAM5採用なのが嬉しいです。
しかし、前世代の「Zen 4」のRyzen 7000シリーズと比較するとわずかな向上に留まっています。新世代という感じは正直しないです。
消費電力が前世代からやや低下し、温度が大きめに改善している点は良いですが、総合コスパは大して変わらないので、価格がRyzen 7000シリーズと大差ない程度まで下がらない限りは有力にはならないのではないかと思います。
どうせ高価なCPUを選ぶなら、ゲームや効率で強力な「X3D」モデルを選択する方が満足度は高そうに思います。
第14世代 Core(14000番台)
超高コスパなマルチコア性能 比較的優れたゲーム性能 電力面が非常に悪い(K付き/高負荷時) 旧世代

| 価格 | (3.5) |
| マルチコア性能コスパ | (4.0) |
| ゲーム性能 | (4.0) |
| 消費電力・電力効率 (K付き / K無し) | (1.5) (3.0) |
| 内蔵GPU ※F版は無し | (1.5) |
| NPU | 無し |
第13,14世代のCore(14000/13000番台)は、処理性能コスパに優れたシリーズです。
価格の割に優れたマルチスレッドを持つ上、ゲーム性能もRyzen X3Dほどではないものの高いです。総合性能コスパ重視なら魅力的な選択肢です。
CPUの特徴としては、低コストのEコア(小型の効率コア)を大量に搭載することで、マルチスレッド性能を引き上げている点があります。現状の主要ゲームの性能は、Pコア(高性能コア)が8コアあればほぼ変わらないというデータがあるので、Pコアは最大8コアにして、後は低コストなEコアにすることで性能コスパを高めています。
ただし、EコアはPコアと比べると、コアあたりの処理性能では大幅に劣るので、全コアを使うような高負荷な処理の場合の電力効率がRyzenよりも悪いのが気になる点です。また、製造プロセスが10nmとなっており、Ryzen 7000~9000の4nm/5nmよりも劣っているため、設計面での効率もやや劣ります。
また、ソケットも既に旧世代化していることもあり、将来性としては微妙なシリーズでもあります。
そのため、安さ重視や雑に全体的な性能コスパを高めたい場合には良いですが、そこ以外では強みが少ないCPUとなっています。
設計面から高負荷時の効率面ではRyzenに敵わないので、個人的には電力設定が始めから低めのK無しモデルがおすすめです。K付きモデルを使う場合でも、電力設定を少し引き下げて使うことをおすすめしたいです。
Ryzen 7000(X3D)
非常に優れたゲーム性能 優れた電力効率 高価

| 価格 | (2.0) |
| マルチコア性能コスパ | (2.0) |
| ゲーム性能 | (4.5) |
| 消費電力・電力効率 | (4.5) |
| 内蔵GPU | (1.5) |
| NPU | 無し |
Ryzen 7000 X3Dはモデルは、64MBの追加L3キャッシュ「3D V-Cache」を搭載した「Zen 4」のRyzenです。これにより、特にゲーム時の性能が高められているのが魅力です。X3D以外のRyzenや、競合のCoreを上回るゲーム性能を持ちます。
更に、電力面が非常に優秀なのも7000X3Dの大きな魅力です。これは、コアの冷却がしにくい構造上、温度、クロック、消費電力の制限が厳しめになっていることに起因します。
この仕様によって、どの処理でも電力効率は非常に優れており、特にゲーム時の効率はものすごく優れているのが大きな魅力です。
ゲームだけでなく、様々な用途で優れた効率を求める場合にもおすすめできるCPUです。重い処理を前提とした総合的な実用コスパに優れたCPUだと思います。
しかし、価格が高価なのはデメリットです。新世代の9000X3Dほどではないものの、コア数を考えると価格が非常に高くい、マルチスレッド性能コスパは悪いです。
後からの調整の必要なく、非常に優れたゲーム性能と効率を手に入れられる点を考慮すれば、長い目で見たコスパは悪いとは思いませんが、初期費用はどうしても高くなるため、予算に応じて選択する必要があります。
Ryzen 7000(X3D以外)
高くはない価格 安価に最新ソケット(AM5)

| 価格 | (3.0) |
| マルチコア性能コスパ | (3.5) |
| ゲーム性能 | (3.5) |
| 消費電力・電力効率 | (4.0) |
| 内蔵GPU | (1.5) |
| NPU | 無し |
Ryzen 7000は「Zen 4」採用のシリーズです。X3Dモデルについては前述しているため、ここではXおよび無印モデルについて触れます。
Ryzen 7000の魅力は、Core(14000/13000番台)よりも優れたマルチスレッド効率を持つことと、ソケットのAM5が2027年までの長期サポートが明言されている点です。同じPCを出来るだけ長く使いたい場合にはおすすめできるシリーズです。
デメリットとしては、第14世代Core(Core 14000)やRyzen 5000と比べると高価ながら、目立って優秀な項目が無い点です。
安さや総合コスパ特化なら旧世代CPUの方が良く、ゲーム重視ならRyzen X3Dの方が良いという感じで、やや中途半端な存在にも思えます。
しかし、長期サポートが期待できるAM5に比較的安価に導入できるのは強みなので、そこでの需要があるCPUです。旧世代CPUはちょっと嫌だけど、費用もできるだけ抑えたいという場合に、丁度良いのがRyzen 7000だと思います。
Ryzen 8000 シリーズ
高性能内蔵GPU NPU搭載グラボ使用時のゲーム性能コスパは悪め
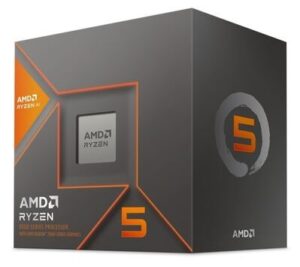
| 価格 | (3.0) |
| マルチコア性能コスパ | (2.5) |
| ゲーム性能(グラボ) | (3.0) |
| 消費電力・電力効率 | (4.0) |
| 内蔵GPU (8700G~8500G) ※F版は無し | (4.5) (4.0) (3.0) |
| NPU | 〇(~16TOPS) |
Ryzen 8000Gは強力な内蔵GPU(グラフィック)搭載が魅力のシリーズです。CPUも「Zen 4」なので世代も新しく、電力面も優秀です。
そのため、グラボを利用せずにグラフィック性能を出来るだけ高めたいなら一択レベルの強力なCPUです。ただし、末尾Fモデルでは内蔵GPUが使えないので要注意。
最上位の「Ryzen 7 8700G」に搭載される「Radeon 780M」では、「GeForce GTX 1650」に迫る性能を持っており、重めのゲームも可能なレベルになっています。更に、ゲームでは手軽に使えるフレーム生成機能「AFMF」も利用できるのも強みです。
省電力なので小型ケースなどでも採用しやすい点も良く、ライトユーザーには非常におすすめできるCPUです。
また、8600G以降のモデルではNPU(AIユニット)も搭載しています。高性能ではありませんが、将来性を考えてAI対応もしておきたい人には嬉しいと思います。
長期サポートが期待できるソケットAM5採用となっているため、安価にAM5を導入したい場合にも選択肢に入るシリーズとなっています。
Ryzen 5000(G以外)
非常に安価 コア性能は低め内蔵GPU無し
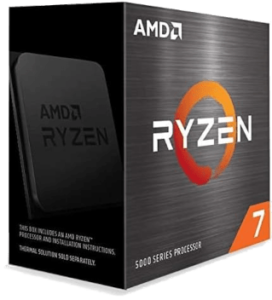
| 価格 | (4.5) |
| マルチコア性能コスパ | (4.0) |
| ゲーム性能 | (3.0+) |
| 消費電力・電力効率 | (3.5) |
| 内蔵GPU | 無し |
| NPU | 無し |
Ryzen 5000は「Zen 3」採用のシリーズです。旧世代となりますが、価格が安価で、電力面も悪くないのが魅力です。
Ryzen 7(8コア16スレッド)でも2万円台前半から販売が続けられており、マルチスレッド性能コスパが優れています。しかも、旧世代ながら省電力で扱い易くて効率も悪くないです。そのため、2025年現在でも低価格PC用のCPUとして強力な選択肢です。
旧世代なのはネックの部分でもありますが、マザーボードやメモリも旧世代で安価なものが採用できるため、PC全体の節約としては想像以上に大きくなります。
最新世代の安さ特化マザボを採用するくらいなら、旧世代のちょっと良いマザボを選びたいという場合にも魅力的です。
グラボ利用時のゲーム性能は最新世代には劣るものの、低価格PCではアッパーミドル以下のグラボ採用が中心であり、その性能帯なら大したネックにならないことが多いため、実質的に弱点も気にならないのも強さの要因です。
ここでは、各モデルナンバーごとで比較していきます。
Core シリーズとRyzen シリーズは、Core i9にはRyzen 9、Core i7にはRyzen 7といったように、各モデルナンバーごとに対抗製品が存在します。
そのため、各対抗製品同士を比較することによって、両者の差をより分かり易く知る事ができます。
以下から主要シリーズの主流製品をざっくりと比較しながら見ていきます。
- Coreでは高性能コア(Pコア)と高効率コア(Eコア)の2種類のコアが搭載されていますが、クロックは高性能コアのものを掲載しています。
- 内蔵GPUは末尾Fモデルでは搭載されない点に注意(Ryzen 5000以下は末尾G以外非搭載)。
- TDP(PL2)が実質の最大消費電力の目安です。PL1やベース電力は、PL2を維持するには冷却や電力に問題がある場合に適用されます。また、省電力モデルでは冷却などに問題がなくてもPL2の継続持続時間に制限が設けられており、一定時間後にPL1に移行するようになっているモデルもあります。
Core Ultra 9 / i9 と Ryzen 9
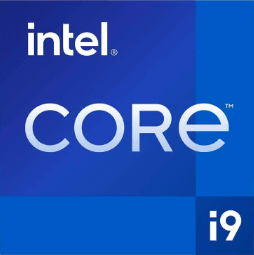

Core Ultra 9 / i9およびRyzen 9は主流CPUにおける最上級モデルです。いわゆるハイエンドと呼ばれる区分に含まれ、ハイエンドの中でも最上位の製品群となります。
主流CPUとしてトップの性能を誇り、両者素晴らしい性能を持っています。その代わり価格は非常に高く、人気モデルの価格はおおよそ7~11万円台となっています(2025年12月時点)。
| CPU名 | マルチ スレッド | シングル スレッド | ゲーミング※ | 消費電力 発熱 | |
|---|---|---|---|---|---|
 | Core Ultra 9(200) 24コア24スレッド 285K 等 | ★5.0 | ★5.0 | ★4.5 | ★2.0 |
 | Ryzen 9 9950系 16コア32スレッド 9950X、9950X3D | ★5.0 | ★5.0 | ★5.0(X3D) ★4.5 | ★2.0(X) |
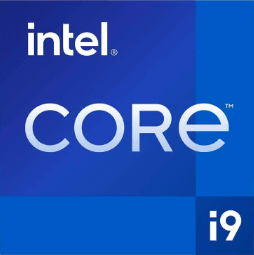 | Core i9(14世代) 24コア32スレッド 13900K、14900K 等 | ★5.0 | ★5.0 | ★4.75 | ★1.25 |
 | Ryzen 9 7950系 16コア32スレッド 7950X、7950X3D 等 | ★5.0 | ★4.75 | ★4.75(X3D) ★4.5(その他) | ★2.75(X3D) ★1.75(X) |
 | Ryzen 9 9900系 12コア24スレッド 9900X、9900X3D | ★4.5 | ★5.0 | ★5.0(X3D) ★4.5 | ★2.75 |
 | Ryzen 9 7900系 12コア24スレッド 7900X、7900X3D 等 | ★4.5 | ★4.75 | ★4.75(X3D) ★4.5(その他) | ★4.0(無印) ★3.0(X3D) ★2.25(X) |
 | Ryzen 9(5000番台) 12/16コア 24/32スレッド 5900X、5950X 等 | ★4.5(16コア) ★4.0(12コア) | ★3.75 | ★4.0 | ★3.25 |
Core Ultra 9 / i9とRyzen 9の人気モデルを一部抜粋して比較しています。クロックは最も高性能なコアのものです。
| CPU | Cinebench R23 Multi | コア/ スレッド | 動作クロック 定格/最大 | TDP (PBP/PL1) | TDP (PL2) | コスパ | 電力効率 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D | 42,369 | 16/32 | 4.3 / 5.7GHz | 170W | 230W | 115,500円 | ||
| Ryzen 9 9950X | 42,349 | 16/32 | 4.3 / 5.7GHz | 170W | 230W | 88,690円 | ||
| Core Ultra 9 285K | 41,989 | 24/24 | 3.7 / 5.7GHz | 125W | 250W | 89,980円 | ||
| Core i9-14900K | 39,203 | 24/32 | 3.2 / 6.0GHz | 125W | 253W | 80,980円 | ||
| Core i9-14900KF | 39,275 | 24/32 | 3.2 / 6.0GHz | 125W | 253W | 75,980円 | ||
| Ryzen 9 7950X | 38,402 | 16/32 | 4.5 / 5.7GHz | 170W | 230W | 82,800円 | ||
| Ryzen 9 7950X3D | 37,436 | 16/32 | 4.2 / 5.7GHz | 120W | 162W | 129,800円 | ||
| Ryzen 9 9900X3D | 34,004 | 12/24 | 4.4 / 5.5GHz | 120W | 162W | 94,980円 | ||
| Core i9-14900 | 33,264 | 24/32 | 2.0 / 5.8GHz | 65W | 219W | 84,800円 | ||
| Core i9-14900F | 35,233 | 24/32 | 2.0 / 5.8GHz | 65W | 219W | 82,800円 | ||
| Core Ultra 9 285 | 33,299 | 24/24 | 2.5 / 5.6GHz | 65W | 182W | 94,980円 | ||
| Ryzen 9 9900X | 32,876 | 12/24 | 4.4 / 5.6GHz | 120W | 162W | 67,800円 | ||
| Ryzen 9 7900X | 29,477 | 12/24 | 4.7 / 5.6GHz | 170W | 230W | 58,980円 | ||
| Ryzen 9 5900XT | 27,986 | 16/32 | 3.3 / 4.8GHz | 105W | 142W | 49,800円 | ||
| Ryzen 9 7900X3D | 27,450 | 12/24 | 4.4 / 5.6GHz | 120W | 162W | 109,980円 | ||
| Ryzen 9 7900 | 25,062 | 12/24 | 3.7 / 5.4GHz | 65W | 88W | 59,980円 |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D | |
| Ryzen 9 9950X | |
| Core Ultra 9 285K | |
| Core i9-14900K | |
| Ryzen 9 7950X | |
| Ryzen 9 7950X3D | |
| Core i9-13900 | |
| Ryzen 9 9900X | |
| Ryzen 9 7900X | |
| Ryzen 9 5900XT | |
| Core i9-12900K | |
| Ryzen 9 7900X3D | |
| Ryzen 9 7900 | |
| Ryzen 9 5900X |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Core i9-14900K | |
| Ryzen 9 7950X3D | |
| Core i9-13900K | |
| Ryzen 9 9950X | |
| Ryzen 9 9900X | |
| Ryzen 9 7950X | |
| Core Ultra 9 285K | |
| Ryzen 9 7900X | |
| Ryzen 9 7900 | |
| Core i9-12900K | |
| Ryzen 9 5950X | |
| Ryzen 9 5900X |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Ryzen 9 7900 | |
| Ryzen 9 5950X | |
| Ryzen 9 5900X | |
| Ryzen 9 7950X3D | |
| Ryzen 9 9900X | |
| Ryzen 9 7900X | |
| Ryzen 9 9950X3D | |
| Ryzen 9 9950X | |
| Core Ultra 9 285K | |
| Core i9-12900K | |
| Ryzen 9 7950X | |
| Core i9-13900K | |
| Core i9-14900K |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Ryzen 9 7950X3D | |
| Ryzen 9 7900 | |
| Core Ultra 9 285K | |
| Core i9-12900K | |
| Ryzen 9 5900X | |
| Ryzen 9 9900X | |
| Ryzen 9 9950X | |
| Ryzen 9 7900X | |
| Ryzen 9 5950X | |
| Ryzen 9 7950X | |
| Core i9-13900K | |
| Core i9-14900K |
下記からは、一部のCPUをピックアップして、所感をざっくりと触れていきます。
Core Ultra 9 285K:競合に劣るゲーム性能が懸念点。NPU搭載をどれだけ重視するか
超多コアで非常に優れたマルチスレッド性能を持つ「Core Ultra 9 285K」です。
24コア(8P+16E)による圧倒的マルチスレッド性能に加え、NPUと内蔵GPUも一般用途なら実用的なものが搭載されているのも魅力です。
ハイパースレッディングが廃止され、Pコアが先代の1コア2スレッドから1コア1スレッドになりましたが、Eコアの性能が格段に向上しているため、最終的なマルチスレッド性能は逆に少し向上しています。「Ryzen 9 9950X」や「Core i9-14900K」を少し上回る圧倒的な性能です。
むしろハイパースレッディング廃止のおかげで高負荷時の電力効率は向上したため、電力面での悪評が凄かった14900Kよりもかなり扱い易くなっています。
ただし、ゲーム性能が競合に劣るのがハイエンドCPUとしては致命的に感じるところです。「Ryzen 9 9950X」や「Core i9-14900K」にも若干劣り、「Ryzen 9 9950X3D / 7950X3D」を含むRyzen X3Dには大きく劣るゲーム性能です。
ゲーム時の電力・温度面は先代よりは改善しているものの、これは先代が悪すぎたのが大きいので、今回の「Core Ultra 9 285K」も普通に悪い部類です。コア数の割には優秀だよねってレベルです。当然、Ryzen X3Dモデルを上回るほどではなく、やはり肝心のゲーム自体のパフォーマンスが劣っていると評価は難しいです。
性能だけ見ると正直微妙感がありますが、明確な優位性としては「NPU」の搭載があります。最大13TOPSなので高性能ではありませんが、競合のRyzen 9000や前世代ではNPUは搭載されていません。今後のAIの将来性を見ると気になる項目です。
ただし、最近の高性能なグラボはAI性能も非常に高いので、ゲーミングPCのCPUのNPU搭載に大きな優位性があるかと言われるとそうでもない点は留意。GPUからAI処理を切り分けられるケースがあるということをどれだけメリットに感じるかという感じですね。
また、ゲーム以外の多くのアプリケーション動作においては先代を上回る結果を残しているため、低いゲーム性能も恐らく最適化の問題で、今後のBIOSアップデート等で改善する可能性もあるので、そこ次第でもあると思います。
Ryzen 9 9950X3D / 7950X3D:トップクラスのマルチスレッド性能とゲーム性能を併せ持つ
Ryzen 9 のX3Dモデルは、非常に優れたゲーム性能とマルチスレッド性能を併せ持つハイエンドCPUです。
ゲーミングPCではあまり恩恵のない内蔵のNPUやGPUを除けば、総合性能では現状トップと言えるモデルなので、予算に糸目を付けない場合には最高の選択肢です。
CPUは16コア32スレッドによる非常に優れたマルチスレッド性能に持つ上、片方のCCD(8コアのまとまり)で「3D V-Cache」という追加のキャッシュメモリが搭載されていることで、合計128MBという驚異的なL3キャッシュを備えており、競合モデルよりもゲーム性能で優れているのが魅力です。「Core Ultra 9 285K」や「Core i9-14900K」を上回るゲーム性能です。
しかし、その代わりにものすごく高価な点が大きなデメリットです。
まず、16コアモデルは2025年6月時点で10万円を大きく超える価格となっており、「Ryzen 9 9950X3D」は約12万円です。
マルチスレッド性能だけで見れば「Ryzen 9 9950X」「Core i9-14900K」「Core Ultra 9 285K」と同レベルなのに2~4万円も高価です。
ゲーム性能で見ても8万円台の「Ryzen 7 9800X3D」にはわずかに及ばず、6万円台の「Ryzen 7 7800X3D」を若干超えるレベルです(3D V-Cacheの設計上、現状は8コアモデルの方が処理効率が若干良い)。
一つのCPUで各方面でトップクラスの性能を備えるのは大きな魅力ですが、各性能で分けて見ると2~4万円安く同等以上の選択肢があるため、実用コスパはどうなのか、と気になるCPUです。
ただし、個人的には多少高価だとしても価値を感じれる総合性能はあると思うCPUです。
また、9950X3Dは先代よりも性能が向上した反面、標準設定では消費電力が増加しているため、先代のように電力面でも優秀なCPUにしたいなら後から調整が必要になった点には注意が必要です。
Core i9-14900K:性能は良いけど、電力面はかなり悪い
「Core i9-14900K/13900K」は、24コア32スレッドによる非常に優れたマルチスレッド性能と、優れたゲーム性能が魅力のハイエンドCPUです。
その性能は素晴らしいですが、気になるのは電力面です。めちゃくちゃ悪いです。
消費電力が非常に多いため、CPUクーラーは水冷が必須レベルになりますし、電力効率もRyzenに劣っているため、電力・発熱面を気にするならおすすめはできないCPUです。
使うにしても、ある程度電力を制限して利用することをおすすめしたいCPUとなっています。
上述の理由から、そこまでおすすめのモデルではないのですが、旧世代&電力面の懸念からコア数の割にはかなり安価になったため、電力面を抜きにしたコスパの良さは非常に良いです。
個人的には、どうせ高い費用を掛けるなら多少の費用を追加しても「Ryzen 9 9950X3D / 7950X3D」を選ぶことをおすすめしたいですが、人によって評価が分かれるCPUだと思います。
また、既に旧世代のCPUなので、マザーボードも旧世代のソケット・チップセットのものが必要となるため、将来的にCPU交換などを考慮するなら微妙な点には注意。
Ryzen 9 9950X / 7950X:優れたマルチスレッド効率が魅力だが、ゲームではX3DやCore i9の方が強い
「Ryzen 9 9950X / 7950X」は16コア32スレッドによる非常に優れたマルチスレッド性能と、優れたマルチスレッド効率が魅力のCPUです。
9950Xと7950Xはアーキテクチャが異なるものの、基本的な特徴はそのままに少し強化された感じなので、まとめて扱うことにします。
マルチスレッド性能は強力なコスパと効率を備えたハイエンドCPUですが、ゲーム性能ではCore i9-14900KやRyzen 7000X3Dに少し劣るのが弱点です。
また、標準設定では水冷推奨レベルで消費電力が多く、14900Kほどでないものの扱いにくいのもやや気になります。
確かにマルチスレッド性能と効率に限れば強力ではあるのですが、そこもRyzen 9 7950X3Dと実用性を画するほどの差がないですし、ほとんどの消費者にとってはゲーム性能と電力面の良さの方が重要度が高いので、一般層の需要はそこまで高くないと思うCPUです。これを買うくらいならX3Dを買いたいと思う人が多い印象です。
Ryzen 9 7900 ~ 9900X:優れたマルチスレッド性能と効率。Ryzen 7 ではコア数に不安がある人向け
「Ryzen 9 7900 ~ 9900X」は12コア24スレッドでコスパが良く、コア数の割には省電力なCPUです。
価格は2025年12月時点では6万円前後~7万円程度なので、どちらかというとCore の「7」に近い立ち位置のCPUです。
このCPUの魅力は、Ryzen 7よりも大きく優れたマルチスレッド性能を持ちつつ。省電力さと非常に優れたマルチスレッド効率も持っている点です。
そのため、Ryzen 7では少しマルチスレッド性能に不安があるけど、そこまで大幅な追加費用は掛けたくないという人におすすめのCPUです。
また、7900X以外はコア数の割には省電力となっているため、マルチスレッド処理&ゲーム時の双方の電力効率が悪くないのも魅力です。
更に、Ryzen 9 7900(Xが付かないモデル)では「Wraith Prism RGB」クーラーが付属し、これが付属品にしては悪くない性能です。標準の最大88Wなら実用レベルなので、費用を抑える選択肢として考えることができるのも強みです。
突出した性能やコスパやゲーム性能の高さこそありませんが、全体的に高水準な性能があり、電力面の良さ、AM5の長期サポートの期待、他の「9」よりは安価な価格を提供してくれます。
目先のコスパや性能よりもバランス重視の思考の人向きのCPUとしては割とおすすめできるCPUです。
Core Ultra 7 / i7 と Ryzen 7
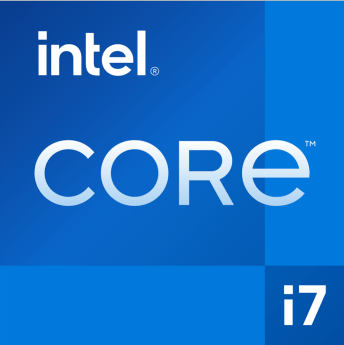

Core Ultra 7 / i7およびRyzen 7は主流CPUにおける上級モデル(上から2番目)です。立ち位置はハイクラスと呼ばれる区分に入りますが、現在では性能が非常に高くなっているので、ハイエンドと評しても良いレベルです。
人気モデルの価格はおおよそ4万円中盤~6万円程度となっています(2025年6月末時点)。
性能は9モデルよりはやや劣るものの、十分に高性能です。ハイエンド用途でも使える性能を持ち、ゲーミング性能だけなら9と大差ないことも多いので、性能もさほど妥協しない実用コスパ重視CPUとして人気のシリーズとなっています。
| CPU名 | マルチ スレッド | シングル スレッド | ゲーミング※ | 消費電力 発熱 | |
|---|---|---|---|---|---|
 | Core Ultra 7(200) 20コア20スレッド 265K 等 | ★4.75(K) ★4.25(K無し) | ★5.0 | ★4.5 | ★4.0(K無し) ★2.75(K) |
 | Ryzen 7 9800X3D 8コア16スレッド | ★4.0 | ★5.0 | ★5.0+ | ★4.25(ゲーム) ★2.75(全コア負荷) |
 | Ryzen 7 9700X 8コア16スレッド | ★3.75 | ★5.0 | ★4.5 | ★4.25 |
 | Core i7(第14世代) 20コア28スレッド 14700F、14700K 等 | ★4.75(K) ★4.0(K無し) | ★4.75 | ★4.75 | ★4.0(K無し) ★1.5(K) |
 | Ryzen 7 7800X3D 8コア16スレッド | ★3.75 | ★4.5 | ★5.0 | ★4.5(ゲーム) ★4.25(全コア負荷) |
 | Ryzen 7 7000(X3D以外) 8コア16スレッド 7700X 等 | ★3.75 | ★4.75 | ★4.5 | ★4.25(無印) ★3.0(X) |
 | Ryzen 7(8000G) 8コア16スレッド 8700G 等 高性能内蔵GPU | ★3.5 | ★4.25 | ★3.75 | ★4.0 |
 | Ryzen 7(5000番台) 8コア16スレッド 5700X 等 | ★3.25 | ★3.75 | ★4.5(X3D) ★4.0 | ★3.5 |
Core Ultra 7 / i7とRyzen 7の人気モデルを一部抜粋して比較しています。
| CPU | Cinebench R23 Multi | コア/ スレッド | 動作クロック 定格/最大 | TDP (PBP/PL1) | TDP (PL2) | コスパ | 電力効率 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 7 265K | 35,812 | 20/20 | 3.9 / 5.5GHz | 125W | 250W | 47,980円 | ||
| Core Ultra 7 265KF | 36,012 | 20/20 | 3.9 / 5.5GHz | 125W | 250W | 45,480円 | ||
| Core i7-14700K | 34,520 | 20/28 | 3.4 / 5.6GHz | 125W | 253W | 59,980円 | ||
| Core i7-14700KF | 34,643 | 20/28 | 3.4 / 5.6GHz | 125W | 253W | 54,980円 | ||
| Core i7-14700 | ~28,424 | 20/28 | 2.1 / 5.4GHz | 65W | 219W | 52,980円 | ||
| Core i7-14700F | ~28,450 | 20/28 | 2.1 / 5.4GHz | 65W | 219W | 49,980円 | ||
| Core Ultra 7 265 | ~28,281 | 20/20 | 2.4 / 5.3GHz | 65W | 182W | 58,360円 | ||
| Core Ultra 7 265F | ~27,767 | 20/20 | 2.4 / 5.3GHz | 65W | 182W | 55,620円 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | 22,911 | 8/16 | 4.7 / 5.2GHz | 120W | 162W | 74,980円 | ||
| Ryzen 7 9700X | 21,393 | 8/16 | 3.8 / 5.5GHz | 65W | 88W | 47,980円 | ||
| Ryzen 7 7700X | 20,135 | 8/16 | 4.5 / 5.4GHz | 105W | 142W | 44,980円 | ||
| Ryzen 7 7700 | 19,403 | 8/16 | 3.8 / 5.3GHz | 65W | 88W | 47,980円 | ||
| Ryzen 7 7800X3D | 18,475 | 8/16 | 4.2 / 5.0GHz | 120W | 162W | 64,800円 | ||
| Ryzen 7 8700G | 17,982 | 8/16 | 4.2 / 5.1GHz | 65W | 88W | 47,800円 | ||
| Ryzen 7 8700F | 17,772 | 8/16 | 4.1 / 5.1GHz | 65W | 88W | 40,800円 | ||
| Ryzen 7 5700X | 14,309 | 8/16 | 3.4 / 4.6GHz | 65W | 76W | 24,480円 | ||
| Ryzen 7 5700X3D | 13,615 | 8/16 | 3.0 / 4.1GHz | 105W | 142W |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Core Ultra 7 265K | |
| Core i7-14700K | |
| Core i7-13700K | |
| Core i7-14700(PL解除) | |
| Ryzen 7 9800X3D | |
| Ryzen 7 9700X | |
| Ryzen 7 7700X | |
| Core i7-14700(65W付近) | |
| Ryzen 7 7700 | |
| Ryzen 7 7800X3D | |
| Ryzen 7 8700G | |
| Ryzen 7 5700X |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Ryzen 7 9800X3D | |
| Ryzen 7 7800X3D | |
| Core i7-14700K | |
| Core i7-13700K | |
| Ryzen 7 9700X | |
| Ryzen 7 7700X | |
| Ryzen 7 7700 | |
| Core Ultra 7 265K | |
| Ryzen 7 5800X3D | |
| Core i7-12700K | |
| Ryzen 7 5700X | |
| Ryzen 7 5700G |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Ryzen 7 5700X | |
| Ryzen 7 7800X3D | |
| Ryzen 7 9700X | |
| Ryzen 7 7700 | |
| Ryzen 7 5700G | |
| Ryzen 7 5800X3D | |
| Ryzen 7 7700X | |
| Ryzen 7 9800X3D | |
| Core Ultra 7 265K | |
| Core i7-12700K | |
| Core i7-13700K | |
| Core i7-14700K |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Ryzen 7 5700G | |
| Ryzen 7 7800X3D | |
| Ryzen 7 5700X | |
| Ryzen 7 5800X3D | |
| Ryzen 7 7700 | |
| Ryzen 7 9800X3D | |
| Ryzen 7 7700X | |
| Ryzen 7 9700X | |
| Core i7-12700K | |
| Core Ultra 7 265K | |
| Core i7-13700K | |
| Core i7-14700K |
Core Ultra 7 265(K/KF/F):大幅な値下がりで、一気に有力CPUへ変貌
20コアを搭載するCoreの最新シリーズの「Core Ultra 7 265(K / KF / F)」です。
初動価格の高さとRyzenよりもゲーム性能が低かったことなどから人気が微妙でしたが、そのおかげで価格が大幅に下落したことにより有力になりました。
2025年12月時点では5万円以下から購入できる格安の3nmプロセス採用のハイクラスCPUとなっており、NPUも搭載しているので、非常にお得感があります。
前世代で不安視された電力面は格段に改善されている点でも選びやすくなっており、5万円程度なら十分有力なCPUです。
ただし、ゲーム性能が競合に劣る点は留意する必要があります。「Ryzen 7 9700X」にも少し劣り、「Ryzen 7 7800X3D / 9800X3D」には大きく劣ります。
最新世代のK付きの上位CPUながら、ゲーム性能は一つ前の世代の省電力CPUと競うレベルになっているという、悪い意味で珍しいCPUとなっています。
やはり最近ではゲーム性能は特に注目度の高い項目なので、やはり致命的に感じます。
しかし、価格がめちゃくちゃ値下がりしているため、多少のゲーミング性能の低さがあっても十分に魅力的になりました。ミドルハイ並みの価格でハイエンド級のマルチスレッド性能を手に入れられるのは魅力的です。
やはり、値下がりによってゲーミング性能の低さも気にならなくなっているのが良いです。2025年末時点では、Ryzen 7 9700Xと同じくらいの価格となっていますが、9700X相手ならゲーム性能差もそこまで大きくはなく、他の良さを考えれば十分に許容できるレベルだと思います。
ゲーム性能コスパは依然として悪めではあるものの、市場の立ち位置では致命的というほどではなくなっているので、納得感も大きくなりました。
更に、おまけでNPUも付いてきますし、GPUも内蔵としては優れた性能(FはGPU非搭載なので注意)です。
しかも、電力面も先代(14700K)から大きく改善しており、空冷でも高性能なクーラーなら運用が可能なレベルにまでになっています。※各上限値は高めに設定されているので、安定運用を目指すなら多少制限しておく方が安心ではありますが
発売当初の価格や評判のせいで良い印象を持っていない人も居ると思いますが、5万円なら普通におすすめできるCPUだと思います。
Ryzen 7 9800X3D:ゲーム最強クラスCPUだが、8コアにしては高すぎるので実用コスパに注意
ゲーム性能でトップ層に君臨するゲーム最強CPUです(2025年12月時点)。
「3D V-Cache」というL3キャッシュが64MB搭載されており、合計96MBという大容量L3キャッシュを備えます。そのおかげでゲーム性能が非常に優れているのが特徴です。ゲーム性能は一般消費者が特に意識する性能なので、そこが強力なのが大きいです。
先代の7800X3Dでは「3D V-Cache」がCCDの上にあることにより、コアの冷却が難しいという課題がありましたが、9800X3DではCCDの下に配置されるようになったため、コアの冷却がしやすくなり、クロックが上がった上にオーバークロックが可能になりました。
そのおかげで、マルチスレッド性能も先代の7800X3Dから20%以上向上し、8コアCPUとしては非常に強力となりました。
ただし、先代から消費電力が増えてしまっている点は注意。クロック上昇による性能増加の代償です。とはいえ、多少電力制限したとしてもゲーム性能の高さは十分保たれるので、気になる方は調整すれば良い話なので、大きなデメリットというほどではないです。
そんな感じで、ゲーム用としてはやはり非常に強力で魅力的な9800X3Dですが、一番のネックは価格です。7万円中盤程度となっており、8コアCPUとしては超高価です。マルチスレッド性能コスパは明らかに悪い点は要注意です。
しかも、ゲームで強力とは言っても、各レビューなどの評価は基本的に、あくまでハイエンドGPUで比較した場合の話です。
GPUの性能が下がるほどCPUがボトルネックになりにくくなるので、差がやや縮まる傾向がある点には留意しておきたいですすし、
1440pや4Kなど解像度が高くなる場合も、描写負荷が高まってGPUの方がボトルネックになりやすくなるので、CPUのゲーム性能差はでにくくなります。
また、ゲームの中にはキャッシュ容量がそこまで活きないタイトルもありますし、軽いゲームではモニターのリフレッシュレート上限のせいで性能向上が意味なかったりするケースもあります。
そのため、ゲームで強力なのは間違いないけど、状況次第では意味なかったりもするので、大幅な追加予算を掛ける価値があるとは言い切れません。
そのことを考慮すると、いくらゲームで強力でも、超高価な8コアCPUを導入するよりもGPUのグレードを一つ上げた方が実用性能・実用コスパは高まるというケースは割と多いと思いますので、雑に選ぶのではなく、慎重に検討したいCPUです。
総評としては、25万円~の予算でゲーム特化のPCを求めるなら、最有力となるCPUの一つだとは思いますが、マルチスレッド性能コスパは非常に悪いですし、ゲームにおいても必ず強力という訳でもないので、強みを理解した上で選びたいゲームCPUです。
Ryzen 7 5700X:旧世代だけど、非常に安価で超高コスパなCPU
「7」モデルで予算節約も考えた上でのコスパ重視で筆頭となるのは、「Ryzen 7 5700X」です。
旧世代のため各種性能は最新世代には劣るものの、2万円台前半という安さが非常に強力です。旧世代のおかげでマザーボードも安価な上、メモリも安価なDDR4なので、実質コスパは更に良くなります。
また、旧世代ながら電力面も優秀で、省電力・低発熱で効率も悪くないというのも選び易いです。
他の最新のCore i7 / Ryzen 7と比べるとマルチスレッド性能は大きく劣りはするものの、性能自体は十分に高性能と言えるレベルで一般用途は困ることはほとんどないです。
ゲーム性能が劣るのは気になる点だとは思いますが、このレベルの安さのCPUの場合、ハイエンドグラボと組み合わせることがほぼなくて、ミドルレンジ以下のGPUなら多少ゲーム性能が低くてもネックになりにくいので、意外と気にならない部分です。
むしろ、安さの分グラボのグレードを一つ上げることができるレベルですから、旧世代なのにゲーム面でも実質的にはマイナスではないというのがズルい強さ。
ちなみに、5700Xにも「3D V-Cache」を搭載した5700X3Dというモデルがあり、こちらならCPUのボトルネック問題も若干改善できます。ただし、最大クロックは下がったりしますし、価格も上がるのでこちらはやや評価が難しいです。
キャッシュ容量の恩恵を受けにくいゲームではむしろ5700Xに劣るケースもあるので、安さの強みを最大化するためにも、5700Xの方が安定の選択だと思います。
Core i7-14700(F):省電力で優れた総合コスパの旧世代CPU
Core i7-14700(F)は、20コア28スレッドによる高いマルチスレッド性能を持ちつつ、省電力で扱い易くて実用コスパが良いのが魅力の旧世代CPUです。
「7」モデルで高性能高コスパに特化したい場合の強力な選択肢です。
ただし、2025年6月時点では「Core Ultra 7 265K(F)」がほぼ同額になっているので、相対的に市場価値が薄まっている感は強めです。
また、性能の割には安価でコスパは良いですが、既に旧世代のCPUなので、マザーボードも旧世代のソケット・チップセットのものが必要となるため、将来的にCPU交換などを考慮するなら微妙な点にも注意。
Ryzen 7 7800X3D:旧世代化しても普通に強力なゲームCPU。効率も非常に良く、実用コスパに優れる
「Ryzen 7 7800X3D」は強力なゲーム性能と省電力性を併せ持つのが魅力のCPUです。ゲーム用CPUながら、一般用途での実用コスパも非常に高い人気CPUです。
7800X3Dは、「3D V-Cache」という追加のキャッシュメモリが64MBも追加で搭載されており、合計96MBという驚異的なL3キャッシュを備えているため、ゲーム性能が非常に優れているのが特徴です。ゲーム性能は一般消費者が特に意識する性能なので、そこが強力なのが大きいです。
また、3D V-Cacheがコアの上方に配置されている関係上、コアの冷却がしにくいという弱点があるのが7000X3Dなのですが、温度をできるだけ低く保つために最大温度が低めの89℃に設定されており、副次効果として消費電力が大幅に抑えられ、電力効率も向上しているという点も魅力です。
このように、優れたゲーム性能と電力面を持ちつつ、価格がCore i9やRyzen 9ほど高価でないため、ゲーム特化の実用コスパ重視CPUとして非常に優れており、特に人気度の高いRyzenです。
ただし、8コアCPUとしては非常に高価なため、マルチスレッド性能コスパは良くないという点があるのは注意です。
2025年12月時点で、7800X3Dは6万円前後程度ですが、同じ8コアの「Ryzen 7 7700」なら4万円ちょっとで買えますし、20コアの「Core Ultra 7 265K(F)」も4万円台から買えます。
計算するまでもなく、マルチスレッド性能コスパは超悪いです。
ただし、7800X3Dのマルチスレッド性能自体は低い訳ではなく、一般消費者にとっては十分な性能を備えているため、大きなデメリットとしては捉えられることが少ないです。
むしろ、「Core Ultra 7 265~ / Core i7-14700~」がオーバースペック感はあるので、無駄なマルチスレッド性能がゲーム性能や効率に振り分けられた、実用コスパが高いCPUとして、非常に人気となっています。
Ryzen 7 9700X:5万円以下になり魅力的になった無難なミドルCPU
Ryzen 7 9700Xは、「Zen 5」を搭載したRyzen 7のスタンダードモデルです。8コア16スレッド。
明確な強みこそないものの、価格もそこそこで選び易い無難なCPUという立ち位置です。
X付ながらTDPが65W~88Wとなったため、省電力で効率に優れるCPUとなっています。
発売当初は約7万円という価格でコスパが悪すぎましたが、値下がりが進行して2025年12月時点では4万円台になったので、普通に有力なミドルCPUです。
最新のX3Dや上位CPUと違って、低消費電力&低発熱CPUとしての魅力もあり、一般用途なら基本十分な性能があり、ゲーム性能もそこそこで、安すぎず高すぎないくらいの価格という、高みを求めない人にとっては凄く丁度良いCPUです。
後述の「Ryzen 7 7700X / 7700」と性能差は小さいので、そちらとの価格差に注意しつつ、お得な方を選びたいです。
Ryzen 7 7700 / 7700X:Ryzen 5 / Core i5 では不安がある人向けの安価な高コスパミドルCPU
「Ryzen 7 7700 / 7700X」は「Zen 4」の8コア16スレッドCPUです。
高くない価格でそこそこの性能と、長期サポートが期待できるAM5(ソケット)を導入できるということで、無難なミドルCPUという印象です。
「Ryzen 5 / Core i5」ではマルチスレッド性能に不安があるという人にとって非常に魅力的なモデルとなりました。
2025年12月時点では、20万円~25万円で総合コスパ特化のPCを求めるなら、最有力となるCPUの一つだと思います。
Ryzen 7 8700G:高性能内蔵GPU搭載で、重めのゲームにも対応可能に
「Ryzen 8000Gシリーズ」は高性能な内蔵GPUを搭載しているシリーズです。2025年12月時点ではIntelに対抗製品がないので、グラボ無しデスクトップPCを検討する際には独壇場のCPUです。
Ryzen 7では「Ryzen 7 8700G」が登場しています。CPUは8コア16スレッドで、GPUは12コアの「Radeon 780M」が搭載されています。
この「Radeon 780M」が内蔵GPUとしては非常に高い性能を持っているのが大きな魅力です。
ゲームのベンチマークでは「GTX 1650」に迫る性能となっており、少し古いエントリーグラボ並みの性能を持ちます。軽いゲームなら非常に快適ですし、重めのタイトルもある程度動かすことが可能なレベルです。
更に、2024年1月下旬にRadeon(RDNA 2以降)で「AFMF」というフレーム生成機能が手軽に使えるようになったこともかなり大きいです。
AFMF前提なら、ほんの数年前のエントリーグラボ並みのフレームレートを出すことができ、結構重めのゲームでもプレイ自体には支障が無いくらいの動作が可能です。
そのため、かなり重量級のゲームを想定したり、常に高fpsを安定させたい訳でないなら、ゲームでグラボの搭載は不要になったと言っても過言ではないレベルです。
また、標準TDPが65W~88Wに設定されているため、非常に省電力・低発熱で扱い易いのも嬉しいです。
動画編集についても、フルHD以下のものなら意外と対応できるレベルですし、高い性能を求めないライトユーザーならこれ一つで全ての処理に対応できるレベルのものとなっており、その汎用性の高さが非常に魅力的です。
ゲームコスパだけを考えるならグラボ搭載の方が高いという点は留意しておくべきですが、どうしてもグラボを搭載したくない場合には非常に有力なCPUです。
また、一つ下位の「Ryzen 5 8600G」とどちらが良いのか迷う方も多いと思いますので、そちらも少し触れておきます。8700Gと8600Gの主な違いは、CPUのコア数が8→6、GPUコア数も12→8になる点です。特にGPUのコア数差が大きいのが気になる点だと思いますが、8600Gでも意外とコア数差ほどの性能能低下はなく、マイナス2割程度までに留まっています。そのため、高いCPU性能を求める訳でないなら、8600Gの方が実用コスパは少し上になると思うので、CPU性能も出来るだけ高くしておきたいなら8700G、内蔵GPUさえそれなりに使えればOKという場合には8600Gという感じで、用途や好みに応じて選択すると良いと思います。
Core Ultra 5 / i5 と Ryzen 5
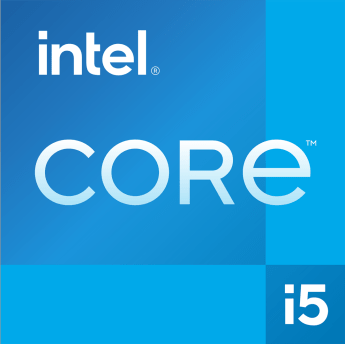
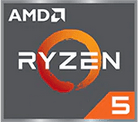
Core Ultra 5 / i5およびRyzen 5は主流CPUにおける中級モデルです。いわゆるミドルレンジに区分されます。
中級とはいっても現在では十分に高性能で、「可・不可」でいえば不可能な事はないレベルの高性能さです。数年前のハイエンドCPUを大きく上回るレベルの性能を持っています。価格はやや幅が広く、おおよそ2万円台~4万円となっています。
| CPU名 | マルチ スレッド | シングル スレッド | ゲーミング※ | 消費電力 発熱 | |
|---|---|---|---|---|---|
 | Core Ultra 5 235~ 14コア(6P+8E) 14スレッド | ★4.0(K) ★3.75(K無し) | ★4.75(K) ★4.5(K無し) | ★4.25 | ★4.25(K無し) ★3.75(K) |
 | Core i5-14600K(F) Core i5-13600K(F) 14コア(6P+8E) 20スレッド | ★4.0 | ★4.5 | ★4.5 | ★2.75 |
 | Core Ultra 5 225(F) 10コア(6P+4E) 10スレッド | ★3.5 | ★4.5 | ★4.25 | ★4.25 |
 | Core i5-14500 Core i5-13500 14コア(6P+8E) 20スレッド | ★3.75 | ★4.25 | ★4.25 | ★4.0 |
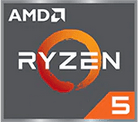 | Ryzen 5 9600系 6コア12スレッド Ryzen 5 9600 等 | ★3.75 | ★4.75 | ★4.25 | ★4.0 |
 | Core i5-14400(F) Core i5-13400(F) 10コア(6P+4E) 16スレッド | ★3.5 | ★4.0 | ★4.0 | ★4.0 |
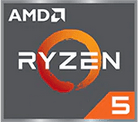 | Ryzen 5(7000) 6コア12スレッド 7600X 等 | ★3.5 | ★4.25 | ★4.25 | ★4.0(無印) ★3.5(X) |
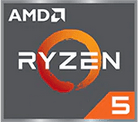 | Ryzen 5(8000G) 6コア12スレッド 8600G 等 高性能内蔵GPU | ★3.25 | ★4.0 | ★3.75 | ★4.0 |
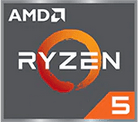 | Ryzen 5(5000番台) 6コア12スレッド 5600X 等 | ★2.75 | ★3.5 | ★3.75 | ★4.0 |
Core i5とRyzen 5の人気モデルを一部抜粋して比較しています。
| CPU | Cinebench R23 Multi | コア/ スレッド | 動作クロック 定格/最大 | TDP (PBP/PL1) | TDP (PL2) | コスパ | 電力効率 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 5 245K | 25,124 | 14/14 | 4.2 / 5.2GHz | 125W | 159W | 34,980円 | ||
| Core Ultra 5 245KF | 25,188 | 14/14 | 4.2 / 5.2GHz | 125W | 159W | 32,880円 | ||
| Core i5-14600K | 24,262 | 14/20 | 3.5 / 5.3GHz | 125W | 181W | 35,980円 | ||
| Core i5-14600KF | 24,645 | 14/20 | 3.5 / 5.3GHz | 125W | 181W | 35,980円 | ||
| Core Ultra 5 235 | 22,658 | 14/14 | 3.4 / 5.0GHz | 65W | 121W | 42,980円 | ||
| Core i5-14500 | 22,049 | 14/20 | 2.6 / 5.0GHz | 65W | 154W | 37,480円 | ||
| Ryzen 5 9600X | 17,067 | 6/12 | 3.9 / 5.4GHz | 65W | 88W | 37,200円 | ||
| Ryzen 5 9600 | 6/12 | 3.8 / 5.2GHz | 65W | 88W | 37,980円 | |||
| Ryzen 5 9500F | 6/12 | 3.8 / 5.2GHz | 65W | 88W | 37,480円 | |||
| Core Ultra 5 225 | 17,043 | 10/10 | 3.3 / 4.9GHz | 65W | 121W | 28,480円 | ||
| Core Ultra 5 225F | 16,415 | 10/10 | 3.3 / 4.9GHz | 65W | 121W | 26,800円 | ||
| Core i5-14400 | 16,000 | 10/16 | 2.5 / 4.7GHz | 65W | 154W | |||
| Core i5-14400F | 16,150 | 10/16 | 2.5 / 4.7GHz | 65W | 148W | 25,980円 | ||
| Ryzen 5 7600X | 15,263 | 6/12 | 4.7 / 5.3GHz | 105W | 142W | 31,500円 | ||
| Ryzen 5 7600 | 14,424 | 6/12 | 3.8 / 5.1GHz | 65W | 88W | 29,980円 | ||
| Ryzen 5 8600G | 14,067 | 6/12 | 4.3 / 5.0GHz | 65W | 88W | 32,590円 | ||
| Ryzen 5 7500F | 13,897 | 6/12 | 3.7 / 5.0GHz | 65W | 88W | 27,280円 | ||
| Ryzen 5 8400F | 13,361 | 6/12 | 4.2 / 4.7GHz | 65W | 88W | 25,270円 | ||
| Ryzen 5 8500G | 11,521 | 6/12 | 3.5 / 5.0GHz | 65W | 88W | 25,760円 | ||
| Ryzen 5 5600X | 11,430 | 6/12 | 3.7 / 4.6GHz | 65W | 76W | 18,480円 | ||
| Ryzen 5 5600T | 11,465 | 6/12 | 3.5 / 4.5GHz | 65W | 76W | 16,980円 | ||
| Ryzen 5 5600GT | ? | 6/12 | 3.6 / 4.6GHz | 65W | 88W | 21,980円 | ||
| Ryzen 5 5600G | 11,077 | 6/12 | 3.9 / 4.4GHz | 65W | 88W | |||
| Ryzen 5 5600 | 10,988 | 6/12 | 3.5 / 4.4GHz | 65W | 76W | 15,980円 | ||
| Ryzen 5 5500GT | ? | 6/12 | 3.6 / 4.4GHz | 65W | 88W | 18,980円 | ||
| Ryzen 5 5500 | 10,605 | 6/12 | 3.6 / 4.2GHz | 65W | 88W? | 16,980円 |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Core Ultra 5 245K | |
| Core i5-14600K | |
| Core i5-13600K | |
| Core Ultra 5 235 | |
| Core i5-14500 | |
| Core i5-13500 | |
| Core i5-12600K | |
| Ryzen 5 9600X | |
| Core Ultra 5 225 | |
| Core i5-14400 | |
| Core i5-13400 | |
| Ryzen 5 7600X | |
| Ryzen 5 7600 | |
| Ryzen 5 8600G | |
| Ryzen 5 7500F | |
| Ryzen 5 8400F | |
| Core i5-12400 | |
| Ryzen 5 8500G | |
| Ryzen 5 5600X | |
| Ryzen 5 5600G |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Ryzen 5 9600X | |
| Ryzen 5 7600X | |
| Core i5-14600K | |
| Ryzen 5 7600 | |
| Core i5-13600K | |
| Core Ultra 5 245K | |
| Core i5-12600K | |
| Ryzen 5 5600X | |
| Core i5-13400F | |
| Core i5-12400F |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Ryzen 5 5600X | |
| Core i5-12400F | |
| Core i5-13400F | |
| Ryzen 5 7600 | |
| Ryzen 5 9600X | |
| Ryzen 5 7600X | |
| Core i5-12600K | |
| Core Ultra 5 245K | |
| Core i5-13600K | |
| Core i5-14600K |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Core i5-12400F | |
| Ryzen 5 5600X | |
| Core i5-13400F | |
| Ryzen 5 7600 | |
| Core Ultra 5 245K | |
| Core i5-12600K | |
| Ryzen 5 9600X | |
| Ryzen 5 7600X | |
| Core i5-14600K | |
| Core i5-13600K |
まず言っておきたいのが、Core i5やRyzen 5と聞くと性能に不安を感じる人も居ると思いますが、今では十分に高性能と言えるレベルの性能を持っていることです。基本的に不可能なことは無いくらいの高性能さを持ちつつも価格が上位モデルよりも安いため、一般用途でのコスパが非常に良いのが魅力です。
中でもゲーミングコスパが非常に良い点は魅力的です。レビューのベンチマークテストなどを見るとゲーム性能でも大きく劣る印象も受けるかもしれませんが、これはレビュー記事では基本的に超高性能なハイエンドGPUと共に使用されるためです(現在ならRTX 4090とか)。
実際には5モデルはミドルレンジGPUと組み合わせるのが基本で、その場合にはCPUへの要求スペックも下がるため、上位CPUと比べてゲーム性能差は実はほとんど無いことも多いです。
Core i7 / Ryzen 7と比べるとコア数で劣るため、マルチスレッド性能を重視する場合には微妙なのは確かですが、ゲーミング単体に限れば、大きなネックになることは思ったよりも少ないため、コスパが良い点は留意しておきましょう。
Ryzen 5 7500F / 7600 / 7600X:優れたコスパとAM5の長期サポートが魅力の低価格CPU
Ryzen 5 7500F / 7600 / 7600Xは、3万円前後という安価さで価格の割に優れたゲーム性能を持ち、AM5対応も得られるのが魅力のCPUです。
以前はDDR4メモリが安価だったことが大きくて、「Ryzen 7 5700X」や「Core i5-14400F」に純粋なコスパでは劣る印象でしたが、メモリ高騰により2025年末頃からはこちらの方が上回った印象です。
比較的安価なので、将来のRyzenへの交換を意識した「とりあえず用」のCPUとしても丁度良く、低価格PCなら現在では非常に選び易い強力な選択肢だと思います。
Core Ultra 245K (F):3万円台まで値下がりしたことで、非常に優れた総合コスパに
「Core Ultra 245K (F)」は14コアを搭載するミドルレンジ最上位クラスのCPUです。
発売当初は価格が高くて微妙でしたが、2025年12月時点では3万円台中盤まで値下がりしており、この価格なら正直破格のコスパです。
4万円未満のCPUとしてはトップクラスのマルチスレッド性能を誇り、「Ryzen 5 7500F~7600X」を格段に上回る性能です。
他の「5」モデルだと、重めのアプリの並行作業に少し不安があることが一般的ですが、245Kでは一段優れたマルチタスク性能があるため、その辺りが安心できるのが大きな魅力です。
更に、NPUも搭載している上、GPUも内蔵品としては優れた性能しているという魅力もあり、非常にお得感があります(F版は内蔵GPU非搭載なので注意)。
といった感じで「Core Ultra 245K (F)」の性能コスパは普通に良いのですが、最優先になりにくい理由が主に二つあります。
一つ目は、単純に選べないことが多いためです。
大手のBTOでは取り扱いがないケースが多いため、そもそも選べないことが基本です。また、選べる場合でも発売当初の価格設定だったりしてお得じゃなかったりすることも多いので、そもそも選択肢に入らないのが残念な点です。
2025年12月時点では、ほぼフルカスタマイズや自作専用に近いCPUとなっています。
もう一つは、ゲームコスパは良くはない点です。
価格を考えればゲーム性能もデメリットというほどでもないのですが、「Ryzen 5 7500F~7600X」にゲーム性能で少し負けており、価格も245Kの方が少し高いので、ゲームコスパでは劣ります。
そのため、ゲーム性能コスパに特化するならやや弱く、他の「5」よりも費用も少し増えてしまうため低価格PC用のCPUとしてはやや致命的で、第一候補になりにくいです。
Core Ultra 225(F):3万円未満になり、安さと総合コスパ両立の選択肢として普通に悪くない
「Core Ultra 5 225(F)」は最新のアーキテクチャ採用のCore Ultra 5の下位モデルです。
3万円未満という安価さながら、NPUを搭載とアーキテクチャが刷新された内蔵GPUを搭載するのが魅力です(F版は内蔵GPU非搭載なので注意)。
発売からしばらくは価格が高く微妙でしたが、徐々に値下がりが進んで、3万円未満になったことで有力になりました。
「Ryzen 5 7500F / 7600 / 7600X」とほぼ同額なので、今では普通に悪くない選択肢です。
CPUの基本性能の面では、先代の「Core i5-14400F」や「Ryzen 7 5700X」と似た傾向を示しますが、高負荷時の効率が向上し、マザーボードのサポートも少し延びるのが強みです。
その上でNPUを搭載し、内蔵GPUも新しい世代のものが搭載されているのが嬉しいCPUです。(※ただ、内蔵GPUは245K以降で大きく性能が向上するので、重視するなら245Kを選んだ方が良い点は一応留意しておくと良い)
競合の「Ryzen 5 7600 / 7600X」との差をまとめると、NPUとGPUで少し有利で、ゲーム性能ではわずかに劣るという感じになります。
明確な有利こそ付きませんが、値下がり前は論外に近いレベルだったので、大きな進歩です。
値下がりが反映されれば、BTOでも有力モデルの一つとして台頭してくるかもしれません。
Ryzen 5 9600X / 9600 / 9500F:非常に優れた6コアCPUだけど、7600との価格差が大きくて厳しめ
「Ryzen 5 9600X / 9600」は「Zen 5」を搭載したRyzen 5です。6コア12スレッド。
6コアCPUとしては非常に優れたマルチスレッド性能を誇り、X付ながらTDPが65W~88Wなので、省電力で効率にも優れるCPUとなっています。6コアCPUとしては非常に優秀です。
ただし、先代の7500F~7600Xと比較すると性能向上率は小さい割に価格が高すぎます。
2025年12月末先代からおおよそ6000円前後ほど高価なのに、性能差はわずかです。マルチスレッド性能差は10%程度で、ゲーム性能差もわずかです。使用感がほぼ変わりません。
しかも、実は「Ryzen 7 7700~9700X」との価格差も8,000円程度しかなくて、そちらにはマルチスレッド性能は20%前後も負けています。
そんな感じで、現状の価格(3.8万円前後~)で 9500F~9600Xをあえて選ぶ理由はかなり小さく感じます。
6コアで十分な処理しか行わず、ゲームメインかつ省電力性重視なら優れた選択肢ですが、その場合でも「Ryzen 7 7700」を選んで8コアを確保しておいた方が安心感は大きいと思います。
少なくとも価格が3万円台前半まで下がらない限りは有力な選択肢にならない気がします。
Ryzen 5 8600G/8500G:高性能内蔵GPU搭載
「Ryzen 8000Gシリーズ」は高性能な内蔵GPUを搭載しているシリーズですが、2024年8月時点ではIntelに対抗製品がないので、グラボ無しのPC用のCPUとしては独壇場となっています。
Ryzen 5では「Ryzen 5 8600G」および「Ryzen 5 8500G」が登場しています。CPUはどちらも6コア12スレッドです。
ただし、8500Gは小型の「Zen 4c」コアが4つ含まれているため、8600Gの方がやや高性能な点に注意が必要です。更に、AI用のNPUである「Ryzen AI」が8500Gには含まれていないのも注意です。
また、GPUコア数にも差があります。8600Gは「Radeon 760M(8コア)」で、8500Gは「Radeon 740M(4コア)」となっています。8500Gだと内蔵GPUコア数が半分になってしまうので、性能には大きな差があります。
このように、8600Gと8500Gは価格差の割には性能差が大きいので、基本的には「Ryzen 5 8600G」の方がおすすめです。
また、8500Gではグラボ用のPCIeレーンがx4しかないのも気になるところです。帯域がかなり制限されるので、高性能なGPUを搭載するには適さない仕様です。8600Gもx8なので良くはありませんが、アッパーミドル程度までのグラボではネックにならないレベルですから、かなり大きな差があります。
購入後にグラボの増設を検討したくなったときに、8500Gでは対応が難しいことを事前に割り切るのは難しい部分かなと思います。
ただし、2024年8月時点では8600Gと8500Gとの価格差は約1万円と大きいので、そこは予算と相談になるかなと思います。8500Gでも内蔵GPUとしては比較的高性能な部類ではあるので、軽いゲームなら十分に対応できますし、AFMFを駆使すれば重めのゲームにもある程度は対応できます。高い性能も求めないレベルのライトユーザーなら8500Gでも正直困ることはあまりないと思うので、グラボ増設を今後絶対にしないと割り切った上での安さ重視なら、8500Gも悪くはない選択肢です。
また、一つ上位の「Ryzen 7 8700G」と「Ryzen 5 8600G」のどちらが良いのか迷う方も多いと思いますので、そちらも少し触れておきます。8600Gと8700Gの主な違いは、CPUのコア数が6→8、GPUコア数も8→12となる点です。特にGPUのコア数差が大きいのが気になる点だと思いますが、意外とコア数差の1.5倍ほどの差はなく、1.2倍程度までに留まっています。価格も発売時点では8700Gの方が1.8万円も高い点も大きいので、高いCPU性能を求める訳でないなら、8600Gの方が実用コスパは少し上になると思います。なので、CPU性能も出来るだけ高くしておきたいなら8700Gの方がおすすめではありますが、内蔵GPUさえそれなりに使えればOKという場合には8600Gという感じで、用途に応じて選択すると良いと思います。
Core i3 と Ryzen 3
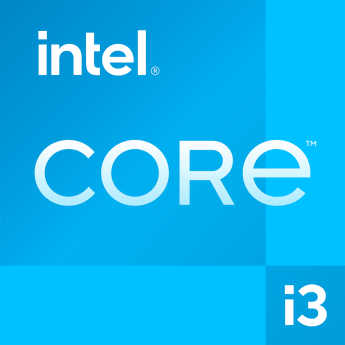
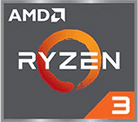
Core i3およびRyzen 3は主流CPUにおける中の下くらいに位置するモデルです。いわゆるミドルレンジ下位くらいに区分されます。価格は安く、おおよそ1万円台前半~2万円程度となっています。
価格の安さが魅力のモデルなので、性能はCore i5 / Ryzen 5以上と比較すると格段に低いです。
とはいえ、現在ではWeb閲覧やOffice作業などの軽作業であれば十分すぎるくらいの性能は持っています。その安価さのおかげで、特に重い作業をしないのであればコスパは良いです。また、消費電力や発熱も少ないため、小さなケースで運用するのにも適しています。ゲーミング用途でも、上位モデルと比べるとパフォーマンスが劣るというだけで、普通に使えはします。
ですが、価格差の割にCore i5やRyzen 5との性能差が大きいため、コスパを考えれば「3を買うなら、少しプラスして5買った方がお得」というのが明らかなので、他モデルより人気は低めです。
そのことをメーカーも承知しているのか、特にデスクトップではIntelもAMDもCore i3およびRyzen 3の販売にあまり積極的ではない印象です。Ryzenに至っては、Ryzen 5000シリーズ以降は消費者向けの一般販売モデルが無いなど、かなり影の薄いCPUになっているレベルです。
とにかく動けば良いので安いPCが欲しいという場合に限り有用なCPUかなと思います。
| CPU名 | マルチ スレッド | シングル スレッド | ゲーミング | 消費電力 発熱 | |
|---|---|---|---|---|---|
 | Core i3(第13,14世代) | ★2.0 | ★3.75 | ★3.25 | ★4.25 |
 | Core i3(第12世代) | ★2.0 | ★3.75 | ★3.25 | ★4.25 |
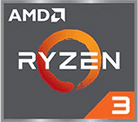 | Ryzen 3(8000G)/OEM限定 ※内蔵GPU重視モデル 性能の詳細不明 | ★1.0 | ★1.0 | ★1.0 | ★1.0 |
Core i3とRyzen 3の人気モデルを一部抜粋して比較しています。
| CPU | Cinebench R23 | コア/ スレッド | 動作クロック 定格/最大 | TDP (PBP/PL1) | TDP (PL2) | クーラー の付属 | コスパ | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i3-14100 | 9,091 | 4/8 | 3.5 / 4.7GHz | 60W | 89W | 〇 | 0.479 | 18,980円 |
| Core i3-14100F | 9,091 | 4/8 | 3.5 / 4.7GHz | 58W | 89W | 〇 | 0.650 | 13,980円 |
| Ryzen 3 8300G | 4/8 | 3.4 / 4.9GHz | 65W | 88W | 〇 | OEM限定 | ||
| Core i3-13100 | 8,812 | 4/8 | 3.4 / 4.5GHz | 60W | 89W | 〇 | ||
| Core i3-13100F | 8,812 | 4/8 | 3.4 / 4.5GHz | 58W | 89W | 〇 | ||
| Core i3-12100 | 8,172 | 4/8 | 3.3 / 4.3GHz | 60W | 89W | 〇 | ||
| Core i3-12100F | 8,172 | 4/8 | 3.3 / 4.3GHz | 58W | 89W | 〇 |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Core i3-14100 | |
| Core i3-14100F | |
| Core i3-13100 | |
| Core i3-13100F | |
| Core i3-12100 | |
| Core i3-12100F |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Core i3-14100 | |
| Core i3-14100F | |
| Core i3-13100 | |
| Core i3-13100F | |
| Core i3-12100 | |
| Core i3-12100F |
軽作業限定の安さ特化なら悪くはないけど、コスパを少しでも考えるなら上位モデルの検討を
Core i3 / Ryzen 3は、特に一般消費者向けとしてはコスパは正直微妙です。実際人気もあまり無く、メーカー側もそこまで力を入れていない印象のモデルになります。
なので、基本的には出来ればCore i5 / Ryzen 5以上の上位モデルの検討をおすすめします。
ただ、一応現行モデルの比較はざっくりとやっておきたいと思いますので、興味があればご覧ください。
比較について、Ryzenでは5000/7000シリーズでは一般消費者向けのRyzen 3は一つも投入されなかったためにCore i3との比較が不可能でしたが、2024年1月にようやく「Ryzen 3 8300G」が登場し、比較対象が生まれました。ただ、こちらもOEM限定(ショップ等の既製品PCでのみの販売)なので、ほとんど流通はしなさそうな気はしますが…。それはとりあえず置いておきます。
「第13・14世代のCore i3」と「Ryzen 3 8300G」のコア・スレッド数はどちらも4コア8スレッドです。ただし、Ryzen 3 8300Gは小型の「Zen 4c」コアを3つ含むため、Core i3の方がCPU性能はやや有利です。とはいえ、劇的な差があるほどではないですし、元々軽作業前提のCPUですから、実用性にはさほど影響はないレベルだと思います。
一応、安価なグラボと併せて安さ特化のゲームPCとして運用したい場合にはCore i3が有利にはなりますが、「Ryzen 3 8300G」がOEM限定のため、気にする必要が生まれていません。
そして、最大のポイントは内蔵GPUです。内蔵GPU性能は「Ryzen 3 8300G」の「Radeon 740M」の方が大幅に有利です。
8300Gの内蔵GPUも特別高性能ではないものの、軽いゲームやFHD以下の簡単な動画編集なら比較的快適に行える性能があります。それに対し、Core i3の内蔵GPUはゲームのベンチマークだと半分程度の性能になってしまうので、大きな差です。動画視聴や特に軽いゲームでは問題ないレベルなものの、その他のグラフィック処理は基本厳しめなので、少しでも良いからグラフィック性能を欲しい場合にはRyzen 3 8300Gの優位性は大きいかなと思います。
前述のように、CPU性能やグラボ利用時のゲーム性能ではCore i3が有利な側面もあるものの、立ち位置的にはそれらは基本求められないのが「Core i3 / Ryzen 3」だと思われ、軽作業前提の汎用PCとして考えるなら「Ryzen 3 8300G」がやや有利だと思います。




詳しい解説参考になります。
年内を目途にデスクトップPCの新調を考えているのですが、ゲームも”少し”したいと考えています。
現在だとryzenよりintelの方がよいとのことですが、他所で聞くと、ゲームならryzen、という意見もあり、他のサイトも色々拝見しているのですが、決めかねているところです。
実際のところ、したいゲームによって最適化されているcpuが違うというのもあるのかと思いますが、全体的な傾向として、ゲームをするのならこっちが無難、という意見はありますでしょうか?
最初に書きましたように”少し”したい程度なのでグラボの購入はしない予定ですが、予算は10万程なので、GTX1650搭載機なら手の届くところではあります。
このあたりも踏まえてアドバイスいただけますと幸いです。
はじめまして。
グラボを使用した際のゲーム性能を「第13世代Core」と「Ryzen 7000」で比較した場合、全体の傾向でいうとCoreの方が少し優れている傾向があります(RyzenのX3Dモデルは除く)。とはいえ、ゲームによってはRyzenが有利になるケースもあるため、一応やるゲーム次第という形にはなります。
ただし、上記は質問者様のケースでは恐らく気にする必要はないと思います。
理由は、一般的にCPUのゲーム性能というのは、ボトルネック差を出来るだけ詳細に知るために、高性能なハイエンドGPU(グラボ)を使用した際のfpsで比較するものとなっているためです。ゲームでCPUに求められる処理というのは、GPUが処理した量(主にフレーム数)に応じて増えるため、基本fpsが高いほど高性能なCPUが求められます。「GTX 1650」レベルのエントリークラス以下のGPUを使用する際には非常に軽いゲームでしか高いfpsは出ないため、現在の最新CPU(Core i5 / Ryzen 5 以上)ならボトルネックが発生することはほとんど無く、ゲーム性能差はほとんど出ません。そのため、質問者様のケースではCPUのゲーム性能はあまり気にする必要はないかと思います。その他の処理も同時に処理したりする場合には多少差が出てくる可能性も考えると、どちらかというとマルチスレッド性能差の方が重要かもしれません。
あと、余談にはなりますが、エントリーレベルのGPUを今検討するなら「GTX 1650」よりも「Arc A380」の方がコスパ的には良いと思います。Arcは発売当初は最適化不足が深刻で評価されませんでしたが、現在ではドライバによる改善が結構進んでいる上に値下げも進み、結構お得になっています。
また、「GTX 1650」ではAV1と呼ばれる映像コーデックに対するサポートが無いのが気になります。詳しくは触れませんが、AV1は将来性が期待されており採用率が増えているコーデックです。今購入するPCでは、出来ればデコードは対応しておきたいです。一応、「第13世代Core」も「Ryzen 7000」も内蔵GPUの方でAV1デコードのサポートがあるので、アプリケーションごとに指定したりすれば対応は不可能ではないかもしれませんが、あまりメジャーとは言えない方法にはなりますし、CPU負荷を下げるためにも出来ればグラボ側で対応しておきたいです。
詳細なアドバイスに感謝いたします。
エントリークラスのグラボだとCPUはボトルネックにならないのでどちらでもよいが、動画再生面で足を引っ張る可能性があるということですね。
となると下手にグラボに予算をさくくらいなら、少しでも高性能なCPUに予算を割り振るべき、という考えもあるのでしょうか?
所詮内蔵GPUはそれなりなので、ゲームをするなら安物でもグラボを積む方がよい、と思っているのですがどうでしょう?
それとも、予算を少し超えてでもGTX1660程度は積むべきでしょうか?
私の場合、買ったPCは6年以上使うつもりなので、ひとまず内蔵GPUで使ってみて後々必要になった時点でグラボを検討するという方が結果的に無駄が少なくなりそうでしょうか?(中途半端なCPUとグラボの両方を買い替えすることと比べて)
私が何に比重を置くのか次第になるのかとは思いますが、さらなるアドバイスいただけますと幸いです。
全体を通して概ね正しい認識だと思います。
現状の3万円以下のエントリーレベルのグラボではAV1のサポートが無いものがほとんどなので、AV1コーデックの動画再生では役に立ちません。AV1はまだ普及段階なので現状で困ることはほぼないですが、最低6年使うと考えるならAV1対応の優先度は高いと思います。
ゲームとCPUに関しても概ね認識の通りです。内蔵GPUの性能も向上しているとはいえ、現状はゲームに限れば安物でもグラボの方が高性能なことが基本です。一応、今年後半の発売が予測されている「Ryzen 7000」のAPUモデル(恐らく末尾G)では飛躍的に内蔵GPU性能が向上することが期待できますので、それが登場すれば少し事情が変わるかもしれませんが、現状では重めのゲームも視野に入れるならグラボは必須に近いです。
グラボ分の予算をCPUに予算を割り振るのも、ゲームを意識しないなら十分理にかなった選択肢です。ただし、低グレードなCPUからアップグレードすることを考えると、CPUクーラーで更なる予算追加が必要になったりする点には注意が必要です。
重いゲームが用途に含まれていないなら、内蔵GPUで様子を見るのも手かなと思います。ただ、質問者様がプレイしたいゲームの重さがわからないので、具体的には何とも言えないです。
一応、最後に低価格帯のグラボについてざっと触れておきますが、まず、「GTX 1650」や「GTX 1660」を含む「GTX 16」シリーズは共通してAV1のハードウェアサポートが無いので、個人的には今購入するのはおすすめしません。
今の市場でいうと、2万円台なら「Arc A380」ほぼ一択で、少し予算を増やせるなら「RTX 3060」、「RX 6600 / 6600 XT / 6650 XT」、「Arc A750 / A770」あたりになるかと思います。
詳しく解説いただきありがとうございます。
今すぐ購入するというわけではないので、Ryzen 7000での大幅な性能向上が見込めるとのことを期待してしばらく待つことにします。
大変参考になりました。
全然ありな選択だと思います。
ただ、一応予測で確定情報という訳でもないので、間違っていたらその際には申し訳ありません。
core i7-12700とRyzen7 5700XのPCで12700の方が5700Xよりも2万円ほど高い構成を見つけたのですが、その値段の差に見合う性能は見られるのでしょうか。その他の構成は同じものとします。
用途とGPUによると思います。
まず、「Core i7-12700」の方がコア数が多い新しいCPUのため、マルチスレッド性能が「Ryzen 7 5700X」の約1.5倍と大幅に高いです。そのため、高負荷なマルチスレッドが重要な処理で使う場合には十分価値はあると思います。一般的なものでいうと、マルチタスク処理全般や、CPUレンダリング・エンコードなどがあります。
関連して、12700の方がGPUのボトルネックもやや発生しにくい他、単純なゲーム性能もCore i7-12700の方が若干上なので、ハイエンドGPUと組み合わせる際には12700の方が有利になると思います。
総評としては、ベンチマークスコアを見るとやはりマルチスレッド性能差が大きく違うため、2万円(恐らく全体の10%~15%程度?)で1.5倍と考えると価格差から得られる性能としては十分な上、ゲームパフォーマンスやボトルネック面でも少し優秀な「Core i7-12700」の方が純粋なコスパは上だと思います。
ただし、重いマルチスレッド処理を頻繁にする訳でなく、ゲームパフォーマンスなども少しでも高い方が良い訳でないなら、実際の使用感はほぼ変わらないと思うので、安い「Ryzen 7 5700X」の方が良いとなると思います。
また、CPU以外の構成は同じものということでしたが、CPUクーラーが低性能なもので統一されている場合には、省電力な「Ryzen 7 5700X」の方が良いという可能性もあると思います。
返信ありがとうございます。
この場合のハイエンドGPUというと何番あたりからのことを指すのでしょうか。
また、12700の発熱ではBTOでよく使われるクーラーでは排熱は足りないですか。その場合、どの程度のクーラーが必要ですか。
ゲームや解像度にもよるので一概には言えないですが、ベンチマークテストの3DMark Time Spyのスコアを参考に見てみると、
【RTX 3060】
5700X:8874(-2.8%)
12700:9128
【RTX 3060 Ti】
5700X:11523(-2.8%)
12700:11855
【RTX 3070】
5700X:12932(-4.4%)
12700:13531
【RTX 3080】
5700X:15929(-6.5%)
12700:17029
上記のような感じになっているので、RTX 3070から少しボトルネック差が出てきているという感じになります。
排熱については、PCケースにもよりますし、CPUクーラーについても具体的な製品がわからないと何とも言えないですが、Core i7-12700の安さ重視製品では120mmファン1基の空冷が多い印象なので、その場合には十分とは言えないかなと思います。
とはいえ、高負荷時に少しだけ性能が落ちるかもって程度で、後から調整も可能な部分なので、CPU付属のクーラーでなければ気にするほどでもないかもしれません。余計なことを言ってしまったかもしれません。
一応、Core i7-12700で空冷なら120mmファン2基 or 140mmファン1基のクーラーがあると安心ではあると思います。
AMD Ryzen 7 5700GとIntel Core i5-12400で迷てます。
タスクをたくさん開くので一度Ryzenを使ってみたいのですがソフトの相性や不具合、故障が
心配です。
恐らく想像しているほどRyzenの方が問題が多発している状況は今ではないと思います。
逆にCoreの方で脆弱性や不具合が発生していることも普通にありますし、よく使用するソフトで問題が多発していないか事前に調べるのは必要だと思いますが、個人的にはそれ以上は気にしても仕方無いのではないかと思います。
ありがとうございました。
今までIntelばかり使用していたので不安でした。
ちなみに、とねりんさんは、どちらがお勧めですか。
価格差と自作とBTOなどで購入するかでも話が変わりますし、どちらが良いとは言えないですね。
理解されているような気がしますが、Ryzen 7 5700Gの他の競合モデルよりゲーミング性能がやや低い点と、Core i5-12400の方がややマルチスレッド性能が低い点を踏まえ、自分の用途や予算などを考慮して決めることになると思います。
また、Ryzenは次世代からチップセットやソケット形状が刷新されるため新世代のものへの交換は不可能になる可能性が高いですが、Coreの方は次世代(13世代)でもソケット形状は維持され既存のマザーボードでも対応されることが予測されているため、後のCPU換装を考えるならCoreの方が有利な点や、DDR5メモリへの対応などでも差があります。
ありがとうございました。
BTOで Ryzen 7 5700GはWindows10でi5-12400はWindows11で価格は同額です、
とねりんさんのおっしゃる通り後の事も考えて、パソコンショップに行って来ます。
差し支えなければ、もう少し詳しい構成(もしくは型番)と価格を教えていただけないでしょうか?
今は次世代のCPUやGPUが控えていて難しい時期なので、一応コスパチェック的なことくらいは出来るかなと思うので、良ければ。
Ryzen3 3250UとRyzen5 4500Uのどちらを購入しようか検討しております。
用途としては初心者のword,excel練習用で、コスト重視です。
どちらがおすすめですか?
オフィス程度の軽作業なら、処理性能はRyzen 3 3250Uでも十分だと思います。
ただ、Ryzen 5 4500Uの方が処理性能は圧倒的に高く、電力効率も大幅に良いです。
長期利用を想定しており、バッテリー駆動時間も長い方が良い場合にはRyzen 5 4500Uの方がおすすめです。
コメントありがとうございます!
有益なご意見とても参考になります。
再度、検討致します。