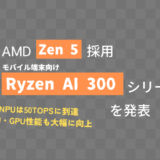この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
IntelはCOMPUTEX TAIPEI 2024にて、新しい「Core Ultra 200V(コードネーム:Lunar Lake)」モバイルプロセッサーシリーズを発表しました。
TSMC 3nmプロセスノード採用、ハイパースレッディング(1コア=2スレッド)の廃止、メモリをパッケージに統合、AI性能の大幅強化など、初代のCore Ultraに引き続き、多くの刷新が含まれる注目のプロセッサーとなっていましたが、本記事ではその概要についてざっくりと触れています。
ざっくり要点まとめ
- タイル設計(チップレット設計)
- 内部構造には変更がありますが、先代の「Meteor Lake」と同様に、「Lunar Lake」も複数のタイルから構成されるタイル設計を採用します。
- TSMC 3nmプロセスノード採用
- 「Meteor Lake」ではコンピュートタイル、グラフィックスタイル、I/Oタイルなどを分散し、それぞれ違うプロセスノードで構築されていましたが、「Lunar Lake」ではそれらのほとんどをコンピュートタイルに統合し、TSMC 3nmノードで構築しています。I/Oタイルに関してはTSMC 6nmとなっています。これまではCPUコアなどの主要部分では自社内ファウンドリー製造のIntel製のシリコンを採用してきたIntelですが、遂に他社製のシリコンを主軸として使用したプロセッサーを出す運びになりました。
- メモリをパッケージ上に配置することで、電力を40%削減
- 「Lunar Lake」ではパッケージにメモリが統合されます。Appleシリコン(M3など)と同じ形式になりました。これによって、今までのマザーボード・ソケットと接続していた場合と比べて、メモリの物理レイヤーによる電力が40%削減されるようです。LPDDR5X-8500、最大32GBがサポートされます。
- 4P + 4E の合計8コア
- 「Lunar Lake」は合計8のCPUコアで、4P + 4Eという構成になります(Pコアは高性能コアで、Eコアは低消費電力の効率コア)。それぞれのアーキテクチャ名は、Pコアは「Lion Cove」、Eコアは「Skymont」です。Eコアクラスターは、Pコアリングとは別に配置されるので、「Meteor Lake」でいうLP Eコアに似た性質のものとなっており、アイドル時や低負荷な処理の際の消費電力を削減することが期待できます。全体としては、合計コア数は8な上に、Eコア4つ含むということで、今までの仕様を考えるとかなり弱そうにも見えますが、特にEコアの凄まじい性能向上(後述)により、「Meteor Lake」以上のパフォーマンスを実現しているようです。
- Pコア:ハイパースレッディングを廃止することでダイ領域・電力削減し・性能を強化
- Pコアでは従来採用していたハイパースレッディングテクノロジー(1コアを2スレッドで運用)を廃止しました。これにより、物理的な部品を減らすことができるため、ダイ領域と電力を削減し、IPCを含めた性能向上に繋がります。「Meteor Lake」の「Redwood Cove」Pコアと比較すると、IPCは平均で14%向上し、同じ電力でのパフォーマンスは10%~18%向上したようです。
- Eコア:IPCと電力効率が飛躍的に向上(第13世代のPコア以上)
- Eコアは「Meteor Lake」のLP Eコアと比較して、IPCはFPで平均+68%という驚異的な向上率を主張しています。また、LP Eコア(Meteor Lake)の最大性能を3分の1の消費電力で達成でき、同じ電力で1.7倍の性能を発揮するということや、Raptol Cove(第13世代のPコア)に対しても、40%少ない電力で1.2倍の性能を実現していることを示すスライドが公開されました。俄かには信じがたいレベルのですが、このEコアの凄まじい性能向上が、Intelが4P + 4Eコアという一見弱そうに見える構成を採用した理由のようです。
- 「Xe2」内蔵GPUは前世代の最大約1.5倍の性能で、XMX(AI性能:67TOPS)も搭載
- 内蔵GPU「Xe2」では、ゲーム性能が「Meteor Lake」のGPU(Xe-LPG)と比較して最大+50%になりました。本当ならモバイル版の「RTX 3050」に匹敵することになる、凄まじい向上です。更に、「Lunar Lake」のGPUでは「XMX」エンジンが搭載される点も大きなポイントです。AI処理にも使用できるXMXは合計で67TOPSの処理性能を備えており、単体でも競合のNPUを大きく上回る性能を持ちます。競合他社は、今のところNPU以外でAIエンジンを搭載していないため、合計AI性能では他社を大きく突き放す要素となっています。
- NPU:48TOPSで、Copilot+のローカル動作要件をクリア
- 「Lunar Lake」のNPUは48TOPSに到達し、Copilot+ PCのローカル動作の要件(40TOPS)をクリアしました。これは「Meteor Lake(推定12TOPS)」の約4倍という驚異的な向上率です。また、48TOPSという数値は、先に発表されている「Snapdragon X(45TOPS)」や「Ryzen AI 300(50TOPS)」と同列ですが、「Lunar Lake」ではGPUにもAIエンジンが統合されており、そちらと合わせると合計115TOPSとなり、圧倒的に優位となっています。ちなみに、「Lunar Lake」のNPUはNPU 4(第4世代)として説明されていますが、実際には「Meteor Lake」に続く2世代目です。GFNIやAVX512といったAIアクセラレーションハードウェアを含んだカウントのためのようですが、それらは単体では現在のNPUとして使用できませんし、ややこしいので特に世代は気にしなくても良さそうです。
- 搭載の製品の出荷は2024年第3四半期頃
- 「Lunar Lake」は2024年第3四半期頃の出荷予定らしいので、6月中旬に発売が開始する「Snapdragon X」や、7月出荷開始予定の「Ryzen AI 300」よりも少し遅れる可能性が高そうです。
今回の発表では具体的なラインナップは公開されませんでしたし、要点は上記でほぼ触れたため、多く語れることはないですが、雑感的なのを少しだけ後に続けます。
かなり良さそうで、「Ryzen AI 300」や「Snapdragon X」よりも魅力的に見える
発表内容を一通りざっと見た印象は「かなり良さそう」です。
既に詳細も明らかになっている「Snapdragon X」や「Ryzen AI 300」と比べても、グラフィック性能はSnapdragonには大きく有利、Ryzenにはやや有利に見えますし、AI性能もNPU単体なら同等ですが、GPU側のAIエンジンも考慮するなら圧倒的に上回っています。
コアについては「4P + 4E」という、競合では10コア~12コアが主流な中で弱い印象を受けましたが、Eコアが第13世代のPコア以上の性能というのが本当なら、薄型の汎用PCとしては十分な処理性能が得られるはずなので、そこまでネックでも無さそうでした。
競合に対してやや劣っている印象もあった省電力性もかなり改善されたように見えますし、注目度の高い「AI性能」で上回っているのも大きな要素だと思います。
少し気になるのは価格とマルチスレッド性能
価格について
「Lunar Lake」の全体的な仕上がりの印象は良さそうですが、気になる点は少しあります。まずは価格です。
「Lunar Lake」はパッケージの大部分を占めるコンピュートタイルにTSMC 3nmを採用しています。最先端のものなので当然コストは高いと思われます。
発売からそこまで期間の経っていない前世代「Meteor Lake」では、自社の「Intel 4(7nm)」をCPU部分に採用した上で、他のノードも最高は5nmでした。それでも「Ryzen 8040」と比べるとやや高価だったので、そこからTSMC 3nmの採用やXMXの搭載など、コストが増大しそうな要素が更に増えているということで、価格面は懸念があります。
ただ、「Lunar Lake」は「Meteor Lake」などのCore Ultraファミリー全体の後継ではないという話もあり、シリーズ名の「Core Ultra 200V」というのもそれを示唆しているにも見えます。
どのメーカーも「AI PC」に乗り遅れないように、急いでAIプロセッサーを用意した感は強いので、価格やコスパ重視の製品についてはこれから登場してくるのかもしれません。これについては続報を待つしかありませんが、高額モデルしかない内は、特に円安の日本においては手を出しにくい価格設定となりそうな気がします。
マルチスレッド性能:Ryzenが頭一つ抜ける形に?
次に気になるのは、マルチスレッド性能です。
「Lunar Lake」は、電力面やIPCを重視するためにPコアのハイパースレッディング(1コア=2スレッド)を廃止した上、合計コア数は8(4P + 4E)でコア数も大きく削減しました。競合の10コア~12コアよりも少なくなっています。
飛躍的なコアパフォーマンスの向上により、それでもモバイル端末向けの汎用プロセッサーとしては十分なパフォーマンス(Meteor Lake以上)を維持できてはいるようですが、純粋なマルチスレッド性能だけを見ると、前世代から大して伸びなかったとも捉えることができます。
となると、依然として全コアでSMT(1コア=2スレッド)が有効な「Ryzen」に対して、最大マルチスレッド性能では大きく劣ることになる気がします(「Ryzen AI 9 HX 370」は発表時に「Core Ultra 9 185H」にマルチタスクで+47%の優位性を主張していた)。
モバイル端末における一般用途では、現状では性能を大きく伸ばす必要は無くなっている感は確かにあるので、効率を重視するのは個人的には良い傾向だとは思いますが、マルチスレッド性能の高さやコスパを重視する層はある程度居ると思います。
その場合には1コア2スレッドの恩恵はやはり大きいですし、Ryzenの小型かつSMT採用の「Zen 4c/5c」はコスパがかなり良さそうに思います。Eコアのみの「Alder Lake-N」のように、小型のZen cコアのみ採用のモデルが登場すれば、安価で非常に競争力のあるSoCになる気がします。
Intelが低~中価格層を切り捨ててRyzen一強となるのを良しとするとは思えないので、直接の競合モデルはまた別で用意する、ということなのかもしれませんが、ただでさえプロセスの微細化で遅れを取っていたIntelがそんなことをして、開発コストや期間が大丈夫なのかなという懸念があります。
様々な要素が絡み合ってきている昨今のプロセッサー事情がどうなっていくのだろうと楽しみな反面、特に最近のモバイルプロセッサー市場は複雑で混沌とし過ぎている感が否めないので、命名規則も含めてもっとシンプルで、普段情報を追っていない人でも分かり易い形になって欲しいなとも思ったりしちゃいますね。
あとがき
「Lunar Lake」の発表で、ひとまずWindows向けのAI PC向けのモバイルプロセッサー3シリーズの情報が出揃いました。
最初に発表されたときは頭一つ抜けた印象のあった「Snapdragon X Elite」が、今ではそこまでの優位性を感じないレベルになっているのが、技術の進歩の早さを感じますね。
「Lunar Lake」の具体的なラインナップやアプリケーションやマルチスレッドの性能が明かされなかったため、3つの予測性能を比較するのが難しいのは残念ですが、そこ抜きでも需要がありそうだったら近い内に簡単な比較記事を出してみようかなと思います。