この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
モバイル版の「Ryzenシリーズ」の世代別の特徴比較です。基本的に最新のものから数世代くらいをピックアップして載せていこうと思います。
現在掲載しているのは、Ryzen AI 300 / Ryzen 8000(200) / 7000 / 6000 で、デフォルトTDPが30W以下に設定されている省電力モデルを対象としています。
はじめに
本題に入る前にいくつかの項目について先に触れています。ここの内容を前提で進めている部分もあるので、見出しだけでも見て貰えると助かります。
本記事では「省電力モデル」が対象
本記事では、モバイル版で最も主流な省電力モデル(デフォルトTDP:15W~30W)に焦点を当てて見ていきます(例:Ryzen 7 8840U)。
主に末尾にHが付くモデル(デフォルトTDP:35W以上)は対象外としているため注意してください。ただし、Ryzenでは高消費電力のモデルも物理的な仕様は同じであることが多いので、参考になる部分も多いとは思います。
Ryzen 7000シリーズの先頭の数字は世代番号ではない点に注意
少しCPUの命名規則について調べたことがある人なら、「CPUの先頭は世代を表す」という認識を持っている人が多いと思います。
実際ほとんどのシリーズではそのようになっていますが、Ryzen 7000に関しては例外なので注意が必要です。
2025年10月時点の主要シリーズでは以下のようになっています。
7030などに搭載の「Vega」は古いため、低性能かつAV1対応もない
Ryzenの内蔵GPUの一つである「Vega」は「AV1」映像コーデックに対するデコード機能を持たない点に注意が必要です。「AV1」映像コーデックはロイヤリティフリーかつ圧縮率が高いということで、各動画サイトでも採用率が急増している将来性が特にあると言われている映像コーデックです。
AV1で圧縮された動画を観る際には、GPUにAV1のハードウェアデコード機能が無いと非常に効率が悪いので、今から新規で購入するPCでは出来ればデコードに対応しておきたいですのですが、「Vega」は「AV1」のハードウェアデコード機能がないのがちょっと微妙です(Vegaが2017年初登場の古いアーキテクチャ採用のGPUであることが起因)。
2025年時点では無くても困ることはあまりない機能ではあるものの、「Vega」は単純に基本性能も低いので、グラフィック性能を少しでも重視したい気持ちがあるなら非推奨です。
2025年10月時点での市場でも、Vega搭載の「Ryzen 7 7730U」「Ryzen 5 7530U」「Ryzen 5 7430U」あたりは見掛けることが結構あるので、要注意です。
コーデックとAV1については下記に補足説明を載せておくので、興味がある方はそちらも良ければご覧ください。
VegaはAFMF(ゲームのフレーム生成機能)も非対応
ゲームでの利用も視野に入れたい方は、Vegaでは「AFMF」に対応しない点も注意が必要です。
「AFMF」はゲームで使える手軽なフレーム生成機能(ドライバ動作でゲーム内での設定不要)で、RDNA 2以降のアーキテクチャで対応しています。
VegaはRDNAの前のアーキテクチャなので対応していません。
ただでさえ性能が低めで効率も劣るVegaですが、フレーム生成やアップスケーリング機能でも差があるため、少しでもグラフィック用途を重視したいならVegaは微妙という点は念頭に置いておきましょう。
簡易比較表
| 参考価格 ※Ryzen 5以降 | 製造プロセス CPUアーキテクチャ | GPUアーキテクチャ 3DMark Time Spy G | NPU | |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen AI 300 | 10万円~ | (2~16CU) ※AIユニットも統合 | ||
| Ryzen 200 Ryzen 8000 | 8万円前後~ | (4~12CU) | ※一部非搭載 | |
| Ryzen 7000 | ※アーキテクチャ次第 7040:8万円~ 7035:7万円台~ 7030:6万円台~ 7020:5万円台~ | (4~12CU) (2~12CU) (AFMFやAV1に非対応) | ※一部非搭載 | |
| Ryzen 6000 | 7万円台~ | (6 / 12CU) |
まず、2025年10月時点の主要シリーズの大まかな特徴をまとめたのが上記の表です。
細かいことは後で触れていきますが、一つだけ先に触れておきたいのは下記のことです。
「Ryzen 7030」は安価だけど、特にGPUが古くて微妙なので非推奨
「Ryzen 7030」シリーズは非常に安価でCPU性能コスパが良いシリーズです。2025年10月時点でも「Ryzen 5 7530U / 7430U」あたりはよく見掛ける人気モデルだと思います。
しかし、7030では内蔵GPUにVegaが採用されており、非常に古い世代のものとなっているためおすすめしません。
単純にグラフィック性能が他のものよりも低めという点もありますが、それよりも痛いのはサポート機能面です。特に痛いのはAV1ハードウェアデコードに非対応な点と、AFMF(ゲームのフレーム生成機能)に非対応な点です。
AV1デコードの点は高画質動画での視聴での負荷が飛躍的に高まる可能性があり、AFMFはただでさえ低いゲーム性能を補うことも難しいという感じです(細かいことは前述の「はじめに」内を参照)。
安さが魅力ではありますが、2025年10月時点では+5000円~1万円くらいで7035が選べるので、出来ればそちらを推奨します。
話が逸れましたが、以下にシリーズごとではなく、2025年10月時点で主要な各モデルについての簡易比較表を載せています。デフォルトTDPが30W未満の省電力モデル限定です。
この後にも色々と触れていきますが、細かく知りたい訳でなく各モデル同士の比較を自分でしたいという場合には下記の表だけでも正直十分かなと思いますので、先に載せておきます。
| CPU | Cinebench R23 Multi | 内蔵GPU ゲーム性能※ | 世代 | コア | スレッド | クロック 定格 – 最大 | TDP | 内蔵GPU | NPU ピーク性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen AI 9 HX 370 | 22246 | 3581 | Zen 5 Zen 5c | 12 (4+8) | 24 | 2.0 – 5.1 GHz 2.0 – 3.3 GHz | 15-54W | Radeon 890M | 50TOPS |
| Ryzen AI 9 365 | 19189 | 3190 | Zen 5 Zen 5c | 10 (4+6) | 20 | 2.0 – 5.0 GHz 2.0 – 3.3 GHz | 15-54W | Radeon 880M | 50TOPS |
| Ryzen 7 250 Ryzen 7 8840U | 13450 | 2779 | Zen 4 | 8 | 16 | 3.3 – 5.1 GHz | 15-30W | Radeon 780M | 16TOPS |
| Ryzen 7 8840HS | 13222 | 2779 | Zen 4 | 8 | 16 | 3.3 – 5.1 GHz | 20-30W | Radeon 780M | 16TOPS |
| Ryzen AI 7 350 | 13088 | 2810 | Zen 5 Zen 5c | 8 (4+4) | 16 | 2.0 – 5.0 GHz 2.0 – 3.5 GHz | 15-54W | Radeon 860M | 50TOPS |
| Ryzen 7 7840U | 12884 | 2779 | Zen 4 | 8 | 16 | 3.3 – 5.1 GHz | 15-30W | Radeon 780M | 10TOPS |
| Ryzen AI 5 340 | 11727 | 1704 | Zen 5 Zen 5c | 6 (3+3) | 12 | 2.0 – 4.8 GHz 2.0 – 3.4 GHz | 15-54W | Radeon 840M | 50TOPS |
| Ryzen 7 7730U | 11490 | 1173 | Zen 3 | 8 | 16 | 2.0 – 4.5 GHz | 15W | Radeon RX Vega 8 | × |
| Ryzen 5 8640HS | 11486 | 2116 | Zen 4 | 6 | 12 | 3.5 – 4.9 GHz | 20-30W | Radeon 760M | 16TOPS |
| Ryzen 7 6800U | 10779 | 2400 | Zen 3+ | 8 | 16 | 2.7 – 4.7 GHz | 15-28W | Radeon 680M | × |
| Ryzen 5 8640U | 10675 | 2116 | Zen 4 | 6 | 12 | 3.5 – 4.9 GHz | 15-30W | Radeon 760M | 16TOPS |
| Ryzen 5 7640U | 10675 | 2116 | Zen 4 | 6 | 12 | 3.5 – 4.9 GHz | 15-30W | Radeon 760M | 10TOPS |
| Ryzen 7 7735U | 10085 | 2400 | Zen 3+ | 8 | 16 | 2.7 – 4.75 GHz | 15-28W | Radeon 680M | × |
| Ryzen 5 7535U | 9814 | 1558 | Zen 3+ | 6 | 12 | 2.9 – 4.55 GHz | 15-28W | Radeon 660M | × |
| Ryzen 5 220 Ryzen 5 8540U | 9632 | 1534 | Zen 4 Zen 4c | 6 (2+4) | 12 | 3.2 – 4.9 GHz | 15-30W | Radeon 740M | × |
| Ryzen 5 7530U | 9284 | 1054 | Zen 3 | 6 | 12 | 2.0 – 4.5 GHz | 15W | Radeon RX Vega 7 | × |
| Ryzen 5 6600U | 8977 | 1558 | Zen 3+ | 6 | 12 | 2.9 – 4.5 GHz | 15-28W | Radeon 660M | × |
| Ryzen 3 7335U | ? | 1558 | Zen 3+ | 4 | 8 | 3.0 – 4.3 GHz | 15-28W | Radeon 660M | × |
| Ryzen 5 7520U | 5149 | 515 | Zen 2 | 4 | 8 | 2.8 – 4.3 GHz | 15W | Radeon 610M | × |
| Ryzen 3 7330U | ? | 839 | Zen 3 | 4 | 8 | 2.3 – 4.3 GHz | 15W | Radeon RX Vega 6 | × |
| Ryzen 3 7320U | ? | 515 | Zen 2 | 4 | 8 | 2.4 – 4.1 GHz | 15W | Radeon 610M | × |
※3DMark Time Spy Graphicsのスコア。内蔵GPU性能は各チップの実際の性能ではなく、同じGPUの平均性能です。モデルによって多少前後します。
ベンチマークスコア
対抗製品となるInteのCoreシリーズの主流モデルも含めたベンチマークスコアです。参考にご覧ください。オレンジ色のバーがRyzenで、青色のバーがCoreとなっています。
マルチコア性能
| CPU | スコア |
|---|---|
| Ryzen AI 9 HX 370 | 22246 |
| Core Ultra 7 255H | 20521 |
| Ryzen AI 9 365 | 19189 |
| Core Ultra 5 225H | 16040 |
| Core Ultra 7 155H | 14654 |
| Ryzen 7 250 | 13816 |
| Ryzen AI 7 PRO 360 | 13794 |
| Core Ultra 9 288V | 13401 |
| Ryzen AI 7 350 | 13088 |
| Ryzen 7 8840U | 12972 |
| Ryzen 7 7840U | 12884 |
| Core Ultra 5 135H | 12678 |
| Core Ultra 7 255U | 11869 |
| Ryzen AI 5 340 | 11727 |
| Core Ultra 5 225U | 11612 |
| Core Ultra 5 125H | 11293 |
| Core Ultra 7 258V | 11196 |
| Core i7-1360P | 10997 |
| Core i5-1340P | 10921 |
| Core Ultra 7 165U | 10797 |
| Ryzen 5 8640U | 10675 |
| Ryzen 5 7640U | 10675 |
| Core Ultra 7 256V | 10580 |
| Ryzen 7 6800U | 10297 |
| Ryzen 7 7735U | 10085 |
| Ryzen 7 7730U | 9908 |
| Core Ultra 5 226V | 9867 |
| Ryzen 5 8540U | 9635 |
| Core 7 150U | 9670 |
| Core i7-1260P | 9603 |
| Core 5 120U | 9114 |
| Core i7-1355U | 9071 |
| Core i5-1335U | 8349 |
| Core Ultra 5 125U | 8320 |
| Core i5-1240P | 8273 |
| Ryzen 5 7530U | 8081 |
| Ryzen 5 6600U | 8018 |
| Core i7-1255U | 7904 |
| Core i5-1235U | 7634 |
| Core 3 100U | 6553 |
| Core i3-1315U | 6187 |
| Core i3-1215U | 5802 |
シングルコア性能
| CPU | スコア |
|---|---|
| Core Ultra 7 255H | 2029 |
| Core Ultra 5 225H | 2015 |
| Core Ultra 9 288V | 1967 |
| Ryzen AI 7 PRO 360 | 1958 |
| Ryzen AI 9 HX 370 | 1953 |
| Ryzen AI 9 365 | 1926 |
| Core 7 150U | 1904 |
| Ryzen AI 7 350 | 1889 |
| Core Ultra 7 258V | 1886 |
| Core Ultra 7 256V | 1886 |
| Core 5 120U | 1881 |
| Core Ultra 7 255U | 1865 |
| Ryzen AI 5 340 | 1862 |
| Core i7-1360P | 1821 |
| Core i7-1355U | 1794 |
| Core Ultra 5 226V | 1780 |
| Core i7-1260P | 1778 |
| Core i7-1255U | 1775 |
| Core 3 100U | 1760 |
| Core Ultra 7 155H | 1749 |
| Core Ultra 5 225U | 1730 |
| Ryzen 7 250 | 1717 |
| Ryzen 5 8640U | 1715 |
| Ryzen 5 8540U | 1715 |
| Core i5-1340P | 1710 |
| Ryzen 7 7840U | 1708 |
| Ryzen 7 8840U | 1707 |
| Core Ultra 7 165U | 1706 |
| Core i5-1335U | 1685 |
| Core Ultra 5 135H | 1692 |
| Core Ultra 5 125H | 1683 |
| Core Ultra 5 125U | 1679 |
| Core i5-1240P | 1663 |
| Core i3-1315U | 1663 |
| Core i5-1235U | 1649 |
| Core i3-1215U | 1633 |
| Ryzen 5 7640U | 1552 |
| Ryzen 7 7735U | 1490 |
| Ryzen 7 6800U | 1480 |
| Ryzen 7 7730U | 1435 |
| Ryzen 5 7530U | 1428 |
| Ryzen 5 6600U | 1425 |
内蔵GPU性能(ゲーム)
| GPU名称 搭載CPUの例 | スコア |
|---|---|
| Intel Arc 140T Core Ultra 7 255H 等 | 3960 |
| Intel Arc 140V Core Ultra 7 258V 等 | 3908 |
| Radeon 890M Ryzen AI 9 HX 370 等 | 3581 |
| Intel Arc 130T Core Ultra 5 225H 等 | 3448 |
| Iris Xe 8コア (128EU) Core Ultra 7 155H 等 | 3412 |
| Intel Arc 130V Core Ultra 5 226V 等 | 3407 |
| Radeon 880M Ryzen AI 9 365 等 | 3190 |
| Iris Xe 7コア (112EU) Core Ultra 5 125H 等 | 3108 |
| Radeon 860M Ryzen AI 7 350 等 | 2810 |
| Radeon 780M Ryzen 7 8840U 等 | 2779 |
| Radeon 680M Ryzen 7 6800U 等 | 2400 |
| Radeon 760M Ryzen 5 8640U 等 | 2116 |
| Iris Xe 4コア (64EU) Core Ultra 7 165U 等 | 1865 |
| Iris Xe G7 96EU (~1400MHz) Core i7-1260P 等 | 1756 |
| Radeon 840M Ryzen AI 5 340 等 | 1704 |
| Iris Xe G7 96EU (~1300MHz) Core i7-1165G7 等 | 1629 |
| Radeon 660M Ryzen 5 6600U 等 | 1558 |
| Radeon 740M Ryzen 5 8540U 等 | 1534 |
| Iris Xe G7 96EU(-950MHz) Core i7-1250U 等 | 1270 |
| Iris Xe G7 80EU(-1300MHz) Core i5-1240P 等 | 1244 |
| Radeon RX Vega 8 Ryzen 7 7730U 等 | 1173 |
| Radeon RX Vega 7 Ryzen 5 7530U 等 | 1054 |
| UHD Xe 64EU Core i3-1220P | 1049 |
| Iris Xe G7 80EU(-850MHz) Core i5-1230U | 941 |
| Radeon RX Vega 6 Ryzen 3 5300U | 839 |
| UHD G4 48EU Core i3-1115G4 | 646 |
電力効率(CPU)
| CPU | スコア |
|---|---|
| Ryzen AI 9 HX 370(33W) | 54.9 |
| Ryzen 7 7840U | 48.0 |
| Ryzen 7 6800U | 40.2 |
| Ryzen AI 7 350(40W) | 39.9 |
| Core Ultra 7 255H(45W) | 39.9 |
| Core Ultra 7 155H(24W) | 37.9 |
| Core Ultra 5 225H(45W) | 37.8 |
| Core Ultra 5 125H(35W) | 32.2 |
| Ryzen 5 6600U | 29.9 |
| Core Ultra 7 258V | 29.7 |
| Ryzen 7 7730U | 29.0 |
| Core Ultra 5 226V | 28.9 |
| Ryzen 5 7530U | 28.8 |
| Core i7-1260P | 28.4 |
| Core i5-1240P | 28.4 |
| Core i7-1355U | 27.7 |
| Core i7-1360P | 25.5 |
| Core i7-1255U | 25.0 |
| Core i5-1235U | 24.4 |
| Core i3-1215U | 17.4 |
各シリーズ
各シリーズの特徴(メリット・デメリット)
まずは各シリーズの特徴をまとめた表を先に載せておきます。表の後に各シリーズ別に触れていこうと思います。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| Ryzen AI 300 Zen 5,5c / RDNA 3.5 Ryzen AI 7 350 等 | ・非常に優れたNPUのAI性能(~50TOPS) ・GPUにもAIアクセラレータ搭載 ・優れたマルチスレッド性能 ・かなり優れた内蔵GPU ・小型コア(Zen 5c)採用で非常に優れたワットパフォーマンス ・最大12コアの超高性能モデルあり | ・ものすごく高価 ・実用コスパは2025年時点では微妙(NPUが効果的に使える場面がまだ少ない) |
| Ryzen 200 Ryzen 8000 Zen 4 / RDNA 3 Ryzen 7 8840U 等 | ・優れたマルチスレッド性能 ・優れた内蔵GPU ・優れたワットパフォーマンス ・NPU搭載(~16TOPS 一部除く) | ・やや高価 ・アイドル時の消費電力が競合モデルよりやや多い(小型コアが無いため) |
| Ryzen 7040 Zen 4 / RDNA 3 Ryzen 7 7840U 等 | ・優れたマルチスレッド性能 ・優れた内蔵GPU ・優れたワットパフォーマンス ・NPU搭載(~10TOPS 一部除く) | ・やや高価 ・アイドル時の消費電力が競合モデルよりやや多い(小型コアが無いため) |
| Ryzen 7035 Zen 3+ / RDNA 2 Ryzen 7 7735U 等 | ・比較的安価 ・優れたマルチスレッド性能 ・優れたマルチスレッド性能コスパ ・比較的優れた内蔵GPU | ・NPU無し ・特別安価ではないのに、最新モデルに少し劣る性能 |
| Ryzen 7030 Zen 3 / Vega Ryzen 5 7530U 等 | ・非常に安価 ・非常に優れたマルチスレッド性能コスパ ・省電力(TDP:15W) | ・内蔵GPU性能が低い ・AV1デコード非対応 ・AFMF非対応 ・最新モデルには劣るCPU性能 ・NPU無し |
| Ryzen 7020 Zen 2 / RDNA 2 Ryzen 5 7520U 等 | ・非常に安価 ・省電力(TDP:15W) ・安価だけどAV1デコード対応 | ・最大4コアでマルチスレッド性能が非常に低い ・内蔵GPU性能も非常に低い ・NPU無し |
| Ryzen 6000 Zen 3+ / RDNA 2 Ryzen 7 6800U 等 | ・Zen 3+モデルのみで分かり易い ・比較的安価 ・優れたマルチスレッド性能 ・優れたマルチスレッド性能コスパ ・比較的優れた内蔵GPU | ・NPU無し ・特別安価ではないのに、最新モデルに少し劣る性能 |
Ryzen AI 300シリーズ

| Ryzen AI 300シリーズ(2025年9月時点) | |||
| アーキテクチャ | Zen 5 + Zen 5c | ||
|---|---|---|---|
| プロセス | 4nm(TSMC) | ||
| コア | 6~12コア | ||
| スレッド | 12~24スレッド | ||
| 内蔵GPU (iGPU) | Radeon 800Mシリーズ (RDNA 3.5) | ||
| 対応メモリ | DDR5 | ||
| CPU | Cinebench R23 Multi | 内蔵GPU ゲーム性能※ | 世代 | コア | スレッド | クロック 定格 – 最大 | TDP | 内蔵GPU | NPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen AI 9 HX 370 | 22246 | 3581 | Zen 5 Zen 5c | 12 (4+8) | 24 | 2.0 – 5.1 GHz 2.0 – 3.3 GHz | 15-54W | Radeon 890M | 50TOPS |
| Ryzen AI 9 365 | 19189 | 3190 | Zen 5 Zen 5c | 10 (4+6) | 20 | 2.0 – 5.0 GHz 2.0 – 3.3 GHz | 15-54W | Radeon 880M | 50TOPS |
| Ryzen AI 7 350 | 13088 | 2810 | Zen 5 Zen 5c | 8 (4+4) | 16 | 2.0 – 5.0 GHz 2.0 – 3.5 GHz | 15-54W | Radeon 860M | 50TOPS |
| Ryzen AI 5 340 | 11727 | 1704 | Zen 5 Zen 5c | 6 (3+3) | 12 | 2.0 – 4.8 GHz 2.0 – 3.4 GHz | 15-54W | Radeon 840M | 50TOPS |
※3DMark Time Spy Graphicsのスコア。内蔵GPU性能は各チップの実際の性能ではなく、同じGPUの平均性能です。モデルによって多少前後します。
Ryzen AI 300:高性能NPU(AIユニット)と小型コア「Zen 5c」採用の最新鋭CPU
Ryzen AI 300シリーズは、2024年6月発表されたシリーズで、CPUアーキテクチャには「Zen 5」が採用されています。
特徴は「AI」と含まれていることからも分かる通り、50TOPS~の高いAI処理性能を誇るNPUを搭載している点です。これにより、Windowsに統合されたAI機能を使うためのCopilot+ PCの要件「40TOPS」をクリアしました。
更には、GPU側にもAIアクセラレータが搭載されています。チップ合計のAI性能が非常に高く、AIプロセッサにふさわしい仕様となっています。
しかも、GPU側のAIアクセラレータも単なる行列演算だけでなく、高度な処理にも対応できることが示唆されているため、将来性も高いです。
また、CPUに小型コアの「Zen 5c」を採用したのもポイントです。高性能な「Zen 5」コアと小型の「Zen 5c」コアの2種類を採用という形になっています。
これにより、8コアから中々増やせなかったコア数を増やすことに成功し、最上位モデルでは12コアを搭載します。
また、他の主要CPUとは異なり、小型コアでも1コア2スレッドのSMTを採用しているため、他の競合CPUと比較して、コア数の割にマルチスレッド性能が非常に優れています。
しかも、小型コアの採用により、従来のRyzenよりもアイドル時および低負荷時の消費電力もわずかに改善しています。
最上位モデルは12コア24スレッドとなり、最大54Wとは思えない非常に優れたマルチスレッド性能を発揮しつつも、効率も非常に優れているため、マルチスレッド性能の効率を重視するなら非常に強力なCPUシリーズとなっています。
また、内蔵GPUには「RDNA 3.5」アーキテクチャが採用されており、前世代の「RDNA 3」から少し向上したことが伺えます。前述のAIアクセラレータの新設もポイントです。
しかも、前世代まではGPUのCU数は最大12(Radeon 780M)でしたが、Ryzen AI 300 では最大16CUの「Radeon 890M」が登場しました。
ゲームのベンチマークでは「GeForce GTX 1650」を少し上回るスコアを記録するなど、少し前のエントリーグラボ並みの性能を発揮します。
「Radeon 880M(12CU)」や「Radeon 860M(8CU)」もCUの割には優れた性能を発揮し、少し重めのゲームや動画編集にも対応できるレベルの性能がありますし、
ゲームのフレーム生成機能である「AFMF」の登場などもあり、優れたNPU性能のおかげで、今後はAuto SR(Windows搭載のアップスケーリング)の利用も期待できるなど、内蔵の割には優れたグラフィック処理での汎用性を備えます。
さすがにまだ重量級ゲームを高い設定&高fpsでプレイというのは厳しいものの、高いレベルを求めなければ割と不自由なく対応できるようになっています。
総合的に見て、各種性能が全体的に大きく底上げしつつ、高いAI性能も備えた、2025年時点で最新鋭の超高性能CPUです。
しかし、デメリットは価格です。搭載PCが高価です。
2025年9月時点での搭載ノートPCの市場のおおよその最安値を見てみると、「Ryzen AI 5 340」が10万円台、「Ryzen AI 7 350」が13万円前後、「Ryzen AI 9」が15万円~程度となっています。
AI性能は非常に高い点は魅力ですが、2025年時点では恩恵が限定的すぎるAI性能のために追加予算を大幅に使うのも中々割り切るのが難しい部分だとは思います。
そのため、おすすめできる人は限られますが、AIとグラフィック性能も含めた出来るだけ高い性能と優れた電力面を兼ね備えたPCが欲しい場合には非常におすすめできるCPUだと思います。
Ryzen 8000・Ryzen 200シリーズ
※Ryzen 200シリーズはRyzen 8000シリーズの実質リネーム版となっているので、併せて表記しています。
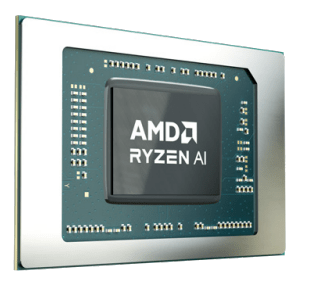
| Ryzen 8000・Ryzen 200シリーズ (2025年10月時点) | |||
| アーキテクチャ | Zen 4 | ||
|---|---|---|---|
| プロセス | 4nm(TSMC) | ||
| コア | 4~8コア | ||
| スレッド | 8~16スレッド | ||
| 内蔵GPU(iGPU) | Radeon 700M (RDNA 3) | ||
| 対応メモリ | DDR5 | ||
| CPU | Cinebench R23 Multi | 内蔵GPU ゲーム性能※ | 世代 | コア | スレッド | クロック 定格 – 最大 | TDP | 内蔵GPU | NPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 8840HS | 13222 | 2779 | Zen 4 | 8 | 16 | 3.3 – 5.1 GHz | 20-30W | Radeon 780M | 16TOPS |
| Ryzen 7 250 Ryzen 7 8840U | 13450 | 2779 | Zen 4 | 8 | 16 | 3.3 – 5.1 GHz | 15-30W | Radeon 780M | 16TOPS |
| Ryzen 5 8640HS | 11486 | 2116 | Zen 4 | 6 | 12 | 3.5 – 4.9 GHz | 20-30W | Radeon 760M | 16TOPS |
| Ryzen 5 8640U | 10675 | 2116 | Zen 4 | 6 | 12 | 3.5 – 4.9 GHz | 15-30W | Radeon 760M | 16TOPS |
| Ryzen 5 220 Ryzen 5 8540U | 9632 | 1534 | Zen 4 Zen 4c | 6 (2+4) | 12 | 3.2 – 4.9 GHz | 15-30W | Radeon 740M | × |
※3DMark Time Spy Graphicsのスコア。内蔵GPU性能は各チップの実際の性能ではなく、同じGPUの平均性能です。モデルによって多少前後します。
Ryzen 200 / Ryzen 8000:競合モデルよりも安価に優れた内蔵GPUとマルチスレッド性能
Ryzen 200 / 8000シリーズはCPUに「Zen 4」、GPUに「RDNA 3」アーキテクチャが採用されたシリーズです。
全モデルで小型コア採用となっているIntel(Core)と異なり、8640U以降のモデルであれば小型コアは採用されないため、処理の種類によらず安定した優れた性能とマルチスレッド効率を発揮します。
内蔵GPUには「RDNA 3」アーキテクチャの「Radeon 700Mシリーズ」を採用しているため、内蔵にしては優れたグラフィック性能を持つのも大きな魅力です。
「Ryzen 7 250 / Ryzen 7 8840U」搭載の「Radeon 780M(12CU)」の場合、ゲームのベンチマークでは「GeForce GTX 1650」を少し下回る程度のスコアを示しており、重めのゲームや動画編集も一応可能なレベルに達しています。
更に、ほとんどのモデルでNPU(AIユニット)まで搭載しています。ピーク性能は16TOPSとなっているため高性能ではないものの、簡単なAI処理には対応できると思われるので将来性もあります。
このように、優れた基本性能を持ちつつ効率も優れているというバランスの良さが特徴のシリーズとなっていますが、その性能の割には価格が安価なのが特に大きな魅力です。
競合モデルとなる「Core Ultra 100H(例:Core Ultra 7 155H)」等よりもやや安価となっており、比較的安価かつ優れた実用コスパでおすすめしやすいシリーズとなっています。
ただし、Ryzen 5ではGPUもコア数が削減されている点に注意です。
「Ryzen 5 8640U」の「Radeon 760M(8CU)」なら性能低下率は小さめなので、予算次第で妥協は可能なレベルですが、
「Ryzen 5 8540U」の「Radeon 740M(4CU)」はGPUのコア数が4つしかなく、Ryzen 7(Radeon 780M)の3分の1しかないため、重めの処理は厳しいレベルになります。
更に、「Ryzen 5 8540U」はNPU(AIユニット)を搭載しないというデメリットもあるので、その点を留意しておきましょう。
ただし、「Ryzen 5 8540U」は一段安価となっている点で優位性がありますし、電力効率は非常に優れています。内蔵GPU性能も価格を考えれば低性能というほどではないです。
基本的には「Ryzen 5 7530U」よりはやや優れた選択肢ではあるので、覚えておくと良いかもです。
Ryzen 7000シリーズ
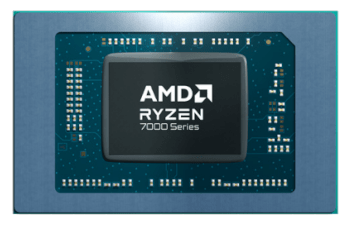
| Ryzen 7000シリーズ | |||
| アーキテクチャ | Zen 2 ~ Zen 4 | ||
|---|---|---|---|
| プロセス | 4nm~7nm(TSMC) | ||
| コア | Zen 2以外:4~8コア Zen 2:2~4コア(Ryzen 5まで) | ||
| スレッド | Zen 2以外:8~16スレッド Zen 2:4~8スレッド(Ryzen 5まで) | ||
| 内蔵GPU(iGPU) | Radeon 700M (RDNA 3) Radeon 600M (RDNA 2) Radeon RX Vega | ||
| 対応メモリ | Zen 2, 3+, 4:DDR5 Zen 3:DDR4 | ||
| CPU | Cinebench R23 Multi | 内蔵GPU ゲーム性能※ | 世代 | コア | スレッド | クロック 定格 – 最大 | TDP | 内蔵GPU | NPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 7840U | 12884 | 2779 | Zen 4 | 8 | 16 | 3.3 – 5.1 GHz | 15-30W | Radeon 780M | 10TOPS |
| Ryzen 7 7730U | 11490 | 1173 | Zen 3 | 8 | 16 | 2.0 – 4.5 GHz | 15W | Radeon RX Vega 8 | × |
| Ryzen 5 7640U | 10675 | 2116 | Zen 4 | 6 | 12 | 3.5 – 4.9 GHz | 15-30W | Radeon 760M | 10TOPS |
| Ryzen 7 7735U | 10085 | 2400 | Zen 3+ | 8 | 16 | 2.7 – 4.75 GHz | 15-28W | Radeon 680M | × |
| Ryzen 5 7535U | 9814 | 1558 | Zen 3+ | 6 | 12 | 2.9 – 4.55 GHz | 15-28W | Radeon 660M | × |
| Ryzen 5 7530U | 9284 | 1054 | Zen 3 | 6 | 12 | 2.0 – 4.5 GHz | 15W | Radeon RX Vega 7 | × |
| Ryzen 3 7335U | ? | 1558 | Zen 3+ | 4 | 8 | 3.0 – 4.3 GHz | 15-28W | Radeon 660M | × |
| Ryzen 5 7520U | 5149 | 515 | Zen 2 | 4 | 8 | 2.8 – 4.3 GHz | 15W | Radeon 610M | × |
| Ryzen 3 7330U | ? | 839 | Zen 3 | 4 | 8 | 2.3 – 4.3 GHz | 15W | Radeon RX Vega 6 | × |
| Ryzen 3 7320U | ? | 515 | Zen 2 | 4 | 8 | 2.4 – 4.1 GHz | 15W | Radeon 610M | × |
※3DMark Time Spy Graphicsのスコア。内蔵GPU性能は各チップの実際の性能ではなく、同じGPUの平均性能です。モデルによって多少前後します。
記事執筆時(2023年2月)にはRyzen 7000シリーズは市場にまだほとんど登場していませんが、末尾U(TDP:15W~28W)の今後主流になると思われるモデルの主要な仕様を雑に並べています。同シリーズ内での比較にお使いください。
未登場の状態でもアーキテクチャはほとんどが既存のものなので、性能や価格に大体の推測が出来ます。そのため、それを基に評価も先駆けて掲載しています。後に変更となるかもしれませんので、参考程度にご覧ください。未掲載のZen 4モデルは詳細な仕様が判明次第掲載します。
Ryzen 7000:Zen 2~Zen 4 が混在するカオスなシリーズ
Ryzen 7000シリーズは2023年をターゲットにしたRyzenです。注意すべき点はアーキテクチャ的には古いものも多数となっており、内部的には新しいとは限らない点に注意です。
CPUのアーキテクチャが「Zen 2 / Zen 3 / Zen 3+ / Zen 4」と4つが混在しているのに加え、内蔵GPUについても「Vega / RDNA 2 / RDNA 3」の3つが混在しているという、非常に混沌としたシリーズになっています。
しかも、後述の命名規則が複雑かつ分かりにくく、場合によってはRyzen 5よりもRyzen 3の方が高性能だったりなどのケースもあり得ます。Ryzen 7000シリーズを選択する際には名前には要注意です。
基本的には、下から2桁目(十の位)がZenの世代を表しているので、そこを見ると分かり易いです。まとめると下記のようになります。
| シリーズ | アーキテクチャ | モデル | 内蔵GPU |
|---|---|---|---|
| Ryzen 7045 | Zen 4(Dragon Range) | Ryzen 5~Ryzen 9 | Radeon 700Mシリーズ(RDNA 3) |
| Ryzen 7040 | Zen 4(Phoenix) | Ryzen 3~Ryzen 9 | Radeon 700Mシリーズ(RDNA 3) |
| Ryzen 7035 | Zen 3+(Rembrant-R) | Ryzen 3~Ryzen 9 | Radeon 600Mシリーズ(RDNA 2) |
| Ryzen 7030 | Zen 3(Barcelo-R) | Ryzen 3~Ryzen 7 | Radeon RX Vega |
| Ryzen 7020 | Zen 2(Mendocino) | Athlon~Ryzen 5 | Radeon 610M(RDNA 2) |
2024年時点では、新しいアーキテクチャと言えるのはZen3 +かZen 4採用のものに限られます。特に内蔵GPU性能はZen 3+以降とそれ以前でかなり差があるので、内蔵GPU性能重視なら「Ryzen 7035 / 7040 / 7045」のどれかを選ぶようにしましょう。
内蔵GPUも高い「Zen 3+(7035)」か「Zen 4(7040)」モデルがおすすめ
Ryzen 7000シリーズでの一番のおすすめは、「Zen 3+(7035)」もしくは「Zen 4(7040)」採用のモデルです。Ryzen 7 7735UやRyzen 7 7840Uなどですね。
特に魅力なのは内蔵GPU性能です。Zen 3+以降で採用される「RDNA 2 / RDNA 3」アーキテクチャの内蔵GPU性能は、それ以前と比べて飛躍的に性能が向上しており、やや重めのゲームや動画編集もビデオカード無しで一応対応できるレベルにまで到達しています。
ビデオカード搭載機と違って薄型・軽量化・バッテリー性能にも障害がないので、モバイル性能にも優れた様々な用途に使えるノートPCが欲しい場合には非常に魅力的です。効率も優れており、非常に汎用性に優れた優秀なCPUです。Zen 4モデルではAI処理用のNPUも搭載します(Ryzen AI)。将来性を考えても魅力的な仕様です。そのため、基本的には下2桁が「35 / 40 /45」のモデルを選ぶのを最優先としたいです。
しかし、実はCPUのマルチスレッド性能に関してはZen 3以降では実はどれも大差がないです。そのため、グラフィック性能を重視しないマルチスレッド性能コスパ重視なら、安価な「Zen 3(7030)」モデルも、やや古い世代ながら非常に強力です。なのですが、内蔵GPUが古いVegaのものとなっているため、グラフィック性能が低いだけでなくAV1というコーデックへのサポートが無いため、将来性的にはやや微妙な選択という点に注意が必要です。AV1デコード機能がないと、AV1形式でエンコードされた高画質動画を観る際などに、ネックとなる可能性があります。
最後に、一番古いアーキテクチャの「Zen 2」採用モデルですが、これは正直少し罠っぽいモデルです。なぜかというと、Ryzen 5でもコア数が4だからです。ここしばらく「Ryzen 5 = 6コア」のモデルしかなかった中で、いきなり4のモデルが出るのはさすがにどうかなと思います。当然マルチスレッド性能は他のRyzen 5よりも明らかに低く、おまけにグラフィック性能も低いです。Web閲覧やオフィス程度の軽作業なら十分な性能ではありますが、コスパ的にはあまり良くはないです。
ただし、内蔵GPUには古いVegaではなく「RDNA 2」の「Radeon 610M」が採用されている点は評価できます。CU数が2と少なく処理性能は低いものの、元々CPUのコア数的に軽作業前提のCPUですから、新しいコーデックに対応している上に最適化が続く「RDNA 2」採用は嬉しいです。また、コア数が少なくTDPが低く設定されているため省電力性は高く、GPUもCU数が少なくCU数が少ないのも消費電力削減に貢献すると思われますから、長寿命バッテリーを魅力に思う場合には非常に優れています。そのため、重い処理を考慮しないのであればVega採用の「Zen 3」モデルよりは「RDNA 2」の内蔵GPU搭載の「Zen 2」モデルの方がおすすめです。
各モデルについての所感は以上です。最後に改めて結論を載せておくと、基本的には「Zen 3+」か「Zen 4」モデル(Ryzen 7 7735U、7840U 等)を選ぶのが無難です。強力な内蔵GPUと効率による汎用性で将来性にも優れる優秀なCPUです。
しかし、価格はやや高価ではあるので、マルチスレッド性能コスパのみを見るなら「Zen 3」モデル(Ryzen 7 7730U)が一番良いです。内蔵GPUがVegaなので、AV1デコードに対応しない点は注意ですが、そこを割り切れるなら悪くない選択肢です。
Ryzen 6000シリーズ
| Ryzen 6000シリーズ | |||
| アーキテクチャ | Zen 3+ | ||
|---|---|---|---|
| プロセス | 6nm(TSMC) | ||
| コア | Ryzen 7 / 9:8コア Ryzen 5:6コア | ||
| スレッド | Ryzen 7 / 9:16スレッド Ryzen 5:12スレッド | ||
| 内蔵GPU(iGPU) | Radeon 600M (RDNA 2) | ||
| 対応メモリ | DDR5 | ||
| CPU | Cinebench R23 Multi | 内蔵GPU ゲーム性能※ | 世代 | コア | スレッド | クロック 定格 – 最大 | TDP | 内蔵GPU | NPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 6800U | 10779 | 2400 | Zen 3+ | 8 | 16 | 2.7 – 4.7 GHz | 15-28W | Radeon 680M | × |
| Ryzen 5 6600U | 8977 | 1558 | Zen 3+ | 6 | 12 | 2.9 – 4.5 GHz | 15-28W | Radeon 660M | × |
※3DMark Time Spy Graphicsのスコア。内蔵GPU性能は各チップの実際の性能ではなく、同じGPUの平均性能です。モデルによって多少前後します。
Ryzen 6000:Zen 3+のみの実用コスパに優れるシリーズ
Ryzen 6000シリーズは2022年発表のシリーズです。複数のアーキテクチャが混在する5000および7000シリーズと異なり「Zen 3+」のみの構成となっているため分かり易いです。
「Zen 3」や「Zen 2」から変わった最も大きい点は、内蔵GPUのアーキテクチャが「Vega」から「RDNA 2」に変わったことです。
「Vega」は初出が2017年の古いアーキテクチャということもあり、最新のものと比べると電力効率やAV1対応の点で明らかに劣るのが弱点でしたが、「RDNA 2」では電力効率および性能が格段に向上し、AV1デコードにも対応しています。特にモバイル端末にとっては非常に大きな向上となりました。
これによって、Vega搭載のRyzenよりは明らかに優位性があるモデルとなりました(例:Ryzen 5 7530U、Ryzen 7 5825U)。
Ryzen 7以降で搭載される内蔵GPU「Radeon 680M」のゲーミング性能は「GTX 1050 Ti(モバイル版)」にも匹敵するレベルとなり、重めの処理にも対応可能となりました。
2025年現在ではやや古いモデルで見掛けることも少なくなりましたが、NPUが無い点を除けば十分現役で通用する性能を持つので、在庫処分価格などで安くなっていれば魅力的です。
といった感じで記事は以上になります。必要があれば色々と修正・加筆を行う予定なので、何か気になった点やこうした方が良いなどあればコメントで教えて頂けると幸いです。


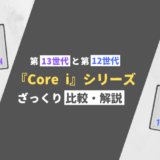

判りやすい解説で参考になりました。
海外系の自動翻訳の比較ベンチマークは直ぐに見つかるけど、Ryzenは細かい型番があり、どれがどれだか判りにくくて困っていました。
メーカーサイトも表示される内容がバラバラだし。
10万円台のビジネスモデルだと、ほぼRyzen 5一択。
7530uが多数を占める中、あえて8540uにする意味あるのか、選んでからも少し心配していましたが、こちらを見て選択は間違ってなかったと確信できました。
コア数の力押しで、少しでもゲームできるように割り切った7530uの方がいいのか、zen4でCPU性能重視の8540uがいいのか。
ゲームはしないから、少しでも長く使えそうな8540uにしたとはいえ、AV1は何故かエンコードだけでデコードに対応していないのが気になるところ。
日常ではデコードのほうが重要だと思うのだけど。
コメントありがとうございます。励みになります。
AV1デコードは現状は無くても困らない部分ではあるので、中々評価が難しい部分ですね。
また、ゲーム性能は「Ryzen 5 7530U」の「RX Vega 7」よりも「Ryzen 5 8540U」の「Radeon 740M」の方が1.5倍ほど高性能となっているので、ゲームでも8540Uの方が上なので、大丈夫です。
更に、8540Uの「Radeon 740M」を含むRadeon 600M以降(RDNA 2~)では「AFMF」というゲームのフレーム生成機能に対応しており、フレームレートを底上げできたりするので、実質のゲーム性能はもっと高くなったりします。
最後に置いていたゲームのベンチマークの位置とか、参考程度にしか触れていなかったAFMFの説明とかもっと分かり易いところに置いた方が良かったなと反省しています…。
一応取り急ぎですが、ベンチマークスコアを上の方に移しておいたので、興味があればご覧くださいませ。
「Dragon Ridge」は「Dragon Range」の誤りではありませんか。
その通りです。ご指摘感謝します。
修正いたしました。
早速の修正と御返事、ありがとうございました。
PCについての知識が豊富ではないので、とねりんさんの記事を読んで、いつも勉強させていただいています。
今回はyoutubeの映像コーデックのAV1への移行状況の見通しについて、とねりんさんの見立てをお聞きしたく、コメントしました。
昨年ノートPCを買い換えた後、本記事で映像コーデックのことを知りました。
調べたところ、そのPCの内蔵GPUがRadeon Vega 8でした。(CPUはRyzen7 5800Hです)
youtubeで動画をよく見るので、AV1への移行が急速に進むことを懸念しております。
(最低でも5年はそのノートPCを使いたいと思っているので)
8K動画などは移行されているという指摘を見ましたし、当然のことながら、今後は4KやFHDでも移行が進んでいくのは避けられませんよね。
私はだいたいFHDで視聴しているのですが、移行はどのぐらいのスピードや年数で進んでいくとお考えでしょうか?
予見が難しいことは承知で質問しております。
ご回答よろしくお願いいたします。
ご覧いただきありがとうございます。記事内での私の書き方が悪かったかもしれませんので、始めに少し補足しておこうと思います。
まず、FHD/60p程度の動画であれば、AV1デコードに対応していなくても「Ryzen 7 5800H」クラスの高性能CPUなら、CPUのみで十分ゴリ押しできるレベルだと思います。そのため、視聴が困難ということにはならないので、その点は安心して良いかと思います。
見返すと、AV1デコードが無いと論外みたいな文章になっていたので、後で修正しておこうと思います。
ただし、CPUにとっては重い処理になりますので、それなりの使用率となり消費電力と発熱が増加すると思われます。最近ではPCで動画を観ることは日常的な人が多いと思いますが、その際に常に高負荷な処理が要求されるのは、特にモバイル端末にとっては好ましくないので、事前に知っておいて少しの追加費用で対応できるならしといた方が良いよねって感じで触れたかった次第でした。
前置きが長くなりましたが、本題のAV1の移行状況についてです。
正直なところ、見当が付きません。YouTubeなどの主要動画サイトの匙加減次第ですから、申し訳ないですが、具体的な年数については参考になる回答はできないかと思います。
ただ、少なくともこれからすぐには急激に移行が進むことはなく、数年は深く気にする必要はない状況が続くとは思っています。一番の理由は、スマホやAppl製品での対応がほとんど進んでいないためです。
まずApple側ですが、Macで搭載されるAppleのプロセッサの最新は現在「Apple M2」ですが、このSoCではAV1に対応していません。また、Apple製品の標準ブラウザである「Safari」でもAV1が現状では正式サポートされていません。
スマホに関しても、Android向けのSoCとしてはQualcommのSnapdragonのシェアがかなりの割合を占めますが、SnapdragonでAV1対応をしているのは、現状最近出たハイエンドSoCである「Snapdragon 8 Gen 2」だけで、現在のAndroidユーザーのほとんどが対応していません。
上記のような状況がある中、無理やりAV1移行が進められることはさすがにないと思うので、少なくともそこがある程度対応するまでは、全体として急激に進むことはない気はしています。時間的余裕はそれなりにあるとは思います。5年絶対持つとは言い切れませんが、今めちゃくちゃ後悔するほどではないと思います。
ただ、最近Apple製品の標準ブラウザである「Safari」のベータ版ではAV1対応がされたとのニュースもあるので、Appleも一応普及に向けて下地は作り始めようとしている感じはありますし、SnapdragonでもAV1対応製品が出たというのは事実なので、少しずつ進んでいくことは確実なのかなとは感じています。そのため、今購入するならやはりAV1対応製品がおすすめかなというのが私見という感じですね。
煮え切らない回答で申し訳ありませんが、以上が回答になります。
お早い回答ありがとうございます。
やはりとねりんさんに質問して良かったです。
懸念が少し解消されました。
数年の猶予はあるということで、気にしすぎることはないですね。
スマホやApple製品での対応が進んでいないのは、意外でした。
しかしながら、対応した製品が出始めている以上は、トレンドとしては徐々に移行されていくのが確実なのですね。
ど素人の考えで恐縮ですが、スマホでの対応がある程度進めば、急速に移行が進むのだろうなと思います。
数年は気にすることがないと分かっただけでも安心できました。
丁寧な回答ありがとうございました。