この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
IntelとAMDの主流CPUシリーズの「Coreシリーズ」と「Ryzenシリーズ」ざっくり比較・解説しています。ノートPC向けの新しめの主要世代(2025年10月21日時点)を対象としています。
※Ryzen AI 300の掲載当初の内容で、GPU側にAIエンジンを搭載していないと記載しておりましたが、実際にはAIアクセラレータがCU数×2分搭載されており、誤りでした。お詫びして訂正いたします。
- 掲載の情報は記事更新時点(2025年10月21日)でのものであり、ご覧になっている際には異なる可能性があるため注意してください。
ノートPC向けの主要世代が対象(メインは最新世代)
本記事はPCの主流CPUの「IntelのCoreシリーズ」と「AMDのRyzenシリーズ」の各種のノートPC向けの主要世代のものを対象としています。
ただし、最近では最新世代は価格が高すぎて主要シリーズと言って良いのか怪しいモデルも増えていたりして、メーカー側も実質リネームなどをして旧世代の安価なCPUを継続して販売することが一般的となっているので、少し前の世代も継続して扱うことが多いです。
主流の省電力モデル(TDP:15W~28W)が対象
新しめのCPUに絞っているとはいえ、全シリーズを網羅するのは難しいので、本記事では最も採用率が高いと思われる主要シリーズのみを扱います。具体的には、やや消費電力が抑えられているモデルになります。
ノートPC向けのCPUはざっくり分けて、以下の3種類があります。
- 性能重視モデル(35W)
- 省電力モデル(15W~28W)※対象
- 超消費電力モデル(10W未満)
※()内はTDP PL1の値
本記事ではこの中で「省電力モデル(TDP:15W~28W)」を見ていきます。また、ここでいうTDPはPL1(1段階目の制限)となっており、実際の最大消費電力とは異なる点は注意してください。
他の2モデルについては詳しくは触れませんが、記事後半に補足として特徴だけ触れているので、気になる方は参考までにご覧ください。
まず、細かな数字などをなるべく省いたざっくり比較表を置いておきます。大まかな特徴は下記だけ見れば大体わかるのかなと思います。
| 特徴と評価 | 参考価格 5モデル以降 | CPU性能 | 内蔵GPU | 消費電力 ベース電力 | AI性能 NPU AI TOPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen AI 300 例:Ryzen AI 7 350 AIプロセッサ | 全方面高水準 隙の無いAIプロセッサ | モデル次第 | (Ryzen AI 7~) (Ryzen AI 5) | 28W ※効率は良い | ~50TOPS (GPUにもAIユニット) | |
| Core Ultra 200V 例:Core Ultra 7 256V 等 AIプロセッサ | 内蔵GPUとAI性能 特化 | 14万円~ | 17W | ~48TOPS (XMX:~67TOPS) | ||
| Ryzen 200 / 8000U 例:Ryzen 7 8840U ※HSもほぼ同評価 ※7040もほぼ同評価 | 高性能CPU&GPU 競合より安価 優れたコスパ | 9万円前後~ | (Ryzen 7~) (Ryzen 5) | 28W ※効率は良い | ~12TOPS ※一部NPUなし | |
| Core Ultra 200H 例:Core Ultra 5 225H 等 | 高性能CPU&GPU コスパ重視 | 11万円~ | 28W~45W | ~13TOPS (XMX:~67TOPS) | ||
| Core Ultra 200U 例:Core Ultra 5 225U 等 | 比較的安価に NPU搭載 | 10万円~ | 15W | ~12TOPS | ||
| Ryzen 7035U 例:Ryzen 7 7735U ※HSもほぼ同評価 | 比較的安価に 高性能CPU&GPU AI無しで高コスパ | 7万円台~ | (Ryzen 7~) (Ryzen 5) | 28W | NPUなし | |
| Core Ultra 100H 例:Core Ultra 7 155H 等 | 比較的安価に 優れたCPUと内蔵性能 | 10万円~ | 28W~45W | ~11TOPS | ||
| Core Ultra 100U 例:Core Ultra 5 125U 等 | 比較的安価に NPU搭載 ※正直安くない | 10万円~ | 15W | ~11TOPS | ||
| Ryzen 7030U 例:Ryzen 5 7530U | 安価な旧世代 CPUコスパ特化 GPU微妙 | 6万円台~ | ※AV1対応なし ※AFMFなし | 15W | NPUなし | |
| Core 100U Core 1300U 例:Core 5 120U Core i5-1335U 等 | 安価な旧世代 安価な割に 機能面まずまず | 6万円台~ | ※軽処理には十分 | Ultra 100Uより 少し低い | 15W | NPUなし |
| Ryzen 7020U 例:Ryzen 5 7520U | 安さ特化 低性能省電力 | 5万円台~ | 4コアのみ ※軽処理なら可 | AV1デコードには対応 | 15W | NPUなし |
ベンチマークスコアまとめ
次に細かい数値の内容です。下記に、2025年10月時点の主要シリーズのCPUと内蔵GPUの性能のベンチマークスコアをまとめています。
PCの頭脳となるCPUの処理性能です。ここでは、デフォルトTDPが28W以下の省電力CPUの性能を載せています。CPUの処理性能がPC全体に影響を与えるため非常に重要です。
ただし、昔と比べて性能が格段に底上げされているため、軽い処理しかしないなら、現在では安価なCPUでも必要十分だったりします。下記のCinebench R23 Multiのスコアでいうと、5,000もあれば軽い処理なら困ることはほぼないと思います。
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Ryzen AI 9 HX 370 | |
| Ryzen AI 9 365 | |
| Core Ultra 7 255H | |
| Ryzen AI 7 350 | |
| Core Ultra 5 225H | |
| Core Ultra 7 155H | |
| Core Ultra 9 288V | |
| Ryzen 7 250 | |
| Ryzen 7 8840U | |
| Ryzen 7 7840U | |
| Core Ultra 5 135H | |
| Core Ultra 5 125H | |
| Ryzen AI 5 340 | |
| Core Ultra 7 255U | |
| Core Ultra 5 225U | |
| Ryzen 7 7730U | |
| Ryzen 7 7735U | |
| Core Ultra 7 258V | |
| Core i5-1340P | |
| Core i7-1360P | |
| Core Ultra 7 165U | |
| Ryzen 7 6800U | |
| Ryzen 5 8640U | |
| Ryzen 5 7640U | |
| Core Ultra 7 256V | |
| Core Ultra 5 226V | |
| Ryzen 5 8540U | |
| Core 7 150U | |
| Core Ultra 5 125U | |
| Core 5 120U | |
| Core i7-1355U | |
| Ryzen 5 6600U | |
| Ryzen 5 7530U | |
| Core i5-1335U | |
| Core i3-1220P | |
| Core 3 100U | |
| Core i3-1215U | |
| Ryzen 5 7520U |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Core Ultra 7 255H | |
| Core Ultra 5 225H | |
| Ryzen AI 9 HX 370 | |
| Ryzen AI 7 350 | |
| Core Ultra 9 288V | |
| Ryzen AI 9 365 | |
| Ryzen AI 5 340 | |
| Core 7 150U | |
| Core Ultra 7 258V | |
| Core Ultra 7 256V | |
| Core Ultra 7 255U | |
| Core 5 120U | |
| Core i7-1360P | |
| Core i7-1355U | |
| Core Ultra 5 226V | |
| Core 3 100U | |
| Core Ultra 7 155H | |
| Core Ultra 5 225U | |
| Ryzen 7 250 | |
| Ryzen 5 8640U | |
| Ryzen 5 8540U | |
| Core i5-1340P | |
| Ryzen 7 7840U | |
| Ryzen 7 8840U | |
| Core Ultra 7 165U | |
| Core Ultra 5 135H | |
| Core i5-1335U | |
| Core i3-1220P | |
| Core Ultra 5 125H | |
| Core Ultra 5 125U | |
| Core i3-1215U | |
| Ryzen 5 7640U | |
| Ryzen 7 7735U | |
| Ryzen 7 6800U | |
| Ryzen 7 7730U | |
| Ryzen 5 6600U | |
| Ryzen 5 7530U | |
| Ryzen 5 7520U |
GPUはグラフィック面の処理を担当するユニットです。ビデオカードを搭載しないノートPCの場合はCPUに内蔵・統合されているGPUを利用することになりますので、そちらの性能をゲームのベンチマークスコアを参考に見ていきます。
ただし、ビデオカードを搭載するPC(主にゲーミングノートやクリエイターノート)の場合は、内蔵GPUは基本使わないので気にしなくても大丈夫です。
2025年3月現在では内蔵GPUの性能も昔よりも飛躍的に向上しています。アップスケーリングやフレーム生成機能の普及も進んでいることもあり、上位モデルでは重めのゲームなどにも対応できるレベルになっています。
しかし、まだ重量級ゲームを快適にプレイしたり、データ量の多い動画の編集等で常用するには厳しい性能なので、そのような用途での利用を検討している場合にはビデオカードを搭載したゲーミングノートやクリエイターノートをおすすめします。
| GPU名称 (搭載CPUの例) | スコア |
|---|---|
| Intel Arc 140T (Core Ultra 7 255H 等) | |
| Intel Arc 140V (Core Ultra 7 256V 等) | |
| Radeon 890M (Ryzen AI 9 HX 370 等) | |
| Intel Arc 130T (Core Ultra 5 225H 等) | |
| Intel Arc 8コア GPU (Core Ultra 7 155H 等) | |
| Intel Arc 130V (Core Ultra 5 226V 等) | |
| Radeon 880M (Ryzen AI 9 365 等) | |
| Arc 7コア GPU (Core Ultra 5 125H 等) | |
| Radeon 860M (Ryzen AI 7 350 等) | |
| Radeon 680M (Ryzen 7 7735U 等) | |
| Radeon 760M (Ryzen 5 8640U 等) | |
| Intel Graphics 4コア(Arc) (Core Ultra 7 165U 等) | |
| Iris Xe G7 96EU (~1400MHz) (Core i7-1360P 等) | |
| Radeon 840M (Ryzen AI 5 340 等) | |
| Radeon 660M (Ryzen 5 7535U 等) | |
| Radeon 740M (Ryzen 5 8540U 等) | |
| Iris Xe G7 80EU(-1300MHz) (Core i5-1340P 等) | |
| Radeon RX Vega 8 (Ryzen 7 7730U 等) | |
| Radeon RX Vega 7 (Ryzen 5 7530U 等) | |
| UHD Xe 64EU (Core i3-1220P 等) | |
| Radeon RX Vega 6 (Ryzen 3 5300U 等) | |
| Radeon 610M (Ryzen 5 7520U 等) |
各比較に入る前に、知っておいた方が良いかもしれない仕様の要点や注意点について軽く触れています。
内蔵GPUでのゲーム性能を重視したい方は注目したいのが、AMDのRadeon(RDNA 2以降)で使える「AFMF」です。
「AFMF」は、AMDの「RDNA 2」以降のアーキテクチャのGPUで対応しているゲームのフレーム生成機能です。モバイル版Ryzenだと「Radeon 600M~」で対応しています(※ただし、Ryzen Z1など一部は対応状況に違いがあるので注意)。RyzenでもVega GPUを採用している場合には非対応なので注意が必要です(例:Ryzen 5 7530U、Ryzen 7 7730U)。
AFMFはゲーム外からフレームを挿入することによってフレームレートを底上げしますが、ドライバによる動作となっており、ゲーム側の対応や設定が必要なく気軽に使えるのが強みです。AMD製品の公式のUIソフト「AMD Software: Adrenalin Edition」から該当機能を事前にオンにしておくだけで利用することができます。ゲームが用途に含まれるなら非常に魅力的な機能です。
これがAMDのドライバの機能のため、IntelのCoreでは使うことができないというのがゲームを重視したい人にとってはポイントとなります。
非常に軽いゲームなら無くても困ることはありませんが、やや重めのゲームにも対応しておきたいならかなり重視しても良い項目だと思います。
NPUはAI処理用のプロセッサのことです。2024年現在、近年の急激なAIの発達や普及から、PCのプロセッサにもNPUが搭載されるものが多くなってきました。
Windows 11においてもローカルで動作できるAI機能が統合されることになり、その要件(NPU:40TOPS以上など)を満たすPCは「Copilot+ PC」と呼ぶことができ、次世代のAI PCとして注目されています。
そのため、今後はこの「40TOPS」の性能を超えるAI性能持つPCが特にAI PCとして魅力的になるのが一つポイントです。ただし、これはNPU単体で到達しないといけない訳ではなく、microsoftが認定した他プロセッサ(恐らく主にGPUやGPU搭載のAIエンジン)との合計でも構わない点に注意です。
特に、GeForceなどのNVIDIA製のGPUはAIに関しても優れた性能と汎用性を備えるので、NPUが無くても基本的に大丈夫な可能性が高いです。
また、オンラインでのチャットボットAIのようなものはNPUが無くても引き続き利用できるので、ローカル動作のAI機能が必要ない場合にもNPUは必要ありません。注目されてはいるものの、全てのユーザーが備えておきたいという訳でもないので、用途次第です。
まず知っておいた方が良いのは、Eコア(小型で省電力性や効率重視コア)についてです。
昔のCPUは、各コアはクロックや質の違いはあれど、物理的な設計は基本同じ1種類のコアを採用しているのが基本でしたが、第12世代以降のCoreでは「高性能コア(Pコア)」と「高効率コア(Eコア)」という、異なるコアが混在する仕様となっています。また、Coreは「Meteor Lake」ではLP Eコア(低電力Eコア)というコアも導入しており、少し複雑な設計になっています。
ポイントとなるのは、EコアはPコアと比べると、コアあたりの性能が劣る点がポイントです。その代わり、Pコアよりもサイズが格段に小さいため、低コストかつ低消費電力稼働に向いてるメリットがあります。
Eコアにもメリットはありますが、コア自体の質はPコアの方が優れているので、CPUのコア数だけで性能を判断することが難しくなっているのが注意しなけえればならない点です。
たとえば、「Core i5-1335U」は10コアCPUですが、その内8コアがEコアとなっており、最終的な性能は「10コアCPU」と呼ぶにはやや非力だったりします。
また、頻発している訳ではありませんが、複数種類のコアを持つCPUでは、各アプリでコアの割り振りが適切に行われずにパフォーマンスや効率が低下する可能性も一応あるので、ベンチマークスコア等が同等なら基本的には1種類のアーキテクチャのコアのみを採用するRyzenの方が少しだけおすすめです。
まず「AV1(AOMedia Video 1の略)」というのは、映像コーデック(映像の圧縮の方式)の一つで、現在特に将来性があると言われている映像コーデックです。高い圧縮率かつロイヤルティーフリーな点が評価されており、採用が進んでいる方式で、YouTubeでも採用が増えています。
このAV1でエンコード(圧縮・符号化)された動画を観る際には、AV1のデコード(複合化)を行う必要がありますが、今回比較するCPUシリーズの中では唯一、Ryzen 7000シリーズのVega搭載モデル(Zen 3/7030モデル)のみ内蔵GPUに「AV1」のハードウェアデコード機能がないため、注意が必要です。Vegaが古いアーキテクチャのGPUのため、性能および機能面でやや遅れていることが原因です。
一応、GPUにデコード機能がなくてもCPUで対応することは可能なので、必須という訳ではありませんが、デコード処理はCPUにとっては非常に高負荷な処理で効率も悪いため、GPUに任せる方が望ましいです。
とはいえ、2024年1月現在ではFHD以下の動画のほとんどはAV1でなくても対応可能であるため、正直無くてもそこまで困らない部分ではあります。
これは、AV1の圧縮率の高さは魅力なものの、エンコードやデコードの負荷が大きい上、対応できないデバイスがまだ多いため、動画サイト側が4Kなどの超高画質動画のみでの対応が現状では主流なためです。
とはいえ、AV1対応デバイスの普及率は高まっていきますし、デバイスやプロセッサの性能が上がれば負荷の高さも問題なくなってきます。将来的にはAV1が主流になっていくとは思います。
それにはまだ時間が掛かるでしょうから、AV1対応をどれだけ重視するかは個人の判断にはよりますが、現状でもあって困るものではないので、個人的にはYouTubeをよく視聴する方が長期利用を見据えた将来性を考えるなら「Vega」は避けた方が無難だと思っています。
NPUはAI処理用のプロセッサのことです。2025年現在、近年の急激なAIの発達や普及から、PCのプロセッサにもNPUが搭載されるものが多くなってきました。
Windows 11においてもローカルで動作できるAI機能が統合されることになり、その要件(NPU:40TOPS以上など)を満たすPCは「Copilot+ PC」と呼ぶことができ、次世代のAI PCとして注目されています。
そのため、今後はこの「40TOPS」の性能を超えるAI性能持つPCが特にAI PCとして魅力的になるのが一つポイントです。
ただし、これはNPU単体で到達しないといけない訳ではなく、microsoftが認定した他プロセッサ(恐らく主にGPUやGPU搭載のAIエンジン)との合計でも構わない点に注意です。
特に、GeForceなどのNVIDIA製のGPUはAIに関しても優れた性能と汎用性を備えるので、NPUが無くても基本的に大丈夫な可能性が高いです。
また、オンラインでのチャットボットAIのようなものはNPUが無くても引き続き利用できるので、ローカルのAI機能が必要ない場合にもNPUは必要ありません。注目されてはいるものの、全てのユーザーが備えておきたいという訳でもないので、用途次第です。
高機能なドッキングステーションや、eGPU(外付けグラボ)、高速なデータ移動が必要な用途などで使いそうな場合には、USB Type-Cを用いた超高速なUSB通信「Thunderbolt4」や「USB4(Thunderbolt3相当)」への対応もチェックしておくと安心です。
「Thunderbolt」について軽く説明しておくと、ThunderboltではないUSBだと、機能や給電能力・通信速度などがバラバラですが、Thunderboltと明記されている場合には総じて高い性能が保証されている、と捉えて貰えれば分かり易いか思います(機能面はこれはUSB Type-Cで利用できるオルタネートモードというものを利用)。
- 高機能なドッキングステーションを利用可能
- eGPU接続(外付けの単体GPU)
- 超高速な通信
- 超高画質な映像の入出力(4K等)
このThunderbolt 4ですが、Coreでは第11世代から対応可能なのに対し、Ryzenでは最新の8000シリーズでも対応していません。そのため、Thunderboltが必須ならCore一択になります。
とはいえ、Ryzen 6000~8000の「Zen 3+以降」ではUSB4には対応しており、これにはThunderbolt 3相当のコントローラが統合されています。eGPUも利用可能となっており、完全互換ではないですがある程度は機能を利用できるので、Thunderboltの機能をフル活用しようとしない限りはUSB4があれば困ることはあまりないと思います。
CoreシリーズとRyzen シリーズは、Core i7 と Ryzen 7といったように、各モデルナンバーごとに対抗製品が存在します。価格帯も大体同じくらいです。この項目ではその両者を比較していきます。
下記の表では各項目を☆で評価していますが、これは相対的な差を比較したものであり、たとえば☆2だから低性能とは限らない点に留意です。また、記事執筆時点では各最新モデルの搭載製品が少なくベンチマークサンプルが少ないため、一部は筆者による推定値となっている点も留意してください(推測値の場合は明記しています)。
Core Ultra 200V と Ryzen AI 300


Core Ultra 200VおよびRyzen AI 300は2024年に発表された、高性能なNPUを搭載したCopilot+ PC対応のAIプロセッサです。
AI以外の性能も非常に優れており、内蔵グラフィック性能は特に魅力的です。ビデオカード無しでも重めのゲームや動画編集に対応します。
Windowsにおいてはゲームでも「Auto SR」というAIによるゲームのfps向上機能(アップスケーリング)も追加・普及していく予定があり、この二つなら十分に活用できるAI性能があると思われるので、ゲーム用途でも期待できるチップとなっています。
また、性能だけでなく、電力面も非常に優秀なのも大きな強みです。双方とも最新鋭のプロセスを採用している上に、優れた小型コアを採用しています。
そのため、薄型軽量機に対応した省電力プロセッサながら性能も高く、様々な分野で活躍できるプロセッサとなっています。
ただし、価格はものすごく高価になっており、発売時点では最安でも17万円~となっているのが大きなデメリットです。同一チップでの総合性能は凄まじいですが、従来の高性能ゲーミングノートを検討できるレベルなので、搭載PCの総合性能コスパは正直良くはないです。
ゲーミングノートと比較すると、GeForceなら優れたAI性能があるので、高性能NPUも大きな利点とはなりにくいですし、ゲーム性能も単体のビデオカードにはまだ大きく及ばないです。
「バッテリー性能の優れた薄型軽量機ながらAIも含めた重い処理もこなせる」という点では非常に強力ですが、そこを重視しないならコスパ的には微妙なシリーズにはなっています。
以下、簡易比較表です。
| CPU名 | マルチ スレッド | 安さ | 内蔵GPU | 省電力性 | |
|---|---|---|---|---|---|
 | Core Ultra 7/9 200V 8コア(4P+4E) 8スレッド 258V 等 | ★4.25 | ★1.0 | ★5.0 | ★4.5 |
 | Ryzen AI 9(12コア) | ★5.0 | ★1.0 | ★4.75 | ★4.25 |
 | Core Ultra 5 200V 8コア(4P+4E) 8スレッド 236V 等 | ★4.25 | ★1.25 | ★4.75 | ★4.5 |
 | Ryzen AI 9(10コア) | ★4.75 | ★1.25 | ★4.5 | ★4.25 |
 | Ryzen AI 7(8コア) | ★4.5 | ★2.0 | ★4.25 | ★4.25 |
 | Ryzen AI 5(6コア) | ★4.25 | ★2.75 | ★3.75 | ★4.25 |
主要モデルを一部抜粋して比較しています。
| CPU | PassMark スコア | コア/ スレッド | 動作クロック 定格/最大 | TDP | 内蔵GPU | NPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen AI 9 HX 370 | 35310 | 12/24 (4+8) | 2.0 / 5.1GHz 2.0 / 3.3GHz | 28W | Radeon 890M(16CU) | ~55TOPS |
| Ryzen AI 9 365 | 29392 | 10/20 (4+6) | 2.0 / 5.0GHz 2.0 / 3.3GHz | 28W | Radeon 880M(12CU) | ~50TOPS |
| Ryzen AI 7 350 | 24525 | 8/16 (4+4) | 2.0 / 5.0GHz 2.0 / 3.5GHz | 28W | Radeon 860M(8CU) | ~50TOPS |
| Ryzen AI 5 340 | 20355 | 6/12 (3+3) | 2.0 / 4.8GHz 2.0 / 3.4GHz | 28W | Radeon 840M(4CU) | ~50TOPS |
| Core Ultra 7 268V | 20246 | 8/8 (4P+4E) | 2.2 / 5.0GHz 2.2 / 3.7GHz | 17W – 37W | Arc 140V(8コア) ※XMX:~66TOPS | ~48TOPS |
| Core Ultra 9 288V | 20144 | 8/8 (4P+4E) | 3.3 / 5.1GHz 3.3 / 3.7GHz | 30W – 37W | Arc 140V(8コア) ※XMX:~67TOPS | ~48TOPS |
| Core Ultra 7 258V | 19468 | 8/8 (4P+4E) | 2.2 / 4.8GHz 2.2 / 3.7GHz | 17W – 37W | Arc 140V(8コア) ※XMX:~64TOPS | ~47TOPS |
| Core Ultra 7 256V | 19320 | 8/8 (4P+4E) | 2.2 / 4.8GHz 2.2 / 3.7GHz | 17W – 37W | Arc 140V(8コア) ※XMX:~64TOPS | ~47TOPS |
| Core Ultra 5 236V | 18872 | 8/8 (4P+4E) | 2.1 / 4.7GHz 2.1 / 3.5GHz | 17W – 37W | Arc 130V(7コア) ※XMX:~53TOPS | ~40TOPS |
| Core Ultra 5 226V | 18769 | 8/8 (4P+4E) | 2.1 / 4.5GHz 2.1 / 3.5GHz | 17W – 37W | Arc 130V(7コア) ※XMX:~53TOPS | ~40TOPS |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Ryzen AI 9 HX 370 | |
| Ryzen AI 9 365 | |
| Ryzen AI 7 350 | |
| Core Ultra 9 288V | |
| Ryzen AI 5 340 | |
| Core Ultra 7 258V | |
| Core Ultra 7 256V | |
| Core Ultra 5 226V |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Ryzen AI 9 HX 370 | |
| Ryzen AI 9 365 | |
| Ryzen AI 7 350 | |
| Core Ultra 9 288V | |
| Ryzen AI 5 340 | |
| Core Ultra 7 258V | |
| Core Ultra 7 256V | |
| Core Ultra 5 226V |
| GPU名称 (搭載CPUの例) | スコア |
|---|---|
| Arc 140V (Core Ultra 7 258V 等) | |
| Radeon 890M (Ryzen AI 9 HX 370 等) | |
| Arc 130V (Core Ultra 5 226V 等) | |
| Radeon 880M (Ryzen AI 9 365 等) | |
| Radeon 860M (Ryzen AI 7 350 等) | |
| Radeon 840M (Ryzen AI 5 340 等) |
Core Ultra 200V:競合モデルより優れたAI性能とグラフィック性能が魅力
「Core Ultra 200V」はCore Ultraの第2シリーズです。先に触れておくと、下位モデルと上位モデルと性能差が小さいので、どのモデルも似たような評価です。
NPUの性能は40~48TOPSとなり、Copilot+ PCのAI性能要件「40TOPS」をNPU単体で満たした他、GPUにもAIエンジンが搭載(53~67TOPS)されており、プロセッサ合計では100TOPSを超えます。
競合となる「Ryzen AI 300」、「Snapdragon X Elite」、「Apple M3/M4」の全てに対してAI性能では頭一つ抜けて上回っているのがまず大きな強みです。
更に、プロセスの大幅微細化やコア仕様の刷新により前世代から電力面も大幅に改善しています。元々優れていた内蔵GPUも性能を伸ばしており、将来性や実用性が前世代から大きく向上しています。
その代わり、少し気になるのはCPUです。CPUのコア・スレッド数は、全モデル8コア8スレッド(4P+4E)です。前世代の最大16コアから大きく削減された上に、ハイパースレッディンツグ(1コア=2スレッド)もなくなりました。
Eコアの性能は前世代より格段に向上したものの、さすがに8コア8スレッドCPUなので、10コア以上が当たり前の競合モデルよりも劣る性能となっています。
しかし、その代わりに電力面が大幅に改善しました。ここ数年のCoreは他の競合モデルに電力面で劣っているのがノートPC向けのSoCとしては大きな弱点でしたが、そこが改善されたのは嬉しいです。Intelとしては、無駄になる可能性の高い最大性能よりも、確実に恩恵のある電力面を重視した形です。
前世代から引き続き内蔵GPU性能が優れているのも大きな強みです。「Arc 130V(7コア)」か「Arc 140V(8コア)」が搭載されています。GPUのコア数は下位モデルでも大差ないので、全モデルで優れたグラフィック性能を期待できます。やや重めのゲームや動画編集に対応できるレベルです。
更に、先にも触れた通り、GPUにもAIエンジン「XMX」が搭載されるようになりました。XMXも単体で53~67TOPSと高性能です。ゲームのアップスケーリングなどでも活躍を期待することができます。
そして、電力面の具体的なところでは、Core Ultra 9以外のベース電力は17Wに設定されており、最大でも37Wです。前世代の主流モデルが28W~64Wだったことを考えると、その数値だけでも格段に改善していることがわかります。
新世代なのにCPU性能が向上しないという異例のシリーズにはなっていますが、CPU性能もモバイル向けとして考えればネkックになるケースはほとんどない人が多いと思いますし、CPU以外では多数の大幅な改善が見られます。実用性に非常に優れたシリーズとなっていると思います。
しかし、大きな問題は価格です。ものすごく高価です。発売直後の2024年10月時点だと、搭載PCは最安でも約17万円となっており、過去に類を見ないほど高額さです。高性能なAIユニットを2つも搭載している上に、ベースとなるプロセスも最新鋭のものなので仕方ないとは思いますが、最低17万円となると高性能なゲーミングノートが普通に購入できますし、最新のGeForceならAI性能も高いので、総合性能コスパという意味では発売時の価格では正直良くないです。
Ryzen AI 300:高性能NPU&GPUに加え、CPU性能の高さと効率が魅力
Ryzen AI 300シリーズは、2024年6月発表のZen 5アーキテクチャ採用のシリーズです。
特徴としては、まず名前に「AI」と含まれていることからも分かる通り、50TOPS~の高いAI処理性能を誇るNPUを搭載しています。Windowsが定めたCopilot+ AI PCの要件「45TOPS」をクリアしており、搭載PCは「Copilot+ AI PC」を名乗ることができます。
また、小型コアの「Zen 5c」を採用したのもポイントです。高性能な「Zen 5」コアと小型の「Zen 5c」コアの2種類を採用という形になっています。
IntelのCore Ultra 200シリーズと異なり、高性能コアと小型コアの両方がハイパースレッディングに対応しているため、CPU性能が非常に高いです。
「Ryzen AI 9 HX 370(12コア24スレッド)」では「Core Ultra 7 258V(8コア8スレッド)」の約1.8倍ものマルチスレッド性能を発揮し、他の競合モデルと比べても明らかに高い性能となっています。そのため、AI性能だけでなくCPU性能も重視したい場合には魅力的です。
そして、Ryzen AI 300は 内蔵GPU性能も強力です。下位モデル(Ryzen AI 5)を除けば、重めのゲームや動画編集にも対応できます。
また、Radeonではドライバ動作で気軽に使えるゲームのフレーム生成機能である「AFMF」があるのも強みです。重量級ゲームで高設定&高fpsでプレイというのはまだ厳しいものの、高いレベルを求めなければ割と不自由なく対応できるようになったかなと思います。
更には、Core Ultra 200と同じように、Ryzen AI 300 のGPU にもAIエンジンが統合されていうます。CU数×2のAIアクセラレータが搭載されています。
Intelと違って性能を数値化して強調していませんが、高度なAI処理への対応も示唆されているので、行列演算に特化したIntelのXMXよりも汎用性では勝る可能性もあるのが一つポイントとなるかもしれません。
CPU・GPU・NPUのどれを取っても非常に高性能な次世代AIプロセッサにふさわしい性能を持っていると思います。
そして、最後に価格ですが、「Core Ultra 200V」と同様にかなり高価です。これが現状はやはりネックです。
2025年7月時点での搭載ノートPCの市場のおおよその最安値を見てみると、「Ryzen AI 5 340」が10万円台後半、「Ryzen AI 7 350」が13万円前後、「Ryzen AI 9 HX 370」が18万円程度となっています。
「Ryzen 8000」シリーズの方が格段に安価で、CPUとGPUの性能コスパで見れば明らかに負けています。
AI性能は格段に上なので総合的なコスパで負けていると断じることはできませんが、2025年時点では恩恵が限定的すぎるAI性能のために追加予算を大幅に使うのも中々割り切るのが難しい部分だとは思います。
そのため、将来を見据えて「Copilot+ PC」の導入やAI性能の強化をしたい人にはおすすめできますが、2025年7月時点での実用性能コスパを重視するなら、正直やや微妙な選択ではあると思います。
Core 7 とRyzen 7
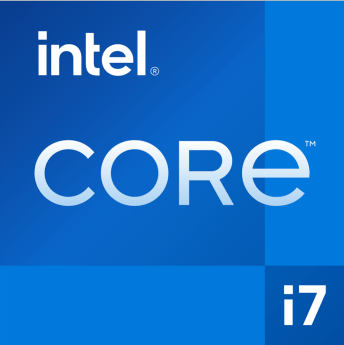

Core Ultra 7 / Core 7 / Core i7およびRyzen 7はモバイル版の主流CPUにおける上級モデルです。両者高い性能を持っていますが、その代わりに搭載製品の価格は高く、高級機を中心に採用されます。ほとんどが10万円を超えるレベルとなっています。
以下、簡易比較表です。
| CPU名 | マルチ スレッド | 安さ | 内蔵GPU | 省電力性 | |
|---|---|---|---|---|---|
 | Core Ultra 7(200H) 16コア(6P+8E+2LP E) 16スレッド 255H 等 | ★4.75 | ★1.25 | ★5.0 | ★4.0 |
 | Core Ultra 7(100H) 16コア(6P+8E+2LP E) 22スレッド 155H 等 | ★4.5 | ★1.5 | ★4.75 | ★3.75 |
 | Ryzen 7(Zen 4) | ★4.5 | ★2.25 | ★4.5 | ★4.0 |
 | Core Ultra 7(200U) 12コア(2P+8E+2LP E) 14スレッド 255U 等 | ★4.25 | ★2.0 | ★4.0 | ★4.0 |
 | Core Ultra 7(100U) 12コア(2P+8E+2LP E) 14スレッド 165U 等 | ★4.0 | ★2.0 | ★3.75 | ★3.75 |
 | Ryzen 7(Zen 3+) | ★4.5 | ★3.0 | ★4.25 | ★4.0 |
 | Core i7(第13世代-P) 12コア(4P+8E) 16スレッド ※14コアモデル除く | ★4.25 | ★3.0 | ★3.75 | ★3.25 |
 | Core 7(シリーズ1) Core i7(第13世代-U) 10コア(2P+8E) 12スレッド 150U/1355U 等 | ★4.0 | ★3.0 | ★3.75 | ★3.5 |
 | Ryzen 7(Zen 3) 8コア16スレッド 7730U 等 | ★4.25 | ★3.5 | ★3.25 | ★3.5 |
Core i7とRyzen 7の人気モデルを一部抜粋して比較しています。
| CPU | PassMark スコア | コア/ スレッド | 動作クロック 定格/最大 | TDP | 内蔵GPU |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 7 255H | 30820 | 16/16 (6P+8E+2LP E) | P:2.0 / 5.1GHz E:1.5 / 4.4GHz LP E:0.7 / 2.5 GHz | 28W – 115W | Arc 140T |
| Core Ultra 7 155H | 24780 | 16/22 (6P+8E+2LP E) | P:1.4 / 4.8GHz E:0.9 / 3.8GHz LP E:0.7 / 2.5 GHz | 28W – 115W | Arc 8コア GPU |
| Ryzen 7 7840U | 24641 | 8/16 | 3.3 / 5.1GHz | 28W | Radeon 780M |
| Ryzen 7 250 | 23552 | 8/16 | 3.3 / 5.1GHz | 28W | Radeon 780M |
| Ryzen 7 8840U | 23403 | 8/16 | 3.3 / 5.1GHz | 28W | Radeon 780M |
| Ryzen 7 7735U | 20555 | 8/16 | 2.7 / 4.75GHz | 28W | Radeon 680M |
| Ryzen 7 6800U | 20557 | 8/16 | 2.7 / 4.7GHz | 15W – 28W | Radeon 680M |
| Core i7-1370P | 20173 | 14/20 (6P+8E) | P:1.9 / 5.2GHz E:1.4 / 3.9GHz | 28W – 64W | Iris Xe Graphics G7 96EU |
| Core i7-1360P | 18633 | 12/16 (4P+8E) | P:2.2 / 5.0GHz E:1.6 / 3.7GHz | 28W – 64W | Iris Xe Graphics G7 96EU |
| Core Ultra 7 255U | 17946 | 12/14 (2P+8E+2LP E) | P:2.0 / 5.2GHz E:1.7 / 4.2GHz LP E:0.7 / 2.4 GHz | 15W – 57W | Arc 4コア GPU |
| Ryzen 7 7730U | 17844 | 8/16 | 2.0 / 4.5GHz | 15W | Radeon RX Vega 8 |
| Core Ultra 7 165U | 16853 | 12/14 (2P+8E+2LP E) | P:1.7 / 4.9GHz E:1.2 / 3.8GHz LP E:0.7 / 2.1 GHz | 15W – 57W | Arc 4コア GPU |
| Core 7 150U | 15042 | 10/12 (2P+8E) | P:1.8 / 5.4GHz E:1.2 / 4.0GHz | 15W – 55W | Iris Xe Graphics G7 96EU |
| Core i7-1355U | 14162 | 10/12 (2P+8E) | P:1.7 / 5.0GHz E:1.2 / 3.7GHz | 15W – 55W | Iris Xe Graphics G7 96EU |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Core Ultra 7 255H | |
| Core Ultra 7 155H | |
| Ryzen 7 250 | |
| Ryzen 7 8840U | |
| Ryzen 7 7840U | |
| Ryzen 7 7730U | |
| Ryzen 7 7735U | |
| Core i7-1360P | |
| Core Ultra 7 165U | |
| Ryzen 7 6800U | |
| Core 7 150U | |
| Core i7-1355U |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Core Ultra 7 255H | |
| Core 7 150U | |
| Core i7-1360P | |
| Core i7-1355U | |
| Core Ultra 7 155H | |
| Ryzen 7 250 | |
| Ryzen 7 7840U | |
| Ryzen 7 8840U | |
| Core Ultra 7 165U | |
| Ryzen 7 6800U | |
| Ryzen 7 7735U | |
| Ryzen 7 7730U |
| GPU名称 (搭載CPUの例) | スコア |
|---|---|
| Arc 140T (Core Ultra 7 255H 等) | |
| Intel Arc 8コア GPU (Core Ultra 7 155H 等) | |
| Radeon 780M (Ryzen 7 7840U 等) | |
| Radeon 680M (Ryzen 7 7735U 等) | |
| Intel Graphics 4コア(Arc) (Core Ultra 7 165U 等) | |
| Iris Xe G7 96EU (~1400MHz) (Core i7-1260P 等) | |
| Radeon RX Vega 8 (Ryzen 7 7730U 等) |
Ryzen 7 7735U:最新世代よりも少し安価でコスパが良い
「Ryzen 7 7735U」などのZen 3+のRyzen 7は、高い性能を備えつつ、Zen 4(Ryzen 7 8840U等)やCore Ultra 7よりは安価なのが魅力です。また、7735HSなどもクロックや電力制限値が少し高くなっているだけで、物理的にはほとんど同じものなので、評価もほぼ同じです。
世代的には旧世代なので、処理性能は最新世代にはやや劣るものの、CPUは8コア16スレッドによる優れた性能を持っている上、内蔵GPUの性能も内蔵の割には高めです。最新世代と比べても実用性が格段に変わるほどではないくらいには高性能です。
それでいて、最新の7モデルよりは一段安価なので、実用コスパが非常に良いです。
特に、比較的安価ながら優れた内蔵GPUは非常に魅力的です。軽いゲームは非常に快適ですし、重いゲームも設定を調整すればプレイはできるレベルです。
最新世代と違って、AI用のユニットは搭載しないため、AI対応を考えたい方には向きませんが、現状の実用コスパは非常に高いCPUだと思います。
Ryzen 7 250 / 8840U / 7840U:Core Ultra Hよりはやや安価でコスパが良い
2025年10月時点のCore 7 / Ryzen 7 で一番コスパが良く見えるのは、「Ryzen 7 250 / 8840U / 7840U」などの「Zen 4」のRyzen 7です。ちなみに、上記の3つは仕様にほとんど差がなくほぼリネーム版となっているので、どれも同評価です。
また、他にも、ほぼ同一のものとして「Ryzen Z1 Extreme(携帯ゲーム機向け)」もある他、8840HSや7840HSなどもクロックや電力制限値が少し高くなっているだけなので、これらの評価もほぼ同じです。
本題の性能評価ですが、「Ryzen 7 250 / 8840U / 7840U」は、8コア16スレッドによる非常に優れたCPU性能に加え、内蔵にしては非常に高性能なGPU「Radeon 780M」を搭載しつつも、対抗のCore(Core Ultra 7 155H等)よりもやや安価なのが魅力の高コスパCPUです。
主な対抗製品となるのは「Core Ultra 7 155H」「Core Ultra 5 135H / 125H」ですが、内蔵GPU以外の実用性能は全体的に少し上回りつつも少し安価でコスパが良いです。
内蔵GPUの基本性能だけはやや負けていますが、大きな差ではなく、内蔵としては十分な性能です。軽めのゲームは快適で、重めのゲームも動作は可能です。
また、Core Ultra 100Hよりも高負荷時のワットパフォーマンスが良いことも魅力です。バッテリー容量にもよりますが、バッテリー駆動で重めの処理を想定する場合には基本的にRyzenの方がおすすめです。
更に、AI用のユニットも搭載しているのも魅力です。高性能ではないながら、成長を続けるAI用途へ先んじて対応しておけるのは嬉しいです。
「Core Ultra 7 155H」との差を見ると、内蔵GPU重視なら若干 Core Ultra 7 有利、電力効率重視なら Ryzen 7(Zen 4)が若干有利という感じになります。
ただ、わずかな性能面よりも電力面が優れている方が使用感に差を感じやすいですし、PC寿命的にも安心感がある上、Ryzen側の方が少し安価な傾向があるので、コスパ的にはRyzenの方が少し上な印象です。
Core Ultra 7 255H:価格は高いが、隙が少なく全体的に高性能
「Core Ultra 7 255H」はCPU・GPU性能は非常に優れており、GPUにもAIエンジン「XMX」が搭載されているため、実はチップ全体のAI性能も高いので、隙の無い性能です。
価格は高価ですが、200Vよりはやや安く、コスパは意外と悪くないです。
まず、CPUは合計16コア(6P + 8E + 2LP E)で、非常に優れた性能を発揮します。
また、先代の「Core Ultra 100H」はCPUの電力効率がRyzenにやや劣る印象があったのが微妙な点でしたが、「Core Ultra 200H」ではTSMC 3nm 先端プロセス採用に加えて、ハイパースレッディングも廃止されたことで、CPUの効率が改善したのが良い点です。
GPU性能も内蔵としては非常に高く、GTX 1650をやや上回る性能を発揮し、RTX 3050 4GB(モバイル版)にもやや迫る性能となっています。
数年前のエントリーグラボ並みのゲーム性能があり、やや重めのゲームにも対応できるのは大きな強みです。
また、AI用ユニットであるNPUも搭載しているのもポイントです。高性能ではないものの、今後AIが普及していくことを考えると、あると嬉しいです。
更に、「Core Ultra 200H」では内蔵GPUにもAIエンジン「XMX」が搭載されているのも嬉しいポイントです。チップ全体でのAI性能は高いです。
このように、2025年6月時点では性能では隙が無く非常に魅力的な「Core Ultra 7 255H」ですが、高価なのがやはりデメリットです。
「Ryzen 7 8840U / 8845HS」の方が一段安い価格で手に入ります。各種性能は一段上回ってはいるものの、Ryzen 7でも一般的な用途なら大体快適な性能があるので、安い分お得感が強いです。
AI性能では上回るものの、2025年時点では個人でAIユニットの性能をフルで活かせる用途が非常に限られていますし、GPU搭載のAIエンジンについても、Intelのアップスケーリング「XeSS」が使える主要ゲームがあまりないということもあり、思ったよりも強みを感じにくいです。
Core Ultra 7 155H:優れた内蔵GPUは魅力的だけど、負荷時の電力効率が悪めで価格も高め
「Core Ultra 7 155H」は、優れた内蔵GPU性能を持つのが魅力のプロセッサです。
モバイル版のGTX 1650に匹敵する性能があります。軽めのゲームなら非常に快適ですし、重めのゲームも動作は普通に可能なレベルにまで到達しており、動画編集などもフルHD以下の簡単なものなら普通にこなせるレベルになっています。従来のエントリーレベルのビデオカードレベルの性能を発揮するほど高性能です。
CPUは合計16コア(6P + 8E + 2LP E)で優れた性能を発揮します。なのですが、高負荷時の電力効率が対抗のRyzenにやや劣るため、省電力性重視だと少し評価を落とすのが気になる点です。
AI用ユニットであるNPUも搭載しているのも一応ポイントです。高性能ではないものの、今後AIが普及していくことを考えると、あると嬉しいです。
全体的にほどよく高い性能を備えていて良く見えますし、実際悪くはないですが、やはり競合の「Ryzen 7 8840U / 8845HS」と比べると優先度が下がる感は少しあります。
大きいのはまず電力面です。
CPUの負荷の電力効率が「Ryzen 7 8840U / 8845HS」の方が良くて、性能差はさほど大きくないです。消費電力はモバイルプロセッサにとって使用感に大きな影響を与える部分なので、ここがやはり大きいと思います。
次に価格です。2025年6月時点ではやや値下がりしてはいるものの、それでも「Ryzen 7 8840U / 8845HS」よりも少し高めの印象です。
恐らくは同額でも「Ryzen 7 8840U / 8845HS」の方が少し有利に見えるのに、少し価格も高いということで、やはり優先度は低くなると思います。
Ryzen 7 7730U:CPU性能コスパは非常に良いが、GPUがVegaなのがネック
「Ryzen 7 7730U」は、「7」モデルの中では安価で、CPU性能コスパが非常に優れるのが魅力のモデルです。
最新のCore Ultra 7 / Ryzen 7搭載機は10万円台中盤が多い中、10万円未満のモデルも複数見つけられるほど安いのが特に魅力的です(2024年8月時点)。
それでいて、CPU性能は普通に高い上にワットパフォーマンスも悪くないので、CPU性能コスパは明らかに良いです。7モデルに限らず、全ノートPCで見ても良いレベルです。コスパ重視志向の人にとっては非常に魅力的だと思います。
しかし、ネックなのは内蔵GPUです。古い「Vega」を採用しているため性能は低いので、ゲームは非常に軽いものだけの対応になる上、AV1のハードウェアデコードのサポートがないのが特に致命的です。
AV1デコード対応が無くても、現状では困ることはほとんどありませんが、AV1は将来性が期待されていて普及が進んでいる映像コーデックなので、出来れば対応しておきたいです。
このように、CPU性能と価格だけを見ればコスパは非常に良く見えますが、GPU込みの実用性ではやや気になるのが「Ryzen 7 7730U」です。
とはいえ、CPU性能コスパが良いのは間違いないので、GPU性能はある程度割り切ることを前提として、出来るだけ安価でCPU面を重視したいなら強力な選択肢です。
Core Ultra 7 255U / 165U:末尾Hよりもコアが大幅に削減され、性能は格段に劣るので注意
採用率が少ないので選択肢に入ることは少ないと思いますが、「Core Ultra」の末尾Uモデルはやや罠っぽい印象もあるので注意です。
末尾Hと同じ「Core Ultra 7」という名前を冠しますが、CPUとGPUともにコア数が大幅に削減されているため、性能はかなり劣ります。その割には価格がさほど安くなっておらず、コスパが悪いです。
一番気になるのはGPUです。内蔵GPUのコア数は4となっており、「Core Ultra 7 255H / 155H」の半分となっています。
Core Ultraは様々な刷新のあったブランドですが、現状一番魅力的なのは非常に優れた「内蔵GPU」性能です。末尾Uではそこの魅力が大幅に失われているので、正直微妙です。
更に、CPUのコアも大幅に削減されています。末尾HはPコアが2~4コアなのに対し、末尾UはPコアが2つしかないのが厳しいです。性能への影響が大きい高性能コアが削られてしまっているので、CPU性能も格段に落ちます。
一応、「Core Ultra 7 255U」などの200Uでは、CPUの製造プロセスがTSMC 3nmと最新鋭のものが採用されており、効率は非常に優れているので、高負荷な処理を考慮しないなら実用コスパ自体は悪くはないですし、
NPUやLP Eコアの追加など、従来のCPUにはない要素があるため、一方的に不利と言い切れないですが、現状の主要性能におけるコスパは前世代にも劣るレベルなので、大幅に値下がりしない限りは正直微妙な選択肢です。
Core i7-1360P:優れたマルチスレッド性能で悪くないコスパ
「Core i7-1360P」は優れたマルチスレッド性能でCPU性能コスパが悪くないのが魅力です。
ただし、最新世代と比べると内蔵GPU性能や電力面で劣るため、現在では在庫処分価格で大幅にお得な場合でのみ有力な選択肢です。
CPUは12コアで、4P+8Eという構成です。効率はそこまで良くありませんが、最大性能はZen 3のRyzen 7と同等レベルで高性能です。ただし、高負荷時の効率では少し劣ります。
内蔵GPUは「Iris Xe Graphics(96EU)」となっており、こちらもZen 3+以上のRyzen 7やCore Ultra 7(H)などの最新世代とと比べると大幅に劣ります。
とはいえ、AV1デコードサポートもありますし、軽いゲームや簡単な動画編集など、ライトユーザー向けのグラフィック処理で使うには困ることは基本ないです。重い処理を意識しないなら意外とネックではないので、価格が安ければ悪くはないです。
Core i7-1355U:Core i5-1335Uとの性能差が小さい割に高価
「Core i7-1355U」は「7」モデルの中では安価かつ、「Ryzen 7 7730U」よりも優れた内蔵GPUを持っているのが魅力です。
ただし、下位の「Core i5-1335U」との性能差が小さい割には高価なので、コスパや安さ重視なら「Core i5-1335U」を選ぶ方が正直良いです。
まず微妙なのが、コア構成が「Core i5-1335U」と全く同じ10コア(2P + 8E)である点です。クロックは若干高いものの、電力や温度面の制限があるため、ほぼ同じ性能と言って良いです。
GPUのユニット数は、1355Uが96EUなのに対し1335Uが80EUという点で少し優位性がありますが、実用性を大きく左右するほどじゃないので、このCPUを候補に入れる人にとっては安さ重視で1335Uを選ぶ方が魅力的であることが多いと思います。
Core 5 とRyzen 5
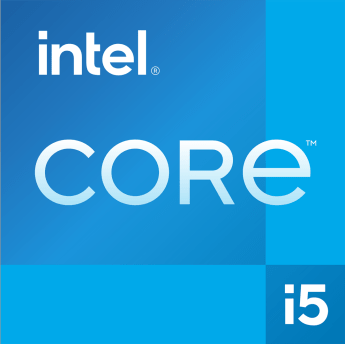
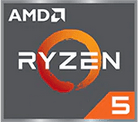
Core Ultra 5 / Core 5 / Core i5およびRyzen 5はモバイル版主流CPUにおける中級モデルです。いわゆるミドルレンジに区分されます。
搭載製品は幅が広く、価格重視の安価なものから、コスパやパフォーマンス重視のやや高価なものまでさまざまな製品が発売されます。また、中級とはいっても現在では十分に高性能で数年前のデスクトップ版のハイエンドCPUを上回る性能を持っている点もポイントです。
| CPU名 | マルチ スレッド | 安さ | 内蔵GPU | 省電力性 | |
|---|---|---|---|---|---|
 | Core Ultra 5(200H) 14コア(4P+8E+2LP E) 14スレッド 225H 等 | ★4.5 | ★2.0 | ★4.75 | ★4.0 |
 | Core Ultra 5(100H) 14コア(4P+8E+2LP E) 18スレッド 125H 等 | ★4.25 | ★2.25 | ★4.5 | ★3.75 |
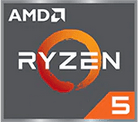 | Ryzen 5(Zen 4) 6コア12スレッド 8640U/ 8540U 等 | ★4.0 | ★3.25 | ★4.0 ★3.5 | ★4.0 |
 | Core Ultra 5(200U) 12コア(4P+8E+2LP E) 14スレッド 125U 等 | ★4.25 | ★2.25 | ★4.0 | ★4.0 |
 | Core Ultra 5(100U) 12コア(4P+8E+2LP E) 14スレッド 125U 等 | ★4.0 | ★2.25 | ★3.75 | ★3.75 |
 | Core i5(第13世代-P) 12コア(4P+8E) 16スレッド 1340P 等 | ★4.25 | ★3.5 | ★3.5 | ★3.25 |
 | Core i5(第13世代-U) 10コア(2P+8E) 12スレッド 1335U 等 | ★4.0 | ★3.75 | ★3.5 | ★3.5 |
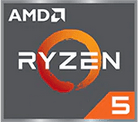 | Ryzen 5(Zen 3+) 6コア12スレッド 7535U / 6600U 等 | ★4.0 | ★3.5 | ★4.0 | ★4.0 |
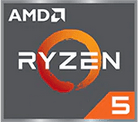 | Ryzen 5(7030/Zen 3) 6コア12スレッド 7530U 等 | ★4.0 | ★4.0 | ★3.25 | ★4.0 |
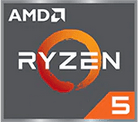 | Ryzen 5(7020/Zen 2) 4コア8スレッド 7520U 等 | ★3.25 | ★4.25 | ★3.0 | ★3.75 |
Core i5とRyzen 5の人気モデルを一部抜粋して比較しています。
| CPU | PassMark スコア | コア/ スレッド | 動作クロック 定格/最大 | TDP | 内蔵GPU |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 5 225H | 29192 | 14/14 (4P+8E+2LP E) | P:1.7 / 4.9GHz E:1.3 / 4.3GHz LP E:0.7 / 2.5 GHz | 28W – 115W | Arc 130T |
| Core Ultra 5 135H | 22300 | 14/18 (4P+8E+2LP E) | P:1.7 / 4.6GHz E:1.2 / 3.6GHz LP E:0.7 / 2.5 GHz | 28W – 115W | Arc 8コア GPU |
| Core Ultra 5 125H | 20845 | 14/18 (4P+8E+2LP E) | P:1.2 / 4.5GHz E:0.7 / 3.6GHz LP E:0.7 / 2.5 GHz | 28W – 115W | Arc 7コア GPU |
| Ryzen 5 7640U | 21017 | 6/12 | 3.5 / 4.9GHz | 28W | Radeon 760M |
| Ryzen 5 8640U | 20289 | 6/12 | 3.5 / 4.9GHz | 28W | Radeon 760M |
| Core i5-1340P | 18638 | 12/16 (4P+8E) | P:1.9 / 4.6GHz E:1.9 / 3.4GHz | 28W – 64W | Iris Xe Graphics G7 80EU |
| Core Ultra 5 225U | 18602 | 12/14 (2P+8E+2LP E) | P:1.3 / 4.3GHz E:0.8 / 3.6GHz LP E:0.7 / 2.4 GHz | 15W – 57W | Intel Graphics 4コア(Arc) |
| Ryzen 5 220 | 18564 | 6/12 | 3.2 / 4.9GHz | 28W | Radeon 740M |
| Ryzen 5 8540U | 18296 | 6/12 | 3.2 / 4.9GHz | 28W | Radeon 740M |
| Core Ultra 5 125U | 17240 | 12/14 (2P+8E+2LP E) | P:1.3 / 4.3GHz E:0.8 / 3.6GHz LP E:0.7 / 2.1 GHz | 15W – 57W | Intel Graphics 4コア(Arc) |
| Core 5 120U | 16514 | 10/12 (2P+8E) | P:1.4 / 5.0GHz E:0.9 / 3.8GHz | 15W – 55W | Iris Xe Graphics G7 80EU |
| Ryzen 5 6600U | 17096 | 6/12 | 2.9 / 4.5GHz | 15W – 28W | Radeon 660M |
| Ryzen 5 7535U | 16976 | 6/12 | 2.9 / 4.55GHz | 28W | Radeon 660M |
| Ryzen 5 7530U | 15415 | 6/12 | 2.0 / 4.5GHz | 15W | Radeon RX Vega 7 |
| Core i5-1335U | 14152 | 10/12 (2P+8E) | P:1.3 / 4.6GHz E:0.9 / 3.4GHz | 15W – 55W | Iris Xe Graphics G7 80EU |
| Ryzen 5 7520U | 9064 | 4/8 | 2.8 / 4.3GHz | 8W – 15W | Radeon 610M |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Core Ultra 5 225H | |
| Core Ultra 5 135H | |
| Core Ultra 5 125H | |
| Core Ultra 5 225U | |
| Core i5-1340P | |
| Ryzen 5 8640U | |
| Ryzen 5 7640U | |
| Ryzen 5 220 Ryzen 5 8540U | |
| Core Ultra 5 125U | |
| Core 5 120U | |
| Ryzen 5 6600U | |
| Core i5-1335U | |
| Ryzen 5 7530U | |
| Ryzen 5 7520U |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Core Ultra 5 225H | |
| Core Ultra 5 225U | |
| Core 5 120U | |
| Ryzen 5 220 Ryzen 5 8540U | |
| Ryzen 5 8640U | |
| Core i5-1340P | |
| Core Ultra 5 135H | |
| Core i5-1335U | |
| Core Ultra 5 125H | |
| Core Ultra 5 125U | |
| Ryzen 5 7640U | |
| Ryzen 5 6600U | |
| Ryzen 5 7530U | |
| Ryzen 5 7520U |
| GPU名称 (搭載CPUの例) | スコア |
|---|---|
| Arc 130T (Core Ultra 5 225H 等) | |
| Arc 8コア GPU (Core Ultra 5 135H 等) | |
| Arc 7コア GPU (Core Ultra 5 125H 等) | |
| Radeon 760M (Ryzen 5 8640U 等) | |
| Intel Graphics 4コア(Arc) (Core Ultra 5 125U 等) | |
| Radeon 660M (Ryzen 5 7535U 等) | |
| Radeon 740M (Ryzen 5 8540U 等) | |
| Iris Xe G7 80EU(-1300MHz) (Core i5-1340P 等) | |
| Radeon RX Vega 7 (Ryzen 5 7530U 等) | |
| Radeon 610M (Ryzen 5 7520U 等) |
Core Ultra 5 225H:5モデルにしては高価だけど、5とは思えない性能の良さでコスパは良い
「Core Ultra 5 225H」は「5」モデルとしてはやや高価ですが、高性能なCPU性能とGPU性能を兼ね備えており、その性能は前世代の「Core Ultra 7 155H」以上となっているため、コスパは良いと思います。
しかも、GPUにはXMX AIエンジンの追加もあり、CPUの効率もやや改善しているので、実質的には上回っていると言っても良いです。
「Ryzen 7 8840U / 8845HS」と比べても性能はやや上回っており、「7」モデル相手なら価格でも不利ではないので、2025年6月時点では、市場全体で見てもかなりコスパが良いモバイルCPUだと思います。
RyzenよりもデフォルトのTDPが高めなので、PCなどの設定で調整する必要になる可能性が高い点は注意が必要ですが、現在では特におすすめできるCPUの一つです。
Ryzen 5 7530U:安価で高コスパだけど、GPUがVegaな点に注意
「Ryzen 5 7530U」などのZen 3(無印)モデルは、安くてCPU性能コスパが非常に良い点が魅力です。やや古いアーキテクチャ&プロセスということもあってか価格が安く、そのコスパは凄いです。16GBメモリ搭載で6万円台の製品が結構あるレベルです。
Core i5-1335Uなどと競合する形ですが、そちらよりも平均で5000円~1万円ほど安いです。それでいてCPU性能は同等レベルなので、CPU性能コスパは勝っています。
ただし、内蔵GPUが微妙な点は注意です。古い「Vega」を採用していて性能は低いため、ゲームは非常に軽いものだけの対応になる上、AV1のハードウェアデコードのサポートがないのが特に致命的です。
AV1デコード対応が無くても、現状では困ることはほとんどありませんが、AV1は将来性が期待されていて普及が進んでいる映像コーデックなので、出来れば対応しておきたいです。
とはいえ、この安さで優れたCPU性能とコスパを備えたCPUは他に中々無いので、弱点を加味しても選ぶ価値があると思うレベルではあります。
ただ、個人的には「Core i5-1335U」にしてAV1対応をしておいた方が、後悔する可能性は低いような気がします。
Core i5-1335U:安価でそこそこの性能で、内蔵GPU性能コスパも良い
「Core i5-1335U」は比較的安価でそこそこの性能を持つのが魅力のCPUです。「Core 5-130U」も中身はほぼ同様のものになります。
このモデルの魅力は安価で豊富な搭載製品がある点と、Vega搭載のRyzenよりも内蔵GPU性能が高く、AV1デコード機能もある点です。
価格は競合の「Ryzen 5 7530U」よりは少し高い程度で、十分安価でコスパが良いのがまず魅力です。搭載製品も非常に多いのでセール品などからも探し易いです。
それでいて、CPUは10コア(2P+8E)搭載で軽作業には十分な性能があり、性能コスパが良いです。
そして、特に良いのは内蔵GPUです。「Iris Xe Graphics 80EU」が搭載されており、高性能という訳ではないですが、価格を考えればコスパは悪くないです。
競合の「Ryzen 5 7530U」のVegaよりも基本性能は上ですし、VegaにはないAV1デコード対応があるのが嬉しいです。総合的に見て、一段上の仕様となっていると思います。
安さとCPU性能コスパでは「Ryzen 5 7530U」の方が上なので、第2候補にされそうな印象がありますが、内蔵GPU面では少し上で、AV1対応という将来性での差もあるので、個人的にはこちらの方がおすすめです。
Ryzen 5 8640U / 7640U:優れたコスパでAIユニットも搭載
「Ryzen 5 8640U / 7640U」などのZen 4のRyzen 5は、Ryzen 7よりも安価ながら優れた性能を持っており、コスパに優れるCPUです。8640HSなどもクロックや電力制限値が少し高くなっているだけで、物理的にはほとんど同じものなので、評価もほぼ同じです。
CPUは6コア12スレッドなので強力には見えないかもしれませんが、最新鋭のプロセスとアーキテクチャ採用のおかげでモバイルCPUとしては非常に優れた性能で、軽作業には十分すぎる性能を持っています。重めの処理でも使える性能です。
また、内蔵グラフィック性能コスパが良いのも魅力です。内蔵GPUの「Radeon 760M(8CU)」は内蔵にしては比較的高性能で、Ryzen 5 7530U搭載の「Vega 8」の約2倍、Core i5-1335U等搭載の「Iris Xe G7 80EU」の約1.7倍の性能があります。
最新のCore Ultra 7やRyzen 7の内蔵GPUと比べると一段劣るものの、安さ重視品(7530Uや1335Uなど)と比べると格段に高いグラフィック性能となっており、やや重めのゲームや動画編集にも対応できるようになっているのが大きいです。
更に、AI用のユニットも搭載しています。高性能というほどではないものの、Windows用のCPUでそこそこの性能のAIユニットを搭載したCPUとしては、2024年8月時点では最も安価というのも強みです。
2024年8月時点では搭載製品が少なく、魅力的な製品が少ないのが残念ではありますが、10万円未満で性能やコスパを最大化したい場合には非常に魅力的な選択肢だと思います。
Ryzen 5 8540U:AIユニットは無いが、優れたコスパと電力効率
「Ryzen 5 8540U」は、8640Uよりも少し性能が制限されたモデルです。
CPUは同じ6コア12スレッドですが、4コアが小型の「Zen 4c」を採用しているため、若干性能が低くなっています。
GPUも「Radeon 740M(4CU)」となっており、8640Uの「Radeon 760M(8CU)」よりもコアが半減しています。ただし、性能は半減まではいかず、3割減程度に留まっているので、意外と悪くない性能です。
AIユニットも8640Uでは搭載していたものが非搭載となっています。
このように、8640Uから全体的にコア類が削減されてしまってはいるのが「Ryzen 5 8540U」となっています。
ただし、最新鋭のプロセスおよびアーキテクチャに基づいたCPUではあるので、Ryzen 7 7530UやCore i5-1335Uなどの旧世代CPUと比べると性能はやや上回っていますし、電力効率も優れています。
そのため、安さ重視で、旧世代のCPUとさほど変わらない価格で購入できる場合には、おすすめできるCPUです。
ただし、8640Uと同様に2024年8月時点では搭載製品が少ないのが難点です。とはいえ、7530Uの代替CPUとしては丁度良さそうですし、8万円未満で魅力的な製品がいくつか出てくれば、一気に人気のCPUとなるのではないかと思います。
Core Ultra 5 125H/135H:強力な内蔵GPU性能搭載で、5モデルにしては高価だけど性能を考えれば高コスパ
「Core Ultra 5 125H / 135H」は「5」モデルとしてはやや高価ですが、高性能な内蔵GPUを搭載しており、総合性能コスパで言えば悪くないです。
Core Ultra 7と比べるとコア数やクロック面が少し削られてはいるものの、大体2~3万円くらい安くなり、その割には性能もそこまで大きく低下しないので、コスパ重視なら魅力的です。
特に注目なのはやはりGPUです。Core Ultra「5」でも内蔵にしては高い性能のGPU「Arc」が搭載されています。125Hだと7コア、135Hだと8コアと異なる点で差がありますが、性能差は小さいです。
135Hの「Arc 8コア GPU」の場合はモバイル版のGTX 1650に匹敵する性能があり、軽めのゲームなら非常に快適ですし、重めのゲームも動作は普通に可能なレベルにまで到達しています。7コアモデルだと少し性能は低下するものの、実用性としては大差はないと思います。どちらも強力です。
CPUはPコアが4つだけなので、価格を考えれば弱めですが、重い処理を前提とする訳でなければ十分な性能だと思います。
2025年6月時点での価格は、安いものだと125H搭載で10万円程度からとなっており、やはりCore Ultra 7より数万円安いです。それでいて、内蔵GPUの実用性的にはそこまで差がないので、内蔵GPU性能重視ならコスパは「Core Ultra 5」の方が少し良いです。
高負荷時の効率が良くないという世代の問題は抱えたままではありますが、この性能コスパの良さなら妥協できる部分だと思います。
Core Ultra 5 225U/125U:末尾Hよりもコアが大幅に削減され、性能は格段に劣るので注意
採用率が少ないので選択肢に入ることは少ないと思いますが、「Core Ultra」の末尾Uモデルはやや罠っぽい印象もあるので注意です。
「Core Ultra 5」の末尾Uは、末尾H(125H)と比べるとCPUとGPUともにコア数が大幅に削減されているため、性能は大きめに低下する点に注意です。
まずCPUは、225U/125UのCPUは、225H/125HよりもPコアが2つ少ないです。マルチスレッド性能は大きめに低下している点は注意が必要です。
また、GPUのコア数も4つしかなく、225H/125H/135Hの7~8コアよりも少ないです。当然性能も大幅に低下します。
4コアでも前世代のCore i5のXe Graphics G7 80EUよりはやや高性能ですが、価格が2025年10月時点では数万円も高価なので、コスパは明らかに悪いです。
一応、「Core Ultra 5 225U」などの200Uでは、CPUの製造プロセスがTSMC 3nmと最新鋭のものが採用されており、効率は非常に優れているので、高負荷な処理を考慮しないなら実用コスパ自体は悪くはないですし、
LP EコアやAI用のNPUが搭載されているなど、旧世代CPUにはない要素があるため、一方的に不利とは言い切れないですが、現状の主要性能におけるコスパは前世代にも劣るレベルなので、大幅に値下がりしない限りは正直微妙な選択肢です。
Ryzen 5 7535U / 7535HS:搭載製品が少ないが、安い割にコスパは良くておすすめ
「Ryzen 5 7535U」などのZen 3+のRyzen 5は、比較的安価な割に優れた性能を持っており、
一応触れておきますが、Ryzen 5の Zen 3+ および Zen 4 モデル(Ryzen 5 7640Uや7535U)は搭載製品が少なすぎて、性能以前の問題です。わずかにある搭載品もほとんどが割高なので、実質的に検討の余地がほぼないので、割愛させていただきます。
Core i5-1340P:CPU性能の高さの割には安価
「Core i5-1340P」は価格の割に優れたマルチスレッド性能を持つのが魅力です。
競合の「Ryzen 5 7530U」と比べるとやや高価ですが、コア数は12コア(4P + 8E)と多いため、性能は上回っておりコスパが良いです。
また、内蔵GPUには「Iris Xe Graphics 80EU」が搭載されており、価格の割には低めの性能ですが、競合の「Ryzen 5 7530U」のVegaよりも基本性能が上で、、AV1デコード対応があるのが強みです。
ただし、最新世代と比べると内蔵GPU性能や電力面で劣るため、現在では在庫処分価格で大幅にお得な場合でのみ有力な選択肢です。
Ryzen 5 7520U:4コアで性能が一段低いので注意
基本的にはおすすめしないのが、Zen 2の「Ryzen 5 7520U」です。
Ryzen 5は従来から基本的に6コアですが「Ryzen 5 7520U」は4コアCPUとなっており、罠っぽい存在です。アーキテクチャもZen 2で古いこともあり、マルチスレッド性能は最近の5モデルとしては明らかに低いです。そのため、基本的にはおすすめしません。
GPUも「Radeon 610M」となっており、コアが2つで低性能です(660Mや680Mは6~12コア)。CPUとGPUのどちらも低性能で、Ryzen 5としてラインナップするのはどうなの?と思うCPUです。
ただし、一応良い点はあります。
まず、価格が安い点です。価格の安さで魅力的な「Ryzen 5 7530U / 7430U」をも少し上回る安さです。軽作業前提なら正直7520Uでも困ることはさほど無いと思うので、安さ特化なら選択肢に一応は入ると思います。
もう一つは、電力設定が8W~15Wと非常に省電力なのと、AV1デコードに対応している点です。「Ryzen 5 7530U / 7430U」の弱点として、内蔵GPUがAV1デコードに対応していない点と、古いアーキテクチャなので電力効率が少し悪い点がありますが、その両方が処理性能と引き換えに改善されています。
処理性能が低いとはいえ、軽作業前提ならさほど困ることはないレベルなので、安さ重視で性能以外の不安要素を減らしたいなら優位性はあったりします。恐らく、メーカー(AMD)もそこを狙ってのラインナップだと思います。
とはいえ、他の5シリーズが遥かに高い基本性能を持っており、価格差も劇的なものではないので、やはり基本的にはおすすめはしないモデルです。
Core 3 とRyzen 3
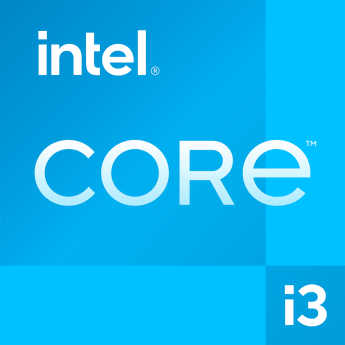
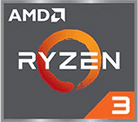
Core 3 / Core i3およびRyzen 3は主流CPUにおける下位モデルです。ただし、もっと低性能なモデルもあるため最低性能という訳ではありません。いわゆるミドルレンジ下位~ロークラス上位くらいに区分されます。搭載PCの価格は比較的安いです。
価格の安さが魅力のモデルのため、上位モデルと比べると性能は高いとは言えないレベルですが、Web閲覧やOffice作業などの軽作業であれば十分な性能は持っています。その安価さのおかげで、特に重い作業をしないのであればコスパは悪くないですし、最近ではCPUの性能は全体的に底上げされているので、モバイル版であれば以前のハイエンドCPUにも匹敵する性能を持っています。
とはいえ、Core 5シリーズやRyzen 5との性能差が大きい割には価格差が意外と小さいので、「3を買うなら、少し予算をプラスして5を買った方がお得」という印象が強いため、人気は低めです。メモリやSSDの標準容量が少ないことが多い点も選びにくい理由の一つです。
| CPU名 | マルチ スレッド | 安さ | 内蔵GPU | 消費電力 発熱 | |
|---|---|---|---|---|---|
 | Core i3(第13世代-U) 6コア8スレッド 1215U 等 | ★3.5 | ★4.0 | ★3.25 | ★4.0 |
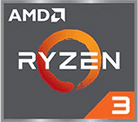 | Ryzen 3(7035/Zen 3+) 4コア8スレッド 7335U 等 | ★3.25 | ★4.0 | ★3.0 | ★4.25 |
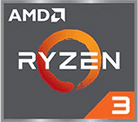 | Ryzen 3(7030/Zen 3) 4コア8スレッド 7330U 等 | ★3.25 | ★4.25 | ★3.0 | ★4.0 |
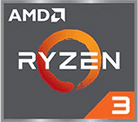 | Ryzen 3(7020/Zen 2) 4コア8スレッド 7320U 等 | ★3.0 | ★4.5 | ★2.5 | ★4.0 |
Core i3とRyzen 3の人気モデルを一部抜粋して比較しています。
| CPU | PassMark スコア | コア/ スレッド | 動作クロック 定格/最大 | TDP | 内蔵GPU |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i3-1220P | 15651 | 10/12 (2P+8E) | P:1.5 / 4.4GHz E:1.1 / 3.3GHz | 28W – 64W | UHD Graphics Xe 64EU |
| Core 3 100U | 14242 | 6/8 (2P+4E) | P:1.2 / 4.7GHz E:0.9 / 3.3GHz | 15W – 55W | UHD Graphics Xe 64EU |
| Core i3-1315U | 12381 | 6/8 (2P+4E) | P:1.2 / 4.5GHz E:0.9 / 3.3GHz | 15W – 55W | UHD Graphics Xe 64EU |
| Ryzen 3 7335U | 11791 | 4/8 | 3.0 / 4.3GHz | 28W | Radeon 660M |
| Core i3-1215U | 11603 | 6/8 (2P+4E) | P:1.2 / 4.4GHz E:0.9 / 3.3GHz | 15W – 55W | UHD Graphics Xe 64EU |
| Ryzen 3 7330U | 11013 | 4/8 | 2.3 / 4.3GHz | 15W | Radeon RX Vega 6 |
| Ryzen 3 7320U | 9268 | 4/8 | 2.6 / 4.0GHz | 8W – 15W | Radeon 610M |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Core i3-1220P | |
| Core 3 100U | |
| Core i3-1215U | |
| Ryzen 3 7335U | |
| Ryzen 3 7330U | |
| Ryzen 3 7320U |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Core 3 120U | |
| Core i3-1220P | |
| Core i3-1215U | |
| Ryzen 3 7335U | |
| Ryzen 3 7330U | |
| Ryzen 3 7320U |
| GPU名称 (搭載CPUの例) | スコア |
|---|---|
| Radeon 660M (Ryzen 5 7535U 等) | |
| UHD Xe 64EU (Core i3-1220P 等) | |
| Radeon RX Vega 6 (Ryzen 3 5300U 等) | |
| Radeon 610M (Ryzen 5 7520U 等) |
Core i3:Core i5より大幅に安いなら全然アリだけど、搭載製品が少ない
第13世代のCore i3は、実は性能コスパは良く、Core i5よりも大幅に安いなら全然アリな選択肢です。
コア数を見ると、末尾Uが6コア(2P+4E)で末尾Pが10コア(2P+8E)です。低価格・低性能モデルにしては多いです。Pコアの数はCore i5/i7の末尾Uモデルと同じ2つなので、処理性能は思ったよりも高いです。軽作業なら十分快適なので、安さ重視なら選択肢に入ります。
内蔵GPUもコア数こそ少ないものの、AV1デコードには対応しており、動画視聴などには十分です。安価なCPUのものとしては十分及第点です。
ですが、やはり問題は実際の製品です。Core i5の方が圧倒的に採用製品が多いのでお得な製品が探し易いですし、Core i5よりも大幅に安い製品が中々無いです。Core i5の安い製品を探す方が楽だし、コスパも結局そちらの方が良いことが基本なので、最終的にCore i3が選ばれるのは稀かなと思います。
Ryzen 3:悪くはないけど、基本Core i3の方が良い
Ryzen 3のコア数は共通で4コア8スレッドです。マルチスレッド性能はCore i3の方が少し勝りますが、元々軽作業前提のCPUなので、思ったほどはネックではないかもしれません。
ただし、価格がCore i3より安いという訳でもなく、内蔵GPU性能も基本Core i3の方が上なので、総合的に見てCore i3の方が有利です。
一応、Zen 3+とZen 4モデル(Ryzen 3 7335UやRyzen 3 7440U)なら、内蔵GPU性能が一段高くなるので有利になりますが、搭載製品がほとんどないので、評価するかは難しいところです。Ryzen 5やRyzen 7ですらZen 3+以降は供給量が限られている印象がありますから、Ryzen 3にまで回る可能性は低そうですし、期待するのも無駄に思えてしまいます。
そのため、基本的にはCore i3の選ぶ方が良いですが、出来れば少し予算を追加してCore i5やRyzen 5を選ぶ方が良いかなと思います。
最後にここまでの内容を踏まえて、用途・予算別に分けておすすめモデルを紹介しています。
価格も高すぎず高コスパで強力なのは「Ryzen 7 7735~」
価格もある程度意識した場合のおすすめCPUは「Ryzen 7 7735 以降」です。
10万円以下の製品も数多くありますが、その性能は普通に優秀です。高いCPU性能に加え、軽めのゲームなら快適な内蔵GPUまで有しており、電力効率も良いです。
ゲームではAFMF 2という気軽に使えるアップスケーリングもあるので、思ったよりも実用ゲーム性能が高いのが特に魅力かなと思います。
そのコスパの良さから採用製品が多くて選択肢が多いのもメリットの一つです。
性能よりも省電力性重視で予算度外視ならを求めるなら「Core Ultra 200V」
性能よりも省電力性重視で予算度外視ならを求める場合には、「Core Ultra 200V」は強力です。
CPU性能こそ価格の割には大分低いものの、電力面とGPU・NPU性能が非常に優秀です。
弱点として挙げられるCPU性能も、モバイルノート向けとしては普通に高性能で、ほとんどの人にとってネックにならないと思うレベルなので、実用性能は非常に高いです。
そして、競合の「Ryzen AI 300」や「Snapdragon X」と比べるとAI性能が上回っているのも決め手の一つです。NPU単体ではほぼ横並びの3シリーズですが、「Core Ultra 200V」ではGPUにも高性能なAIエンジンが搭載されているので、合計のAI性能は頭一つ抜けて上回っています。
価格がものすごく高い点さえ妥協できるなら、WindowsのAIやモバイル性能を重視したPC向けのSoCとしては2025年6月時点では非常に強力な選択肢だと思います。
「Core Ultra 5 100H / 200H」も高すぎない価格でコスパ重視なら良い
総合コスパでは「Core Ultra 5 100H / 200H」もおすすめです。
「Ryzen 7 7735~8845」と比べると選択肢こそ少ないものの、10万円~ほどからの販売があるので、価格は近いです。
それでいて、内蔵GPU性能は少し上回っているため、ゲーム性能コスパは特に魅力的です。
ただし、高負荷時の電力効率ではRyzenには若干劣ることが多いことや、ゲームではAFMFの存在での差が少しあるため、機種次第ですが、少し魅力度的には劣ることが多くなりそうな気はします。
6~8万円くらいでコスパ重視ならCore i5が無難
6~8万円くらいの中価格帯でコスパ重視で選ぶなら、やはり安定はCore i5です。具体的には「Core i5-1235U」「Core i5-1335U」「Core i5-1334U」「Core i5-1240P」「Core i5-1340P」などが主です。
性能スコアなどだけを見ると、「Ryzen 5 7530U / 7430U」が非常に強力に見えると思いますが、GPUのVegaがネックです。処理性能も低いですし、AV1デコードが無いのが大きいです。将来性や機能性も考えると、GPU性能がやや高く、AV1デコードにも対応しているCore i5が無難です。
また、Core i5はどの時期でも搭載製品が非常に豊富で、セール品なども候補にしやすく、お得な製品が選び易い点も大きなメリットです。一応より優れた候補になりうるCPUがあるので一択とまでは言えませんが、非常に無難な選択肢です。
搭載製品が少ないけど、「Ryzen 5 8640U / 8540U」も中価格帯では強力
搭載製品が少ないのが難点ですが、10万円をやや下回る中価格帯では「Ryzen 5 8640U / 8540U」も魅力的です。
特に、8640Uは高いGPU性能とNPU(AIユニット)も搭載しているので、比較的安価ながら優れた実用コスパと将来性も兼ね備える魅力的なCPUです。
8540Uも7530Uの代替品としては良いですし、2024年8月時点では搭載製品が少ないのがどうしてもネックにはなりますが、どちらも有力なCPUです。
本記事では省電力モデルに焦点を当てて見ていきましたが、その他にも「性能重視モデル(末尾H)」や「超省電力モデル(廉価モデル)」があります。主要シリーズという感じではないので、ざっくりとにはなりますが下記で大まかな特徴だけ少し触れています。
性能重視モデル(TDP:35W~)
- 処理性能が高い使える電力が多く、コア数やクロックを上げることができるため
- 消費電力が多い(バッテリー持続時間も短くなる)
- 発熱処理のため、PCが大型化する傾向がある
- 価格が高い(ビデオカード搭載機が中心のため)
末尾Hのモデルは、消費電力が多めに設定されている性能重視モデルです(Core / Ryzen 共通)。
主に、ビデオカードを搭載したゲーミング・クリエイターノートPCによく採用されます。
ただし、2025年現在では末尾Hモデルでも電力設定の幅を大きく設けられることが多くなり、省電力動作が可能なモデルも増えているため、省電力モデルとの境界が曖昧になってきている印象もあります。
具体的な数値としては、TDPと呼ばれる電力の目安の数値が、主流モデルだと15W~28Wが多いのに対し、性能重視モデル(H)は35W以上が基本となっています。
より多い電力を使えるようにすることで、コアを多く搭載したり、クロックを上げることができ、性能が上がります。
しかし、消費電力だけでなく発熱も多くなってしまうのが注意点です。その結果、従来の薄型ノートよりも大きめの冷却システムが必要となるため、搭載機はやや大型化してしまう傾向があります。
性能が高いのはメリットですが、逆に言えば、処理性能が高い以外には良い点が無く、デメリットとして消費電力や発熱の増加が追加される感じです。
そのため、バッテリー持続時間や発熱・重量の悪化を多少受け入れてでも性能を重視したい人のモデルとなっているため、特に性能に特化したい訳でない場合にはやや不適なモデルということは承知しておく必要があります。
超省電力モデル(TDP:~10W)
- 消費電力・発熱が非常に少ない
- 発熱が少なく、ファンレスにしやすい(静音化・薄型化しやすい)
- 処理性能が低い
- 高負荷時にすぐにクロックが下がってしまう
- 最大性能が低いのに価格は安くなく、コスパが悪い(上位モデルを電力制限して使った方がお得感がある)
薄型軽量のPCやタブレットに適しているのが、TDP(PL1)が10W未満の超省電力モデルです。
2025年10月時点ではRyzen側では該当モデルが実質ないため、Core側が独占している形になります。以下の説明もCoreのみの説明となります。
主流モデルではTDP(PL1)が15W~28Wなのに対し、超省電力モデルのTDPは10W未満となっており、消費電力と発熱が大幅に抑えられています。
そのおかげで、搭載する冷却用のファンを小型化することができ、ファンレス運用も他モデルより比較的容易になっています。これにより静音化・薄型化しやすいことが大きなメリットです。
ただし、電力制限が厳しいために処理性能もかなり制限されるのがデメリットです。そのため、高負荷な作業を前提とする場合には向きません。軽作業前提の非常に使い勝手の良いCPUという感じです。
また、性能が制限されるのはコスパ面でも悪影響です。もう少し電力を使えば上げられる性能をあえて低く保つように調整されているため、性能コスパが基本悪めです。
要するに、主流モデルと比べて最大性能が低いにも関わらず、物理的な仕様は大差がなくて価格がほぼ変わらないので、コスパが良くないことが多いです。
正直、このモデルを採用するくらいなら、TDPが15W~28Wの主流モデルの標準の電力制限を引き下げて使った方がコスパが良いし汎用性も高いです。
そのため、あまり有力モデルという感じではなく、性能度外視で安さとモバイル性特化のPCを中心に採用されています。
ただ、メーカー側もその需要の無さは従来からわかっていたので、2025年時点では少しアプローチが変わってきています。
具体的には、CPUのコアのほぼ全てを小型コアにすることでコスト面も大きく節約する手法が進められています。
性能の低さというデメリットは残りますが、コストを従来よりも抑えることができ、価格での魅力が少し増している印象はあります。
CPUの性能の全体的な底上げも進んでおり、ローエンドCPUでも軽作業なら不自由なくなってきているので、今後は有力モデルとして台頭していく可能性もあるかもしれません。
それでは、内容はここまでとなります。ご覧いただきありがとうございました。

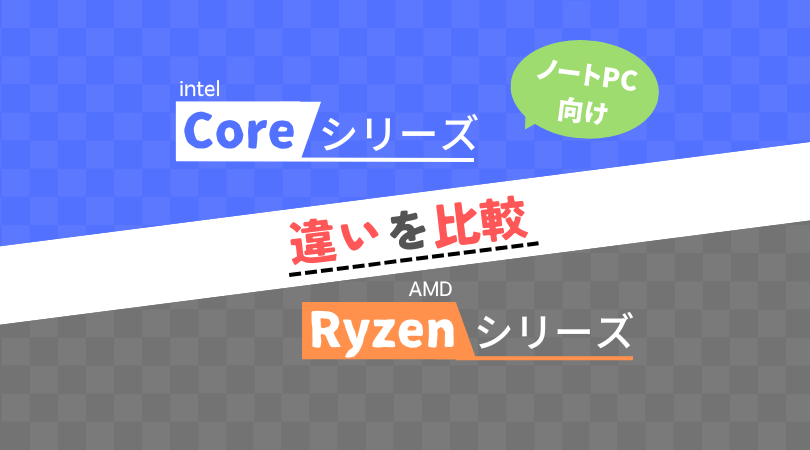

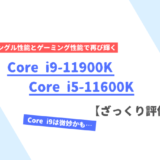
はじめまして。
現在、NECのVALUESTAR Gという一体型PCを10年以上使用しており、そろそろ買い替えを考えています。
スペースの問題と個人的な好みから、デメリットは承知の上で次もまた一体型PCにしたいと思い、HPのRyzen 5 5625UのPCに目星をつけていました。
検討の中でこちらのサイトにたどり着き勉強させていただきましたところ、本ページの「要点や注意点」にある「YouTubeをよく視聴する方が長期利用を見据えた将来性を考える」がまさに自分に当てはまり、「Vega」は避けた方が無難、とあったため、Ryzen 5 5625Uはやめるべきかと悩んでいます。
使用用途は主にYouTube視聴とブラウジングで、特にYouTubeはTV代わりに一日中流しっぱなしのため、消費電力や音が気になります。
また次も出来るだけ長く使用したいと考えており、用途に対してオーバースペックかもしれませんが買うなら性能のよいものを、予算10万円強で探しています。
検討したのがHP Pavilionシリーズの以下3機種なのですが、やはりRyzenは避けてCore i5のほうがいいでしょうか…?
なお3機種とも悩んでる間に生産終了となり、最近アウトレットに出たためまた悩み始めました。
・Core i5-12400T /16GB(8GB×2)/256GB SSD + 2TB HDD
・AMD Ryzen 5 5625U /16GB(8GB×2)/256GB SSD + 2TB HDD
・AMD Ryzen 7 5825U /16GB(8GB×2)/512GB SSD + 2TB HDD
特にCore i5-12400Tの256GBとRyzen 7 5825Uの512GBの比較で優劣をご教示いただければ幸いです。
Ryzen 5との比較ではCore i5が無難と記事中にはありましたが。。(ちなみにそのあとの「第13,12世代のCore i5」の後は文章がないのでしょうか?)
長文申し訳ございません。どうぞよろしくお願いいたします。
はじめまして。
総評のCore i5の部分抜けちゃってましたね…。申し訳ありません。後で改めて書いておきます。
本題ですが、やはり個人的な意見としては、内蔵GPU利用で長期利用を見据えたPCを今購入するならAV1デコードには対応しておいた方が良いと思うので、Ryzen 5 5625UなどのVega搭載Ryzenはおすすめではないです。
GPUの再生支援が無くても全く観れないということではないですが、かなり高負荷で発熱や消費電力増加に繋がるため、長期利用を見据えると好ましくないです。
また、候補機についてはHPの同機種に何かこだわりや特別な魅力を感じた訳ではないなら、
LenovoのIdeaCentre AIOやDELLのInspiron 24 オールインワンなどの方がコスパは良いように見えるので、ご覧になっていないならチェックしてみると良いかもしれません。
Core i5-12400Tの256GBとRyzen 7 5825Uの512GBの比較についてですが、
まずCPU性能はRyzen 7 5825Uの方が少し上ですが、実用性を左右するほどではないと思います。
GPUは、Core i5-12400Tはデスクトップ向けのCPUで、本記事に載せているようなモバイル版のCore i5のGPUと比べると性能が劣る点に注意です。
それを踏まえた上でGPU性能ですが、Ryzen 7 5825Uの方が高く、ベンチマークスコアはおおよそ2倍程度と大幅に高いです。
とはいえ、どちらも低性能なので重いグラフィック処理は厳しく、ライトな用途に限るなら恐らく差はほとんど感じられないとは思います。
そして、Ryzen側はAV1デコード機能が無いので、実用性はCore i5-12400Tの方が少し上かなという感じです。
ただ、GPUの処理性能自体はRyzen 7 5825Uの方が高くはあるので、軽いゲームなどを用途に入れるならRyzenの方が上になると思います。
ストレージ容量については、HDDが2TB付いてくるものの、やはりSSDが256GBは心許ないです。
大きなデータを保存せず、SSDはほぼOS動作用ということなら問題はないと思いますが、ストレージ容量は耐久性にも影響するので、SSD容量も出来るだけ活用しつつ長期間使いたいなら256GBは微妙かなと思います。
また、最後に少しお聞きしたいのですが、最近ではミニPCと呼んだりする、小さめの弁当箱くらいの大きさでコスパの良いPCが結構出ているのですが、それ+ディスプレイとケーブル1,2本という形は満足できない感じでしょうか?
液晶一体型もメリットはありますし、デメリットも理解しているようなので絶対止めろと言う気はないですが、機械的なデメリットを抜きにしても、やはり選択肢が少ないこともあってコスパ的に劣ることが多いのがネックだったりするので、ミニPC許容できるならコスパは大きく改善できると思います。
さっそくのお返事ありがとうございます。
やはりVega搭載Ryzenは避けたほうが良いのですね。。
LenovoやDELLも見てはいたのですが、個人的にLenovoはあまり好きではなく、DELLの口コミで画面がガビガビする・音響がよくないというのを見てHPに絞っていました。
Core VS Ryzenの比較もありがとうございます。
ストレージ容量については、Ryzenを避けたところでSSD256GBはどうなのか?と私も気になっていたところでした。やはり心許ないのですね。
今使用している機種がCドライブ852GBと謎に大容量で、買い替えるのにそれより少ない512GBになるのはどうなのか?と思い、SSD+HDDだったりSSD1TBなどで探していると選択肢がほとんどなく。。
HDDがなくても、SSD512GBあれば長く使えるものでしょうか?今のPCは画像や動画をため込んで300GBほど使っています。
ミニPCやモニター裏にくっつけられる形のものも少し見ていて、このくらいの省スペースであれば必ずしも一体型でなくてもよいと考えています。
ただ、HPと同等くらいのスペックでミニPC+モニター(+スピーカー)で10万弱のコスパのものが私では見つけられず、それならHPの一体型でいいのではと思ってしまって。。
ミニPCのメーカーも聞きなれないものが多く、初心者にセッティングできるのかも不安で、変に一体型に固執しているところがあります。
改めての用途と希望ですが、
・YouTube視聴・ブラウジング(ゲームもやってみたいが出来なければ諦める)
・Switchを繋げるためHDMI入力が欲しい
・DVD鑑賞・CD取り込みのため光学ドライブを外付け予定
・省スペースで長く使いたい
上記の要件で予算10万弱で、おすすめのミニPCや構成がありましたらご教示いただきたいです。
質問というよりわがままな相談になってしまいました、すみません。。
Vega搭載Ryzenも処理性能自体のコスパは良いですし、現状はAV1動画が主流って訳でもないので、一概に悪いって訳ではないんですけどね…。あくまで私的な意見ですが、おすすめはできないかなと思います。
ストレージの寿命について明確なことを言うのは難しいですが、メイン機としての長期利用でSSD512GBだけは安心とは言えない容量だと思いますし、容量に不安を抱えたまま長期利用するのも微妙かなと思います。
一応、ミニPC自体が小型化に特化しているため、長期利用でも安心と断言まではできませんが、おすすめの製品があって、
Minisforum UM773 SE/ Lite
https://store.minisforum.jp/collections/all-product/products/minisforum-um773-lite
【SEの構成】
Ryzen 7 7735HS/16GB/512GB ¥67,980
Ryzen 7 7735HS/32GB/512GB ¥74,380
Ryzen 7 7735HS/32GB/1TB ¥77,580
上記の商品などいかがでしょうか?
ミニPCですがポート類は豊富ですし、プラス2~3万円使えればモニターやスピーカーも高いものでなければ揃えられると思います。
また、筐体の蓋の裏にSATAのSSD/HHDを増設することが可能になっているので、ストレージ面の懸念も軽減されると思います。
性能についても、CPUの性能も候補に挙がっていた「Core i5-12400T」や「Ryzen 7 5825U」より高性能ですし、
内蔵GPUに関しては現状ではかなり高性能な部類なので、ゲームも軽めのものなら快適なはずです。
お返事ありがとうございます!
おすすめミニPC拝見しました。桜色にちょっと驚きましたがw こんなにコンパクトでコスパ良いものがあるんですね。確かにこれなら予算内に収まりそうです。ゲームができるのも魅力的です。
ただ如何せん初心者なもので、セッティングやトラブル時のサポート面に不安があります。。
中華メーカーの評判も良し悪しのようですし…(Minisforumは大丈夫そうですが)
ですがこちらで伺わなければ考えもしなかった選択肢なので、とても参考になりました。
Vega搭載Ryzenの件やストレージ容量についてアドバイスを参考にし、ミニPCも視野に入れてもう少し検討しようと思います。
素人質問に丁寧にお答えいただき、ありがとうございました!大変助かりました。
セールで値下がりしているのを少し前に見まして、実は今回の相談を貰ったときに良さそうだなと思っていました。
シンプルな黒っぽいやつも選択できるかと思うので、桜がちょっと…という場合はそちらでも良いと思います(黒の方が少し安いです)。
あと、仰っていたようなモニター裏にも取り付けられるよう、VESAマウンタが付属しているらしいので、実質液晶一体型みたいな使い方も可能だと思います。
確かに、Minisforumが台頭してきたのはここ数年ということもあり、サポート面の不安は拭えないかと思います。
ただ、国内の代理店はあるメーカーでこのコスパの良さは他では中々ないと思うので、それを考慮しても魅力が勝つかなと思いました。
お力添えできたなら幸いです。また何かありましたらお気軽にお尋ねください。