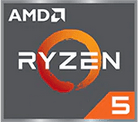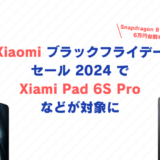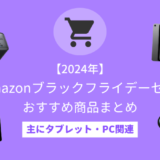この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
デスクトップ向けCPUのAMDの「Ryzen」シリーズの各モデル「9 / 7 / 5 /3」などのナンバリングごとの違いをざっくり解説しています。
本記事の主な対象は記事更新時点の主要世代です。2025年6月時点では「Ryzen 5000~9000シリーズ」を対象としています。
「マルチスレッド性能」と「ゲーム性能」
まず始めに、「CPUで重要な性能」について触れておきます。
CPUの性能を決める項目はたくさんありますが、2025年時点のデスクトップ向けCPUで特に重視されているのは「マルチスレッド性能」と「ゲーム性能(高性能なグラボと併用時)」の2つです。
下記にざっくりとした説明を載せています。
この二つの性能について、この後詳しく触れていきます。
また、用途次第では「iGPU(CPUの内蔵GPU)」や「NPU(AI用ユニット)」も重視されますが、デスクトップにおいては重要でないケースが多いので、本記事では参考程度の扱いとしています。
これは、最近のデスクトップではグラフィックボード(グラボ)を搭載したものが選ばれることが多いためです。
グラボがあれば、内蔵GPUやNPUよりも高度なグラフィック処理やAI処理に対応できます。そのため、CPUにそれらが搭載されている必要性がありません。
そのため、特にゲーミングPCを検討している方の場合は、前述した「マルチスレッド性能」と「ゲーム性能」を気にしていればOKです。
まずは、マルチスレッド性能から触れていきます。
マルチスレッド性能は、複数コアを使用した際の処理性能で、全コア稼働時のCPUの最大性能を指すことが一般的です。
主にマルチタスク(重い処理複数)や、単体で非常に重いCPU処理の際に重要となります。
マルチスレッド性能の高さはコア数が非常に重要です。コア数が多いほど高性能なのが基本です。
そして、Ryzen(デスクトップ)におけるコア数は非常に分かり易いです。たとえば、「Ryzen 7 なら 8コア」みたいな感じで分けられています。
デスクトップ版のRyzenにおいては、2017年発売の初代から2025年現在までモデルナンバー(3~9)とコア数がずっと一致しているので、例外を考える必要もないので覚えるのが楽です。下記の表の通りになっています。
基本的には、数字が大きい(コア数が多いほど)マルチスレッド性能が高いと思って良いです。
一応、必ずしもコア数が多い方がマルチスレッド性能が高いとは限らないですが(新しいモデル世代ほど1コアあたりの性能が高いため)、
2025年5月時点の主要シリーズである「Ryzen 7000~9000」内での比較なら、コア数だけの判断で基本OKです(世代間の性能向上が小さかったため)。
また、デスクトップ版Ryzenの主要シリーズにおけるナンバリングの各モデルの特徴について、下記でそれぞれ触れているので、興味があればご覧ください。
- Ryzen 9(16コア):16コアで圧倒的なマルチスレッド性能のハイエンドモデル
- Ryzen 9は16コアと12コアの2種類のモデルがあります。ここでは、16コアモデル(950系)について説明します。
Ryzen 9の16コアモデルはRyzenシリーズにおける最上級モデルです(例:Ryzen 9 7950X、Ryzen 9 9950X3D)。デスクトップ版でのコア構成は全て同じで、16コア32スレッドとなっており、圧倒的なマルチスレッド性能を発揮します。
競合の「Core i9-14900K / Core Ultra 9 285K」などは24コアなので、パッと見は劣るようにも見えますが、コア構成が異なるので実質的には同等クラスです。
これは、Core側は半分以上(24コアの内16コア)がEコアで構成されるのに対し、Ryzenでは全てが高性能なコア1種類のコアで構成されるためです。
全てが高性能なコアで構成されることで、タスクのコア割り当ての複雑化によるリスクが発生しないことや、マルチスレッド効率が非常に優れているという特徴があります。そのため、Ryzen 9は高負荷な処理をガンガンするのであれば非常に優秀なCPUです。
その代わり、価格は非常に高価なのがまずデメリットです(2025年5月時点で約9~13.3万円)。更に、高負荷時の消費電力が非常に多いため、電源容量やCPUクーラーにも十分に注意を払う必要があります。
ゲームにおいても高い性能を持ちますが、現状は重いゲームでもコア数で恩恵があるのは8コア程度まで(Pコア)と言われており、Ryzenはほとんどのモデルで1つのCCD(コアのまとまり)のL3キャッシュ容量も同じなので、下位モデルとゲーム性能は実はほぼ変わりません。そのため、9モデルを検討するのは、費用や消費電力を犠牲にしてもマルチスレッド性能を少しでも高めたいという場合になります。
そのため、ほとんどの人にとっては実用面ではマイナスになることも珍しくないと思うので選ぶ際には慎重になる必要があります。 - Ryzen 9(12コア):優れたマルチスレッド性能と効率が魅力。「9」だけどCoreでは「7」が比較対象
- Ryzen 9は16コアと12コアの2種類のモデルがあり、12コアモデルはRyzenシリーズにおける上級モデル(上から2番目)です。名前の後ろ3桁が900となっている点で見分けられます(例:Ryzen 9 7900X、Ryzen 9900X)。
デスクトップ版ではコア構成は全て同じで、12コア24スレッドです。非常に優れたマルチスレッド性能を持ちます。また、コア数や価格の割には大容量のL3キャッシュを持ち、特に省電力動作時のマルチスレッド効率が非常に優れているのが魅力です。
しかし、「9」モデルながら、一つ上の16コアモデルや「Core i9 / Core Ultra 9」と比べると、マルチスレッド性能自体は大きめに劣っている点に注意です。
その代わりに価格も少し低くなっているので、価格・性能的にCoreに対しての比較対象は「Core i7 / Core Ultra 7」となっています。
ゲーム性能も優れていますが、現状は重いゲームでもコア数で恩恵があるのは8コア程度まで(Pコア)と言われているため、実は16コアモデルや8コアモデルともゲーム性能はほぼ変わらない点は注意が必要です。
やや中途半端な立ち位置なのは正直否めないですが、Ryzen 7ではマルチスレッド性能には不安があるけど、16コアモデルほどは費用を掛けたくないという人向けのCPUです。
価格は、他の「9」モデルよりは少し安価ですが、やはり高価です(2025年5月時点で約6~8万円台)。
高負荷時の消費電力もそれなりに多めで、X付モデルを採用する場合には電源容量やCPUクーラーにもしっかりと注意を払う必要があります。
ポジション的には「Core i7 / Core Ultra 7」がライバルですが、Coreの方が少し安価なことが多いのが厳しめポイントです。
そのため、実用コスパ的に若干劣ることが多いのは否めないです。
ゲームコスパ特化なら「Ryzen 7 X3D(例:7800X3D / 9800X3D)」の方が強力ということもあり、中々第一の選択肢にはなりにくい印象です。 - Ryzen 7(8コア):ゲーム性能は「9」にも劣らないミドルレンジモデル
- Ryzen 7は、Ryzenシリーズにおけるミドルレンジモデルです。8コア16スレッドです。
優れたマルチスレッド性能で、ほとんどの人にとっては十分な性能を持ちます。
ゲームに関しては、現状は重いゲームでもコア数で恩恵があるのは8コア程度まで(Pコア)と言われているため、Ryzen 9にも劣らないゲーム性能を持ちます。それでいてRyzen 9よりも安価なので、ゲーム性能コスパに優れているのが特に魅力です(Ryzen 8000G除く)。
価格はRyzen 7000以降は高価です(4万円台後半~9万円程度)。
ライバル製品の「Core i7 / Core Ultra 7」は20コアなので(2025年5月時点)、マルチスレッド性能は圧倒的に劣っています。
更に、価格も大差ないので、マルチスレッドコスパも大幅に劣るのがデメリットです。CPUに高負荷な処理をガンガンさせたいならやや不向きなモデルなのは留意しておくと良いです。
とはいえ、そのマルチスレッド性能自体は一般用途ならほとんどの人にとって十分なレベルです。電力面やゲーム性能ではCoreよりも優秀な部分も見られるので、無駄な性能よりも実用コスパを重視する場合に有力な選択肢です。
また、Ryzen 7はゲーム特化ならX3Dモデルが特に注目のモデルです(例:Ryzen 7 7800X3D、Ryzen 9 9800X3D)。
X3Dモデルは大容量のL3キャッシュを搭載したことで、ゲームで強力になったモデルです。
更に、Ryzenは旧世代の5000シリーズが2025年5月現在でも販売が継続しており、Ryzen 7 5700Xは2025年現在でも人気のモデルです。価格は2万円台中盤と非常に安価ながら、マルチスレッド性能と電力効率は悪く無くてコスパが良いのが魅力です。
コアあたりの性能はRyzen 7000以降には大きく劣るものの、L3キャッシュ容量は最新世代と同じ容量が設定されているため、古い世代の割にはゲーム性能は低くなくてマルチスレッド性能コスパも良いのも魅力です。実用コスパが非常に良いとして未だに人気となっています。 - Ryzen 5(6コア):安価ながらL3キャッシュ容量はRyzen 7と同じなので、実用性能コスパが良い
- Ryzen 5は、Ryzenシリーズにおけるミドルレンジ下位モデルです。Ryzen 5000以降ではコア構成は全て同じで、6コア12スレッドです。全体で見るとやや低性能な立ち位置ですが、一般用途ならほとんどの人にとっては困らないくらい高性能です。
そして、Ryzen 5の最大の魅力は安さです。Ryzen 7000以降では約3万円~4万円台ほどとなっており、「7」以降と比べると一段安いです。
また、その安さでゲーム性能は「7」以降とほとんど変わらないのが強みです(Ryzen 8000G除く)。これは、L3キャッシュ容量が「Ryzen 7」と変わらないことが主な要因と思われます。そのため、ゲーム性能コスパは非常に優れており、低価格ゲーミングPC用のCPUとしては非常に強力です。
旧世代のRyzen 5(例:Ryzen 5 5600)なら1万円台で購入ができるモデルもあるため、そちらのコスパも非常に良いです。
しかしやはり、マルチスレッド性能が低めで、コスパ的にも「Ryzen 7」や「Core i7 / Core Ultra 7」と比べると少し劣る印象があるので、あまり人気ではない印象です。 - Ryzen 3(4コア):安さが魅力のエントリーモデルだが、需要もコスパも低め
- Ryzen 3は、Ryzenシリーズにおける安さ重視のエントリーモデル(下位モデル)です。Ryzen 5000以降ではコア構成は全て同じで、4コア8スレッドです。わずか4コアで性能は低いので、ゲームを含めて快適な性能を求めるには向かないCPUです。魅力は価格の安さです。軽作業前提で少しでも費用を減らしたい層をターゲットにしたCPUです。
しかし、やはりRyzen 5との性能差が大きくて需要が小さく、AMDも投入に消極的です。基本的に最新世代ではすぐには投入されず、販売されてもOEM(メーカー限定)です。
将来的なことを考えると、内蔵GPUやNPUの性能がRyzen 3でも高めの性能になれば有力になる可能性もありますが、2024年現在では基本的にはおすすめしないモデルです。
次に、ゲーム性能について触れていきます。
近年ではPCゲームが大きく流行&普及したことで、一般層では特に「高性能グラボと組み合わせた際のゲーム性能」が重視されています。
そのゲーム性能を大きく左右するのが、「世代(アーキテクチャ)」と「キャッシュメモリの容量」です。
デスクトップ向けRyzenの、超高性能なGPUと組み合わせた際の、おおよその平均ゲーム性能は下記の表にようになっています(Ryzen 7 5700X 基準)。
同じGPUを使用していても、大きめの性能差が付くことがわかります。
ただし、これはウルトラハイエンドGPU(超高性能グラボ)と組み合わせた場合の性能なので、実際にここまでの差が付くことはあまり無かったりします。
とはいえ、折角高額なグラボを用意したのにその性能が制限されるのは嫌ですし、CPUのキャッシュメモリが凄く重要なゲームもあるので、
高性能なグラボを用意するなら、CPUもゲーム性能が出来るだけ高いものを用意したいというのが一般的な考えとなっています。
ゲーム性能以外の面も含めて、各世代(シリーズ)のメリット・デメリットをまとめたものを載せておくので、参考程度にご覧ください。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| Ryzen 9000 | ・優れたコア性能 ・優れたゲーム性能 ・優れたマルチスレッド効率 ・ソケットAM5の長期サポート 【X3D限定】 ・大容量L3キャッシュ(+64MB) ・現状トップのゲーム性能(2025年5月時点) ・非常に優れたゲーム時の電力効率 | ・高価(X3D以外:3.8万円~8.7万円) ・純粋なコスパは悪め ・NPU無し(AI用ユニット) ・内蔵GPUが低性能 【X3D】 ・ものすごく高価(8万円~11.9万円) ・マルチスレッド性能コスパが悪い |
| Ryzen 7000 | ・優れたコア性能 ・優れたゲーム性能 ・優れたマルチスレッド効率 ・ソケットAM5の長期サポート 【X3D限定】 ・大容量L3キャッシュ(+64MB) ・非常に優れたゲーム性能 ・非常に優れたゲーム時の電力効率 ・省電力でマルチスレッド効率も良い | ・やや高価(X3D以外:2.8万円~7.3万円) ・NPU無し(AI用ユニット) ・内蔵GPUが低性能 【X3D】 ・非常に高価(6万円~10.5万円) ・マルチスレッド性能コスパが悪め ・コアの冷却がしにくく、消費電力の割に温度が高め |
| Ryzen 8000 | 【共通】 ・優れたマルチスレッド効率 ・省電力(~88W) ・ソケットAM5の長期サポート 【末尾G】 ・優れた内蔵GPU ・NPU搭載(8500G除く) 【末尾F】 ・ベースモデルよりも安価(内蔵GPU無し) ・8700GはNPU搭載 | 【共通】 ・最大8コア ・グラボ利用時のゲーム性能が少し低い(L3キャッシュ容量が少ないため) ・グラボ用のPCIeレーン数に制限があるので注意 【一部モデル】 ・末尾Fは内蔵GPU無し ・8400F,8500GはNPU無し |
| Ryzen 5000 (G以外) | ・非常に安価 ・マザーボードも安価 ・DDR4メモリ対応で安価 ・比較的優れた電力効率 | ・既に2世代以上も旧世代 ・DDR5メモリに非対応 ・ゲーム性能が低め ・内蔵GPU無し ・NPU無し(AI用ユニット) |
| Ryzen 5000G | ・非常に安価 ・内蔵GPU搭載(価格の割には悪くない性能) ・マザーボードも安価 ・DDR4メモリ対応で安価 ・比較的優れた電力効率 | ・既に2世代以上も旧世代 ・内蔵GPUの機能性が低い(AV1デコードやAFMFにも非対応) ・DDR5メモリに非対応 ・グラボ利用時のゲーム性能が低い ・NPU無し(AI用ユニット) |
ここではベンチマークスコアを載せています。要するに、実際のパフォーマンスです。
本記事の主旨は一応「Ryzen 3~9」の違いなのですが、必要かわからない知識を詰め込むよりも、ベンチマークと価格から判断した方が楽だし、間違いにくいという気もするので、先に載せておこうと思います。
後ろに「主要CPUの仕様と価格一覧」も併せて載せておくので、必要に応じて活用してくださいませ。
マルチスレッド性能
マルチスレッド性能は全コア稼働時の処理性能を指します。コア・スレッド数が多い方が有利な傾向があります。ゲーム性能と必ず関連性がある訳ではない点に注意してください(ゲーム性能比較は後述)。
下記にレンダリングのベンチマークであるCinebench 2024での比較表を載せています。ライバルのIntel CPUの数値も併せて載せています。
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Core Ultra 9 285K | |
| Ryzen 9 9950X3D | |
| Ryzen 9 9950X | |
| Core i9-14900K | |
| Core i9-13900K | |
| Ryzen 9 7950X | |
| Ryzen 9 7950X3D | |
| Core Ultra 7 265K | |
| Core i7-14700K | |
| Ryzen 9 9900X | |
| Core i7-13700K | |
| Ryzen 9 7900X | |
| Core i9-12900K | |
| Ryzen 9 5950X | |
| Core Ultra 5 245K | |
| Core i5-14600K | |
| Core i5-13600K | |
| Core i7-12700K | |
| Ryzen 9 5900X | |
| Ryzen 7 9700X | |
| Ryzen 7 7700X | |
| Ryzen 7 7700 | |
| Ryzen 7 7800X3D | |
| Core i5-12600K | |
| Ryzen 5 9600X | |
| Ryzen 5 7600X | |
| Ryzen 7 5800X3D | |
| Ryzen 5 7600 | |
| Core i5-13400F | |
| Ryzen 7 5700X | |
| Core i5-12400F | |
| Ryzen 5 5600X |
ゲーム性能(ハイエンドグラボ利用時)
高性能なGPU(グラフィックボード)と併用した際のCPUのゲーム性能のテスト結果を載せています。重量級ゲームが中心です。ライバルのIntel CPUの数値も併せて載せています。
ただし、より低い性能のグラフィックボードを使用する場合にはCPUによって差は生じにくくなる他、ゲームによってはCPUの重要度が低かったり、非常に軽いゲームの場合はマルチスレッド性能が重要になったりなど、プレイタイトルによって大きく左右されるので、参考までにご覧ください。
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Ryzen 7 9800X3D | |
| Ryzen 7 7800X3D | |
| Core i9-14900K | |
| Ryzen 9 7950X3D | |
| Core i9-13900K | |
| Core i7-14700K | |
| Core i7-13700K | |
| Ryzen 9 9950X | |
| Ryzen 7 9700X | |
| Ryzen 9 9900X | |
| Ryzen 5 9600X | |
| Ryzen 9 7950X | |
| Core Ultra 9 285K | |
| Ryzen 7 7700X | |
| Ryzen 9 7900X | |
| Ryzen 7 7700 | |
| Ryzen 5 7600X | |
| Core i5-14600K | |
| Core Ultra 7 265K | |
| Ryzen 7 5800X3D | |
| Core i5-13600K | |
| Core i9-12900K | |
| Core Ultra 5 245K | |
| Core i7-12700K | |
| Ryzen 9 5950X | |
| Ryzen 9 5900X | |
| Core i5-12600K | |
| Ryzen 7 5700X | |
| Ryzen 5 5600X | |
| Core i9-11900K | |
| Core i5-13400F | |
| Core i5-12400F | |
| Ryzen 7 5700G | |
| Core i5-11400F |
消費電力
ここでは消費電力の実測値を載せています。全コア稼働時(レンダリング)と、ゲーム時の2つの平均消費電力です。ライバルのIntel CPUの数値も併せて載せています。
| CPU名称 | 消費電力 |
|---|---|
| Core i5-12400F | |
| Ryzen 7 7800X3D | |
| Ryzen 5 5600X | |
| Core i5-13400F | |
| Ryzen 7 5700X | |
| Ryzen 7 5800X3D | |
| Ryzen 7 7700 | |
| Core Ultra 5 245K | |
| Core i5-12600K | |
| Ryzen 7 9800X3D | |
| Ryzen 5 9600X | |
| Ryzen 5 7600X | |
| Ryzen 9 7950X3D | |
| Ryzen 7 7700X | |
| Ryzen 9 7900 | |
| Ryzen 7 9700X | |
| Core i7-12700K | |
| Core i5-14600K | |
| Core Ultra 7 265K | |
| Core i5-13600K | |
| Core Ultra 9 285K | |
| Ryzen 9 5900X | |
| Core i9-12900K | |
| Ryzen 9 9900X | |
| Core i7-13700K | |
| Ryzen 9 9950X | |
| Ryzen 9 7900X | |
| Ryzen 9 5950X | |
| Core i7-14700K | |
| Ryzen 9 7950X | |
| Core i9-13900K | |
| Core i9-14900K |
| CPU名称 | 消費電力 |
|---|---|
| Ryzen 7 5700X | |
| Ryzen 5 5600X | |
| Core i5-12400F | |
| Core i5-13400F | |
| Ryzen 7 7800X3D | |
| Ryzen 9 7900 | |
| Ryzen 7 7700 | |
| Ryzen 5 9600X | |
| Ryzen 7 9700X | |
| Ryzen 7 5800X3D | |
| Ryzen 5 7600X | |
| Ryzen 9 5950X | |
| Core i5-12600K | |
| Ryzen 9 5900X | |
| Core Ultra 5 245K | |
| Ryzen 7 7700X | |
| Core i5-13600K | |
| Core i5-14600K | |
| Ryzen 9 7950X3D | |
| Ryzen 7 9800X3D | |
| Core Ultra 7 265K | |
| Core i7-12700K | |
| Ryzen 9 9900X | |
| Ryzen 9 7900X | |
| Ryzen 9 9950X3D | |
| Core i7-13700K | |
| Ryzen 9 9950X | |
| Core i7-14700K | |
| Core Ultra 9 285K | |
| Core i9-12900K | |
| Ryzen 9 7950X | |
| Core i9-13900K | |
| Core i9-14900K |
内蔵GPUとNPU
CPU以外のプロセッサー、内蔵GPU(主にグラフィック処理用)とNPU(AI処理用)についてです。
ただし、どちらともグラフィックボードが搭載されている場合(主にゲーミングPC)では恩恵がほとんどないのが基本という部分なので、重視したい人は少ないと思います。
主要シリーズの現状の性能は以下のようになっています(Intel CPUも含む)。ただし、Ryzenについては5000シリーズではGが付くモデル以外は内蔵GPUがなく、7000以降についても「F」が付くモデルについては内蔵GPUが使えないため、その点に注意してください。
主要なデスクトップCPU(Windows向け)に搭載されているGPUとNPUの性能比較表です。
| GPU | スコア | 搭載CPU(例) |
|---|---|---|
| Radeon 780M | Ryzen 7 8700G | |
| Radeon 760M | Ryzen 5 8600G | |
| Intel Graphics 4コア (Core Ultra 200) | Core Ultra 7 265K | |
| Intel Graphics 3コア (Core Ultra 200) | Core Ultra 5 235 | |
| Radeon 740M | Ryzen 5 8500G | |
| Intel Graphics 2コア (Core Ultra 200) | Core Ultra 5 225 | |
| Intel UHD Graphics 770 | Core i7-14700K | |
| Radeon Graphics (RDNA 2 / 2CU) | Ryzen 7 7700 | |
| Intel UHD Graphics 730 | Core i5-14400 |
| CPU | 理論性能(INT8) | 搭載CPU(例) |
|---|---|---|
| Ryzen 8000 (8600~) | Ryzen 5 8600G | |
| Core Ultra 200 | Core Ultra 7 265K | |
| その他 |
内蔵GPU:Ryzen 8000Gがダントツの性能
まず、GPUについては、「Ryzen 8000G」が頭一つ抜けて高性能であることがわかります。軽めのゲームなら快適に動かせるようになりましたし、軽い動画編集も快適になりました。
Ryzen 7000 / 9000でもほとんどのモデルで内蔵GPUが搭載されているものの、性能は低いため、性能差は大きいです。
AMDの新しめのGPUでは「AFMF」というフレーム生成機能がゲームで使えたりすることもあって、実用性は数値以上に大きかったりするので、内蔵GPUを重視するならRyzen 8000G一択です。
NPU:Ryzen 8000のみ搭載
NPUについてもRyzen 8000が有利です。
2025年5月時点の主要Ryzen(デスクトップ)ではRyzen 8000シリーズでしかNPUは搭載されていません。
最大16TOPSというのは高性能ではないものの、これでも多くのAI処理をローカルで行えるようになっているとCPUメーカーが主張していて、実際軽いものなら対応できると思います。
2025年5月時点ではほぼ役立つことはないので決め手となるかは正直微妙ですが、今後利用範囲が拡大され、細かな処理でも活用できるようになれば優位性として機能するかもしれません。
主要モデルの簡易比較表
まずは、記事更新時点(2025年5月)の市場で主要なRyzenの簡易比較表を下記に載せています。※CPU名のリンクはAmazonのもの
| CPU | Cinebench R23 Multi | コア/ スレッド | 動作クロック 定格/最大 | L3 Cache | TDP (PL1) | TDP (PL2) | コスパ | 電力効率 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D | 42,623 | 16/32 | 4.3 / 5.7GHz | 128MB | 170W | 230W | 0.358 | 185.3 | 118,980円 |
| Ryzen 9 9950X | 42,062 | 16/32 | 4.3 / 5.7GHz | 64MB | 170W | 230W | 0.486 | 182.9 | 86,500円 |
| Ryzen 9 7950X | 38,657 | 16/32 | 4.5 / 5.7GHz | 64MB | 170W | 230W | 0.533 | 168.1 | 72,590円 |
| Ryzen 9 7950X3D | 35,769 | 16/32 | 4.2 / 5.7GHz | 128MB | 120W | 162W | 0.311 | 220.8 | 104,980円 |
| Ryzen 9 9900X3D | 32,960 | 12/24 | 4.4 / 5.5GHz | 128MB | 120W | 162W | 0.333 | 203.4 | 98,980円 |
| Ryzen 9 9900X | 32,491 | 12/24 | 4.4 / 5.6GHz | 64MB | 120W | 162W | 0.508 | 200.6 | 63,950円 |
| Ryzen 9 7900X | 29,516 | 12/24 | 4.7 / 5.6GHz | 64MB | 170W | 230W | 0.470 | 128.3 | 62,800円 |
| Ryzen 9 7900X3D | 27,084 | 12/24 | 4.4 / 5.6GHz | 128MB | 120W | 162W | 0.271 | 167.2 | 99,800円 |
| Ryzen 9 7900 | 25,062 | 12/24 | 3.7 / 5.4GHz | 64MB | 65W | 88W | 0.456 | 284.8 | 54,980円 |
| Ryzen 9 5900XT | ? | 16/32 | 3.3 / 4.8GHz | 64MB | 105W | 142W | 56,680円 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | 22,911 | 8/16 | 4.7 / 5.2GHz | 96MB | 120W | 162W | 0.286 | 114.0 | 79,980円 |
| Ryzen 7 9700X | 20,824 | 8/16 | 3.8 / 5.5GHz | 64MB | 65W | 88W | 0.425 | 236.6 | 48,980円 |
| Ryzen 7 7700X | 19,973 | 8/16 | 4.5 / 5.4GHz | 32MB | 105W | 142W | 0.454 | 140.7 | 43,980円 |
| Ryzen 7 7700 | 18,720 | 8/16 | 3.8 / 5.3GHz | 32MB | 65W | 88W | 0.457 | 212.7 | 40,980円 |
| Ryzen 7 7800X3D | 18,475 | 8/16 | 4.2 / 5.0GHz | 96MB | 120W | 162W | 0.308 | 114.0 | 59,980円 |
| Ryzen 7 8700F | 18,040 | 8/16 | 4.1 / 5.1GHz | 16MB | 65W | 88W | 0.432 | 205.0 | 41,800円 |
| Ryzen 7 8700G | 17,676 | 8/16 | 4.2 / 5.1GHz | 16MB | 65W | 88W | 0.449 | 192.0 | 39,350円 |
| Ryzen 7 5700X | 14,211 | 8/16 | 3.4 / 4.6GHz | 32MB | 65W | 76W | 0.618 | 187.0 | 22,980円 |
| Ryzen 7 5700X3D | 13,786 | 8/16 | 3.0 / 4.1GHz | 96MB | 105W | 142W | 105.7 | ||
| Ryzen 5 9600X | 17,036 | 6/12 | 3.9 / 5.4GHz | 32MB | 65W | 88W | 0.437 | 193.6 | 38,980円 |
| Ryzen 5 9600 | 6/12 | 3.8 / 5.2GHz | 32MB | 65W | 88W | 38,980円 | |||
| Ryzen 5 7600X | 15,315 | 6/12 | 4.7 / 5.3GHz | 32MB | 105W | 142W | 0.568 | 107.9 | 26,980円 |
| Ryzen 5 7600 | 14,240 | 6/12 | 3.8 / 5.1GHz | 32MB | 65W | 88W | 0.527 | 161.8 | 27,030円 |
| Ryzen 5 7500F | 14,160 | 6/12 | 3.7 / 5.0GHz | 32MB | 65W | 88W | 160.9 | OEMのみ | |
| Ryzen 5 8600G | 14,067 | 6/12 | 4.3 / 5.0GHz | 16MB | 65W | 88W | 0.442 | 153.9 | 31,800円 |
| Ryzen 5 8400F | 13,361 | 6/12 | 4.2 / 4.7GHz | 16MB | 65W | 88W | 0.535 | 151.8 | 24,980円 |
| Ryzen 5 8500G | 11,521 | 6/12 | 3.5 / 5.0GHz | 16MB | 65W | 88W | 0.449 | 130.9 | 25,680円 |
| Ryzen 5 5600X | 11,268 | 6/12 | 3.7 / 4.6GHz | 32MB | 65W | 76W | 0.610 | 148.3 | 18,480円 |
| Ryzen 5 5600GT | ? | 6/12 | 3.6 / 4.6GHz | 16MB | 65W | 88W | 20,980円 | ||
| Ryzen 5 5600 | 11,040 | 6/12 | 3.5 / 4.4GHz | 32MB | 65W | 76W | 0.737 | 145.8 | 14,980円 |
| Ryzen 5 5500GT | ? | 6/12 | 3.6 / 4.4GHz | 16MB | 65W | 88W | 18,980円 | ||
| Ryzen 5 5500 | 10,605 | 6/12 | 3.6 / 4.2GHz | 16MB | 65W | 88W? | 0.817 | 120.5 | 12,980円 |
| Ryzen 3 8300G | 9,637 | 4/8 | 3.4 / 4.9GHz | 8MB | 65W | 88W | OEM限定 |
X:高性能モデルです。クロックや消費電力設定が高めに設定されています。
X3D:ゲーム性能特化モデルです。64MBの大容量L3キャッシュ「3D V-Cache」が搭載されています。
G:高性能内蔵GPUモデルです。モバイル版のRyzenが基になっており、APUと呼ばれたりします。L3キャッシュ容量が元々デスクトップ向けのモデルよりも少ないため、高性能グラボとの併用時の性能がやや低くなる点に注意。
F:内蔵GPU(iGPU)が無効化されているモデルです。Ryzen 7000以降では内蔵GPU搭載が標準となった関係で追加されました。Ryzen 5000以前では末尾G以外のほぼ全モデル内蔵GPUが無いため、Fの表記が無くても内蔵が無い場合があるので注意。
性能スコア:CPUのベンチマークで有名なCinebenchのマルチスレッドスコアです。全コア稼働時のマルチスレッド性能が高い(=コア数が多い)ほど高いスコアが出ます。
クロック:CPUのクロック周波数です。見易さ重視でPコアのみ掲載しています。高負荷時には全コアが記載の最大クロックまで上がる訳ではないので注意。
L3 Cache:CPUに付属するL3キャッシュメモリ容量です。L3キャッシュ容量が多いとゲーム性能が高くなる傾向があるので最近注目が高まっています。ゲーム以外でも遅延の少なさが重要な処理では有利に働きます。
TDP:熱設計電力です。CPUの消費電力や発熱の目安となる指標です。従来はTDP PL2が実際の最大消費電力という感じでしたが、2024年現在では電力効率重視志向が強まっているため、標準設定では最大負荷でもPL2の値を下回るケースも散見されます。
コア:CPUが実際に処理を行う部品の名称です。コア数が多いほど発熱が多くなる傾向があります。
スレッド:ざっくりいうと、コアが行う仕事を表します。原則は、1コアにつき1スレッドですが、ハイパースレッディング・テクノロジーという技術により、1コアを疑似的に2コアに見せることで、1コアにつき2スレッドを実現したCPUも今では珍しくありません。
電力効率:1Wあたりの性能スコアです。
コスパ:1円あたりの性能スコアです。
参考価格:CPUの現在の価格の参考です。記事更新時点での、価格.comやAmazonなどの最安値となっています。最終更新は2024年11月21日です。
各モデルの特徴【3 / 5 / 7 / 9】
前置きが長くなりましたが、本題の「3 / 5 / 7 / 9」各モデルの特徴解説です。3~9のそれぞれに分けて解説しています。
「CPUのゲーミング性能」は基本的に「高性能なグラフィックボードを使用した場合」のものを指しています。CPUの内蔵GPU(iGPU)の性能を示すものではないため、注意してください。
また、一応全モデルの評価一覧表も下記に載せておきますが、大分見辛いので興味がある方だけご覧ください。
各モデルの評価一覧
各モデルの各項目の性能の筆者が★1~5で評価したものです。ゲーム性能は高性能GPUと併用時の場合です。ミドルレンジ以下のGPUの場合にはCPUがボトルネックになりにくいので、表の評価ほどの差は出ない点を留意してください。
| CPU名 | マルチ スレッド | シングル スレッド | ゲーミング ※高性能GPU | 消費電力 発熱 | NPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950系 16コア32スレッド 9950X、9950X3D | ★5.0+ | ★5.0 | ★5.0(X3D) ★4.5+ | ★2.0 | × | |
| Ryzen 9 7950系 16コア32スレッド 7950X、7950X3D | ★5.0 | ★4.75 | ★4.75(X3D) ★4.5(その他) | ★2.75(X3D) ★1.75(X) | × | |
| Ryzen 9 9900系 12コア24スレッド 9900X、9900X3D | ★4.5 | ★5.0 | ★5.0(X3D) ★4.5+ | ★2.75 | × | |
| Ryzen 9 7900系 12コア24スレッド 7900X、7900X3D | ★4.5 | ★4.75 | ★4.75(X3D) ★4.5(その他) | ★4.0(無印) ★3.0(X3D) ★2.25(X) | × | |
 | Ryzen 7 9800X3D 8コア16スレッド | ★4.0 | ★5.0 | ★5.0+ | ★4.25(ゲーム) ★2.75(全コア負荷) | × |
 | Ryzen 7 9700X 8コア16スレッド Ryzen 7 9700X | ★4.0 | ★5.0 | ★4.5 | ★4.0(X) | × |
 | Ryzen 7 7800X3D 8コア16スレッド | ★3.75 | ★4.5 | ★5.0 | ★4.5(ゲーム) ★4.25(全コア負荷) | × |
 | Ryzen 7 7000 (X3D以外) 8コア16スレッド 7700X 等 | ★3.75 | ★4.75 | ★4.5 | ★4.0(無印) ★3.0(X) | × |
 | Ryzen 7 8000G 8コア16スレッド 8700G 等 高性能内蔵GPU | ★3.5 | ★4.25 | ★3.75 | ★4.0 | 〇 ~16TOPS |
 | Ryzen 7 5000番台 8コア16スレッド 5700X 等 | ★3.25 | ★3.75 | ★4.5(X3D) ★4.0 | ★3.5 | × |
Ryzen 5 9600X 6コア12スレッド Ryzen 5 9600X | ★3.75 | ★4.75 | ★4.25 | ★4.0 | × | |
Ryzen 5 7000 6コア12スレッド 7600X 等 | ★3.5 | ★4.25 | ★4.25 | ★4.0(無印) ★3.5(X) | × | |
Ryzen 5 8000G 6コア12スレッド 8600G 等 高性能内蔵GPU | ★3.25 | ★4.0 | ★3.75 | ★4.0 | × / 〇 ~13TOPS ※8600G~ で搭載 | |
Ryzen 5 5000番台 6コア12スレッド 5600X 等 | ★2.75 | ★3.5 | ★3.75 | ★4.0 | × |
Ryzen 9:圧倒的なマルチスレッド性能が魅力のハイエンドモデル

マルチスレッド ★5.0 | ゲーム ~★4.5~★5.0(X3D以外~X3D) | 発熱・消費電力 ★1.75~★4.0 | 価格 ★1.25~★2.5
| CPU名 | マルチ スレッド | シングル スレッド | ゲーミング ※高性能GPU | 消費電力 発熱 | NPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950系 16コア32スレッド 9950X、9950X3D | ★5.0+ | ★5.0 | ★5.0(X3D) ★4.5 | ★2.0(X) | × | |
| Ryzen 9 7950系 16コア32スレッド 7950X、7950X3D 等 | ★5.0 | ★4.75 | ★4.75(X3D) ★4.5(その他) | ★2.75(X3D) ★1.75(X) | × | |
| Ryzen 9 9900系 12コア24スレッド 9900X、9950X3D | ★4.5 | ★5.0 | ★5.0(X3D) ★4.5 | ★2.75 | × | |
| Ryzen 9 7900系 12コア24スレッド 7900X、7900X3D 等 | ★4.5 | ★4.75 | ★4.75(X3D) ★4.5(その他) | ★4.0(無印) ★3.0(X3D) ★2.25(X) | × |
Ryzen 9 X3D(7000 / 9000):総合性能トップの超高性能CPU。しかし、ものすごく高価
Ryzen 9 のX3Dモデルは、非常に優れたゲーム性能とマルチスレッド性能を併せ持つハイエンドCPUです。
ゲーミングPCではあまり恩恵のない内蔵のNPUやGPUを除けば、総合性能では現状トップと言えるモデルです。
しかし、その代わりにものすごく高価な点が大きなデメリットです。
まず、16コアモデルは2025年6月時点で10万円を大きく超える価格となっており、Ryzen 9 9950X3Dは約12万円です。
マルチスレッド性能だけで見れば「Ryzen 9 9950X」「Core i9-14900K」「Core Ultra 9 285K」と同レベルなのに2~4万円も高価です。
ゲーム性能だけで見ても8万円台の「Ryzen 7 9800X3D」にはわずかに及ばず、6万円台の「Ryzen 7 7800X3D」を若干超えるレベルです(3D V-Cacheの設計上、現状は8コアモデルの方が処理効率が若干良いため)。
一つのCPUで各方面でトップクラスの性能を備えるのは大きな魅力ですが、各性能で分けて見ると、2~4万円安く同等以上の選択肢があるため、実用コスパはどうなのか、と気になるCPUです。
また、12コアモデル(7900X3D / 9900X3D)も優れたマルチスレッド性能とゲーム性能を併せ持つ優れたCPUなのは間違いないものの、
マルチスレッド性能コスパが16コアモデル(7950X3D / 9950X3D)に劣りつつ、ゲーム性能も8コアモデル(7800X3D / 9800X3D)に若干劣るという中途半端なモデルになっており、基本的には第一候補にはならないモデルだと思います。
しかし、7900X3Dはその不人気さからか値下がりが進み、7800X3Dとほぼ同額で販売された時期もあったりしました。そこまでの値下がりがあれば、マルチスレッド性能重視で選択する可能性は一応あるので、価格動向は気になるモデルです。
Ryzen 9 X3D以外(7000 / 9000):小型コア無しの多コアCPUで、優れたマルチスレッド性能とコスパが魅力
X3D以外のRyzen 9は、優れたマルチスレッド性能とコスパが魅力のモデルです。
12コアもしくは16コアを搭載し、非常に優れたマルチスレッド性能を持ちます。
また、コア全てが同種のコアで構成される点もポイントです。競合のCoreは「高性能コア+小型コア」という構成のため、処理ごとのタスク割り振りが複雑になり、適切に割り振られなかった場合の性能や効率低下の懸念がありますが、Ryzenではそのようなことがないため安心できます。
それでいて、最新世代の同性能帯(マルチスレッド)の他CPUと比べて、価格も同等か少し下くらいに位置することが多いので、マルチスレッド性能を重視するなら強力なモデルです。
しかし、気になるのはゲーム性能です。
ゲーム性能はX3Dモデルと比べるとやや大きめに劣りますし、競合の第14世代Coreと比べても若干劣ります。最近ではゲームメインでPCを利用する方が多いため、この点はやや致命的になります。
プレイするゲームや使用するGPUやモニターのスペックなどによっては、CPUのゲーム性能がさほど重要でないケースもあるので、その場合には逆に有利になることもあるものの、ゲームメインの場合には基本的には第一候補にはなりにくいモデルだと思います。
ただし、Coreと比較する場合なら、長期サポートが期待できるソケットAM5採用という点での優位性があるため、将来性を考慮して魅力的に感じるケースもあるとは思うので、頭の片隅には置いておくと良いかもしれません。
Ryzen 7:実用コスパの高さとX3Dのゲーム性能が魅力のミドルレンジモデル

マルチスレッド ★3.75~★4.25 | ゲーム ~★4.5~★5.0+(X3D以外~X3D) | 発熱・消費電力 ★1.25~★3.75 | 価格 ★1.75~★4.0
| CPU名 | マルチ スレッド | シングル スレッド | ゲーミング ※高性能GPU | 消費電力 発熱 | NPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | Ryzen 7 9800X3D 8コア16スレッド | ★4.0 | ★5.0 | ★5.0+ | ★4.25(ゲーム) ★2.75(全コア負荷) | × |
 | Ryzen 7 9700X 8コア16スレッド | ★4.0 | ★5.0 | ★4.5 | ★4.0(X) | × |
 | Ryzen 7 7800X3D 8コア16スレッド | ★3.75 | ★4.5 | ★5.0 | ★4.5(ゲーム) ★4.25(全コア負荷) | × |
 | Ryzen 7 7700系 8コア16スレッド 7700X 等 | ★3.75 | ★4.75 | ★4.5 | ★4.0(無印) ★3.0(X) | × |
 | Ryzen 7 8000G 8コア16スレッド 8700G 等 高性能内蔵GPU | ★3.5 | ★4.25 | ★3.75 | ★4.0 | 〇 ~16TOPS |
 | Ryzen 7 5000 (G以外) 8コア16スレッド 5700X 等 | ★3.25 | ★3.75 | ★4.5(X3D) ★4.0 | ★3.5 | × |
Ryzen 7 X3D(7000 / 9000):ゲーム性能が非常に強力で効率まで良い。ただし、8コアの割にはかなり高価
「Ryzen 7000 / 9000」のRyzen 7は、「X3D」モデルのゲーム性能の強力さが際立つシリーズです。
特に「Ryzen 7 9800X3D」は、2025年6月時点の最強クラスのゲーミングCPUとなっており、記事執筆時点で凄まじい人気を誇っており、需要を見るにその人気は継続していくと思います。
また、先代の「Ryzen 7 7800X3D」も市場では上位のゲーム性能を持つため、「Ryzen 7 X3D」がいかに強力であるかが分かります。そのため、「Ryzen 7 X3D」はゲーム性能に特化するなら非常に魅力的なモデルです。
「Ryzen 7 X3D」が素晴らしいのは、ゲームでは性能だけでなく電力効率も良い点です。
ゲーム時の消費電力は、他CPUで例えると省電力性重視の「無印」モデル程度となっており、それでいて最強のゲーム性能なので、電力効率が非常に優れています。
他のハイエンドCPUだと、より多くの電力を使いつつも性能で届かないということなので、その差はかなり大きいです。この電力面の良さの後押しもあり、非常に人気のゲーム用CPUとして君臨しています。
そんなゲームでは最強のX3Dですが、弱点は価格です。
8コアという現状ではさほど強力でもないコア構成ながら、2025年6月時点での市場価格は6~8万円台となっており、コア数の割にめちゃくちゃ高価です。
これにより、7800X3D / 9800X3D のマルチスレッド性能コスパは他の新しい世代のCPUよりも格段に悪いですし、CPU費用を節約すればグラボのグレードをワンランク上げれるレベル高価さだというのは留意しておいて損は無いかなと思います。
とはいえ、実際には8つの高性能コアによるマルチスレッド性能は普通に高性能で、ゲームをメインとするほとんどのユーザーにとっては十分な性能を得ることができるため、あまり気にされていないことが多いです。
実際、8を超えるコアでないと厳しいという状況が頻繁に発生することは、一般のユーザーにとっては非常に稀だと思うので、ハイエンドCPUを選ぶ場合と比べて、実用コスパ的には大きな差があるケースはあまりないと思います。
ゲーム最強なので、予算が潤沢なら文句無しでおすすめできるCPUですが、8コアの割には高価であり、グラボの性能やプレイするゲーム次第ではX3Dの恩恵が小さい可能性もある点は考慮して、慎重に選択することをおすすめしたいCPUです。
Ryzen 7 X3D以外(7000 / 9000):やや中途半端さはあるミドルレンジCPU
X3D以外の「Ryzen 7000 / 9000」の「Ryzen 7」(例:Ryzen 7 7700 / Ryzen 7 9700X)は、シンプルな8コアのミドルレンジCPUです。価格は4~5万円程度です。
比較的安価で優れたコスパを持つのが魅力です。安さを重視したいけど、「Ryzen 5 / Core 5」では高性能コアの数の少なさに不安がある人向けです。
以前は、Coreと比べるとマルチスレッド性能コスパが悪いのにゲーム性能も高くはなかったので、パッとしない印象でしたが、Intelの不具合問題や大幅な値下がりを経て、低価格コスパ重視で魅力的な選択肢となりました。
2025年6月時点では、20万円前後のゲーミングPC向けとしてはかなり無難に思える選択肢となっています。
Ryzen 7 8000G:強力な内蔵GPUが魅力。重いゲームをしないならこれ一つでOK
「Ryzen 8000」の「Ryzen 7」は、強力な内蔵GPUが魅力のモデルです。実質的には「Ryzen 7 8700G」のピンポイントモデルです(一応「Ryzen 7 8700F」といった内蔵GPU非搭載のグラボ必須モデルがありますが、こちらは正直おすすめではないです)。
「Ryzen 7 8700G」は「RDNA 3」アーキテクチャのGPU「Radeon 780M」を搭載しており、これが内蔵の割には非常に高性能です。少し前のエントリーグラボ「GTX 1650」に匹敵するくらいの性能があるため、グラボ無しでも少し重めくらいのゲームまでなら対応できます。
また、「RDNA 2」以降では「AFMF」というAMDの手軽に使えるフレーム生成機能(fpsの底上げ機能)が利用できることも大きく、実質の性能は更に上となり、少し古いミドルレンジGPU並みの性能となることもあるほどです。
そのため、グラボが必須のような重いゲームをやらないライトユーザーにとっておすすめのモデルとなっています。
グラボ搭載での利用もできますが、L3キャッシュ容量が少なかったり、グラボ用のPCIeレーン数が制限されていることもあっておすすめではないので、基本的にグラボ無しで使う人向けのCPUです。
更に、「Ryzen 7 8700G」ではNPU(AI用のユニット)も搭載されているのも地味に嬉しいです。ピーク性能は16TOPSなので高性能ではありませんが、WindowsやIntelによれば10TOPS台でも使える機能は多数あるようなので、グラボ無しの場合は先んじて対応しておけるのは安心感があります。
価格はやや高価(5万円前後)なので、CPU性能単体で見た場合や、グラボ搭載向けのCPUとしてのコスパが悪めな点は留意しておく必要がありますが、グラボ無し運用を出来るだけ長く続ける場合には非常に魅力的なCPUだと思います。
Ryzen 7 5000(G以外):非常に安価な低価格高コスパCPU。ゲーム性能も効率も旧世代の割には悪くない
旧世代となる「Ryzen 5000」の「Ryzen 7」(例:Ryzen 7 5700X、Ryzen 7 5700X3D)は、新しいCPUと比べると非常に安価で実用コスパに優れるのが魅力のモデルです。
まず良い点は、小型コアを含まない8コアを搭載しながら2万円台前半~という価格です。マルチスレッド性能コスパが良いです。ここは最新CPUと比べても優れている部分なので、低価格PC用としては非常に魅力的です。
また、もう一つ良いのはゲーム性能が旧世代の割には悪くない点です(末尾Gモデルを除く)。これは、CCDあたりのL3キャッシュ容量が旧世代の割には多めの32MB確保されていることが恐らく要因です。
さすがに最新のハイエンドGPUとの組み合わせだと力不足が目立つレベルであるものの、このレベルの安価なCPUはグラボも良くてアッパーミドル程度までの採用が多いことを考えると、大きなネックにはならない程度のゲーム性能を備えているため、多くの旧世代CPUで見られるゲーム性能の低さというデメリットが実質的にあまり気にならないのが良いです。
また、電力面も旧世代の割には優れており、省電力設定なら気にならないレベルというのも良い点です。
既に旧世代であるため、メモリがDDR4にしか対応していない点や、マザーボードの拡張性や規格面ではやや劣り、今後良くなることもないという点は留意しておくべきですが、
DDR4メモリは容量単価が安いという点で優位性もありますし、購入後にパーツ交換を考えない人で、今すぐに実用コスパの良い安いPCが欲しいという場合には非常に強力なモデルです。
ちなみに、「Ryzen 7 5700X3D」は気になるX3Dモデルですが、7000以降と比べるとちょっと微妙なので注意。これはクロックが大分低めに設定されているため思ったほどゲーム性能が高くないためです。
Ryzen 7000(無印)の劣るゲーム性能となっている上、価格も元の「Ryzen 7 5700X」から1万円ほど高くなってしまい、安さの利点も薄れてしまっていることが大きく、優先度が高くありません。
「Ryzen 7 5700X3D」を選ぶなら「Ryzen 5 7600」などを選択した方が新しいソケットに対応できる分有利なので、新規で導入するというよりは、既にAM4マザーボードを所持している人が移行先として選ぶ感じのCPUとなっています。
Ryzen 5:安価で優れたゲーム性能が魅力のミドルレンジ下位モデル

マルチスレッド ★2.75~★3.75 | ゲーム ~★4.25 | 発熱・消費電力 ★3.5~★4.0 | 価格 ★2.5~★4.5
| CPU名 | マルチ スレッド | シングル スレッド | ゲーミング ※高性能GPU | 消費電力 発熱 | NPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 9600系 6コア12スレッド 9600、9600X | ★3.75 | ★4.75 | ★4.25 | ★4.0 | × | |
Ryzen 5 7000 6コア12スレッド 7600X 等 | ★3.5 | ★4.25 | ★4.25 | ★4.0(無印) ★3.5(X) | × | |
Ryzen 5 8000G 6コア12スレッド 8600G 等 高性能内蔵GPU | ★3.25 | ★4.0 | ★3.75 | ★4.0 | × / 〇 ~13TOPS ※8600G~ で搭載 | |
Ryzen 5 5000番台 6コア12スレッド 5600X 等 | ★2.75 | ★3.5 | ★3.75 | ★4.0 | × |
Ryzen 5(7000 / 9000):安価で優れたゲーム性能が魅力。AM5に安価に対応できるのも良い
「Ryzen 7000 / 9000」の「Ryzen 5」は安価でゲームコスパに優れており、最新ソケットに安価に対応できるのが魅力のモデルです。
まず良いのはやはりゲーム性能です。安価な割にはゲーム性能が高いです。これは「Ryzen 5」は6コアしか搭載しませんが、「Ryzen 7」と同じ32MBのL3キャッシュを持つことが主な要因です。
これはIntelの「Core i5 / Core Ultra 5」の20MB~24MB(2025年6月時点)よりも多く、同価格帯ではRyzen 5の方がゲーム性能は大体若干有利というのも覚えておくと良いかもしれません。
コア自体は少ないので、一部のゲームやグラボの性能次第では若干ネックになるケースもあるものの、Ryzen 7とのゲーム性能は実は大差ないです。
Ryzen 5を選ぶ時点でハイエンドグラボを採用するケースがほぼ無いことを考えると、無視しても良いレベルとなっており、CPUの分の予算をグラボや他パーツに回せるのが大きな強みです。
更に、「Ryzen 7000 / 9000」の場合は同時にソケットがAM5に対応できるというのも嬉しいところです。AMDのソケットは長期サポートとなる傾向があり、AM5も最低で2027年までのサポートが明言されています。
マザーボードをそのままに新世代CPUへ移行できる余地を残せるというのは安心感があります。ライバルのIntelのソケットのサポートが短めでCPUの販売もすぐに打ち切られることから、Intelよりも導入しやすさは一段上になると思います。
このように、低価格用の汎用性に優れた「Ryzen 5」ですが、弱点はやはりマルチスレッド性能がやや低い点と、マルチスレッド性能コスパが有力な上位モデルと比べると基本劣る点です。
最近の6コアCPUは十分高性能と言えるレベルだと思うので、性能自体は用途次第でネックにはならないかと思いますが、他CPUの性能も向上していますし、重い処理も増えているので、全体で見れば高いとは言えない性能です。
特に気になるのは「Core i7 / Core Ultra 7」との性能差で、価格でいえばおおよそ2~3万円前後といった感じですが、コア数に劇的な差があるので、マルチスレッド性能差は約1.5倍~2.4倍(電力設定次第)くらい違います(2025年6月時点)。
CPU単体価格は2倍前後なので、そこだけ見ればコスパは良い勝負に見えますが、PC総額でいうと、話が違ってきます。
たとえば、20~30万円台のPCとするなら、2~3万円の価格増加率は10%台です。それで2倍前後のマルチスレッド性能を得られるとなると、やはり総合コスパはかなり違いを感じると思います。
「Ryzen 5」でも困ることはないと思っていても、これだけの差があるとやはり気になる人は多く、「7」以降のモデルの方が無難な選択肢として人気となっている印象です。
Ryzen 5 8000G:安価で高性能な内蔵GPUが魅力。8600Gはライトユーザーへの実用コスパが非常に良い
「Ryzen 8000」の「Ryzen 5」は、高性能な内蔵GPUが魅力のモデルです。
「RDNA 3」アーキテクチャのGPU「Radeon 760M or 740M」を搭載しており、グラボ無しでも少し重めくらいのゲームなら対応できます。
グラボ搭載での利用もできますが、L3キャッシュ容量が少なかったり、グラボ用のPCIeレーン数も少し制限されていることもあって、基本的にグラボ無しで使う人向けのCPUです(グラボへの影響はほぼないレベルだとは思いますが)。
また、「RDNA 2」以降では「AFMF」というAMDの手軽に使えるフレーム生成機能(fpsの底上げ機能)が利用できることも大きく、実質の性能は少し前のエントリーグラボを少し超えるレベルも期待することができます。
そのため、グラボが必須のような重いゲームをやらないライトユーザーにとっておすすめのモデルとなっています。
グラボを搭載しなければ消費電力・発熱を格段に減らすことができますし、設置スペースも浮くので、PCの小型化にも貢献することもライトユーザー向けの理由の一つです。
選択肢は主に「Ryzen 5 8600G」か「Ryzen 5 8500G」となりますが、特におすすめなのは「Ryzen 5 8600G」です。
「Ryzen 5 8500G」の方が7千円ほど安いですが、「グラフィック性能が30%以上も低下(GPUコア半分)」「NPU(AI用のユニット)が省かれる(16TOPS→無し)」、「コアの一部が小型コアになってマルチスレッド性能も少し落ちる」などの違いがありますし、GPU用のPCIeレーンが基本4しかないので、ゲーミングPC向けにも使いづらく、安さ特化で内蔵GPUでしか利用しないという場合のみで需要があるCPUで、汎用性を考えると正直おすすめではないです。
Ryzen 5 5000(G以外):安さ特化のゲームCPUとしては強力だけど、総合コスパを考えると良くはない
旧世代となる「Ryzen 5000」の「Ryzen 5」(例:Ryzen 5 5600 / 5600X / 5600T)は、安さ特化のゲーム用CPUとして強力なモデルです。
最安で1万円台後半という非常に安価なCPUながら、L3キャッシュを32MB搭載する関係で、他の2万円以下のCPUよりもグラボ搭載時のゲーム性能が落ちにくいのが魅力です。
そのため、ミドルレンジ以下のGPUを採用する場合の低価格ゲーミングPC用の安さ特化の選択肢として非常に強力です。
このように、単体で見ると悪くないのですが、+5,000~7,000円ほどでマルチスレッド性能は約1.3倍高い「Ryzen 7 5700X」選べるため相対的に微妙に見えるCPUです。
PC総額で考えてみると、+5,000~7,000円は15万円以下の低価格PCなら基本5%前後程度の費用増加です。それで1.3倍のマルチスレッド性能向上が得られるとなると、明らかに「Ryzen 7 5700X」の方が魅力的なので、相対的に評価を落としている印象です。
Ryzen 3:ほぼメーカー機専用でコスパも微妙な下位モデル
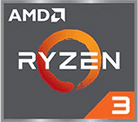
マルチスレッド ★2.0 | ゲーム ★2.75 | 発熱・消費電力 ★4.5
概要:比較一覧表
本記事の主旨となる内容は以上で終わりですが、上記では触れなかった内容も参考程度に触れていこうと思います。
ここでは、ゲーム以外の部分も含めた世代の違いについて触れていきます。
まず、2025年5月時点での主要シリーズの主な概要が以下のような感じになっています。
| シリーズ | アーキ テクチャ | プロセス | ソケット | CCD(8コア) あたりの L3 Cache | NPU | GPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9000 | Zen 5 | 4nm(CCD) +6nm(IOD) | AM5 | 32MB X3D:+64MB | × | RDNA 2 / 2CU |
| Ryzen 8000G | Zen 4 | 4nm | AM5 | 16MB | 〇/× | RDNA 3 / 4~12CU |
| Ryzen 7000 | Zen 4 | 5nm(CCD) +6nm(IOD) | AM5 | 32MB X3D:+64MB | × | RDNA 2 / 2CU |
| Ryzen 5000 | Zen 3 | 7nm | AM4 | 32MB X3D:+64MB | × | × |
| Ryzen 5000G | Zen 3 | 7nm | AM4 | 16MB | × | Vega 6~8 |
以下から、各項目についてざっくりと触れていこうと思います。
また、シリーズ別の特徴まとめも参考までに載せておくので、興味がある方はご覧ください(長くて見辛いので初期は非表示にしています)。
- Ryzen X3D:大容量L3キャッシュ搭載で、非常に優れたゲーム性能
- Ryzenの「X3D」と付くモデルはゲームで非常に強力なモデルです。「3D V-Cache」と呼ばれる大容量のL3キャッシュメモリ(64MB)を垂直方向に積層する形で実装した大容量キャッシュモデルとなっており、ベースモデルからゲーム性能の大きな向上が見られます。ゲームにおいては電力効率が良い傾向も見られるので、重い処理はほとんどゲームしかしないという人にとって非常に魅力的な選択肢です。
ただし、価格は大体ベースモデルから+2万円前後と大きく高価になる点は要注意です。コア数は同じでマルチスレッド性能はほぼ変わらないので、同価格帯の他CPUよりもマルチスレッド性能が低く、ゲーム以外の処理では大体コスパが悪いのがデメリットです。
ゲームで非常に強力なのは間違いないですが、ゲームでも「3D V-Cache」が大きくは活きない場合もありますし、ミドルレンジ以下のGPUではCPUのゲーム性能の高さがあまり活きないことが多い点も要注意です。
価格の高さを考えると、X3Dモデルにする費用分をグラボへ回した方が最終的なゲーム性能は高くなるケースも多いと思うので、その辺りも考慮して慎重に選択したいです。
また、「3D V-Cache」がCCD一つ(8コア)しか適用されない関係で、8コアモデルの方がゲーム性能が少し高い点もポイントです。 - Ryzen 9000:最新世代で優れた効率と電力面が魅力。だけど、7000との性能差は小さめ
- 「Ryzen 9000」シリーズは、2025年6月時点で最新の世代です。アーキテクチャには「Zen 5」が使用されており、細いほど良いとされている製造プロセスは4nm + 6nm(CCD + IOD)と最新鋭です。優れたマルチスレッド性能効率と電力面が魅力です。
ただし、Ryzen 7000(Zen 4、5nm + 6nm)との処理性能差はさほど大きくないです(モデルによりますが、おおよそ+5%~10%)。新しい分価格がやや高価な点もあるので、その辺りも考慮して選択したいです。
また、アーキテクチャの刷新を伴う最新世代ですが、ソケット形状は7000と同じAM5で600番台のチップセットが使える上、CPUクーラーも同じものが使えるので、新規導入や7000からの移行に際して、CPU以外の費用的なデメリットがほぼ無いのは強みです。 - Ryzen 7000:優れた効率と総合コスパの良さが魅力。AM5を安価に採用できるのも良い
- 「Ryzen 7000」シリーズは、2025年6月時点で9000の一つ前の世代です。アーキテクチャは「Zen 4」が採用されており、製造プロセスは5nm + 6nm(CCD + IOD)です。旧世代となりましたが、9000の「4nm+6nm」とプロセス的には差がほとんどなく、性能差も小さめなので十分新しい世代として戦える性能です。
旧世代化しても十分通用するマルチスレッド効率の良さは魅力ですし、X3Dモデルは最新のCore(Core Ultra 200S)よりもゲーム性能が高いです。それでいて最新世代よりもやや安価なので、9000シリーズの価格が落ち着くまではコスパ的には7000の方が少し良いことが多いと思います。供給状況がどうなるかは不明ですが、市場に在庫が残る限りは有力な状態が続くと思います。
また、Intelはアーキテクチャを伴う刷新では対応マザーボードも互換性が無くなるのが通例ですが、AMDは同じソケットを長期間サポートし続ける傾向があるのも注目です。「Ryzen 7000」で採用されるAM5は最新の「Ryzen 9000」でも採用が続けられており、最低でも2027年までのサポートが明言されているので、後のCPU交換などを視野に入れる際には魅力的です。AM5をコスパを良く安価に採用できる「Ryzen 7000」シリーズは性能以外の面でもメリットがあると思います。 - Ryzen 8000G:高性能な内蔵グラフィックが魅力
- Ryzen 8000G(例:Ryzen 7 8700G、Ryzen 5 8600G)は高性能な内蔵グラフィックが魅力のモデルです。上位モデルでは少し前のエントリーグラボ並みの性能があるので、少し重めのゲームや動画編集くらいならグラボ無しで対応できるのが強みです。PCを出来るだけ小型化したい人や電力をできるだけ削減しつつ重めのグラフィック処理にも対応したい人に適したモデルです。
更に、Ryzen 5 8600G以降ではAI処理用のNPUも搭載されています。最大性能は16TOPSなので高性能ではありませんが、WindowsのAI機能にも活用できることが期待されています。8500G以下はNPU搭載がなく、GPUのコア数も少なくなるので、出来れば8600G以降がおすすめです(ただし、8500Gは2万円台中盤と非常に安価なので、安さ特化なら無しではないです)。
デメリットとしては、グラボ搭載用のCPUとしてはやや不向きという点があることが要注意です。Ryzen 8000は実はモバイル版のCPUをベースにしているため、CCDあたりのL3キャッシュが他モデルの半分(16MB)となっており、キャッシュ容量が重要なゲームでの性能が他の新しめのCPUよりも劣ります。
更に、グラボに回せるPCIeレーン数も他のデスクトップ向けのCPUよりも少ないので、上位クラスのグラボでは性能が制限される可能性もあります。
ミドルレンジ以下のGPUならさほどネックにはならない点ではありますが、L3キャッシュが少ない点もあり、グラボ搭載前提なら他CPUよりも総合コスパがやや悪めなので、基本的にはグラボ無し運用前提のCPUとして捉える方が良いです。
ちなみに、GではなくFが付く8000シリーズ(例:Ryzen 7 8700F、Ryzen 5 8400F)もありますが、そちらでは内蔵GPUが省略されており、最大の強みが無くなってしまっています。2025年1月時点では内蔵GPU搭載モデルよりも価格が5000円~8000円ほど安くなっていることで、マルチスレッド効率は優れているというメリットはあるものの、上述のグラボ搭載時のゲーム時の性能の問題があるため、基本的にはおすすめはしないモデルです。 - Ryzen 5000 (G以外):旧世代だが、非常に安価で実用コスパが非常に良い。ゲーム性能も割と悪くはない
- Ryzen 5000(例:Ryzen 7 5700X、Ryzen 5 5600)は、初登場が2020年の旧世代Ryzenです。そのため、処理性能は新しい世代には大きく劣るものの、非常に安価で実用コスパに優れるのが魅力のシリーズです。そのため、未だに販売が継続している上に人気のシリーズです。
CPU価格が安いだけでなく、旧世代チップセット採用のマザーボードが非常に安価で豊富な点でも、費用面で利点があります。更に、メモリがDDR5ではなくDDR4のみ対応ですが、そちらも安さ重視なら利点になるため、PC全体で大きく節約できることが非常に大きなメリットです。
それでいて、性能面でも高いレベルを求めないなら十分なレベルを提供してくれます。Ryzen 5000は登場時には最新鋭のプロセスを採用したCPUであったため、2024年時点でも省電力動作時の電力効率は悪くないですし、コアあたりのL3キャッシュ容量も2024年時点の最新CPUと比べても劣らないため、ハイエンドGPUと組み合わせなければ、ゲームでも大きなネックになることは意外と少ないです。
むしろ、節約した費用分をグラボに回すことで最終的なゲーム性能の向上すら期待できるレベルという、安さとコスパ特化なら反則レベルのCPUになっていると思います。 - Ryzen 5000G / 4000:非常に安価だけど、基本非推奨
- Ryzen 5000G / Ryzen 4000(例:Ryzen 5 5700G / 5500、Ryzen 5 4500)は、旧世代のRyzenです。そのためコア性能が低いのは仕方ないとしても、実はモバイル版のものが基になっている関係で、L3キャッシュ容量が少ない点に注意が必要です。
そのため、高性能なグラボとの併用やCPU性能が重要なゲームでは、他の新しめのCPUよりも性能がやや低くなることが多いですし、その他のパフォーマンスも低いです。
L3キャッシュを32MB搭載する「Ryzen 5 5600系」と比べると価格差が小さい割に性能差が大きい印象なので、個人的には非推奨です。
Zen 5とか(アーキテクチャ)
「Zen 5」などはCPUのマイクロアーキテクチャのことです。CPUの内部の設計面の世代を表します。
このアーキテクチャが新しいほど、1コアあたりの性能が上がり、電力効率も向上する傾向があります。そのため、出来るだけ良いCPUが欲しい場合には最新のアーキテクチャのCPUを選ぶことになります。
しかし、アーキテクチャ間の性能差は一定ではない点に注意が必要です。
2025年6月時点の主要アーキテクチャだと、Zen 5 と Zen 4 の差は小さいことがポイントです。Zen 3とは大きめの性能差があるので、性能重視ならZen 4以降を選ぶのを意識すると良いです。
下記が現在の主要Ryzenのアーキテクチャです。
表を見て貰えるとわかるように、アーキテクチャは基本的には世代番号と連動しています(Ryzen 7000 なら Zen 4 みたいな感じ)。
Ryzenの一部のシリーズで例外はあるものの、デスクトップ向けのRyzenではRyzen 5000以降は分けられている(上記の表参照)ので、2025年時点では例外を気にする必要もなく、数字が大きいほど新しいという認識でOKです。
しかし、このアーキテクチャが新しいほど高価な傾向もあるので、予算と相談することになります。
プロセスルール(ノード):配線の幅
「4nm」などは、CPUの製造プロセスルールを表しています。これは配線の幅のことです。
これが細いほど少ない消費電力で運用できるので、電力効率が良い傾向があります。
また、より複雑で緻密な設計が可能となるので、処理性能や機能面でも高くなっていることが多いです。
CPUの性能を決める要素はたくさんありますが、基盤となるのはやはり素材と配線なので、このプロセスルールがCPUの質を決める大きな要素の一つとして重要となっています。
しかし、やはりこのプロセスが細いものほど高価な傾向があるので、予算との相談になります。
なのですが、2025年時点のRyzenでいうと、Ryzen 7000~9000ではCPU部分は4m~5nmとわずかな差しかないので、プロセス面の差はあまり考えなくても構わないです。
また、従来ではチップを単一のダイ(素材)で作られていましたが、最近では主にコスト面の問題からチップレット設計(複数チップから構成)採用が増えているのもポイントです。
補足説明やプロセスルールなどについて下記に載せています。
ソケット:Ryzenは同じソケットを長くサポートするのも強み
CPUのソケットとは、CPUをマザーボードに取り付ける場所のことです。
CPUの世代によって決まっており、対応したマザーボードでないと使用することができないようになっています。
そのため、世代が新しくなってソケットが変更になってしまうと、既存のマザーボードでは対応ができなくなるため、その新しいCPUを使う場合にはマザーボードも変更する必要があるのが注意する点です。
しかし、Ryzenではこのソケットを長い期間サポートすることが特徴で、強みの一つとなっています。
たとえば、2016年に導入されたソケット「AM4」も、2025年になっても新CPUが追加されたという実績があります。
2025年で最新の「AM5」も最低でも2027年までのサポートが明言されており、地味に嬉しいです。
ライバルのIntel(Core)の場合は、一つのソケットを長く使い続ける傾向があまり無く、最近では長くても3年くらいで新しいソケットへと切り替わり、古いソケットを利用した製品は新たに追加されることがほぼないこともあり、相対的に優位性があるという状況となっています。
そのため、後からCPU交換を検討の余地も残しておきたい際には、Ryzenは非常に心強い味方となっています。
下記に各Ryzenのソケットと発売日について載せています。
末尾のアルファベット(サフィックス)の意味
後回しの説明となってしまいましたが、ここまでの説明でも少し登場したように、CPUを見ていると、「Ryzen 9 9950X3D」などのように、末尾にアルファベットが付いているものがあります。
これは主にCPUの大まかな特徴(他製品と比較した場合)を表すものとなっています。AMDの消費者向けデスクトップ版CPUでは、現在では主に以下のようなものが使われています。
| 末尾(サフィックス) | 特徴 | 概要 |
|---|---|---|
| X | 性能重視 | 高性能モデルです。消費電力やクロックが高めに設定されています(ただし、モデルによっては普通に省電力)。 |
| X3D | ゲーム性能 重視 | ゲーム性能重視モデルです。大容量のL3キャッシュ「3D V-Cache」を搭載し、ゲーム性能が強化されています。 消費電力は無印よりは多いですが、Xほどは多くないです。モデルによりやや差があります。 |
| 無印 | 標準 (省電力) | 省電力性の高さが特徴の標準モデルです。Intelと違い、無印でもクロック倍率はロックされていないことが多いです。 |
| G | 高性能 内蔵GPU | 高性能な内蔵グラフィックス搭載が特徴のモデルです(APUと呼ばれたりする)。 2024年時点では、上位のものはGTX 1650に匹敵する性能を示したりもしている他、「AFMF」というフレーム生成機能が手軽で効果的なので、ライトゲーマーならこれでも十分だったりします。 |
| F | 内蔵GPUなし | 内蔵GPU無効化モデルです。その分価格が少し安くなっています。 Ryzen 7000以降で内蔵GPU搭載が標準となったことに伴い追加されました。 |
ゲーミングPC用の場合は大体別途グラフィックボードを搭載しており、内蔵GPUが必要でないため、「F」が最も安価でコスパが良いです。
無印はオーバークロックができず、省電力な設定になる傾向があります。しかし、電力設定を調整することで、初期設定よりも性能を少し引き上げたりは出来る場合がある点は覚えておくと良いかもしれません。
K付きはオーバークロックが可能なだけでなく、標準のクロックや電力設定値も高い性能特化モデルです。しかし、ほとんどの場合においては無印の方が電力効率が良く、少しの性能向上のために電力を多く使って発熱も爆増するみたいな場合が多い点に注意。後から悪い意味でK付きの特徴が嫌になった人は、少し最大クロックや最大の消費電力を下げると良いかもしれません。
L3キャッシュとゲーム性能
キャッシュメモリというのはよく使うデータを置いておくメモリのことです。CPUには処理を出来るだけ待たせないための仕組みとして、このキャッシュメモリが導入されています。
キャッシュメモリは容量は非常に少ないのですが、CPUとの通信が非常に高速となっており、特に処理の遅延改善に役立ちます。
そして、このキャッシュメモリの容量が多いと高性能になりやすい処理の一つにゲームが含まれるため、最近では特に注目されています。
X3D:L3キャッシュを増量したモデル
キャッシュメモリが多いとゲーム性能が高くなる傾向を利用して、Ryzenには大容量L3キャッシュを搭載したゲーム向けのモデル「Ryzen X3D」があります。
これは大容量の64MBのL3キャッシュ「3D V-Cache」を搭載したモデルです(例:Ryzen 7 7800X3D)。ゲームパフォーマンスの向上に実際に大きな効果を示しています。
しかし、X3Dモデルはベースモデルよりも高価になるため、マルチスレッド性能コスパが悪化する点は注意する必要があります。
一部モデルはCCDあたりのL3キャッシュが16MBなので、低価格帯は特に注意
一応、注意しておきたいのは、CCDあたりのL3キャッシュ容量です。
CCDというのは、Ryzenにおけるコアの管理単位のことで、「8コアごとのコアのまとまり」です。Ryzenでは、このCCDごとにL3キャッシュが用意されるという構造になっています。
そして、このCCDあたりのL3キャッシュですが、現行のほとんどのデスクトップ向けのRyzenではCCDあたり32MBなのですが、一部のモデルはCCDあたり16MBとなっている点が注意したい点です。主に、APUと呼ばれるモデルがこれに該当します。
これらのRyzenでは高性能なグラボを搭載した場合のゲーム性能がやや低くなる可能性がある点に注意が必要です。
2025年5月時点で市場で見られるモデルだと、「Ryzen 8000」、「Ryzen 5000G」、「Ryzen 5000の下位(5500以下)」などが該当します(Ryzen 4000はZen 2なので少し構造が違うけど、L3キャッシュ容量は同様に少ないです)。
この差の原因は、デスクトップ版のRyzenでも、モバイル版のRyzenを基にした設計のものが含まれているためです。特に末尾G(高性能内蔵GPU)は全てこの仕様になっていることに注意する必要がある他、Gが無くても一部モデルでは同様の仕様となっています。
Gが付かない該当モデルはコア数が少なく安価な傾向があるので、見慣れない番号で妙に安いなと感じたら一応チェックしておくと良いかもしれません。