この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
デスクトップ向けのIntelの「Core」シリーズの各モデル「9 / 7 / 5 /3」などのナンバリングごとの違いをざっくり解説しています。
本記事の主な対象は「最新世代」+「最新の一つ前の世代」としています。2025年6月時点では「Core Ultra 200」+「第14世代Core」です。本来はナンバリングごとの違いに焦点を当てたページでしたが、Core Ultraで世代間の差も多く出てきたので、現在はそちらの内容も多めです。
「マルチスレッド性能」と「ゲーム性能」
まず始めに、「CPUで重要な性能」について触れておきます。
CPUの性能を決める項目はたくさんありますが、2025年時点のデスクトップ向けCPUで特に重視されているのは「マルチスレッド性能」と「ゲーム性能(高性能なグラボと併用時)」の2つです。
下記にざっくりとした説明を載せています。
この二つの性能について、この後詳しく触れていきます。
また、用途次第では「iGPU(CPUの内蔵GPU)」や「NPU(AI用ユニット)」も重視されますが、デスクトップにおいては重要でないケースが多いので、本記事では参考程度の扱いとしています。
これは、最近のデスクトップではグラフィックボード(グラボ)を搭載したものが選ばれることが多いためです。
グラボがあれば、内蔵GPUやNPUよりも高度なグラフィック処理やAI処理に対応できます。そのため、CPUにそれらが搭載されている必要性がありません。
そのため、特にゲーミングPCを検討している方の場合は、前述した「マルチスレッド性能」と「ゲーム性能」を気にしていればOKです。
まずは、マルチスレッド性能から触れていきます。
マルチスレッド性能は複数コアを使用した際の処理性能で、全コア稼働時のCPUの最大性能を指すことが一般的です。
主にマルチタスク(重い処理複数)や、単体で非常に重いCPU処理の際に重要となります。
マルチスレッド性能の高さはコア数が非常に重要です。コア数が多いほど高性能なのが基本です。
本記事で対象とする「Core Ultra 200」と「第14世代Core」のデスクトップ版においては、どちらもコア構成が同じとなっているためわかりやすいです。
Pコアが「Core Ultra 200」では1スレッド1コアなのに対し、「第14世代Core」では1コア2スレッド(ハイパースレッディング有効)となっている点で差があります。
下記の表の通りになっています。
2025年6月時点の主要世代では、基本的にコア数が多い(数字が大きい)ほどマルチスレッド性能が高いと思って頂いて大丈夫です(Core Ultra 200 と Core 14000)。
新しい世代の方が1コアあたりの性能が高くなる他、CPU内には複数種類のコアが存在するため、必ずしもコア数とマルチスレッド性能の高さが比例する訳ではありませんが、Core Ultra 200 と Core 14000 に関してはコア構成が同じですし、マルチスレッド性能もかなり近いので、特に気にする必要がありません。
また、デスクトップ版Coreの主要シリーズにおけるナンバリングの各モデルの特徴について、下記で文章でもそれぞれ触れているので、興味があればご覧ください。
- Core Ultra 9 / i9(24コア):最もコア数が多いハイエンドモデルだが、性能以外の面は犠牲に
- Core Ultra 9 / i9はCoreシリーズにおける最上級モデルです。2025年2月時点の主要世代「Core Ultra 200S / 第13,14世代Core」の場合、コア数は24コア(8P+16E)と非常に多いです。Coreシリーズで最も多いコア数を持ち、そのマルチスレッド性能は圧倒的な高さです。
その代わり、価格は非常に高価ですし(2025年5月時点で約7.5~9.8万円)、高負荷時の消費電力がものすごく多いため、電源容量やCPUクーラーにも十分に注意を払う必要があります。
ゲームにおいても高い性能を持ちますが、現状は重いゲームでもコア数で恩恵があるのは8コア程度まで(Pコア)と言われているため、実は「Core Ultra 7 / Core i7(8P+12Eコア)」と比較してもゲーム性能は大して変わりません。クロック差などによるわずかな差となっています。そのため、9モデルを検討するのは、費用や消費電力を犠牲にしてもマルチスレッド性能を少しでも高めたいという場合になります。ほとんどの人にとっては実用面ではマイナスになることも珍しくないと思うので選ぶ際には慎重になる必要があります。
また、「Core Ultra 9(200)」はゲーム性能が先代のCore i9と比べて少し低下している点に注意(2025年のBIOSアップデートにて改善が示唆されてはいる)。その代わりゲーム時の温度面は改善し、NPUを搭載するなどの別の面で少し優位性があります。 - Core Ultra 7 / i7(20コア):ゲーム性能は「9」とも大差ない高性能高コスパな人気モデル
- Core Ultra 7 / i7はCoreシリーズにおける上級モデルです。コア数は20コア(8P+12E)となっています(2025年5月時点の主要世代「Core Ultra 200S / 第14世代Core」の場合)。非常に多いコアを持ち、そのマルチスレッド性能は非常に高いです。
「9」モデルと比べるとコアが4つ少ないですが、削減されているのは小型のEコアのみで、高性能なPコアの数が変わらないのがポイントです。現状は重いゲームでもコア数で恩恵があるのは8コア程度まで(Pコア)と言われているため、実は「Core Ultra 9 / Core i9(8P+16Eコア)」とゲーム性能は大して変わりません。
マルチスレッド性能は、ほとんどの消費者にとっては「7」でも十分すぎる性能が得られるということもあり、実用コスパという意味では「9」モデルを上回ることが多いため、高性能CPUを求める際に特に人気なのが「7」です。
ただし、価格が「9」ほどではないものの非常に高価な点がデメリットです(2025年2月時点で約5~7万円台)。
電力面に関しては、K無しモデルは省電力な他、Core Ultra 7(例:Core Ultra 7 265K)ではK付きでも電力面が格段に改善しているので以前ほど気を遣わなくてよくなっています。
前世代のi7のK付き(例:Core i7-14700K)は電力面が凄く悪いですが、そこさえ避ければ良いので、「9」と比べれば電力面でも融通は利きやすいです。 - Core Ultra 5 / i5(10 / 14コア):性能も悪くなく、価格の安さとコスパが魅力のミドルレンジモデル
- Core Ultra 5 / i5はCoreシリーズにおける中級モデル、いわゆるミドルレンジモデルです。コアは2つの構成が存在し、10コア(6P+4E)か、14コア(6P+8E)です(2025年5月時点の主要世代「Core Ultra 200S / 第14世代Core」の場合)。
「7」と比べるとコア数が6~10コアも少ないため、マルチスレッド性能は大きく劣りますが、十分に高性能と呼べる性能となっており、重い処理でも普通にこなせる性能です。
それでいて、価格は比較的安価なのが強みです。2025年2月時点では2万円台中盤~5万円程度となっています。
ゲーム性能は基本的に「7」以降にやや劣る傾向がありますが、それはあくまでハイエンドGPUと組み合わせたときの話であり、ミドルレンジGPUと併用する場合にはさほどネックではなかったりすることも多いので、特に低価格ゲーミングPCでコスパを最大化する選択肢として強力で人気です。
消費電力や発熱に関しても「7」モデルよりも余裕があり、K付きであっても空冷で運用出来るレベルです。
ただし、K付きのモデルは「7」の下位モデルとの価格差が小さいため、コスパ的には少し微妙なことが多いです。基本的に安さ・コスパ重視でK無しモデルを前提に考えるモデルだと思います。 - Core i3(4コア):安さが魅力のエントリーモデルだが、需要もコスパも低め
- Core i3はCoreシリーズにおける下位モデルです。最新のCore Ultraでは「3」モデルは投入されておらず、古い世代のものしかありません。
第13,14世代CoreではPコアが4つだけのシンプルな構成となっており、10コア以上を搭載するCore i5以上と比べると性能は圧倒的に劣ります。
そのため、ゲームを含め高い性能を求めるには向かないCPUです。魅力は価格の安さです。
性能もオフィスやWeb閲覧などの軽作業なら十分な性能はあるので、軽作業前提で少しでも費用を減らしたい層をターゲットとしたCPUです。しかし、Core i5の下位モデルとの価格差は1万円前後程度となっており、小さい価格差ではないものの、性能差が如何せん圧倒的なので、コスパは明らかに劣っています。
そのため、予算を節約したい場合でもCore i5の下位モデルが選ばれるケースが多く、Core i3の需要はそこまで高くない印象です。それはIntelも認識しているようで、Coreでも第11世代ではCore i3は投入が無かったり、競合のRyzenでもRyzen 3は投入が遅れたり無かったり、明らかに力が入れられていません。基本的にはおすすめしないモデルです。
次に、ゲーム性能について触れていきます。
近年ではPCゲームが大きく流行&普及したことで、一般層では特に「高性能グラボと組み合わせた際のゲーム性能」が重視されています。
そのゲーム性能を大きく左右するのが、「世代(アーキテクチャ)」と「キャッシュメモリの容量」です。
2025年時点のデスクトップ向けCoreの、超高性能なGPUと組み合わせた際のおおよその平均ゲーム性能(1080p)は下記の表にようになっています(Core i5-12400F 基準)。
上の表を見ると、同じGPUを使用していても大きめの性能差が付くことがわかります。
特に、ゲーム性能は世代更新やキャッシュ容量が増えることによって大きめの変化があることがわかると思います。
そして、2025年6月時点に関して言えば、最新世代の「Core Ultra 200」よりも、一つ前の「第14世代Coreの上位モデル(14600K~)」の方がゲーム性能が高いという点も要注意ポイントです。
この点に関しては、Intelも本来の性能が発揮できていないことを認めており、主にWindowsやゲームに対しての最適化が原因であるという主旨の声明を出しています。
他のベンチマークテストを見るとPコアの性能自体は確実に上がっているので、最適化が原因というのは事実なのだと思いますが、2025年5月時点で発売から半年以上経っても大きな改善が見られていません。
Intelは改善する意志を示してはいるものの、明確な見通しは無い状況なので、中々難しい現状です。
ただし、これはウルトラハイエンドGPU(超高性能グラボ)と組み合わせた場合の性能なので、実際にここまでの差が付くことはあまり無かったりします。
とはいえ、折角高額なグラボを用意したのにその性能が制限されるのは嫌ですし、CPUのキャッシュメモリが凄く重要なゲームもあるので、
高性能なグラボを用意するなら、CPUもゲーム性能が出来るだけ高いものを用意したいというのが一般的な考えとなっています。
そのため、Core Ultra 200シリーズは大幅な値下げ等が行われても人気が思ったより上がらない状況が続いています。
しかし、電力面は格段に改善していますし、内蔵GPU性能も大きく向上し、NPUもおまけで付いてきますので、ゲーム特化じゃなければ普通に有力な選択肢だと思います。
ゲーム性能以外の面も含めて、各世代(シリーズ)のメリット・デメリットをまとめたものも載せておくので、参考程度にご覧ください。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| Core Ultra 200 例:Core Ultra 7 265K | ・優れた電力効率 ・優れたマルチスレッド性能コスパ ・NPU搭載(~13TOPS) ・比較的優れた内蔵GPU ・高負荷時でも消費電力が少なめ(285K 以外) | ・やや高価 ・ゲーム性能が競合モデルよりも低め(2025年6月時点) ・マザーボードがやや高価 |
| 第13・14世代 Core(上位) (13600K~/14600K~) 例:Core i7-14700F | ・非常に優れたマルチスレッド性能コスパ ・優れたゲーム性能 ・競合モデルよりも安価 ・マザーボードが安価 ・DDR4メモリも採用可能 ・比較的優れた電力面(K無し) | ・旧世代 ・高負荷時の消費電力・発熱が非常に多い(K付き) ・高負荷時の電力効率が悪い(K付き) ・致命的な不具合があった 【現在は修正用BIOS提供済み】 |
| 第13・14世代 Core (~13400/14400) 例:Core i5-14400F | ・非常に安価(2.1万円~) ・非常に優れたマルチスレッド性能コスパ ・省電力(ベース:65W) ・マザーボードが安価 ・DDR4メモリも採用可能 | ・旧世代 ・ゲーム性能が低い ・NPU無し(AIユニット) ・【F】内蔵GPU無し |
ここではベンチマークスコアを載せています。要するに、実際のパフォーマンスです。
本記事の主旨は一応「Core 3~9」の違いなのですが、必要かわからない知識を詰め込むよりも、ベンチマークと価格から判断した方が楽だし、間違いにくいという気もするので、先に載せておこうと思います。
後ろに「主要CPUの仕様と価格一覧」も併せて載せておくので、必要に応じて活用してくださいませ。
マルチスレッド性能
マルチスレッド性能は全コア稼働時の処理性能のことで、コア・スレッド数が多い方が有利な傾向があります。ゲーム性能と必ず関連がある訳ではない点に注意(ゲーム性能比較は後述)。
下記にレンダリングのベンチマークであるCinebench 2024での比較表を載せているので、参考までにご覧ください。対抗のAMDの数値も併せて載せています。
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Core Ultra 9 285K | |
| Ryzen 9 9950X3D | |
| Ryzen 9 9950X | |
| Core i9-14900K | |
| Core i9-13900K | |
| Ryzen 9 7950X | |
| Ryzen 9 7950X3D | |
| Core Ultra 7 265K | |
| Core i7-14700K | |
| Ryzen 9 9900X | |
| Core i7-13700K | |
| Ryzen 9 7900X | |
| Core i9-12900K | |
| Ryzen 9 5950X | |
| Core Ultra 5 245K | |
| Core i5-14600K | |
| Core i5-13600K | |
| Core i7-12700K | |
| Ryzen 9 5900X | |
| Ryzen 7 9700X | |
| Ryzen 7 7700X | |
| Ryzen 7 7700 | |
| Ryzen 7 7800X3D | |
| Core i5-12600K | |
| Ryzen 5 9600X | |
| Ryzen 5 7600X | |
| Ryzen 7 5800X3D | |
| Ryzen 5 7600 | |
| Core i5-13400F | |
| Ryzen 7 5700X | |
| Core i5-12400F | |
| Ryzen 5 5600X |
ゲーム性能(ハイエンドグラボ利用時)
高性能なGPU(グラフィックボード)と併用した際のCPUのゲーム性能のテスト結果を載せています。重量級ゲームが中心です。対抗のAMDの数値も併せて載せています。
ただし、より低い性能のグラフィックボードを使用する場合にはCPUによって差は生じにくくなる他、非常に軽いゲームの場合は、マルチスレッド性能が重要になったりする点も留意してください。ゲームによって差が出るので、参考までにご覧ください。
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Ryzen 7 9800X3D | |
| Ryzen 7 7800X3D | |
| Core i9-14900K | |
| Ryzen 9 7950X3D | |
| Core i9-13900K | |
| Core i7-14700K | |
| Core i7-13700K | |
| Ryzen 9 9950X | |
| Ryzen 7 9700X | |
| Ryzen 9 9900X | |
| Ryzen 5 9600X | |
| Ryzen 9 7950X | |
| Core Ultra 9 285K | |
| Ryzen 7 7700X | |
| Ryzen 9 7900X | |
| Ryzen 7 7700 | |
| Ryzen 5 7600X | |
| Core i5-14600K | |
| Core Ultra 7 265K | |
| Ryzen 7 5800X3D | |
| Core i5-13600K | |
| Core i9-12900K | |
| Core Ultra 5 245K | |
| Core i7-12700K | |
| Ryzen 9 5950X | |
| Ryzen 9 5900X | |
| Core i5-12600K | |
| Ryzen 7 5700X | |
| Ryzen 5 5600X | |
| Core i9-11900K | |
| Core i5-13400F | |
| Core i5-12400F | |
| Ryzen 7 5700G | |
| Core i5-11400F |
消費電力
ここでは消費電力の実測値を載せています。全コア稼働時(レンダリング)と、ゲーム時の2つの平均消費電力です。対抗のAMDの数値も併せて載せています。
| CPU名称 | 消費電力 |
|---|---|
| Core i5-12400F | |
| Ryzen 7 7800X3D | |
| Ryzen 5 5600X | |
| Core i5-13400F | |
| Ryzen 7 5700X | |
| Ryzen 7 5800X3D | |
| Ryzen 7 7700 | |
| Core Ultra 5 245K | |
| Core i5-12600K | |
| Ryzen 7 9800X3D | |
| Ryzen 5 9600X | |
| Ryzen 5 7600X | |
| Ryzen 9 7950X3D | |
| Ryzen 7 7700X | |
| Ryzen 9 7900 | |
| Ryzen 7 9700X | |
| Core i7-12700K | |
| Core i5-14600K | |
| Core Ultra 7 265K | |
| Core i5-13600K | |
| Core Ultra 9 285K | |
| Ryzen 9 5900X | |
| Core i9-12900K | |
| Ryzen 9 9900X | |
| Core i7-13700K | |
| Ryzen 9 9950X | |
| Ryzen 9 7900X | |
| Ryzen 9 5950X | |
| Core i7-14700K | |
| Ryzen 9 7950X | |
| Core i9-13900K | |
| Core i9-14900K |
| CPU名称 | 消費電力 |
|---|---|
| Ryzen 7 5700X | |
| Ryzen 5 5600X | |
| Core i5-12400F | |
| Core i5-13400F | |
| Ryzen 7 7800X3D | |
| Ryzen 9 7900 | |
| Ryzen 7 7700 | |
| Ryzen 5 9600X | |
| Ryzen 7 9700X | |
| Ryzen 7 5800X3D | |
| Ryzen 5 7600X | |
| Ryzen 9 5950X | |
| Core i5-12600K | |
| Ryzen 9 5900X | |
| Core Ultra 5 245K | |
| Ryzen 7 7700X | |
| Core i5-13600K | |
| Core i5-14600K | |
| Ryzen 9 7950X3D | |
| Ryzen 7 9800X3D | |
| Core Ultra 7 265K | |
| Core i7-12700K | |
| Ryzen 9 9900X | |
| Ryzen 9 7900X | |
| Ryzen 9 9950X3D | |
| Core i7-13700K | |
| Ryzen 9 9950X | |
| Core i7-14700K | |
| Core Ultra 9 285K | |
| Core i9-12900K | |
| Ryzen 9 7950X | |
| Core i9-13900K | |
| Core i9-14900K |
内蔵GPUとNPU
CPU以外のプロセッサー、内蔵GPU(主にグラフィック処理用)とNPU(AI処理用)についてです。
ただし、どちらともグラフィックボードが搭載されている場合(主にゲーミングPC)では恩恵がほとんどないのが基本という部分なので、重視したい人は少ないと思います。
主要シリーズの現状の性能は以下のようになっています。ただし、「F」が付くモデルについては内蔵GPUが使えないため、その点に注意してください。
主要なデスクトップCPU(Windows向け)に搭載されているGPUとNPUの性能比較表です。
| GPU | スコア | 搭載CPU(例) |
|---|---|---|
| Radeon 780M | Ryzen 7 8700G | |
| Radeon 760M | Ryzen 5 8600G | |
| Intel Graphics 4コア (Core Ultra 200) | Core Ultra 7 265K | |
| Intel Graphics 3コア (Core Ultra 200) | Core Ultra 5 235 | |
| Radeon 740M | Ryzen 5 8500G | |
| Intel Graphics 2コア (Core Ultra 200) | Core Ultra 5 225 | |
| Intel UHD Graphics 770 | Core i7-14700K | |
| Radeon Graphics (RDNA 2 / 2CU) | Ryzen 7 7700 | |
| Intel UHD Graphics 730 | Core i5-14400 |
| CPU | 理論性能(INT8) | 搭載CPU(例) |
|---|---|---|
| Ryzen 8000 (8600~) | Ryzen 5 8600G | |
| Core Ultra 200 | Core Ultra 7 265K | |
| その他 |
GPUとNPUどちらについても、「Core Ultra 200」の方が一段有利となっています。
まず、GPUについては、「Core Ultra 200」は内蔵GPUとしては比較的高い性能を持ちます。上位モデルなら、軽めのゲームなら快適に動かせるようになりましたし、軽い動画編集も快適になりました。第14世代Coreの内蔵GPUは性能が低く、実用性にかなり差があります。
ただし、モデルによってGPUのコア数に差があるため、その点は注意してください。出来るだけ性能を高くしたいなら、Core Ultra 7 265~のFが付かないモデルを選びましょう。
次にNPUについてです。
「Core Ultra 200」は最大13TOPS(INT8)のNPUを全モデルで搭載しています。第14世代以前のCoreでは搭載されていないので、明確な優位性です。
13TOPSというのは高性能ではないものの、これでも多くのAI処理をローカルで行えるようになっているとIntelは主張しています。実際軽いものなら対応できると思います。
2025年5月時点ではほぼ役立つことはないので決め手となるかは正直微妙ですが、今後利用範囲が拡大され、細かな処理でも活用できるようになれば優位性として機能するかもしれません。
主要モデルの簡易比較表
まずは、記事更新時点(2025年6月)の市場で主要なCoreの簡易比較表を下記に載せています。基本的には「Core Ultra 200S」と「第14世代Core」ですが、旧世代でも一部の人気のCPUは載せている場合があります。
ただし、特に電力面については電力設定通りという訳ではないことが多く、表の電力効率もTDP PL2から単純計算したものとなっているため実際とは異なる点に注意。電力面についても後ろで詳しめに触れているので、気になる方はそちらを参照のこと。
末尾Fのモデルは、Fの付かないモデルから内蔵GPUが無効化されたモデルで、Fの付かないモデルとCPUとしての処理性能は基本的に同じです。クロックに関しては見易さ重視でPコアのもののみ記載しています。
| CPU名称 | 評価 | 性能 スコア | コア | スレッド | TDP | クロック 定格 / 最大 | 電力 効率 | コスパ | 参考価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pコア | Eコア | 合計 | 基本 | 最大 | ||||||||
| Core Ultra 9 285K | 〇 | 67,890 | 8 | 16 | 24 | 24 | 125W | 250W | 3.7 / 5.7GHz | 94,880円 | ||
| Core i9-14900K | 〇 | 59,000 | 8 | 16 | 24 | 32 | 125W | 253W | 3.2 / 6.0GHz | 71,980円 | ||
| Core i9-14900KF | 〇 | 59,000 | 8 | 16 | 24 | 32 | 125W | 253W | 3.2 / 6.0GHz | 67,980円 | ||
| Core Ultra 7 265K | ◎ | 58,700 | 8 | 12 | 20 | 20 | 125W | 250W | 3.9 / 5.5GHz | 50,980円 | ||
| Core Ultra 7 265KF | ◎ | 58,700 | 8 | 12 | 20 | 20 | 125W | 250W | 3.9 / 5.5GHz | 44,980円 | ||
| Core i7-14700K | 〇 | 53,100 | 8 | 12 | 20 | 28 | 125W | 253W | 3.4 / 5.6GHz | 55,480円 | ||
| Core i7-14700KF | 〇 | 53,100 | 8 | 12 | 20 | 28 | 125W | 253W | 3.4 / 5.6GHz | 49,780円 | ||
| Core Ultra 7 265 | 〇 | 48,000 | 8 | 12 | 20 | 20 | 65W | 182W | 2.4 / 5.3GHz | 53,980円 | ||
| Core Ultra 7 265F | 〇 | 48,000 | 8 | 12 | 20 | 20 | 65W | 182W | 2.4 / 5.3GHz | 50,980円 | ||
| Core Ultra 5 245K | 〇 | 43,600 | 6 | 8 | 14 | 14 | 125W | 159W | 4.2 / 5.2GHz | 47,280円 | ||
| Core Ultra 5 245KF | 〇 | 43,600 | 6 | 8 | 14 | 14 | 125W | 159W | 4.2 / 5.2GHz | 41,980円 | ||
| Core i7-14700 | ◎ | 42,150 | 8 | 12 | 20 | 28 | 65W | 219W | 2.1 / 5.4GHz | 48,980円 | ||
| Core i7-14700F | ◎ | 42,150 | 8 | 12 | 20 | 28 | 65W | 219W | 2.1 / 5.4GHz | 46,980円 | ||
| Core Ultra 5 235 | ◎ | 40,460 | 6 | 8 | 14 | 14 | 65W | 121W | 3.4 / 5.0GHz | 41,480円 | ||
| Core i5-14600K | ◎ | 38,750 | 6 | 8 | 14 | 20 | 125W | 181W | 3.5 / 5.3GHz | 34,780円 | ||
| Core i5-14600KF | ◎ | 38,750 | 6 | 8 | 14 | 20 | 125W | 181W | 3.5 / 5.3GHz | 33,480円 | ||
| Core i5-14500 | 〇 | 31,350 | 6 | 8 | 14 | 20 | 65W | 154W | 2.6 / 5.0GHz | 37,480円 | ||
| Core Ultra 5 225 | 〇 | 31,510 | 6 | 4 | 10 | 10 | 65W | 121W | 3.3 / 4.9GHz | 38,980円 | ||
| Core Ultra 5 225F | 〇 | 31,510 | 6 | 4 | 10 | 10 | 65W | 121W | 3.3 / 4.9GHz | 36,980円 | ||
| Core i5-14400 | ◎ | 25,460 | 6 | 4 | 10 | 16 | 65W | 154W | 2.5 / 4.7GHz | 25,680円 | ||
| Core i5-14400F | ◎ | 25,460 | 6 | 4 | 10 | 16 | 65W | 148W | 2.5 / 4.7GHz | 20,480円 | ||
| Core i5-12400 | △ | 19,360 | 6 | 0 | 6 | 12 | 65W | 117W | 2.5 / 4.4GHz | 22,580円 | ||
| Core i5-12400F | △ | 19,360 | 6 | 0 | 6 | 12 | 65W | 117W | 2.5 / 4.4GHz | 17,380円 | ||
| Core i3-14100 | △ | 15,310 | 4 | 0 | 4 | 8 | 60W | 89W | 3.4 / 4.5GHz | 17,980円 | ||
| Core i3-14100F | △ | 15,310 | 4 | 0 | 4 | 8 | 58W | 89W | 3.4 / 4.5GHz | 12,980円 | ||
K:オーバークロック可能モデル
クロック周波数を従来より引き上げる事が可能なモデル。しかし、オーバークロックは想定されていない発熱の増加が懸念されるため、基本的には非推奨。ただし、オーバークロックをしなくても、無印版より定格やTB時の周波数が高くなっており、オーバークロックを利用しなくても性能が高いので、オーバークロックをする気が無くても、ただの高性能モデルとして扱える。
F:内蔵GPU(iGPU)が無効化モデル
CPU自体に画面出力機能を含むグラフィック機能がないため、別途GPUが必須となる。価格が少し安い。
評価:筆者の主観によるオススメ度を表しています。主に性能と価格から判断しています。
性能スコア:CPUのベンチマークで有名なPassmarkのスコアです。総合性能を測るテストですが、マルチスレッド性能が高い(=コア数が多い)ほど高いスコアが出る傾向があります。
クロック:CPUのクロック周波数です。見易さ重視でPコアのみ掲載しています。高負荷時には全コアが記載の最大クロックまで上がる訳ではないので注意。
TDP:熱設計電力です。CPUの消費電力や発熱の目安となる指標です。長期的に維持する電力はK無しモデルはベース電力(~65W)、K付きは最大ターボ電力(~253W)となっています。
コア:CPUが実際に処理を行う部品の名称です。コア数が多いほど発熱が多くなる傾向があります。
スレッド:ざっくりいうと、コアが行う仕事を表します。原則は、1コアにつき1スレッドですが、ハイパースレッディング・テクノロジーという技術により、1コアを疑似的に2コアに見せることで、1コアにつき2スレッドを実現したCPUも今では珍しくありません。
電力効率:1Wあたりの性能スコアです。
コスパ:1円あたりの性能スコアです。
参考価格:CPUの現在の価格の参考です。記事更新時点での、価格.comやAmazonなどの最安値となっています。最終更新は2024年10月29日です。
各モデルの評価一覧
各モデルの主要項目の性能の筆者が評価したものを参考に載せています。ゲーム性能は高性能GPUと併用時の場合です。ミドルレンジ以下のGPUの場合にはCPUがボトルネックになりにくいので、表の評価ほどの差は出ない点を留意してください。
| CPU名 | マルチ スレッド | シングル スレッド | ゲーム | 消費電力 発熱 | NPU | 内蔵GPU ※Fは非搭載 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Core Ultra 9(200) 24コア(8P+16E) 24スレッド | ★5.0 | ★4.75 | ★4.5 | ★1.5 | ~13TOPS | ★3.5 |
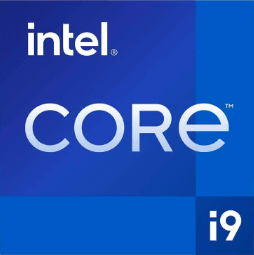 | Core i9(第14世代) 24コア(8P+16E) 32スレッド | ★5.0 | ★4.75 | ★4.75 | ★1.0 | 無し | ★2.0 |
 | Core Ultra 7(200) 20コア(8P+12E) 20スレッド | ★4.5:K | ★4.75 | ★4.25 | ★2.5:K ★3.75:K無し | ~13TOPS | ★3.5 |
 | Core i7(第14世代) 20コア(8P+12E) 28スレッド | ★4.5:K ★4.25:K無し | ★4.5 | ★4.75:K ★4.5:K無し | ★1.25:K ★3.75:K無し | 無し | ★2.0 |
 | Core Ultra 5(200) 14コア(6P+8E) 14スレッド | ★4.0:K ★4.25:K無し | ★4.5 | ★4.0 | ★3.0:K ★4.0:K無し | ~13TOPS | ★3.5:245 ★3.0:235 |
 | Core i5 14コア (第14世代) 14コア(6P+8E) 20スレッド | ★4.0:K ★3.75:K無し | ★4.25:K ★4.0:K無し | ★4.25:K ★3.75:K無し | ★2.75 | 無し | ★2.0 |
 | Core Ultra 5(200) 10コア(6P+4E) 10スレッド | ★3.25 | ★4.25 | ★4.0 | ★4.25 | ~13TOPS | ★2.5 |
 | Core i5 10コア (第14世代) 10コア(6P + 4E) 16スレッド | ★3.25 | ★4.0 | ★3.75 | ★4.0 | 無し | ★1.75 |
 | Core i3(第13世代) 4コア8スレッド | ★2.0 | ★3.75 | ★3.0 | ★4.5 | 無し | ★1.75 |
ゲーミングPC用の場合は大体別途グラフィックボードを搭載しており、内蔵GPUが必要でないため、「F」が最も安価でコスパが良いです。
無印はオーバークロックができず、省電力な設定になる傾向があります。しかし、電力設定を調整することで、初期設定よりも性能を少し引き上げたりは出来る場合がある点は覚えておくと良いかもしれません。
K付きはオーバークロックが可能なだけでなく、標準のクロックや電力設定値も高い性能特化モデルです。しかし、ほとんどの場合においては無印の方が電力効率が良く、少しの性能向上のために電力を多く使って発熱も爆増するみたいな場合が多い点に注意。後から悪い意味でK付きの特徴が嫌になった人は、少し最大クロックや最大の消費電力を下げると良いかもしれません。
各モデルの特徴【3 / 5 / 7 / 9】
前置きが長くなってしまいましたが、「3 / 5 / 7 / 9」各モデルの特徴をそれぞれざっくり解説しています。
「CPUのゲーミング性能」は基本的に「高性能なグラフィックボードを使用した場合」のものを指しています。CPUの内蔵GPU(iGPU)の性能を示すものではないため、注意してください。
Core Ultra 9 / i9:性能特化のハイエンド(24コア)
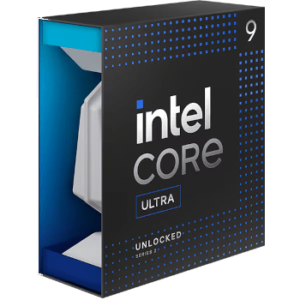
マルチスレッド ★5.0 | ゲーム ★4.5~★4.75 | 発熱・消費電力 ★1.0~★1.5 | 価格 ★1.25~
| CPU名 | マルチ スレッド | シングル スレッド | ゲーム | 消費電力 発熱 | NPU | 内蔵GPU ※Fは非搭載 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Core Ultra 9(200) 24コア(8P+16E) 24スレッド | ★5.0 | ★4.75 | ★4.5 | ★1.5 | ~13TOPS | ★3.5 |
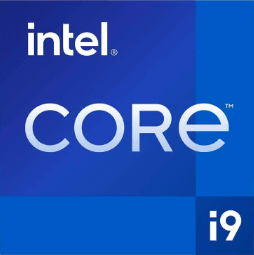 | Core i9(第14世代) 24コア(8P+16E) 32スレッド | ★5.0 | ★4.75 | ★4.75 | ★1.0 | 無し | ★2.0 |
「Core Ultra 9(200)」および「第14世代Core i9」は24コア(8P+16E)を搭載し、圧倒的なマルチスレッド性能を発揮するハイエンドCPUです。Intelの主流CPUとしては最上位のCPUになります。
「9」モデルの魅力は、やはり何といっても24コアによる圧倒的なマルチスレッド性能です。とにかく高い処理性能を必要とする、重いマルチスレッド処理を日常的に行う人にとって非常に魅力的なCPUとなります。
マルチスレッド性能以外でもその処理性能は基本的にトップクラスです。シングルスレッド性能やゲーム性能(ハイエンドGPU使用時)も素晴らしいです。そのため、予算が潤沢で色々調べるのが面倒という人が雑に選ぶケースも多いと思います。
ただし、「Core Ultra 9」については先代よりも少しゲーム性能が少し低下しており、トップクラスというほどではなくなったしまった点に注意が必要です。ゲーム性能だけを求めるなら先代のCore i9(Core i9-14900K)の方が少し強いです。
若干のゲーム性能低下と引き換えに、NPUを搭載し、電力面が改善した点をどこまで評価するか、という感じですが、これは人によるので難しい点です。
その他のデメリットとしては、処理性能の高さの代わりに価格は非常に高価(7万円~9万円台)で、消費電力と発熱が非常に多い点が挙げられます。
特に電力面については要注意です。K付きモデルの最大ターボ電力は250W~となっており非常に高い上、冷却に余裕があれば少し負荷を上げる機能が「9」では標準で有効となっていることもあるので、更に増加する可能性もあります。性能を最大限引き出すためには冷却性能が非常に高いクーラーが必要となる点は十分に留意しておく必要があります。最低でも240mm以上の水冷が推奨され、BTOなどでは大体360mm水冷が標準となっていることが多いと思います。
また、その消費電力の多さから、マザーボードもVRMが強力なものが望ましい他、電源高容量かつ高品質なものが求められるので、CPU以外でも追加費用が求められるため、Core i7以下と比べると導入費用に大きな差が出る点は留意しておく必要があります。
圧倒的なコア数のおかげでマルチスレッド性能コスパは悪くはないため、とにかく性能重視なら有力な選択肢ではありますが、やはり気軽には手を出しにくいです。
また、「9」の処理性能はどの方面から見てもCoreシリーズでトップなのは確かですが、Core i7に対して大きな優位性があるのはほぼマルチスレッド性能のみという点も留意しておくと良いです。
特に注目なのはゲーム性能で大差が無い点です。先にも軽く触れましたが、ゲーム性能に貢献するのは基本Pコアのみで、8コア程度あれば十分と言われています。
そして、2025年6月時点の主流モデルだと、「Core Ultra 9 / Core i9」と「Core Ultra 7 / Core i7」は全て同じ8Pコアなので、大きな差が付きにくいです。
クロックやキャッシュ容量のわずかな増加によるゲーム性能向上はあるものの、差は小さいですし、特にクロック増加は消費電力や発熱の増加と引き換えの性能向上ですから、一概に褒められるものでもないです。
「7」の価格は「9」よりも大体3万円前後も安いですし、ほとんどの人にとっては「7」でもマルチスレッド性能は十分だと思うので、ゲームメインであれば実用コスパは基本「7」の方が上という点は覚えておいて損は無いかなと思います。
Core Ultra 7 / i7:コスパも優れた高性能モデル(20コア)

マルチスレッド ★4.25~★4.5 | ゲーム ★4.25~★4.75 | 発熱・消費電力 ★1.25~★3.75 | 価格 ★1.75~★2.5
| CPU名 | マルチ スレッド | シングル スレッド | ゲーム | 消費電力 発熱 | NPU | 内蔵GPU ※Fは非搭載 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Core Ultra 7(200) 20コア(8P+12E) 20スレッド | ★4.5:K ★4.25:K無し | ★4.75 | ★4.25 | ★2.5:K ★3.75:K無し | ~13TOPS | ★3.5 |
 | Core i7(第14世代) 20コア(8P+12E) 28スレッド | ★4.5:K ★4.25:K無し | ★4.5 | ★4.75:K ★4.5:K無し | ★1.25:K ★3.75:K無し | 無し | ★2.0 |
「Core Ultra 7(200)」および「第14世代Core i7」は、20コア(8P+12E)を搭載し、非常にマルチスレッド性能を発揮する高性能CPUです。
そして、「7」モデルは、昔から迷ったらCore i7と言われることもあるほど、高性能CPUの安定択として常に高い人気を誇っている人気モデルです。ゲーミング性能が「9」と大差なく高い点も人気の要因の一つです(現状のゲームはPコアが8あれば十分と言われているため)。
実際に、ほとんどの時期において競合モデルよりもコスパは優れていることが多いため、雑におすすめできるのが「7」です。
ただし、ゲーム性能について、「Core Ultra 7(200)」については先代よりも少しゲーム性能が少し低下してしまい、競合シリーズ(Ryzen 9000)にもやや劣る性能となった点に注意が必要です。
NPUを新規で搭載し、電力面が改善しているため、下位互換という訳ではありませんが、ゲーム性能と引き換えにそれらの点が向上する点をどこまで評価するか、という感じです。
しかし、恐らくはそこが大きく影響して、「Core Ultra 7 265K(F)」が大幅に値下げされたことで、先端プロセス採用のCPUとは思えないほど安価になったため、かなり魅力的になりました。
ゲーム性能がRyzen X3Dなどと比べると低い点こそあるものの、マルチスレッド性能コスパで大きく有利となり、価格も競合のRyzenよりもやや安価になったので、妥協できるレベルとなったと思います。
ゲーム性能特化なら魅力的とは言えませんが、総合コスパは普通に良いと思います。
その他のデメリットとしては、やはり価格が高価である点がまず挙げられます。2025年6月時点では、大体5万円前後という価格になっており、「9」ほどではないものの高価です。
また、K無しモデルは省電力ですが、K付きは消費電力(発熱)が非常に多い点も注意が必要です。基本の電力設定は「9」と同様というレベルなので、性能を最大限引き出すためには240mm以上の水冷が推奨です。
一応、「Core Ultra 7 265K」はK付きでも電力面が改善しており、実測値では数値上は高性能な空冷クーラーでも一応なんとかなるようになっているので、挑戦してみても良いですが、万が一を避けるために最大電力設定は下げておくことを推奨します。
また、K無しの性能はK付きと比べると低くなってしまうものの、BIOS等の設定からTDP PL2の最大値(14700なら219Wまで)までは制限値を引き上げることも可能なので(保証外にはなるので自己責任)、場合に応じてある程度は負荷を上げることも可能です。
Core Ultra 5 / i5:安さとコスパが魅力のミドルレンジCPU(10コア~14コア)

マルチスレッド ★3.25~★4.0 | ゲーム ★3.75~★4.25 | 発熱・消費電力 ★2.75~★4.0 | 価格 ★2.5~★4.0
| CPU名 | マルチ スレッド | シングル スレッド | ゲーム | 消費電力 発熱 | NPU | 内蔵GPU ※Fは非搭載 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Core Ultra 5(200) 14コア(6P+8E) 14スレッド | ★4.0:K ★3.75:K無し | ★4.5 | ★4.0 | ★3.0:K ★4.0:K無し | ~13TOPS | ★3.5:245 ★3.0:245 |
 | Core i5 14コア (第14世代) 14コア(6P+8E) 20スレッド | ★4.0:K ★3.75:K無し | ★4.25:K ★4.0:K無し | ★4.25:K ★3.75:K無し | ★2.75:K ★4.0:K無し | 無し | ★2.0 |
 | Core Ultra 5(200) 10コア(6P+8E) 10スレッド | ★3.25 | ★4.5 | ★4.0 | ★4.25 | ~13TOPS | ★2.5 |
 | Core i5 10コア (第14世代) 10コア(6P + 4E) 16スレッド | ★3.25 | ★4.0 | ★3.75 | ★4.0 | 無し | ★1.75 |
※10コアモデルと14コアモデルで性能に大きな差があるので、別々に見ていきます。
「Core Ultra 5(200)」および「第14世代Core i5」はの上位モデルは、14コア(6P+8E)を搭載し優れたマルチスレッド性能を発揮します。十分ハイエンドな用途にも対応できる性能があります。
それでいて価格は4万円未満のものもあるので、マルチスレッド性能コスパが非常に優れているのが大きな強みです。
ただし、「Core i7 / Core Ultra 7」との価格差が1万円~程度しかないのが気になるところです。
「5」モデルはPコアが6コアですが、「7」では8コアになるため、最大のマルチスレッド性能差は大きく、一部のゲームやハイエンドGPUとの併用時にはゲームでもやや差が出ることもあります。
そのため、カタログスペックから見た性能やコスパだけで見れば優秀ですが、実用コスパ的なところで良い評価が得られないことが多いのが14コアモデルです。
ただし、消費電力が「7」以降よりもマイルドになっているのは強みです。K付きでも空冷で対応が可能なレベルです(高性能なものが必要にはなるけど)。
また、「7」以降と同様に「Core Ultra 5(200)」が「第14世代のCore i5(K付き)」よりもゲーム性能が少し下がっているという問題はあるものの、この問題はGPUの性能が低い(fpsが低い)ほど気にならないか無視できるレベルになるので、低価格~ミドル機の採用が主流の「5」モデルではそこまで気にする必要がないため、ネックに感じにくいです。
なのですが、記事更新時点(2025年6月)ではCore Ultra 200Sシリーズはマザーボードがやや高価なので、14世代と比較すると合計費用では高価になってしまうため、安さ重視で有力になるためにはもう少し値下がりするのを待つ必要がある点は注意が必要です。
総評としては、実用コスパでいえば全然悪い選択肢ではないですし、その需要の低さから価格が大きく下がることもたまにあるので、頭の片隅に置いておくと良いかもしれません。
「5」の下位モデル(2025年2月時点)は、10コア(6P+4E)を搭載し、安価ながら優れたマルチスレッド性能を発揮するミドルレンジCPUです。
最安2.5万円前後という安価さながら10コアを持ち、重めの処理でも使える高性能さが魅力です。その安さのおかげで実用コスパが良く、低価格ゲーミングPCの定番CPUとしてよく見掛けるモデルとなっています。
また、従来から「5」の下位モデルにはK付きが存在せず、最大クロックも低めなので、消費電力や発熱が少ないです。やや小型の空冷クーラー1基でも冷却が間に合うレベルなので、細かいことや騒音を気にしたくないライトユーザーにとっては嬉しいです。
デメリットとしてはやはり、上位モデルとの性能差が大きいことが挙げられます。特に「7」以降と比べるとコア数差が大きいため、マルチスレッド性能は圧倒的に劣ります。
更に、最大クロックの低さやキャッシュ容量の少なさから、ゲーム性能でも上位モデルには大きめに劣るのも気になる点です。ただし、この問題はGPUの性能が低い(fpsが低い)ほど気にならないか無視できるレベルになるので、ハイエンドGPUが採用されることがほとんどない「5」モデルではそこまで気にする必要がないとも思います。
「7」と比較してマルチスレッド性能の差は大きいものの、ゲームがメインのほとんどの人にとっては大きなネックになるほどではないので、低価格高コスパゲーム用CPUとしては優秀な選択肢です。定番になるのもわかるCPUだと思いますし、Intelもそれを狙っていると思うので、今後も似たような立ち位置を保っていくのではないかと思います。
ちなみに、第13・14世代CoreのCore i5 の下位モデルより下のモデルは、Pコアの仕様が実は12世代を引き継いでいたりして、ゲーム性能が低かったので、他モデルでは低下が見られた「Core Ultra 200」のゲーム性能の低さも「Core i5-14400」VS「Core Ultra 5 225」での比較なら大差ないため、選び易いです。
価格的にハイエンドGPUと組み合わせることもほとんど無いと思うので、他の「Core Ultra 200シリーズ」よりもゲーム性能で避ける理由がないのは嬉しいかもしれません。
ただし、記事更新時点(2025年2月)ではCore Ultra 200Sシリーズはマザーボードが高価なため、14世代と比較すると合計費用では高価になってしまうため、結局安さ重視ではまだ第14世代(14400)の方が強力となっています。しかし、値下がりすれば十分にコスパ最強候補になれる素質はあると思うので、市場を見守りたいところです。
Core i3:安価だけど性能不足が気になる(4コア)

マルチスレッド ★2.0 | ゲーム ★3.0 | 発熱・消費電力 ★4.5 | 価格 ★4.5
| CPU名 | マルチ スレッド | シングル スレッド | ゲーム | 消費電力 発熱 | NPU | 内蔵GPU ※Fは非搭載 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Core i3(第14世代) 4コア8スレッド | ★2.0 | ★3.75 | ★3.0 | ★4.5 | 無し | ★1.75 |
Core i3はコア数が少なく性能が低い代わりに価格が安いエントリーモデルです。最新モデルでも最高で2万円前後に留まる安さで、「5」の最下位モデルと比べても1万円~1.5万円も安価なのが強みです。
消費電力も少ないため扱いやすいですが、コアが4つしかないためマルチスレッド性能がCore i5以上に圧倒的に劣るのがデメリットです。重い処理には向かない、軽作業前提のCPUです。
Webブラウジングやオフィス作業などなら十分な性能を持っているので、それらの用途がメインのライトユーザーやビジネス用途での採用が主なモデルです。消費電力と発熱も少ない点は省スペースPCなどでも採用しやすいのもライト用途に向いている要素の一つです。
数値だけ見たコスパ自体は悪くはないのですが、やはり上位モデルと比べると重い処理への対応力が大幅に低いのが致命的です。1万円~1.5万円の追加費用で「Core i5」を選ぶことができ、そちらでは重い処理への対応力が圧倒的に高まっているので、実用コスパは明らかに負けています。
最近ではミドルレンジGPUでも性能が上がっていることもあり、ゲームでもボトルネックになり易いため、ゲーミングPCでの採用にも向きません(実際ほとんど採用されません)。
軽作業に限ればメリットも感じることができるモデルではあるものの、出来れば「Core i5」以上をおすすめしたいです。
概要
本記事の主旨となる内容は以上で終わりですが、上記では触れなかった内容も参考程度に触れていこうと思います。
ここでは、ゲーム以外の部分も含めた世代の違いについて触れていきます。
まず、2025年5月時点での主要シリーズの主な概要が以下のような感じになっています。
| シリーズ | コードネーム | プロセス | ソケット | L2キャッシュ | L3 キャッシュ | NPU | GPU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pコアあたり | 4Eコアあたり | |||||||
| Core Ultra 200 例:Core Ultra 7 265K | Arrow Lake | 3nm(CPU) +6nm(IOD/SoC) +5nm(GPU) | LGA1851 | 3MB | 4MB | 22~36MB | ~13TOPS | Xe-LPG (Arc) |
| Core 第14・13世代 (14600K/13600K~) 例:Core i7-14700F | Raptol Lake | 10nm | LGA1700 | 2MB | 4MB | 24~36MB | × | Iris Xe |
| Core 第14・13世代 (~14400/13400) 例:Core i5-14400F | Raptol Lake Alder Lake | 10nm | LGA1700 | 1.25MB | 2MB | ~20MB | × | Iris Xe |
以下から、各項目についてざっくりと触れていこうと思います。
また、シリーズ別の特徴まとめも参考までに載せておくので、興味がある方はご覧ください(長くて見辛いので初期は非表示にしています)。
世代ごとの比較【Core Ultra 200 と 第14世代 Core】
Core Ultra 200

Core Ultra 200シリーズは数多くの刷新を伴うCoreの新世代です。
製造プロセス(CPUの素材のようなもの)には、3nmプロセスが採用され、前世代で課題だった電力面が大幅に改善されたことが特にアピールされていました。
他にも、モノシリックからタイル設計への移行、NPU(AI計算用のユニット)搭載、内蔵GPU性能の大幅な向上など、たくさんの改善が含まれます。
その「数多くの刷新」を印象付けるためにブランド名まで変更されています(Core i → Core Ultra)。
しかし、CPU自体のコア数と構成は前世代(第14世代Core)と同じで、マルチスレッド性能も同水準なので、変更の多さの割には基本性能は分かり易いです。前世代を少し上回ってはいるものの、差は大体1割未満なので同等レベルです。
なのですが、先ほど列挙した通り多くの刷新を含むCPUなので、実は内部的には大きく変わっています。まず、Eコア(小型コア)の性能が格段に向上しました。
そして、Pコアのハイパースレッディング(1コア2スレッド)が無くなり1コア1スレッドとなりました。これにより、コアあたりの消費電力が減り、効率が改善しています。最終的な性能こそほぼ変わらなかったですが、前世代で問題視されていた電力面が改善しているのは嬉しい点です。
しかし、上述のように前世代で大きく問題視された点が改善されても、Core Ultra 200の評価は正直低いです。その大きな理由は、グラボ利用時のゲーム性能が前世代から若干低下しているためです。ゲーム性能は競合のRyzenに対しても基本少し劣りますし、X3Dモデルが相手となると大きく劣っています。
ゲーム性能は非常に注目度が高い項目なので、これは結構致命的に感じる人が多いと思います。
ゲーム時の電力面や温度は前世代から改善しているのは良い点ですが、肝心の性能がダウンとなってしまっていると、中々評価し辛いところです。一応、Intelは2025年でのBIOS更新などでの改善を示唆しているものの、6月時点ではまだほとんど変わっていない状況なので、微妙な立ち位置です。
しかし、逆にそのことが影響してか、価格がコストを考えると破格の安さとなっており、マルチスレッド性能コスパでは非常に強力なので、ゲームに特化する訳ではないなら割と普通に有力な選択肢です。
また、一応の既存CPUとの明確な優位性としては、NPUが搭載されている点があります。
ただし、これはゲーミングPCではあまり重視されない項目です。最近の高性能グラボは高いAI性能も持ち合わせているためです。
内蔵GPUの性能が先代から最大3倍程度に性能が向上し、軽いゲームなら快適にプレイできるくらいになった点も大きく改善した点ですが、こちらもゲーミングPCでは重視されない項目です。
新世代ということもあって、旧世代CPUよりはやや高価ですし、マザーボードも同様なので、総合的に見てゲーミングPC基準では微妙さばかりが気になるCPUとなっています。
第14世代 Core(14000番台)

第14世代のCore(14000番台)は処理性能コスパに優れたシリーズです。ゲーム性能も、AMDのRyzen X3Dほどではないものの高いです。
既に旧世代化しているものの、マザボも含めて価格が安価なので、総合性能コスパ重視なら2025年現在でも魅力的な選択肢です。
特に魅力的なのはゲーム性能で、Core i7以降では2025年4月時点では新世代の「Core Ultra 200」よりも優れたゲーム性能を発揮します。
価格も、2025年4月時点ではライバルのRyzen 7000 / 9000シリーズよりも一段安価なので、コスパが良いです。
Core i5-14500以下についてはPコアのL2キャッシュが少ないために低めのゲーム性能となっていますが、価格が非常に安価なので、そちらもコスパは悪くないです。
出来るだけ安く性能コスパを良くしたいなら強力なシリーズとなっています。
ただし、気になるのは高負荷時の電力面です。高負荷時の消費電力が多くてワットパフォーマンスが悪く、発熱も多いです。
製造プロセス(小さいほど良い)が10nmとなっており、3nm~5nmが採用される最新シリーズよりも格段に劣っている点でも、設計面の時点で電力面は劣るのが仕方ないシリーズだったりします。
また、以前に電力関係で致命的な不具合(破損にも繋がる)があったこともあり、安全性と長期利用性面での一般評価はかなり低くなったことも印象的なシリーズです(2025年4月時点では修正版パッチが提供されているため、基本問題はないですですが)。
CPUのソケット(CPUを装着する部分の規格)も既に旧世代化していることもあり、NPU(AIユニット)の搭載も無く、内蔵GPU性能も低いなど、色々な面で将来性としては微妙なシリーズなのは否めないかなと思います。
とはいえ、問題の電力面もK付きモデルを避けたり、電力設定を調整することで気にせず使うことも可能です。NPUもゲーミングPCならほとんど恩恵がない部分だったりするので(2025年時点)、安さ重視や雑に全体的な性能コスパを高めたい場合には良いシリーズです。
そのため、PCは一度替えたら構成は変えずに壊れるまで使う、といった場合にはデメリット面もさほど大きくはないので、普通におすすめできるシリーズだと思っています。
Arrow Lakeとか(コードネーム)
Intel CPUの説明によく現れる「Arrow Lake」などはCPUのコードネームのことです。~Lakeという名前が特徴です。
ここで知っておきたいのが「アーキテクチャ」というものです。これはCPUの内部の設計面の世代を表します。
厳密にはコードネームとアーキテクチャは異なるのですが、結構相関性があるので、基本的にはどちらでも新しいものほど高性能という認識で良いです。
そしてアーキテクチャ・コードネームが新しいものほど、1コアあたりの性能が上がり、電力効率も向上する傾向があります。そのため、出来るだけ良いCPUが欲しい場合には最新のアーキテクチャ・コードネームのCPUを選ぶことになります。
しかし、このアーキテクチャが新しいほど高価な傾向もあるので、予算と相談することになります。
2025年5月時点の主要Coreシリーズのコードネームは下記のような感じになっており、基本的には新しいほど高性能ですが、Core Ultra 200はゲーム性能のみ第14世代Coreよりも少し低い点に注意が必要です(ただし、最適化の問題らしいので、今後改善される可能性あり)。
プロセスルール(ノード):配線の幅
「3nm」などは、CPUの製造プロセスルールを表しています。これは配線の幅のことです。この製造プロセスが小さいほど良いです。
これが細いほど少ない消費電力で運用できるので、電力効率が良い傾向があります。また、より複雑で緻密な設計が可能となるので、処理性能や機能面でも高くなっていることが多いです。
CPUの性能を決める要素はたくさんありますが、基盤となるのはやはり素材と配線なので、このプロセスルールがCPUの質を決める大きな要素の一つとして重要となっています。
2025年のCoreでいうと、「Core Ultra 200」がCPUに3nm、それ以前だと10nmで大きな差があります。そのため、特に電力面においては「Core Ultra 200」の方が格段に優秀なので、電力面重視ならUltraが付くものを選ぶのがおすすめです。
しかし、やはりこのプロセスが細いものほど高価な傾向があるので、予算との相談になります。
また、従来ではチップを単一のダイ(素材)で作られていましたが、最近では主にコスト面の問題からチップレット設計(複数チップから構成)採用が増えているのもポイントです。
ソケット:ソケット面ではIntelは正直微妙
CPUのソケットとは、CPUをマザーボードに取り付ける場所のことです。
CPUの世代によって決まっており、対応したマザーボードでないと使用することができないようになっています。
そのため、世代が新しくなってソケットが変更になってしまうと、既存のマザーボードでは対応ができなくなるため、その新しいCPUを使う場合にはマザーボードも変更する必要があるのが注意する点です。
そして、残念ながらIntelはソケット面では微妙な状況が続いています。一つのソケットの採用期間がRyzenと比べると短いです。
大体2~3年で終了となりますし、その2~3年ではアーキテクチャの大幅刷新を伴わないことも多いので、実質的には基本1世代分しかサポートしないことが多いです。
今後方針が変わる可能性こそあるものの、2025年時点ではそのような気配はないです。
これに対し、Ryzenは一つのソケットのサポート期間が非常に長い上、X3Dといったゲーム性能を押し上げるモデルもあるため、明らかな差があります。そのため、長期利用かつCPU変更も視野に入れる場合には、正直Ryzenの方がオススメなことが多いです。
その他参考
その他の参考情報です。
オーバークロック(OC)
オーバークロック(OC)とは、CPUに標準で設定されている動作クロックよりも高い値を設定して、性能を本来を引き上げることです。引き換えに消費電力や発熱が多くなるデメリットがあります。また、基本的にオーバークロックは保証の範囲外の動作となる点も注意です。基本的には実用性を考慮して使用するものというよりは、一部のPC好きの人が好奇心のために利用する機能になっています。
Intel製の主流CPUの場合、末尾(接尾語)に「K」が付くCPUは「オーバークロック(OC)」が可能となっています。ただし、オーバークロックを利用しない場合でも、定格のクロックがK付きモデルの方が高く、K無しモデルよりは高性能であることが基本のため、オーバークロックしないならK無しの方が良いとは限らない点は注意です。
また、デスクトップ向けのCore i9では基本的に、温度に余裕があると判断できる場合には、本来の設定よりも少しクロックを引き上げる機能、いわゆる「自動オーバークロック機能」が標準搭載されていることが多いです(Adaptive Boost TechnologyやThermal Velocity Boostなど)。
CPUクーラー
CPUはクーラーによる冷却が重要です(ノートPCやタブレット向けのCPUではファンレス駆動向け製品もありますが)。
CPUの冷却が間に合わないと「サーマルスロットリング」という機能が働き、クロックを下げることで低温化を図るため、性能が低下したり動作が不安定になる恐れがあります。そのため、CPUの消費電力に合わせたクーラーを導入することが重要です。
Intel製CPUではTDPが65W以下のモデルではクーラーが付属していますが、基本的に性能は良くないので別のものを使用することが望ましいです。BTOパソコン等では、何もしなくても何かしらのクーラーが搭載されていますが、コスト削減のため冷却性能が十分でないクーラーを標準採用しているケースも多いです。事前に確認しておきましょう。
また、空冷クーラーはPCケース内部の空気を冷却に使用するため、PCケースのエアフロー(排熱性)も非常に重要ということも頭に入れていきましょう。
推奨CPUクーラーのざっくりとした目安を表にまとめています。参考までにご覧ください。
| CPU | 推奨クーラー |
|---|---|
| Core Ultra 9(K) Core i9(K) Core i7(K) | 簡易水冷 (280mm以上のラジエーター) |
| Core Ultra 7(K) Core Ultra 5(K) Core i5(K) | 簡易水冷 (240mm以上のラジエーター) 大型空冷 (120mm以上のファン2基 or 140mmのファン1基) |
| Core Ultra 5~9(K無し) Core i5~i9(K無し) | 簡易水冷 (120mm以上のラジエーター) 空冷 (120mm以上のファン1基以上) |
| Core i3 | 付属クーラー(BOX) 空冷 (92mm以上のファン1基以上) |
記事はここまでになります。ご覧いただきありがとうございました。
また、CPUのその他の情報に関しては、下記の記事も参考になるかもしれません。良ければご覧ください。



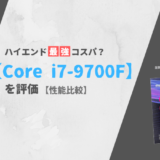

説明がとてもわかり易かったです。
最初は10900kを使おうと思っていたのですが11700kのほうが良いということがわかってよかったです
とても分かりやすい記事をありがとうございます。
当方corei7 9700KFというモデルを使っています。
マザーボードがオーバークロックできないものでKのものでなくてもよかったかなと思いましたがベースのものよりも性能高いんですね。この記事に出会わなければわからなかったことです。あと内臓GPU非搭載というのは何かデメリットなどはあるのでしょうか。わたしのPCにはグラフィックボード積んでいます。
内蔵GPU非搭載のデメリットは、グラフィックボードを利用する前提ならほぼ無いと思います。
強いていうなら、グラフィックボードが故障して使えなくなった際に画面が表示する事ができない事や、グラフィックボードを搭載しにくい超小型PCでの利用が難しいというくらいだと思います。
追記:内蔵GPU非搭載モデルではQSVエンコードを利用する事ができません。恐らく大丈夫とは思いますが、積んでいるグラフィックボードがハードウェアエンコード未対応だった場合には困る可能性はあります。
Kが付かないとOCってできないのですか?
いいえ、必ずしもそうではありません。ですが、”Intelの主流CPU”内なら、基本的にその認識でも構わないです。
「Core X(Extreme Edition)」というシリーズは末尾がXでOC可能ですが、非常に高価かつ消費電力が多いため一般向けではありませんし、以前に末尾CのCPUでOC対応のものがありましたが、現在は恐らく廃止されている、など例外はあります。
また、AMD製のCPUでは末尾Kは関係なく、無印でもOCに対応していたりします。
Core i3:エントリー~ミドルレンジ の説明で
悪い点:消費電力(発熱)が少ない
とありますが、冬場の暖房器具としての性能かな?
確認不足でした。「良い点」の間違いですね。申し訳ございません。訂正いたしました。