この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
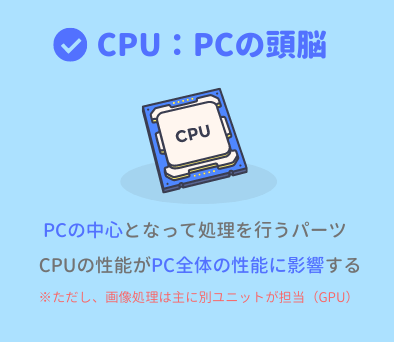
- CPUはPCの頭脳CPUはPCの頭脳とよく表現されるパーツです。PCの中心となって処理を行うパーツとなっており、CPUの性能がPC全体のパフォーマンスを左右するため、非常に重要なパーツです。基本的にどんな用途のPCでもCPUは重要なので、PCにおいては最も重要なパーツと言っても過言ではありません。
- ただし、画像処理は別ユニット(GPU)が担当先に述べたようにCPUはPCの中心となるパーツですが、画像処理に関しては基本的にGPUと呼ばれる別のユニットが担当する点には注意が必要です。たとえば、処理の負荷が大きい3Dゲームなどは、いくら高性能なCPUを搭載してもGPUの性能が低ければパフォーマンスは上がりません。
CPUとは、PCの中心となって処理を行うパーツのことを指します。PCの頭脳とよく表現される、PCにおいて最も重要なパーツと言っても過言ではないパーツになります。
CPUという名称は「Central Processing Unit(セントラル プロセッシング ユニット)」の略称となっていて、直訳すると「中央処理装置」となります。翻訳通り、PCのシステムの中心となって処理を行うパーツです。PCの核とも言えるパーツとなっており、CPUの性能がPC全体に影響を及ぼすため、PCの性能を決定付ける非常に重要なパーツとなっています。
CPUの性能が高いほど動作は快適で重い処理もこなせるようになり、CPUの性能が低いほど動作はもっさりして重い処理が厳しくなります。そのため、出来れば高性能なCPUを搭載することが望ましいですが、高性能なCPUほど高価な他、消費電力・発熱が多いなどのデメリットもあります。
また、CPUはPCの中心となるパーツですが、画像処理に関してはGPUという別ユニットが担当する点は注意が必要です。これは、画像処理(特に動画)は負荷が非常に大きい処理であるため、汎用プロセッサであるCPUにとっては荷が重い処理であるためです。そのため、画像処理に特化したGPUというユニットが担当することが基本となっています。
また、「メモリ」といった言葉もCPUと併せてよく聞くと思います。こちらについては後ほど触れていきますが、ざっくりとしたイメージとしては下記のような感じだと思って頂ければ幸いです。

全般的な説明はここまでにして、この後は各仕様などについて軽く触れていきたいと思います。
次に、CPUの各仕様について説明しています。まずは各項目を箇条書きにしたものを下記に記載しているので、そちらを見た後、一つずつ各項目について見ていきたいと思います。
- コア:核となる部品CPUのメインの処理を行う核となる部品です。コア数が多いほどCPU全コアでの処理の能力が上がり、複数の処理を並行して行う場合(例:ゲーム配信)や膨大な量のデータ処理(例:レンダリング)で有利になります。
- スレッド:仕事の単位コアが行う仕事の単位です。ざっくり分かり易くいうと、システム上で認識するコア数といった感じ。
- クロック(動作周波数):データ処理の速度CPUのデータ処理の速度を示す指標です。単位はHz(ヘルツ)。
- TDP(熱設計電力):おおまかな消費電力消費電力のおおまかな目安となる値です。単位はW(ワット)。高性能なCPUでは表向きのTDPは最大消費電力を示している訳ではないことも多いので注意。あくまで目安。高性能なCPUではTDP PL2の方を参照することを基本としましょう(2022年9月時点)。
- メモリ:CPUの作業スペースメモリはCPUの作業スペースです。基本的にCPUとは別にPCの基盤上に搭載されています(一部製品ではチップ上に実装しているものもあります)。
- キャッシュメモリ:よく使うデータを格納キャッシュメモリは、メインメモリとは別にCPU自体に搭載しているメモリです。よく使うデータを格納しておき、処理の効率化を図ります。
- プロセスルール:配線の太さCPUの配線の太さです。単位はnm(ナノメートル)。細いほどより複雑な設計が可能になるため効率化が図れる他、消費電力の面でも有利です。
- ベンチマークスコア:性能を数値化したものCPUの処理性能を数値化したものです。専用のソフトを用いて測定します。様々な種類があり、測れる性能の傾向などが異なります。有名なソフトはPassMarkやCinebenchなど。
コア:実際に処理を行う部品
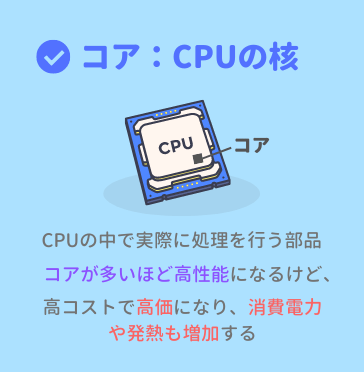
- コアは実際に処理を行う部品コアはCPUのメインの処理を行う部品です。そのため、コアの性能がCPUの性能を最も大きく左右します。
- コア数が多いほど高性能になる単純にコアの数が多いほどCPU自体の処理性能は向上します。他にもCPUの処理性能を上げる手段はありますが、最も手っ取り早くCPUの処理性能を上げることが出来ます。コア数が多いほど複数のアプリケーションを同時に動作させる「マルチタスク」や、データ量の非常に大きい処理(レンダリングなど)などで有利になります。
- コア数が多いほど発熱・消費電力は多くなるし、コストも高くなるコア数が多くするとCPUの処理性能は上がりますが、逆にデメリットもあります。主なデメリットは発熱・消費電力が多くなることと、コストが高くなることです。発熱や消費電力が多くなると、冷却や電源でより高い性能が求められるため、特にノートPCやタブレットなどのモバイル端末では痛いデメリットです。また、コア数を増やすことは単純にコスト増大に繋がるため、コア数が多く高性能なCPUは高価になってしまう点も要注意です。
CPUの「コア」は処理を実際に行う部品です。CPUの性能に直結する部品となっているため、非常に重要です。
コアの注目ポイントはまず数です。コアの数が出来るだけ多い方がCPU全体としては高性能となります。CPUの性能を上げる方法としては、最も効果的かつ手っ取り早い方法です。そのため、現在では一つのCPUで複数のコアを搭載する「マルチコア」が主流となっています。その数は増加の一途をたどり、2024年3月現在では個人向けでも最高24コアにまで達しています。
ただし、CPUのコア数が増えるというのは、電力を消費する部品が増える、熱源が増えるということでもあります。そのため、コア数が多いほど発熱と消費電力が多い傾向があるのは注意が必要です(コア自体の仕様にもよるけど)。また、コアを多く搭載するということはコストが増えることでもありますから、CPU自体の価格も高価になる傾向があるのもデメリットです。
そこで、コア数の出来るだけ抑えつつも性能上げる手段として重要なのが、コア自体の性能を上げることです。こちらでもCPUの性能はもちろん上がります。
ただし、コアの質を上げるには、設計や素材の質の向上などの様々な要素の見直しや改良が必要となるので、コア数を増やす方法ほどは簡単には上げることが出来ません。
そのため、2024年現在ではどれだけ省電力性を高めて多くのコアをCPUに搭載するかというのが主なアプローチになっている状況があります。CPUに小型で省電力な「省電力・高効率コア(通称:Eコア)」というコアを採用することで、CPU全体のコア数を増やして、全体の性能を上げる方法を各種メーカーが取っていたりします。
スレッド:コアが行う仕事の数(1度に行える作業の手数)
- 原則は1コアにつき1スレッドだけど、SMTという技術で1コア2スレッドのコアも一般的スレッドは、ざっくりいうとコア行う仕事の数を表すものです。コアあたりのスレッド数は原則では1ですが、同時マルチスレッディング(SMT)という1コアで2スレッド処理を実現する技術があり、1コアで2スレッドのコアも一般的となっています(ちなみに、IntelではSMTではなくハイパースレッディングと呼称しています)。システム的には1コア2スレッドのコアは2コアと見えているような感じとなっているので、スレッドは「システム上で認識するコア数」と考えても分かり易いかもしれません。
- SMT(1コア2スレッド)を使用すると、コアあたりの処理性能は向上するけど、消費電力と発熱も増えるSMTを使用して1コアで2スレッドとして運用すると、1コアあたりの処理性能は大きく向上します。直接コアを増やすよりもコストを削減できるため、少ない費用で性能を大きく伸ばせる嬉しい技術です。しかし、1コアに掛かる負荷も当然増えるので、発熱や消費電力も増えます。
簡単に言うと、スレッドはコアが行う仕事の単位です。CPUの仕様を見る際、「8コア16スレッド」や「8C16T」など、スレッドという仕様を目にすることがありますが、スレッドはコアのようなパーツのことでは無い点に注意です。たとえば、8コア16スレッドの場合は、8人で合計16個の仕事を一度に担当できるといった感じの意味になります。
スレッド数が多いほど仕事の手数が多くなり作業を効率的に分担できるため、重い処理での処理に掛かる時間が短くなります。特にエンコードやレンダリングなどの膨大な量の処理や、マルチタスクの処理などで有利に働きます。
このスレッドは、原則は1コアにつき1スレッドで「1コア=1スレッド」で、1つのコアが1つの仕事を担当するという形です。しかし、この使い方だと、たとえば10の仕事がある場合でも8つのコアで対応しなければならずに効率が悪くなるケースが考えられます。スレッド数が少ないと、パフォーマンスの低下や処理効率の低下の可能性が高くなるため、スレッド数は出来るだけ多い方が良いです。
そこで出てきた技術が「同時マルチスレッディング(SMT)」です。これは疑似的に1コアを複数コア(2コア)に見せる事で、1コアで2スレッドを処理するという技術です。IntelではSMTではなくハイパースレッディング(HT)と呼称しています。現在ではこの技術を使用したCPUが一般的となっています(例:8コア16スレッドCPUなど)。仕組み的にはスレッド数はシステム上で認識するコア数と考えても分かり易いかもしれません。
このように、1コアを2コアとして扱うことで、コアの性能を最大限活かしつつ、効率よく処理を行うことができるため、非常に有益です。単純にCPUの最大性能を押し上げることにも繋がるので、コスパ面でもプラスです。
ただし、1コアを2コアとして扱うということは、コアあたりの負荷が重くなるため、消費電力の上昇が懸念されるというデメリットもあります。
同時マルチスレッディング(SMT)は、1コアで複数スレッド処理を実現する技術です。コアの個数を変えずに性能を上げれるというのは、コスト効率の高い有益な技術です。デメリットとして、未使用時より高負荷時の消費電力や発熱が増加するなどの点もあるため、モバイルデバイスでは採用に一考の余地はあるものの、その問題も基本的に低負荷時には問題にならないものなので、2024年現在ではスマホ向けを除いて多くのCPUでは採用されています。
ちなみにハイパースレッディングというのはCPUの大手メーカー「Intel」の商標で、PCにおけるCPUが長期間「Intel」製CPUがほぼ一強状態だったために普及しましたが、他メーカー製CPUだとこの名前は使えないため、同様の技術の広義的な名前であるSMT(Simultaneous Multi-Threading、同時マルチスレッディング)と呼ばれます。
TDP(熱設計電力):発熱や消費電力のおおまかな目安
TDP(Thermal Design Powerの略)は直訳すると熱設計電力です。大体の消費電力や発熱量の目安として扱われています。単位はW(ワット)です。TDPの数値を見て、CPUクーラーの冷却性能はこれくらいあった方が良いとか、電源ユニットの容量はこれ以上はあった方が良いとかの判断基準にします。
- TDPは発熱や消費電力のおおまかな目安TDPは熱設計電力の略称で、大体の発熱や消費電力の目安となる指標です。TDPの値を見て使用するCPUクーラーや電源ユニットを決めることになります。ただし、見るのはTDPの最大値という点に注意が必要です(詳細は下記から)。PL2の値が基本的に最大値(2024年現在)TDPは発熱や消費電力の目安となる数値ですが、現在の主流のCPUの多くは複数の段階的に複数のTDPが設けられているのが一般的になっているため、表向きの数値が最大の消費電力とは限らない点に注意が必要です。PL1、PL2(PLはPower Limitの略)という風に複数の値が設定されており、2023年現在では高負荷時には基本的に最終段階のTDP(PL2)で動作します。ただし、このTDP PL2や消費電力の上限値は、各メーカーが固有の名称を使用したりしているため、普段から情報を追っている人以外は簡単に見分けるのが難しいのが不便な点です。
TDPで難しいのは、基本的に表向きに表記されているTDPの数値は基本最大消費電力を表したものではない点です。たとえば、TDPが65Wと表記されているCPUだからといって、最大の消費電力が65Wとは限らないという事です。
それに関するPower Limite(PL)について下記で説明しています。
- Power Limit(PL)
- Power Limit(以下:PL)はCPUの消費電力の制限のことです。たとえば、PLが100Wの場合には、CPUは100Wを超えない範囲で稼働するということになります。PLには何らかの条件が設けられており、その条件を満たしている間にそのPLで稼働するという感じになっています。
- PL1
- PL1は1段階目の電力制限値です。表向きのTDPとして表示されることが多いものの、現在ではPL2以降のより高い電力制限が採用されているCPUが多いため、最大の消費電力では無いことが多い点に注意です。現在PL1で稼働する状況というのは、PL2以降の設定では問題が生じる(主に発熱の増加により冷却が追いつかない)場合やPL2以降に時間制限がある場合などが主です。また、モバイル端末向けの省電力CPUや、ブーストクロックが設定されていない低性能なCPUではPL2以降が設定されていない場合もあり、その場合にはPL1かベース電力が常時適用されます。
- PL2
- PL2は2段階目の電力制限値です。2023年現在では事実上の最大消費電力値となっています。PL2の適用条件はCPU・マザーボードの設定により多少異なることもありますが、基本的に冷却に問題がない場合に適用されると思うと分かり易いかと思います。2023年現在の主流の高性能CPUでは基本PL2の値で稼働し、低負荷時や何らかの問題がある場合のみPL1に移行するという設定が多いです。その他、ノートPC向けのCPUや省電力CPUでは、PL2は時間制限付きの稼働となっており、一定時間後にPL1に移行するという設定のケースもあります。いずれにせよ、CPUの冷却性を高め、PL2状態での稼働状態を維持することがCPU性能の最大化に繋がるため、CPUクーラーやエアフローの強化は、安心感だけでなく実性能にも影響してくる点は留意しておくと良いです。ちなみに、2023年現在の高クロックな高性能CPUではPL1とPL2が同値に設定されているケースもあり、PL1はユーザーが調整しない限り実質的に存在せず、PL2が唯一のPL値となっていることもあります。
- ベース電力
- 必ず採用されている訳ではありませんが、一部のCPUではベース電力値がPL1やPL2に加えて設定されています。PL1以下の値が設定されており、いわゆる安全装置みたいな感じの設定です。
一つ「Core i7-12700」を例として見ていきましょう。このCPUはPBP(PL1)が65W、MTP(PL2)が180Wという設定になっています。表向きには65W TDPと表記され、省電力CPUとして扱われることもあるCPUですが、実はPL2は180Wとなっており高負荷時には省電力とは言えない消費電力となります。性能を出来るだけ発揮させたいのであれば高性能なクーラーに加え、電源容量にも余裕が必要なることに注意が必要があります。
このようにTDPの扱いには少し注意が必要です。2023年現在では主にTDP PL2が最大値となっていることが多いですが、先のMTPのようにメーカーごとに異なる名称を使用していたりするため、少し分かり難いです。少し面倒にも感じるかもしれませんが、CPUの性能を出来るだけ高く、効率良く発揮させたい場合には重要な項目となるので、調べてみることをおすすめしたいです。
余談になりますが、PCにはCPUの他にも消費電力が非常に多いパーツに「GPU」があり、このGPUにもTDPが示されていますが、こちらはCPUと違って最大消費電力とほぼ一致しているため、上述のような細かい調査は必要なく、表向きの数値を信じて基本構いません(2023年現在)。
メモリ:CPUの作業スペース
メモリはCPUそのものに関わることではないですが、関係性が強いため軽くここでも触れておこうと思います。
- メモリはCPUの作業スペースメモリはCPUの作業スペースとなるパーツです。CPUが満足に作業できるように、適切な容量を搭載することが求められます。ただし、用途やCPUの性能によってはメモリを大容量搭載しても無駄になる可能性もあり、多ければ多いというものでもないので、用途と予算に応じて選択しましょう。
- 速度(帯域幅)も用途によっては重要メモリの速度や帯域幅も用途によっては重要です。メモリを大量に使用する用途では全般的に重要になるのはもちろんのこと、特にCPUの内蔵GPUを利用する場合にも重要です。
- デュアルチャネル(デュアルチャンネル)は必須メモリには2つのメモリを同期させることで、一度に扱えるデータ量(帯域幅)を倍増させるデュアルチャネル(デュアルチャンネル)機能があります。非常に大きなメリットがあります。メモリスロットを二つ使うことと、同一規格に対応したメモリが2枚必要という条件はありますが、条件さえクリアすれば特にデメリットもなく大きなメリットがある機能なので利用が前提となっています。恐らく現在の多くの既製品PCでは始めからデュアルチャネルで動作するようになっていると思いますが、特にメモリが合計8GB以下のPCでは初期では対応していない可能性もあるので注意が必要です。
PCにおけるメインメモリは、CPUの作業スペースの役割を果たします。CPUとは別パーツながら、切っても切り離せない存在がメモリです。
CPUのコア・スレッド・やクロックに関しては、上げることで消費電力や発熱の増加といったデメリットがありましたが、メモリの容量の追加に関しては、電力増加はわずかにあるものの無視できるレベルなので、予算に余裕がある人は多めに搭載しておくと安心です。
容量だけでなく、もちろん速度も高いと高性能なので、余裕があればそちらもチェックすると良いです。
キャッシュメモリ:よく使うデータを傍に置いておく ※ゲームでも重要
- キャッシュメモリはよく使うデータを格納キャッシュメモリは、CPUがよく使うデータを格納し、必要になった先にすぐに取り出して使えるようにしておく場所です。これによって処理の効率化を図ります。
- CPUに直接搭載メインメモリと異なり、キャッシュメモリはCPU自体に搭載されます。そのため、より遅延が少なくアクセスすることが可能となっていますが、後からの増設等や仕様変更は不可能となっています。
- メインメモリよりも高速だけど容量が少ないキャッシュメモリは基本的にメインメモリよりも高速です。その代わり、設計が難しく単価も高価になることもあって、搭載容量は非常に少ないです。2025年現在では、CPU用のメインメモリは16GB~32GBが主流ですが、キャッシュメモリはハイエンドCPUの合計でも200MB未満ですし、ほとんどのモデルは100MB未満です。圧倒的に少ないことがわかります。
- キャッシュ容量はゲームでも重要また、高性能グラフィックボード・ビデオカード利用時のゲーム性能においても、CPUのキャッシュメモリ容量が重要となっています。
この特性を利用して、大容量のL3キャッシュメモリを追加搭載したゲーム特化モデルなども出ています(Ryzen X3D)。
キャッシュメモリは、よく使うデータを格納しておき、必要になったときにすぐに使えるようにしておく保存領域です。キャッシュメモリはメインメモリよりも高速かつ遅延が少ないので、出来るだけキャッシュメモリからデータを受け取るようにした方が処理が高速化されます。
容量が多い方がよく使うデータをより多く格納でき、より低速なメインメモリに頼る場面が減るため良いですが、高速な分高価なこともあり、メインメモリと比べると圧倒的に容量は少ないです。
また、キャッシュメモリはゲームでも重要な点もポイントです。基本的に、CPUにおけるゲームでの処理は単純なマルチスレッド性能ではなく、次のフレームの処理へ移るまでの遅延がどれだけ少ないかという点の方が重要なため、キャッシュメモリが有効に働きます。
この特性を利用し、大容量のL3キャッシュを搭載したRyzen X3Dモデル(例:Ryzen 7 7800X3D)があり、2025年現在では非常に人気となっています。
動作周波数(動作クロック):データ処理の速度
- 動作周波数(クロック)は処理の速度クロックはCPUのコアのデータ処理の速度を示します。基本的にGHzという単位で表されます。そのため、クロックが高いほどコアの処理性能は高くなります。
- クロックが高くなるほど発熱と消費電力は多くなるクロックを上げると処理性能を向上させることができますが、負荷が高くなるため、発熱と消費電力も増えてしまいます。
動作周波数(動作クロック)は、CPUのデータの処理の速度を示すものです。GHzという単位で表されます。
クロックが高いほど高い性能を発揮する事が可能になりますが、クロックを上げるほどコアの負荷が大きくなり、消費電力や発熱が増加するというデメリットがあります。
また、クロック以外でもIPC(クロックあたりの命令数)や、レイテンシ(遅延)など性能を左右する項目はたくさんあるため、動作クロックが高いから性能が高いとは限らない点も留意しておきましょう。
2022年現在ではCPUの多コア化が進んでおり、以前よりも並列化処理の効率化やコアやCPU自体の設計の改良など、他の性能向上の余地が大きくなっていますし、CPUにおける性能の重要度としてはやや低くなっている印象です。
ただし、クロックは物理仕様を変えないで性能を上げることが出来、ユーザー側からも環境によっては変更することが出来るのは強みです。オーバークロックなどは有名なクロックを上げることで性能を上げる手段です。
CPUによっては「オーバークロック(略称:OC)」という、本来の仕様よりも動作周波数を引き上げることができるものがあります。これを利用すると、CPUの性能を従来より引き上げる事が可能です。しかし、想定されていない発熱の増加が発生する可能性があるため、故障のリスクが高まります。上級者向けの機能で、基本的に推奨されません。
プロセスルール・ノード:配線の太さ
- プロセスルール・ノードは配線の幅プロセスルール・ノードとはCPUの半導体の回路の配線の幅を指します。単位はnmで、5nmのように表現します。ルールというと何かの決まりという印象を受けますが、細かい規定のようなものを表現するものではなく、単純に配線の幅と捉えて問題無いです。
- 小さいほど良い(電力効率が良くなる他、配線の利用幅が広がる)プロセスルールは細いほど良いです。配線の幅が広がるとより細かな回路設計が可能となりますし、消費電力も減るので電力効率も良くなります。良い事尽くめで、コストと設計の難しさ以外ではデメリットもありませんので、プロセスの微細化がCPU性能躍進の大きなカギを握っていると言っても過言ではありません。実際の半導体にはトランジスタ密度だったり、ゲートピッチだったりも取り沙汰されることはあり、それらも確かに重要な要素ではありますが、少なくとも消費電力が多いPC向けのユニットの場合はプロセスルールがやはり最も影響が大きいと思い餡巣。
- IntelとAMDではAMDの方が先を行っている(2023年時点)2023年10月現在ではWindows PC向けのCPUの主要メーカーはIntelとAMDですが、各メーカーの最新CPUのプロセスルールは、Intelは10nmで、AMDは5nmです(AMDはTSMCの半導体を使用)。プロセスルールの微細化においてはAMDが一歩先を行っています。微細化だけがCPU向け半導体の質の全てを決める訳ではないですが、2018年頃からずっとAMDが有利な状況が続いており、この差で特に影響を受けやすい電力効率もAMDが実際に優勢なので、プロセス面ではAMDが暫く有利という状況となっています。これに対してIntelは、恐らくゲートピッチやトランジスタ密度などでは競合他社の7nmに匹敵していることを要因として、10nmでも「Intel 7」といった名称を付けたりもしていますが、結局効率を見る限りはAMDの利用するTSMC 7nmクラスよりも明らかに劣っており、少なくともPCにおいてはプロセスルールがやはり重要なんだなというのが個人的な意見です。
プロセスルール(またはノード)はCPUの半導体の回路の配線の幅を指します。単位はnm(ナノメートル)。ルールというと何かの決まりや規定を想像してしまいますが、単純に配線の幅と捉えた方が分かり易いです。
端的にいうと、プロセスルールは小さいほど良いです。デメリットもコスト増加の可能性や開発の難しさくらいで、性能面でのデメリットは基本的にありません。配線の幅が細くなると、より細かな回路設計が可能な他、消費電力も少なくなるなど、良い事尽くめです。
CPUの歴史を見てもプロセスルールの微細化はCPU性能の大きな底上げに貢献しているので、CPUの性能の躍進の大きなカギを握っています。ただし、単位がnmと非常に小さいですから、それを更に微細化するのは並大抵のことではありません。
他にもトランジスタ密度やゲートピッチなども半導体の性能を決める要素として挙げられることがありますが、あまり表には出てこない数値ですし、少なくとも消費電力の多いPC向けのユニットでは、プロセスルールの細い(小さい)ものほど効率が良いんだな、程度の認識で良いと思います。
ベンチマークスコア:CPU性能を数値化したもの
- ベンチマークスコアはCPUの性能を数値化したものベンチマークスコアとは、CPUの処理性能をベンチマークテストを用いて測定して数値化したものです。CPU以外のプロセッサでもよく使われます。ここまでコアなどのCPUの仕様について説明してきましたが、そのような仕様だけでは各CPU間の性能差を測るには不十分なので、ベンチマークが用いられます。ベンチマークテストにはたくさんの種類がありますが、CPUにおいてはPassMarkやCinebenchというものが使用率が高い印象です。
CPUの性能は非常に重要ですが、上述したコアの数などから詳細な性能を知るには限界があり、実際に動作してみた性能の方が重要です。
そこで便利なのが、ベンチマークスコアです。ベンチマークスコアは、PCの処理性能を測る専用のベンチマークテストを用いて処理性能を数値化したものです。この数値を見ることで、CPUの性能をある程度知ることができるのでCPUを選ぶ際には必見です。
CPUでは「PassMark」や「Cinebench」などのベンチマークソフトが特に有名なので、選ぶ際には参考にしましょう。本ブログでもまとめた記事があるので、良ければ参考にしてみてください。
また、一口にCPU性能といっても、用途や処理によっていくつか種類があります。大きく分けると「マルチスレッド性能」「シングルスレッド性能」「ゲーミング性能(高性能GPU使用時)」という感じで見るのが、個人向けCPUでは一般的です。下記にざっくりと説明をまとめているので、良ければご覧ください。
CPUの各種性能のざっくりとした説明です。
- マルチスレッド性能CPUの全力(全コア)での処理性能です。一般的なCPUの処理性能といえばこれを指します。マルチスレッド性能が高いと、単純に重い処理を行う際に有利になるのはもちろん、複数の処理を並行して行う(マルチタスク)際や膨大なデータ量の処理(レンダリングなど)の際に特に役立ちます。
- シングルスレッド性能1スレッド(1コア)の処理性能です。シングルスレッド性能が高いとレスポンスが良くなる(サクサク動く)他、基本的にどんな処理に関しても有利に働く汎用性の高い性能です。高いマルチスレッド性能を持っていても重い処理をしないのであれば大して意味を成さない可能性もありますが、シングルスレッド性能は無駄になることがないため、重い処理を想定しないデバイスではマルチスレッド性能よりも重要な場合もあると思います。ベンチマークソフトではマルチスレッド性能と同時に測られることが多いです。
- ゲーミング性能(外部GPU)高性能なGPU(グラボ等)搭載時のゲームパフォーマンスです。ゲームにおける描画処理の中心は基本的にGPUになりますが、ゲームではソフト内の圧縮されたデータを解凍するなどの処理が逐次大量に発生し、その処理に関しては基本CPUが行うため、CPUにもGPUが処理できるフレーム数に対して負けないくらいの処理性能が必要になります。CPUのゲーミング性能はIPC(1クロックあたりの処理命令数)やシングルスレッド性能が重要と言われています。ベンチマークテストもありますが、ゲーミング性能はGPUにおける比重の方が圧倒的に大きいので、同じGPUを用いて複数のCPUの多数のゲームの平均フレームレート(1秒あたりのフレーム数:以下fps)数を算出したりして調べたデータなどの方が信頼性は高いです。
NPU(AI用のユニット):今後に注目
- AI用の処理に特化したユニットNPUとは「ニューラル・プロセッシング・ユニット(Neural Processing Units)」の略称で、AI用の処理に特化したユニットを指します。
2024年以降の活躍に注目したいのが、AI用のNPUです。2023年はフェイクニュース・画像生成AIなどを始め、様々なことにAIが活用されて注目を浴びた年で、日本では「AI元年」とも称されるほどAIが盛り上がりました。
もちろん世界的にもAIは重要な要素として認識されており、CPUでは各社がAI用のNPUを搭載し始めました。2024年3月現在では個人における活用法はあまりないのが現状のため、恩恵を感じることは少ないですが、今後は様々なソフトの処理がNPUへと最適化されていく可能性があり、そうなると非常に重要な項目となりますので、気になる方はNPUが搭載されていない旧世代のCPUは避けるのも手かなと思います。
- 内蔵GPUは画像処理用のGPUをCPUに統合したもの冒頭で触れましたが、PCの画像処理に関しては基本的に「GPU」と呼ばれるCPUとは別のユニットが担当します。GPUがないと画面に映像を出力できないため、実質的にGPUはPCにとって必須のパーツです。場合によってはグラフィックボードを搭載するなどして別に実装する事も可能ですが、利便性やスペースなども考慮してCPUにはGPUを内蔵しているものが多くあります。
- 性能は単体のGPUと比べると低く、重いゲームや動画編集は厳しい内蔵GPUの性能は、グラフィックボードに搭載される単体のGPUと比べると大幅に低いです。そのため、基本的に重い3Dゲームや動画編集などに使うには性能不足な点には注意が必要です。上記のような用途で使いたい場合には、高性能な単体GPUを搭載したゲーミングPCやクリエイターPCと呼ばれるタイプのPCが必要になります。
- 基本CPUのメインメモリを使用するので、メモリ性能が重要CPUの内蔵GPUは、基本的にCPUのメインメモリの一部を共有または割り当てられて使用します。そのため、メモリの性能が重要となります。特に、画像処理はデータ量が大きいため帯域幅が重要なので、帯域幅の広いメモリ(帯域幅はDDR4-3200とかの3200の部分)を使用すると内蔵GPUの性能を向上させることに繋がります。
- 最近では性能が向上しており、高性能なものなら多少は重い処理もいける内蔵GPUでは重いゲームや動画編集は厳しいと前述しましたが、性能自体は最近かなり向上してきています。そのため、内蔵GPUでも特に高性能なものであれば、重いゲームや動画編集などの重い処理も多少はいけるほどの性能になってきています。
CPUにはGPUが内蔵しているものが多くあります。軽く前述しましたが、GPUとは画像処理に特化したプロセッサで、GPUは重いグラフィック処理でも重要ですが、単純にディスプレイ・モニターに映像をまとも表示するためにも必須のパーツなので、利便性やコスト面を加味して内蔵しているという感じです(一応GPUが無くても全く映せない訳ではないけど)。
デスクトップ向けCPUではGPUを内蔵していないものがあり、その場合には主にグラフィックボードを搭載する形でGPUを導入する必要があるので一応注意です。逆にデスクトップ向け以外のCPUでは基本的に内蔵しているため、画面出力という点で困ることはありません。
ですが、CPUにGPUが内蔵している場合でも、内蔵GPUの性能はグラフィックボードなどに搭載の単体GPUと比べると圧倒的に低いため、重いゲームや動画編集を用途とする場合にはグラフィックボードを搭載することが求められる点は注意です。
ただし、近年では内蔵GPUの性能も大幅に向上しています。以前は重いゲームや重めの動画編集をするならグラボは必須という感じでしたが、今では内蔵GPUでも多少重い処理も不可能ではないレベルにまで到達しています(高性能なものに限るけど)。
本記事はCPUの記事なので深くは触れませんが、最後に内蔵GPUの長所と短所を下記にまとめているので、参考程度に見てください。
- 追加費用が要らない
- 消費電力が少ない
- 幅広い用途に最適化(多くのAPIに対応)
- 重い処理(重い動画編集やゲームなど)をしないなら十分な性能
- 単体のGPUと比べると性能が大幅に低い
- メモリが基本的にCPUと共有のため、低速で使える容量も少ない
内蔵GPUについては、下記の記事でもう少しだけ詳しく解説しているので、気になる方はご覧ください。
CPUの主要メーカーを軽く紹介しています。本記事は主にWindows PCを前提として書いていますが、ここではスマートフォンやApple製品なども含めて全般的に触れています。
- デスクトップ・ノートPC向け
- Intel言わずと知れた大手CPUメーカーのIntelです。2023年現在ではWindowsでは圧倒的なシェアを誇ります。しかし、2023年時点ではプロセス面の遅れが問題視されています。ライバルであるAMDにシェアが少しずつ奪われつつあり、巻き返しが期待されています。
- AMDWindowsの主要CPUメーカーのAMDです。WindowsではIntelとAMDの2つが二強としてずっと続いています。以前はIntelがほぼ一強として君臨しており、実際性能でもAMDは遅れていましたが、2017年に投入した「Ryzen」によって一気に競争力を取り戻し、2023年現在ではプロセス(電力効率)面ではIntelを上回っており、シェアを伸ばしつつあります。
- AppleApple製PC「Mac」では、以前はIntel製のCPUを採用していましたが、2020年からはPC向けのApple開発・製造の「Apple M」シリーズのSoC(CPU)を搭載するようになりました。最先端のプロセスに加え、高性能なGPUとメモリと統合したチップとなっており、非常に優れた電力効率を備えています。
- Qualcomm※2023年時点ではシェアはわずかですが、一部のArm版のWindowsなどでQualcomm製のSoC(CPU)採用のPCが登場しています。x86系がメインであるデスクトップ・ノートPC市場では最適化や互換性の面でのデメリットが大きいため普及が進んでいませんが、今後の動向は注目です。
- Intel
- スマートフォン・タブレットPC向け
- AppleiPhoneやiPadで自社開発チップを採用しているAppleです。非常に高いコア性能はトップを維持し続けており、優れた技術力が伺えます。
- Qualcomm「Snapdragon」で有名なQualcommです。かなり幅広い性能のSoCを多数出しており、Android端末でのシェアはNo.1です。
- Samsung韓国企業のサムスンです。アメリカや中国が台頭するCPU市場では唯一に近い別の国のメーカーです。モバイル端末向けに「Exynos」シリーズを開発しており、自社製品を中心に搭載しています。他のほとんどのメーカーと異なり、素材である半導体も製造しているため、ポテンシャルは非常に高いメーカーですが、近年ではその半導体の歩留まり率(良品の割合≒不良品の少なさ)がTSMCにやや劣ることが指摘されており、TSMC製のダイを採用する他メーカー相手にやや苦戦している印象です。
- MediaTekMediaTekは台湾のメーカーです。コストパフォーマンスが良く、近年採用が増えている印象です。Androidではミドルレンジ~エントリーモデルで高いシェアを誇ります。
- UNISOCUNISOCは中国のメーカーです。全体のシェアは少ないですが、製品が非常に安価で、安さ特化製品で少し採用が見られます。
- HUAWEI※HUAWEIは中国のメーカーです。「Kirin」というSoCを自社製品に搭載していましたが、米国による禁輸措置の影響で急速にシェアを落とし、2020年から2023年現在まで新製品を投入しておらず、恐らく出荷用の製品も製造していません。しかし、以前は一大シェアを誇っていましたし、未だに開発は続けているという話もあるので、今後復帰してくる可能性があります。
- Apple
CPUとは別パーツですが、CPUと関係性の特に深いパーツについても軽くこちらで触れています。メモリについては前述したので、それ以外のものになります。
グラフィックボード(GPU)

(C) NVIDIA
グラフィックボードは単体のGPUを搭載したパーツで、内蔵GPUを大幅に上回るグラフィック性能持ちます。また、専用のビデオメモリ(VRAM)が付属しているのも強みです。
GPUコア性能差も内蔵GPUよりも大きく有利ですが、特に差が大きいのはVRAMです。GPU用のメモリ「GDDR」はCPU用のメモリ(DDR)よりも圧倒的に高速なので、特に高解像度・高画質のゲームや動画編集への対応力に関しては内蔵GPUの性能が多少上がったところで追い付くのは厳しいレベルです。
近年では内蔵GPUの性能が飛躍的向上しているため、フルHD以下の処理は割と対応できたりはするものの、依然として重量級ゲームや重い動画編集ではグラフィックボードがないと厳しいですし、生成AIに関しての優位性も最近ではあるので、重いグラフィック処理が用途に含まれているなら欲しいパーツです。
しかし、グラフィックボードはその高性能なグラフィック性能と引き換えにデメリットがある点に注意です。
まず、グラフィックボードは非常に高価です。製品にもよりますが、重いゲームや動画編集もある程度対応できるものは、最低でも3万円弱程度のグラフィックボードを検討する必要があります(2024年7月時点)。
人気のコスパの良い製品となると4万円以上が基本になりますし、それでも安い部類で、VRAM容量やコスパ特化を考えるなら6~8万円は欲しいところだったりします(2024年7月時点)。このように、グラフィックボードは非常に高価なのが、大きなデメリットです。
次に大きいデメリットは、消費電力が多い点です。これは、特にノートPC等のモバイル端末ではバッテリー持続時間の低下などにも繋がるので致命的です。そのため、モバイル端末においては高い性能があっても搭載していれば良いというものではなく、高いグラフィック性能が必要でないならむしろ搭載しない方が実用性は高くなる可能性が高い点は留意です。
他にもスペース面や発熱の点などのデメリットがあり、高い性能と引き換えに多くのデメリットをがあるのは留意しておくべき部分です。
CPUとの関連性という点では、先にも軽く触れましたが「ボトルネック」がポイントです。GPUにおけるボトルネックとは主にゲーム用途で言われる用語で、ざっくり言うとCPUの性能の低さが原因でGPUの性能を活かし切れていない状態のことを指します。
画像処理はGPUが担当するとはいえ、ゲームやソフトなどでは画像関連以外の処理も発生しますから、CPUも無関係ではありません。GPUが高性能であるほどフレームレートが上昇し、CPUももそれに応じた処理が必要となるため、そのGPUが処理できる膨大なデータ量についていける性能をCPUが持っていなければ、活かす事ができない可能性があります。
要するに、高性能なGPU(グラボ)の性能を最大限活かすには、それに見合った高性能なCPUが必要となります。
- ボトルネックGPUにおいては、CPUの性能の低さが原因でGPUの性能を活かしきれないことを指します。
- 内蔵グラフィック(CPUの内蔵GPU)CPUにはGPUを内蔵しており、別途グラフィックボード等を用意しなくても良いものがあります。Intel製の主流CPUは、ほとんどがGPUを内蔵しています。ただし、内蔵GPUは、グラフィックボード等に搭載される単体GPUより性能は大きく劣るため、高画質の3Dゲーム等を動作させるのは難しいです。(2019年9月時点)
GPUについては、下記でもう少しだけ詳しく説明しています。良ければご覧ください。
 GPU(グラボ)とは?【ざっくり解説】 [/box]
GPU(グラボ)とは?【ざっくり解説】 [/box]
CPUクーラー

虎徹 MarkII
CPUはその小さなユニットの中で膨大な量の処理を行うため、高負荷時には大きく発熱します。そのため、発熱の多いCPUでは冷却しながらの使用が必須です。その際に利用するのが「CPUクーラー」です。
高性能なクーラーを採用するとCPUが常に全力で稼働しやすくなりますし、電力効率も良くなるというデータもあるので(要確認)、高性能で発熱の多いCPUを採用する場合にはCPUクーラーも出来るだけ高性能なものを採用することが望ましいです。
以下はデスクトップ向けの話になります。
CPU自体にクーラーが付属しているモデルもあるため、別途の用意が必須という訳ではありませんが、付属のクーラーは基本的に性能が低く、安価な別売りクーラーより劣ることが多いので、静音性や冷却性にこだわりたいなら別のものを採用するのをおすすめします。
また、そもそもTDPが95W以上のモデルではクーラーが付属しないことが基本なので、クーラーは別途の用意は必須となっています。BTOパソコンや既製品のPCでは何かしらのクーラーが始めから取り付けられていますが、初期採用のものだとあまり良くない安価なものが採用されていることも結構多いので、高性能なCPUの場合にはチェックが必要です。
次に仕様面の話も軽くしていこうと思います。CPUクーラーにはの冷却方式は、大きく分けて「空冷式」と「水冷式」の2種類があります。下記からそれぞれについて軽く説明しています。
空冷

DEEPCOOL AS500 PLUS
良い点
- 水冷より安価
- 故障率が非常に低い
- CPU周辺のエアフローを強化できる
悪い点
- 最大の冷却性能という点では水冷に劣る(主に搭載可能なファン的に)
- 大型のものはケースやメモリの高さによっては使えない
- エアフローがしっかりしていないと上手く機能しない可能性がある
簡易水冷

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT
良い点
- 空冷よりも冷却性能を高くできる
- 熱をPCケースの外に排出できるため、ケースに熱がこもりにくい
悪い点
- 空冷よりやや高価
- ラジエーターを別箇所に設置しないといけない(ケースファンの搭載可能数が減る)
- 環境によっては高負荷での継続使用で冷却能力が落ちる可能性がある
- 確率自体は非常に低いけど、空冷よりはトラブルが発生する可能性が高いし、トラブルが発生した際のリスクも大きい
最後に、全体の要点を箇条書きにしてまとめています。
- CPUはPCの頭脳CPUはPCの中央処理装置であり、CPUの性能がPC全体のパフォーマンスに影響するため非常に重要です。
- コアが多い方が高性能だけど、発熱や消費電力が増えるCPUはコア数が多い方が高性能で、複数の重いソフトを動作させる場合や、レンダリングなどの重い処理の際に有利に働きます。ただし、コア数が多いほど発熱や消費電力が増える傾向があるので要チェックです。高発熱・高消費電力のCPUを使う際には、CPUクーラーや電源に注意が必要です。
- メモリがCPUの作業スペースPCのメモリはCPUの作業場になります。出来るだけ高速で容量が多い方が、CPUがより性能を発揮しやすいです。特に動画・画像編集ソフトなどはメモリを大量に消費する傾向があるので、注意しておくと良いかもしれません。
- TDPは発熱・消費電力の大まかな目安(だけど、2022年時点では重要なのは基本TDP PL2)CPUの消費電力の基準として提示されているかにように思えるTDPですが、これはあくまで目安という点に注意です。2022年現在では高性能なCPUにおいては、表向きのTDPがあまり意味を成していない場合も多いです。TDP125Wでも最大消費電力は実はもっと多いという感じのことが基本です。最大消費電力を調べたいならTDP PL2にあたるものを調べる必要があります。
- 内蔵GPUは軽いグラフィック処理なら十分な性能だけど、重い処理は厳しいCPUにはGPUを内蔵しているものが多くあります。その場合には別途GPU(グラボ)が必須ではありません。内蔵GPUの性能は近年急激に向上していることもあり、軽いグラフィック処理なら十分な性能ですが、未だに重いグラフィック処理(重いゲームや動画編集)は荷が重い点には注意です。
- ゲーミングPCではボトルネックに注意ボトルネックとは、ざっくり言うと「CPU性能の低さが原因で、GPUが性能を最大限発揮できない」という問題のことです。そのため、高性能なGPUを搭載する場合には、CPU性能もそれに見合ったものが必要となる点に注意が必要です。
記事はここまでです。ご覧いただきありがとうございました。

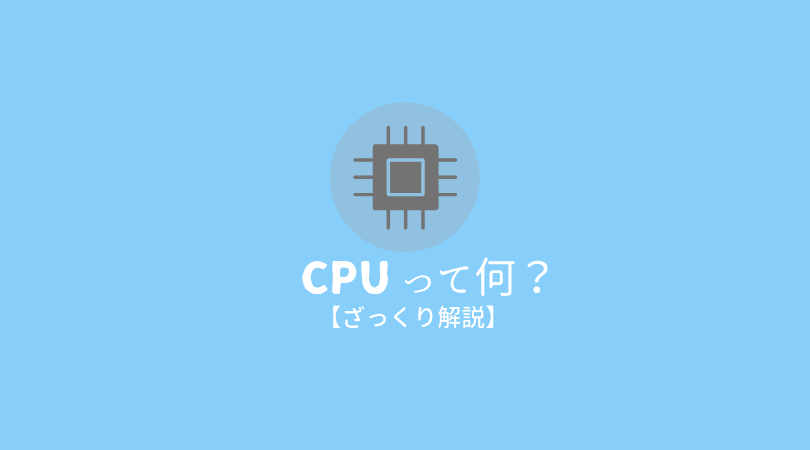


intelだけかと思ってました。GPT?内蔵型もあるんですね。中国独自の製品もあると思うのですが?
Windows用のCPUでは、IntelとAMDの二つが主流となっています。GPTとは多分内蔵GPU?のことでしょうか?
以前にIntel一強時代みたいな期間が長かったことがあったため、CPUと言えばIntelというイメージが強い人も多いと思いますが、今ではAMDも十二分に渡り合っている主要メーカーです。
また、Appleも最近ではPCのCPUも自前のものを開発して製造しており、自社製品で採用しています。
確かに、日本で一般販売されていないものも含めれば中国製のCPUもありますが、全体のシェアとしてはごくごくわずかですし、PC用のものは性能がIntelとAMDに圧倒的に劣るので正直主要製品とは言い難いと思います。
ただし、スマホ用のCPU(SoC)ではMediaTek(台湾)やUNISOC(上海)なんかは主要メーカーとしてシェアもそれなりに多いと思います。