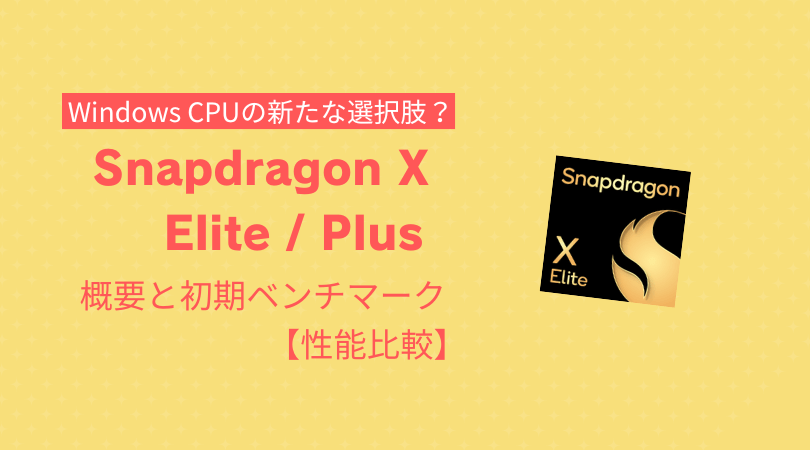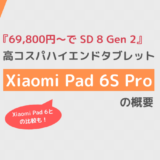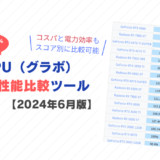この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
昨年(2023年)10月の発表から大きく期間が空いた「Snapdragon X(Elite)」ですが、ようやく具体的な搭載製品が発表され、来月6月18日頃に一斉発売されることとなりました。
特に効率面での期待が掛かるArmアーキテクチャのWindows 向けCPUの期待の新星の仕様や期待される性能について、スペックの再確認と、Microsoftから委託を受けたベンチマークを公開されていたので、そちらを見ていきます。
ラインナップ
2024年5月23日時点で、Qualcommが公開している「Snapdragon X」のラインナップは下記のようになっています。表には含まれませんが、TSMC 4nm プロセスで構築されます。また、「USB4/Thunderbolt 4」に対応する他、GPUも「DirectX 12」に対応するため、規格面はしっかりとWindowsに最適化されています。
| プロセッサ | Oryon CPU | GPU | NPU | メモリ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コア | 合計 キャッシュ | マルチスレッド 最大周波数 | デュアルコア ブースト周波数 | TFLOPS | TOPS | タイプ/転送速度 | |
| Snapdragon X Elite | |||||||
| X1E-84-100 | 12 | 42MB | 3.8GHz | 4.2GHz | 4.6 | 45 | LPDDR5x-8448 |
| X1E-80-100 | 12 | 42MB | 3.4GHz | 4.0GHz | 3.8 | 45 | LPDDR5x-8448 |
| X1E-78-100 | 12 | 42MB | 3.4GHz | – | 3.8 | 45 | LPDDR5x-8448 |
| Snapdragon X Plus | |||||||
| X1P-64-100 | 10 | 42MB | 3.4GHz | – | 3.8 | 45 | LPDDR5x-8448 |
CPUは、Eliteは12コア、Plusは10コアで、GPUコア数はPlusも含めて同じ
上位の「Snapdragon X Elite」に加え、後から下位の「Snapdragon X Plus」が追加されました。
Eliteでは3製品がラインナップされていますが、どのモデルもCPUとGPUのコア数は同じで、上位モデルほど最大クロックが高く設定されています。上位モデルほど最大性能では上回るものの、薄型のノートPCやタブレットでは冷却や電力面での制限があるため、電力を使ってでも少しでも高い性能が欲しいという場合でなければ、特にどのモデルかを気にする必要はないかなと思います。
コア数については、EliteのCPUは合計12コアです。Plusの方はコア2つ削減された10コアという構成です。GPUのコア数はPlusも含めて同じです。
PlusのCPUではコアが2つ削減されるため、性能が低下することが予想されますが、Qualcommは「Snapdragon X Elite」のCPU性能は「Core Ultra 7 155H」の最大37%高速と主張しているため、それを考えればコアが2つ減っても十分に高い性能を維持できると思われます。
その他の面は現状ではどれもトップクラスの仕様
その他の共通の仕様ですが、まずキャッシュ量は全モデル42MBとなっています。
「Ryzen 7 8840U(24MB)」や「Apple M3(20MB)」を上回り、「Core Ultra 7 155H」等と同じ容量です。現状ではトップクラスのキャッシュ容量を誇ります。
AI用のコアとしては、「Hexagon NPU」が搭載されており、処理性能は全モデル45TOPSとなっています。「Core Ultra 7 155H」のNPUが単体で最大11TOPS、「Ryzen 8840U」が最大16TOPSと言われているので、現行の競合シリーズよりも格段に高い性能を持っていることになります。
ただし、先日概要が発表されたIntelの次世代「Lunar Lake」ではNPU単体で同じ45TOPSとなるようで、GPU側でもAI用のコアを搭載するようなので、そちらが登場すればトップではなくなると見られます。
メモリはLPDDR5x-8448という超高速メモリまで対応します。
Armアーキテクチャという点にも注目
「Snapdragon X」シリーズは「Arm」という命令セットアーキテクチャ(ISA)に基づいたプロセッサーとなっており、これは従来のWindows向けの主要CPUのアーキテクチャ「x86/x64」とは異なるものとなっています。
Armは省電力性の高さから、モバイル端末においてはそれが強みとして挙げられており、特にスマホ向けのプロセッサーとしては支配的な地位を持っているアーキテクチャになっています。
しかし、Windowsではx86-64が主流で、各アプリケーションもそちらに最適化されていたので、Armアーキテクチャでは多くのアプリをネイティブ環境で実行できないという問題点があり、Windowsでは普及が進んでいませんでした。
とはいえ、やはりモバイル端末においては非常に強みにあるアーキテクチャということで、Qualcommが遂に本腰を入れて参入してきたという形です。
Armアーキテクチャがどう働くかについては、実際の製品が発売されて各所で利用されて評価されないと難しい部分ではありますが、購入を検討する際にはそちらも頭に入れておくことをおすすめします。
初期ベンチマーク
搭載製品の発売はまだ先ですが、「Snapdragon X Elite(X1E-80-100)」を搭載する新しい「Surface Laptop」の先行レビューを、Microsoftからの委託を受けてベンチマークを公開している海外サイトがあるので、そちらの結果いくつか抜き出して、軽く見ていこうと思います。
ただし、メモリには「LPDDR5x-8448」という超高品質な高速メモリが採用されており、現状の競合機種よりは一段良いメモリとなっているので、パフォーマンス面で少し優位性がある点は注意です。また、Microsoftの委託レビューなので、多少好意的な内容になっている可能性がある点も一応頭に置いておく必要があるかもしれません。
その他の細かな各端末の仕様などについては、お手数ですがリンク先をご確認ください。
CPU性能
Cinebench 2024
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Snapdragon X Elite New Surface Laptop 15 | |
| Core Ultra 7 155H MSI Prestige 16 EVO AI | |
| Apple M3 MacBook Air 15 | |
| Core i7-1255U Surface Laptop 5 13 | |
| Microsoft SQ3 Surface Pro 9 5G |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Apple M3 MacBook Air 15 | |
| Snapdragon X Elite New Surface Laptop 15 | |
| Core Ultra 7 155H MSI Prestige 16 EVO AI | |
| Core i7-1255U Surface Laptop 5 13 | |
| Microsoft SQ3 Surface Pro 9 5G |
Core Ultra 7 155Hをわずかに上回るレンダリング性能
マルチスレッドでは「Core Ultra 7 155H」の方が5%低速で、「Snapdragon X Elite」の方がわずかに上回る性能を示しています。ただし、LPDDDR5x-8448の恩恵を考えると、ほぼ同等と評しても良いかもしれません。
明確な優位性こそ無いものの、先代の「Surface Laptop 5(Core i5-1255U)」と比較すると約2倍のパフォーマンスとなっていますし、 非常に高いパフォーマンスで、重めの処理でも十分使える性能です。
Armアーキテクチャの最大の期待はワットパフォーマンスだと思いますが、純粋な性能でもネックにならないというのは大きいです。
シングルスレッド性能に関しては、「Core Ultra 7 155H」は上回っていますが、「Apple M3」の方が17%高速で、やや劣っていることがわかります。
次世代の「Apple M4」もiPadの方で既に登場していますが、そちらではM3と比較して2割近いシングルスレッド性能の向上が確認されたので、合わせると35%以上の差となります。AppleとWindowsの客層はそこまで被らないとは思うので、考慮する必要は大して感じませんが、同世代のCPUのシングルスレッド性能でこれだけの差が付くのは地味に珍しい気がします。
Geekbench 6.3
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Snapdragon X Elite New Surface Laptop 15 | |
| Core Ultra 7 155H MSI Prestige 16 EVO AI | |
| Apple M3 MacBook Air 15 | |
| Core i7-1255U Surface Laptop 5 13 | |
| Microsoft SQ3 Surface Pro 9 5G |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Apple M3 MacBook Air 15 | |
| Snapdragon X Elite New Surface Laptop 15 | |
| Core Ultra 7 155H MSI Prestige 16 EVO AI | |
| Core i7-1255U Surface Laptop 5 13 | |
| Microsoft SQ3 Surface Pro 9 5G |
Geekbenchも似たような傾向で、「Core Ultra 7 155H」を少し上回る性能
Geekbenchも似たような傾向で、マルチコアでは「Core Ultra 7 155H」の方が約11%低速で、「Snapdragon X Elite」の方が少し上回る性能でした。
GPU性能(グラフィック性能)
3DMark Wild Life(DX12/Metal)
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Apple M3 MacBook Air 15 | |
| Snapdragon X Elite Adreno New Surface Laptop 15 | |
| Core Ultra 7 155H Arc 8コア iGPU MSI Prestige 16 EVO AI | |
| Core i7-1255U Iris Xe G7 96EU Surface Laptop 5 13 | |
| Microsoft SQ3 Adreno 690 Surface Pro 9 5G |
ゲームでは「Core Ultra 7 155H」をわずかに上回る性能(発売直後追記:恐らく最適化不足で性能が大幅低下)
※追記:発売直後のレビューによると、DicrectX動作(3DMark含む)では基本的に「Core Ultra 7 155H」よりも大幅に低い性能となっています(おおよそ5~7割ほどの性能)。エミュレーション動作だとしても性能低下率が大きすぎるので、主に最適化不足によるものと考えられます。発売後のドライバー更新で改善される可能性はありますが、発売直後時点では競合SoCと比べるとグラフィック性能は大きく劣るので注意です。
3DMark Wild Lifeのグラフィック性能テストでは、「Core Ultra 7 155H(Arc 8コア iGPU)」の方が約5%低速で、わずかに上回る性能となっています。CPUのマルチスレッド性能と同様の差となっていました。
しかし、例の通り「LPDDR5x-8448」の恩恵があることを考えると、同等と評しても良いのかなと思います。
また、「Apple M3」はさすがの性能で、「Snapdragon X Elite」よりも31%も高速となっています。とはいえ、WindowsとMacでは用途の違いなどからグラフィック面で単純比較するのが難しいので、とりあえず置いておきます。
いずれにせよ、内蔵GPUとしては非常に高いパフォーマンスを持つのは確かです。「Core Ultra 7 155H(Arc 8コア iGPU)」と同等レベルの性能ということは、Ryzenの「Radeon 780M」も少し上回るということですから、現状のWindows機の内蔵GPUとしてはトップクラスの立ち位置です。
ワットパフォーマンスや価格次第では有利に立つこともあり得ますし、Windowsでは高性能内蔵GPU搭載機の選択肢が増えることなります。いよいよ、「重めのゲームでも高いfpsを求めないならビデオカードは要らない」という認識が当たり前になってきそうな気配を強く感じますね。
ただし、少し気になるのは、まず少し古いアーキテクチャに基づいている可能性が指摘されている点です。IntelやAMDの最新の内蔵GPUでは、一応レイトレーシング用コアを搭載していますが、初代の「Snapdragon X」ではレイトレーシングには対応しないと見られている他、対応のDirectXのバージョンも「12」ですが、Ultimate互換はないなど、少し古いものと見られています。
レイトレーシングについては現状内蔵GPUでは性能が足りなさ過ぎて実用レベルではないので、そこまで気にする必要はない点だとは思いますが、性能は同等で機能面での欠如があるということは事実です。その上で性能もわずかにリードする程度ですから、遅れて登場した割には物足りない性能であるとも見れます。
また、今回比較された「3DMark Wild Life」はArmでもネイティブ動作が可能なものですが、現状のDirectX対応ゲームの多くはArmではエミュレーション動作となるので、性能が大きく低下する可能性がある点には注意が必要です。
しかも、この後にはIntelやAMDの次世代プロセッサーも発表も控えているので、正直現時点でこのわずかなリードは無いも同然だと思います(むしろArmの制限を考えるなら不利に見える)。
ワットパフォーマンス次第ですが、GPUの純性能を重視するなら、一番とはならない可能性が高いです。
また、「Snapdragon」はWindowsでは主流ではなかったArmアーキテクチャである上、GPUのAdrenoもWindows向けのゲームを主戦場としてきた訳ではないので、予期せぬ不具合などが発生する可能性もあるという点も、一応考慮しておく必要があるかもしれません。
バッテリー寿命
動画再生
| CPU名称 | 持続時間 |
|---|---|
| Snapdragon X Elite New Surface Laptop 15 | |
| Apple M3 MacBook Air 15 | |
| Core Ultra 7 155H MSI Prestige 16 EVO AI | |
| Microsoft SQ3 Surface Pro 9 5G | |
| Core i7-1255U Surface Laptop 5 13 |
「Apple M3」を上回る非常に優れたバッテリー性能
動画再生時のバッテリー持続時間は、「Apple M3」の方が16%の方が短くなっており、非常に優れたワットパフォーマンスを発揮していることがわかります。
「Apple M3」搭載のMacBook Airも優れたバッテリー持続時間を提供するデバイスなのですが、それを特別多いバッテリー容量備えている訳でもなく(15インチで64~66Wh)、15%以上も上回るというのは驚異的です。
「Core Ultra 7 155H」は25%短い持続時間となっており、ここはArmアーキテクチャが活きているのかなという印象です。
Coreについては次世代「Lunar Lake」の概要で、x86では考えられなかった効率を実現すると主張している点が気になるものの、仮にそれが本当だったとしても、「Snapdragon X」側のワットパフォーマンスが悪くなる訳ではないので、価格面で有利に立てれば競争力は保てると思います。
現状トップのNPU性能から「AI PC」という側面を強く推されている印象の「Snapdragon X」ですが、少なくとも現状では、そちらよりもバッテリー性能の高さの方が恩恵を感じる人は多い気がします。
Procyon Battery Life(Office)
| CPU名称 | 持続時間 |
|---|---|
| Snapdragon X Elite New Surface Laptop 15 | |
| Apple M3(推定) MacBook Air 15 | |
| Core Ultra 7 155H MSI Prestige 16 EVO AI | |
| Microsoft SQ3 Surface Pro 9 5G | |
| Core i7-1255U Surface Laptop 5 13 |
オフィス生産性のバッテリーテストでも優れた性能
※「Apple M3」は元データでなぜか「0.00x(0%)」表記でしたが、文中では同等だったと触れられていたので、恐らく記入漏れとして扱い、推定値100%として載せています。
Procyonのオフィスの生産性シナリオによるバッテリーテストでもトップのバッテリー性能を示しています。「Core Ultra 7 155H」は10%短い持続時間となっており、競合製品に対する優位性を保っています。
ただし、動画再生時と比べると少し差が縮まっているのは若干気になるものの、「Apple M3」搭載のMacBook Air 15と同等の持続時間なら、非常に優れたバッテリー性能なのは間違いないと思います。
AI推論性能(NPU)
Procyon AI Computer Vision
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Snapdragon X Elite(45TOPS) New Surface Laptop 15 | |
| Apple M3(推定18TOPS) MacBook Air 15 | |
| Microsoft SQ3(29TOPS?) Surface Pro 9 5G | |
| Core Ultra 7 155H(推定11TOPS) MSI Prestige 16 EVO AI | |
| Core i7-1255U(NPU無し) Surface Laptop 5 13 |
NPU単体の性能は現状トップ
ProcyonのAI性能テストでは、他を圧倒的に突き放してトップの性能を示しています。「Microsoft SQ3」「Apple M3」の約2倍、「Core Ultra 7 155H」の3倍以上のスコアです。
「AI PC」という触れ込みで多数の搭載製品の販売が予定されているだけあり、NPU性能の高さは確かなようです。現状、「Copilot+」をローカルで実行するのに必要と言われる45TOPsを唯一クリアしています。実際にはGPU側の処理性能も加算しての計算で良いとの回答もあったと思うので、実用性能は上記の表ほどの差ではない可能性もありますが、それを考慮しても現状でトップなのは間違いないNPU性能です。
ただし、多数のSnapdragon X製品が発表されるのとほぼ同時に概要が発表された、Intelの次世代CPU「Nunar Lake」において、NPUは45TOPSに到達するのに加え、GPU側にも60TOPSのAIエンジンが搭載される見込みということが判明したので、そちらが発売されればトップの地位は失ってしまうことになるかもしれません。発売も2024年第3四半期(7~9月)を予定ということで近いので、AI性能を重視したいなら考慮しておくべきかもしれません。
また、特にノートPC用CPUのNPUというのは、現状ではビジネス用途を除くと、そこまで恩恵を感じる使い道が無さそうに見えるため、個人的には決め手とするにはまだ弱い印象です。
個人でも高いAI性能が欲しい場面もありますが、たとえば、Stable Diffusionのような画像生成AIなど、非常に負荷の高い専用のAI処理などにおいては、現状はGPUで行う方が高速であり、設定なども明らかに楽です。
最近のAIの活用はどんどん広まっているので、急激に画期的な使い道がたくさん出てくる可能性も大いにあるため、軽視すべきではないとは思うものの、少なくとも現状ではCPU(SoC)に高性能なNPUがあるからといって、AI処理がなんでも快適にできるという訳では無い点は、勘違いのないようにしないといけないかなと思います。将来性との準備という感じです。
エミュレーションでのパフォーマンス
エミュレーションでのアプリケーションのパフォーマンス比較です。「Snapdragon X Elite」はArmアーキテクチャですが、Windowsは現状x86、x64のCPUで利用することが一般的であるため、各アプリではArmアーキテクチャにネイティブ対応していない可能性があります。
そして、Arm非対応のアプリケーションを利用したい際には、エミュレーション動作が必要となる可能性があります。ただし、その際には余計な処理が必要となり、多少パフォーマンスが失われてしまったり、動作が不安定になったりすることがある点に注意が必要です。
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Snapdragon X Elite New Surface Laptop 15 | |
| Core Ultra 7 155H MSI Prestige 16 EVO AI | |
| Core i7-1255U Surface Laptop 5 13 | |
| Apple M3 MacBook Air 15 | |
| Microsoft SQ3 Surface Pro 9 5G |
| CPU名称 | スコア |
|---|---|
| Core Ultra 7 155H MSI Prestige 16 EVO AI | |
| Apple M3 MacBook Air 15 | |
| Snapdragon X Elite New Surface Laptop 15 | |
| Core i7-1255U Surface Laptop 5 13 | |
| Microsoft SQ3 Surface Pro 9 5G |
良くて「Core Ultra 7 155H」と同等、3割以上性能が低下する可能性も
エミュレーションでのベンチマークは、Ligthroom Classicの場合は「Core Ultra 7 155H」と同等のパフォーマンスでした。上述の基本のベンチマークでは基本少し上回っていましたし、高速なメモリの優位性があることを考えると、実質的には少し劣ると見た方が良さそうです。ただし、性能自体は高く、ネックというほどでもありません。
次に、レンダリングのベンチマークである「Blender 4.1.1」を見てみると、「Core Ultra 7 155H」の方が46%も高速で、大幅に劣る結果となっています。負荷の高い処理の場合は、エミュレーション負荷も恐らく高くなるので、その影響が出ている可能性があります。
「Core i7-1255U」と比べると約1.5倍も高速なので、十分に高性能とは言える水準ですが、価格や競合モデルとの差を考えると魅力はかなり落ちます。
エミュレーション動作が必要となるかどうかや、エミュレーション動作時にパフォーマンスが大幅に低下するかどうかの判断は難しいですが、頻繁に使う予定のアプリがある場合は、対応状況を事前に少し調べておくと良いかもしれません。
総評
基本性能は「Core Ultra 7 155H」と同等レベルで、NPU性能は格段に上
「Snapdragon X Elite」のCPUとGPUの基本性能は、レビュー機の超高速メモリ分を考慮すると、「Core Ultra 7 155H」と同等クラス程度かなという結果でした。
レビュー機だったSurface基準でいえば、第12世代Coreからのグレードアップなので圧倒的な性能向上とはなるものの、現在の最新世代の競合モデルと比べると優位性はほぼないですし、WindowsにおけるArm版アーキテクチャの対応もまだ少し不安が残ります。そのため、最新のプロセッサーとして相応な非常に高いパフォーマンスを持ちますが、性能重視の場合には現状は最高の選択肢とはならなさそうです。
しかし、NPU性能に関しては、Procyonのベンチマークで「Core Ultra 7 155H」の3倍以上、「Apple M3」の約2倍のスコアを記録するなど圧倒的な性能を示していました。「Copilot+」の最低要件と見られる40TOPSを現状唯一満たせる、現状の最高性能NPU搭載プロセッサーであることは確かです。
ただし、気になるのはIntelの次世代CPUの「Nunar Lake」です。「Nunar Lake」では、NPUは「Snapdradon X Elite/Plus」と同じ45TOPSに到達するのに加え、GPU側にも60TOPSのAIエンジンが搭載される見込みとなっています。発売も2024年第3四半期(7~9月)を予定となっており、割とすぐなので、AI重視ならそちらを待ってみたいという気もするのは覚えておいて損は無いかなと思います。
バッテリー性能は「Apple M3」をも上回れるレベル
「Snapdragon X」で現状で特に魅力的なのはバッテリー性能です。Armアーキテクチャということで期待されていた点ですが、しっかりと良い結果を示してくれていました。
動画再生時のバッテリー持続時間では「Apple M3」を約19%上回る時間を記録しており、非常に優れたワットパフォーマンスを備えることがわかります。
notebookcheckのベンチマークによると、よく似た状況での「MacBook Air 15(Apple M3)」の動画再生時の持続時間は、約18.6時間となっていることを考えると、22時間程度の稼働を期待することができます。非常に長いです。
オフィスでのシナリオを想定した生産性ベンチマークの場合にはやや地位を下げるものの、それでも「Apple M3」と同等クラスで、「Core Ultra 7 155H」を10%以上も上回る時間を記録しています。
現状は最高の省電力性能を持つプロセッサーとして確かな実力を示しています。
発表時ほどのインパクトは無いが、強力な電力効率とNPU性能を備えた優秀なSoC
「Snapdragon X Elite」の発表は昨年(2023年)10月下旬にされ、その頃の主な比較対象はCoreの第13世代だったため、特にワットパフォーマンスでは圧倒的すぎる差を見せつける結果となっており、「ライバルを完封」といった見出しも生まれるほどでした。
しかし、その発表の後に「Core Ultra」が登場して、GPU性能や効率が改善した他、AppleもM3とM4をリリースするなど、登場前のわずか半年ほどの間に、競合相手が更に一段強力となった経緯があります。
そのせいで、発表時ほど圧倒的なインパクトを得られなくなってしまってはいますが、各種パフォーマンスは非常に高いものを持っているのは確かですし、バッテリー性能については今でも競合モデル相手を上回る性能を持っており、非常に魅力的でした。
高コスパ機の価格がどうなるかということや、ArmアーキテクチャのWindowsがどれだけネックにならないか、という点にも左右されそうですが、Windows CPUの新たな選択肢として、どのようになっていくのか楽しみです。